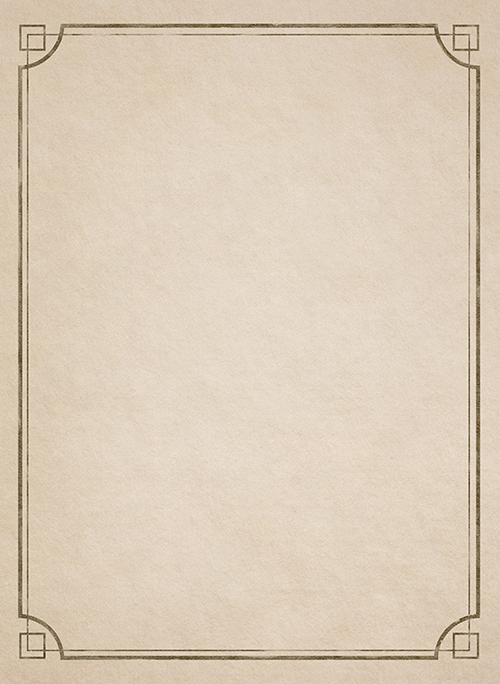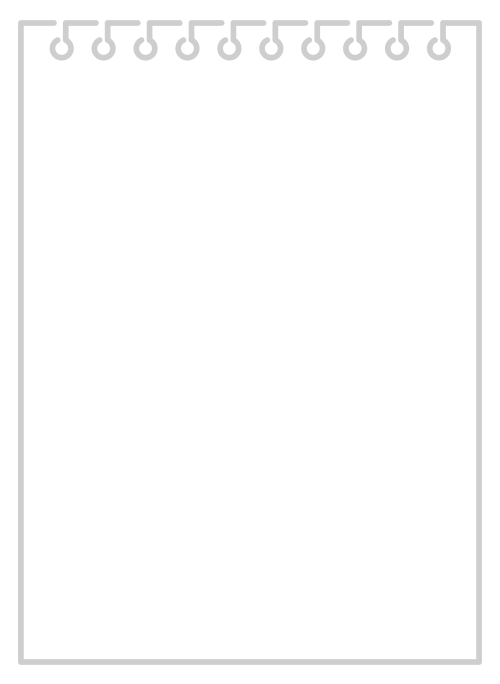近くのお店に入った私たちは、お互いに飲み物を頼み正面に座る。
真由はいつもよりメイクが濃く、服も露出が目立つものを着ていて学校では見せないような姿をしていた。
「なに、話って」
運ばれてきたジュースをストローで飲んで、ストローの端を歯で噛んだ真由が少女のような笑みを浮かべてそう言う。
私は、カバンの中から一枚の写真を取り出して彼女の前に置いた。
それを視界に入れた瞬間、真由は写真を裏返して私を睨みつける。
「なんでこれを萌香が持ってるの」
ということは、このカヨラの封筒が写っているこの写真を真由は一度誰かに見せられたことがあるということ。
そしてそれは私ではなく、
「広菜のやつ、捨ててなかったんだ」
満尾広菜さんが持っていた。
「捨ててなかったってどういうこと?」
「っ」
「満尾広菜さんのこと前にきいたら知らないって言ってたよね?」
言いたくなさそうに顔を俯かせた真由に私はもう一度写真を表にして真由の視界に映るところへ持っていく。
「この写真は何?満尾広菜さんになんて言われて見せられたの?」
「…わっ、私は、ただ、お金がほしいの、メイク道具とかブランドのものとか、そういうものがただ欲しいだけ。自分がこういうことやりたいからサラに頼んでやらせてもらってるだけ」
独り言のように呟いた真由に私は顔を近づける。
サラに、頼んでやらせてもらっている。そしてこの写真がすべてを物語っている。
カヨラとサラと売春、そして記憶の消去と改ざん。
すべては絶対に繋がっている。
「カヨラには入信してるんだよね」
真由がぱっと顔を上げた。
「…何を信仰しようが自由でしょ」
「当たり前じゃない、でもカヨラは売春に手を出してるんでしょ?犯罪なんだよ?なんで見て見ぬふりするの?」
「大丈夫だよ、結局忘れるんだから」
無理矢理、口角をあげて変な笑顔をつくった真由。嘘だ。楽しくてやっているわけない。
記憶がなくなろうが、罪は罪できっとそれは真由自身も分かっている。
「忘れるって、売春の記憶を消されるってことだよね」
「そうだよ、辛い記憶とか全部消してくれる。それでお金がもらえる、ウィンウィンじゃない?」
「同じことを満尾広菜さんにも言ったの?」
「まあ、やってたこと責められたし。自分だってお金欲しさにサラに頼んで売春してたくせにさ。
だけど、広菜は記憶が消えなかった。なんでか分からないけど、広菜自身はその理由を知ってたんじゃないかな」
記憶が消えなかった理由って。
それを誰かに吐き出すことなく、満尾広菜さんは死んでいったのかな。それとも、私には話してくれていた?
「広菜は、カヨラで行われている売春の顧客を知って、告発しようとしてた。
それをサラは止めたかった。何せサラのお父さん、カヨラと関わってるし」
投げやりのようにそう言った真由は、椅子の背もたれに体を預け、「あーあ」と顔を上に向ける。
「言っちゃったあ」と笑った。
「もうさ、私はこの日々から抜けられんないわけ。一度はまったら最後、広菜みたいに死ぬまで私は記憶を消して、誰かに体を売って、金をもらっての繰り返し」
ーーーつらい。
その本音が垣間見える。
真由も晴美も、サラも許せない。その気持ちは変わらない。だけど、晴美や真由は罪悪感とずっと戦っている。
少しの軽い気持ちで飛び込んで、闇に沈んでいく。
気づいたらもう抜け出せなくなっている。つらいといってもがこうがあがこうが、それは無意味なことだと突きつけられる。諦めて、これが幸せなんだと自分に言い聞かせた。
ーー私だって同じだった。
「私が失踪中に何をしていたか、真由は知っているの?」
「…サラに聞いたら?」
「答えるかな」
「答えないだろうね、だけど」
真由はぐいっと私に顔を近づける。
「広菜が最後に何かをあんたに託して死んでいったとしたら、サラはそれを見つけ出そうと必死にはなるだろうね」
「…それって」
「カヨラの闇の証拠」
真由が放ったその言葉。
久松先生は私に言った。何か思い出したら共有してほしいと。
そして、それを言った人物はもう1人いる。
私は「そう」と必死に冷静を装ってアイスココアを飲み込んだ。正直味なんてしたもんじゃない。
「…広菜から託されたものがそれだとしたら、私が記憶をなくしたのも私の意思じゃないってことね」
「あははは、そうかもねえ」
「何も知らないの?」
「知ってたとしても、私の記憶消されてるって」
そう言った真由。
嘘をついているようには見えなかったけれど、本当のことを言っているようにも見えない。
何かに依存してしまっている彼女は、感情のどこかの部分を自らで壊しているように思えた。
辛さを、辛いと言えなくなってしまっている。
「もういい?今日は稼ぎたいんだけど」
「最後に一つだけ」
腰を上げた真由が顔を顰めながら、再び椅子に腰を下ろす。
私はカヨラのホームページを出して、下にある『記憶』のボタンをおした。
「これは、なんなの?」
「…教えない」
「真由」
「私に聞いたってサラに言うでしょ」
「言わないから」
真由はひどくサラにたいして恐怖心があるようだった。同じ歳なのに服従しているようなそんな雰囲気。晴美だって同じだ。
真由をじっと見つめていれば、真由は諦めたように私からスマホを奪い取り画面をしばらくいじって、荒々しくテーブルの上に置いた。
「…なんてことないでしょ、カヨラの教えが英語で書かれてるだけ」
表示されたそれをゆっくりとスクロールする。彼女の言う通りそれは英語で書かれていた。
あとで調べ上げるために、画面を写真に収めていく。
だけど、カヨラの教えって、本当にそれだけなんだろうか。
そしてしばらくそれを眺めていれば、字の色が違う箇所がいくつかあるのに気づく。
「ねえ、これなんで色が違うの」
「いちいちなんでそういうの気づくかな、広菜と仲良かったっていうの、なんか納得するわ、類友ってやつ?」
「はぐらかさないで答えて」
そう言えば、真由の口から舌打ちがもれて画面を覗き込んだ。
「…売春してる女の子たちのイニシャルになってんの」
「イニシャル?」
確かにその色が変わっている文字は、ローマ字で2文字。それを指先で触れようとするがその手は真由によって止められた。
「押したら、あっちに誰を指名したか情報がいくようになってんの」
「っえ?」
「どこから、誰がこれを押したかもカヨラに届く。下手にやるとやばいよ」
咄嗟に手を離す。
真由は安堵の息をはいて、「あたしがどんな目に合うかわかんないんだから勘弁して」と背もたれに体重を預けた。そしてため息をついたあと、カバンを持って立ち上がる。
「もう話せることはないから、行くわ」
「真由」
「もう、いい加減に」
「真由たちのこと、許せないけど、話してくれて感謝してる」
「っ」
「自分のこともっと大切にした方がいいよ」
真由は一瞬泣きそうな顔をしたあと、顔を背けて「うざいんだよ」と掠れた声を残してその場を去っていった。