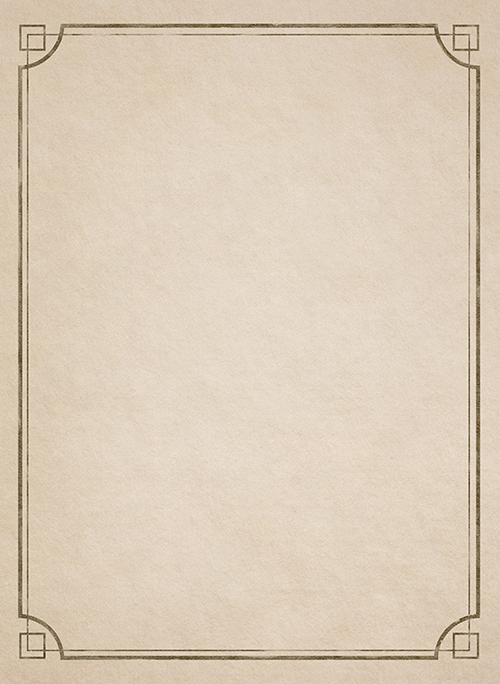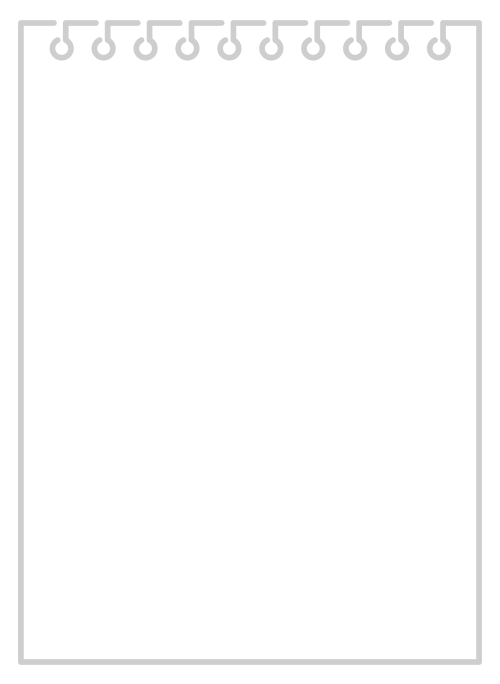ーーーー『復讐』
その言葉が私の中で深く根付いた。
現実味をもたないその言葉。だけど、可能性はあると思っている。
満尾広菜さんの母親にぶつけた過去の憎悪が本当だとすれば、私はすくなからず満尾広菜さんと一緒にいて、友達だと思っていて、大切な存在だったのかもしれない。
今私が生きていて、今からやろうとしていることは現実だと言い聞かせながら長い廊下を歩いた。
そして黒い絵の前に立つ。
こわくて目を逸らしていたそれを目に焼き付けた。
それからゆっくりと美術室へと歩みを進める。
戸を開けた先。「あら」とその人が穏やかな笑みを私に向けた。
「職員室にいったら、重田先生ここにいるってきいたので」
美術室の扉を閉めて、重田先生の前にたった私。
私の失踪中のことをよく知らなくて、満尾広菜さんのこと、そしてあの絵のことを知っているのも美術部顧問である重田先生。何かを聞き出すにはうってつけの存在だった。
「どうしたの?立見さん」
「色々とききたいことがあって」
「なあに?」
重田先生は正面に椅子を置いて、私に座るように促す。私は「ありがとうございます」と緊張がぬけきれない硬い声をだして腰を下ろした。
膝の上でぎゅっと拳を握る。この人も、嘘をついたらどうしよう。
「立見さん?」
「先生は、満尾広菜さんのこと、知っていますよね」
重田先生が私の言葉に反応して眉が上がる。
そしてせつなげに笑った。
「ええ、当たり前じゃない。あの子美術部だったから」
「どんな、人でしたか」
「絵がうまくて、コンテストで受賞もしてたわ。期待してたのだけれど、学校を辞めちゃったのよね」
「亡くなったのはご存じですか」
重田先生は驚いたように顔を上げて、腰を上げた。
そして感情をぶつけようにもどうしたらいいのか分からず押さえ込むように、大きく息をついて腰を下ろす。
「…変な噂はきいていたわ、家庭環境のこととか、売春をしていたとか。学校を辞めたあと、どうしてたか気になっていたの、まさか亡くなってたなんて」
そう言って、耐えきれなくなったように両手で顔を抑える。「なんで」と。
「なんで、あの子は亡くなったの、どうして」
「自殺だそうです」
「…だから、私が復帰後先生たちにきいても誰も満尾さんのことを教えてくれなかったのね。
学校のイメージを守るためとかくだらない理由かしら」
「おそらく、そうです」
「最低だわ」と涙を拭きながら、重田先生は自身を落ち着けるように何度か息を吸ってはいたあと、私に「教えてくれてありがとう」と微笑んだ。
安堵した。
この人は、満尾広菜さんの味方だ。
「重田先生」
美術室の扉へと指先を向ける。
「廊下の壁に飾られているあの絵は、誰が描いて、いつ頃、飾られたものですか」
その問いに重田先生は、唇をかんだ。
瞳には、悲しみや嘆き、そして憎しみが含まれている。
「描いたのは満尾さんよ、私が一度お休みする時にはまだ飾っていたのに、
復帰してみたらなぜか取り外されてて、彼女の絵が好きだったからまた飾り直したの」
あの絵は、私が失踪している間まだ飾られていた。
だからあの映像にも映っていたんだ。
そして私が帰ってくる前に、満尾広菜さんの存在を消すために誰かが取り外した。
重田先生が「そういうことだったのね」とせつなげに笑う。おそらく取り外されていた理由を察したのだろう。
「あの絵のタイトル、あなたなら知っているわよね」
「っ、ごめんなさい、きいてもいいですか」
「『陽炎』よ」
黒い中に立ち上る白い炎。彼女は恐れていたものを絵にぶつけたんだろうか。
なんと言ったらいいか分からず、私はうつむき、そしてゆっくりと震える声で言葉を放った。
「なぜ、私なら分かると」
重田先生は、それが当然のように、まっすぐな声で私に真実をぶつける。
「親友でしょ、あなたたち」
真実のその先。
私は私たちを知る誰かから、その言葉がききたかっただけなのかもしれない。
すべてをなかったことにして『普通』を生きようとしていた自分が惨めで、憎悪が込み上げてくる。
ーーーー忘れて、ごめん。
写真に映った幼い彼女の笑みを、刻み込んだあの大切な人を私は絶対に忘れてはならない。
そう、思った。