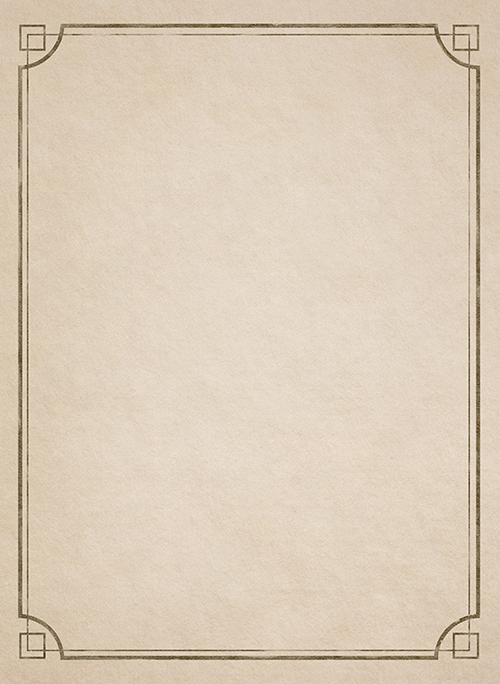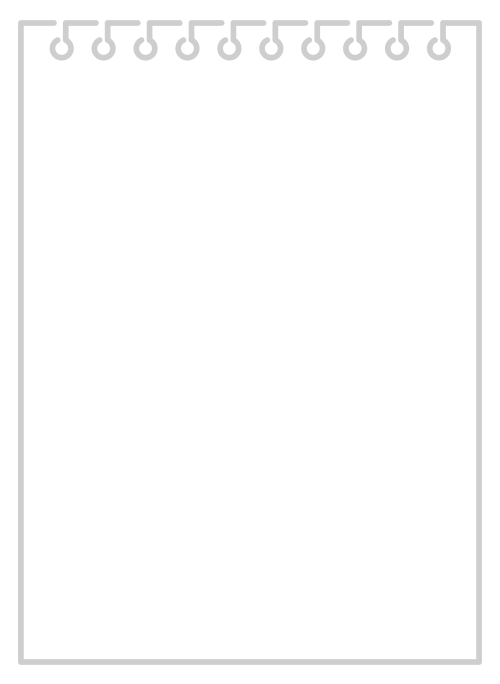高橋さんが去ったあと、後ろから「おい」と不機嫌そうに声をだした泉さん。
「無駄話してないではやく行くぞ」
準備をしていたのか、黒っぽい服装に着替えていた。
黒のパーカーはこの季節にしては少し暑そうだ。
「なんで着替えているんですか」
「尾行しやすいだろ、目立たない方がいい」
「前に私を追いかけてきた時もそういうの意識したんですか」
「根にもつのな、お前」
苦い顔をしてそう言った泉さんに思わず笑ってしまう。まあ、あれがなければ私はここにいないのは確かだ。根に持っていると言われればそうなるかもしれない。
泉さんは「悪かったって何度も言ってるだろ」とぶつぶつの文句を言いながら私の横を通り過ぎて靴を履き始める。
あの時のことは、泉さんも泉さんなりに本当に反省しているのだろう。本人も言っていたが、それくらい必死なんだ。
私も泉さんの横に並び、靴を履いてつま先を地面にぶつける。
「行くぞ、立見萌香」
「はい」
私たちは、傷つくかもしれない真実を追うために一歩踏み出した。
学校に行っていないのに、学校の近くに来ているのが不思議だった。
非日常をつきつけられている気がしている。だって、門の近くでこうやって誰かを尾けるために待ち構えているなんて善の人間、普通の人間がやることじゃない。
そんな考えをなんとか取っ払って門をじっと見つめているとサラがいつもの屈託のない笑みを浮かべながら、晴美、真由と門から出てきた。
今日は晴美の部活がない日だ。
おそらく3人でどこかに寄り道して帰るのだろう。
私はいつもあの3人と行動していた。楽しそうに笑い合っている彼女たちと一緒に普通の学校生活を…。
やっぱり、違和感だ。つくりもののような、私の妄想のような、そんな感覚。
いつも彼女たちの前でどんな顔をして一緒にいたのか思い出せない。
「…つけるぞ、お前まじでバレないように気をつけろよ」
泉さんがそう言って私のパーカーのフードを荒々しく被せて彼女たちの後を追い始める。
逆に怪しいのに。
と、私は被せられたそれを静かに外して泉さんのあとを追った。
バレないように距離を離しているため見失わないように彼女たちの背中姿をじっと見つめる。
「あいつら、本当に友達か?」
「なんですか急に」
「失踪して帰ってきて早々学校休んでるのによ、楽しく笑い合いながら帰ってんだぞ」
「…そういう、もんなんですよ」
学校という狭い空間。どうやってうまく生きていくか模索して輪の中から外れないように必死だった。
誰かが輪から外れれば、よってたかってその人を攻めたてる。そんな理解し難い空間。
満尾広菜さんが、あの母親から逃げた先が学校ではなく別の場所だったのも頷ける。
所詮、狭い場所へおしこめられて必死にグループを作っているのだから満尾広菜さんからしたら家も学校もさして変わらない場所だったのかもしれない。
「…やっぱり変な仕組みだと思うんだが、記憶を消したり改ざんしたりって、矛盾が生じてくるだろ、お前そういうの感じたことないのかよ」
「…正直、逃げてきてたのもあります。感じても、普通に生きていければいいやってそう思ってました」
「今は違うだろうが」
「はい。でも、やっぱりうまく思い出せる自信がないんです。
満尾広菜さんのことにしても時々存在を感じることは出来るんですが、顔や声、姿を思い出すことはできません」
「…そんなこと、本当に可能なのか」
「記憶のことに詳しい先輩はそう言ってました」
「そいつが今回の件に絡んでるっていう可能性、あるよな」
ーーーそれは確実だ。
でも彼は教えてくれないだろう。聞けば答えるが核心的なものはうまくはぐらかしている。
原島先輩を探らないといけないのは確実だけど、まずは彼女たちが隠していることを調べないと進めない気がする。すべてを把握したうえで原島先輩の正体を突き詰めるべきだ。
「あ」
しばらく歩いていると、3人は寄り道はせず手を振りながら別々の方向に別れていった。泉さんと顔を見合わせてサラの方を追っていく。
サラは茶色い緩く巻いた髪を軽く指先でいじりながら、歩いてスマホを取り出し、耳に当てた。
「…誰と電話してんだ?」
「さすがにこの距離じゃ声は聞こえませんね」
「近づくか?」
「さすがにバレるのでやめときましょう」
泉さんも流石にこの状況でバレるのはまずいと思ったのか大人しく頷いて早めていたスピードを戻してサラの姿を睨みつける。
そんな中、私はごくりと唾を飲み込んだ。
ーーー嫌な予感がする。
それは、泉さんがよく言っている勘などではなかった。今私たちが歩いているこの道は私が失踪後何度も通っている道だったからだ。
「泉さん」
「あ?」
「私、」
ある建物が見えてくる。
言葉をとめて、サラの姿にわたしは何度も心の中で叫んだ。
ーーー止まるな、止まるな。
「っ」
「おい」
無情にもサラの足が建物の前で止まる。
そしてサラが周りを気にするようにこちらを向いたが、瞬時に泉さんが私の腕をひきサラから見えない死角へと引き摺り込んだ。
「あっぶね、なんだよあいついきなり足止めやがって」
心臓が嫌な音をたてつづけるなか、私達は物陰からサラの様子を伺う。
泉さんが私の頭を掴んで「見えない」と少し下に下げた。
建物の前で、サラがまたスマホを耳にあてた。
「…あの建物の2階に私がお世話になっている病院があります」
「あ?」
「看板、見えますか」
泉さんが「ああ、なんか書いてんな」とそれを読み上げようとした時、建物から人が出てくる。
何がどうなっているの。
なんで、サラと、
「…久松先生」
あの人が繋がっているんだろう。