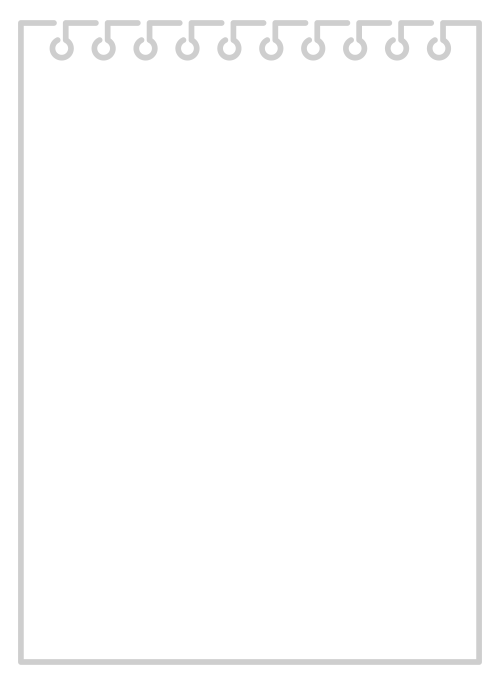写真は許可なんてとらずに勝手に鞄の中へといれた。
どうせなくなってもあの母親は気づかないだろう。
再度母親のところへ戻れば、まだ窓の外を眺めていた。
すべてを諦めているかのような、そんな背中姿をこちらに向けている。
「あたしに『広菜はあんたから何も教わらない』って言ったけど、ひとつ教えたことはあんのよ」
独り言のように吐き出されたその言葉足を止める。
泉さんは、「もうあいつは情報をもっていない、さっさと行くぞ」と気にしない様子で玄関の方へと向かっていくが私は足を止めたままその背中をじっと見つめる。
この人にも、私と同じように『罪悪感』があるのだろうか。母親なのに、1番近くにいたはずなのに、愛情をもてなかったのはなんでなんだろう。
「何を広菜さんに教えたんですか」
母親は新しいタバコに火をつけたあと口から煙をはいて、私の方を振り返る。
「そこ、みえるでしょ」
タバコの先が窓の外をさして、灰が少し床に落ちた。私は母親が示した先へと視線を向ける。
窓の外は、アスファルトの地面からゆらゆらと空気が揺れていた。
まさか。
「あの現象、『かげろう』っていうの。広菜にそう教えた」
ーーー『陽炎』
夢の中で彼女は何度も何度も私に訴えかけていた。
そしておそらくその言葉を私に教えてくれたのも彼女だ。きっと、そんな気がする。
それに加えて、何も思い出せないなかで記憶の扉を叩くように彼女の言葉が蘇ることがあるのだ。それは規則性なんてものはなくふとした時に刹那におこる。
「あの中に、足を踏み入れると自分は燃えちゃうんじゃないかってあの子小さい頃に泣いたことがあんのよ。くだらないでしょ?
私はすぐに泣いて私に縋るあの子が嫌いで嫌いで仕方がなかった」
「じゃあなんで」
ーーー子供を産んだのよ。その言葉は放たれることはなかった。そんなことを言う権利は彼女を傷つけたかもしれない私に言う資格なんてない。
「陽炎の中なんて当然燃えやしないし、足を踏み入れたところでなんてことないって、泣き声が鬱陶しくて握られた手を振り払った」
足を踏み入れたところでなんてことない。
彼女は、それで納得したんだろうか。
地面から炎のように透明の火が立ち昇り視界を揺らしているその有様に小さいながらに恐怖を覚え、母の手を握ったがそれは振り解かれてしまう。
彼女のせつなげに歪んだ表情が思い浮かび、唇を噛んだ。
「広菜さんは、失踪前に『記憶』について何か言ってませんでしたか」
母親がちらりと私を見て「記憶?」と息を短くもらした。灰皿で押し付けたタバコがあっけなく潰れて倒れる。
「ああ、最後にあの子に言われたわね『どうせならあんたのこと記憶から消したかった。私には記憶を消すこともできないんだ』って」
ーーーーやっぱり、満尾広菜さんは記憶を消すことを望んでいた。
消したい記憶は、売春のことなのか、この母親のことなのか、私のことなのか、あるいは、全部、か。
「広菜は、あんたには心を開いてる様子だったけど、売春のことも知らなかったなんて所詮うわべだけの友達だったってことね。
ま、本当の友達がいたら自殺なんてしないわよね」
まるで全く知らない他人が死んだかのように、そう語った母親。
「違う」と叫びたかったが、叫ぶほど自分に自信もなければ友達だったと胸を張って言えるほど私は彼女のことを知らない。
「すくなからず、あんたより満尾広菜のことを知っていて、そばにいたのはこいつだ」
耐えきれなくなったのか、泉さんが荒い足音でこちらに向かってきて、母親にそう言う。
泉さんは私の猜疑心を取っ払おうとしてくる。
やり方や、言い方は荒っぽいけど泉さんの言動は信頼関係が伴ってくる。私はどうやっても悪人には見えないし、母親よりも私の方が彼女のことを知っていた、と。また、お得意の勘だろうか。
「満尾広菜は言葉の通り、あんたのことを忘れたかったんだと思うぜ、誰かに縋ってまでそれを望んだ」
「っ、ただの記者に何が分かるのよ」
「お前が最低な母親だってことだけは分かるさ、またすべてが終わったらあの骨を受け取りにこいつが来る。せいぜい娘に呪われないように気をつけとけよ、くそババアが」
吐き出された暴言。母親がヒステリックに怒り出す前に泉さんは「行くぞ」と私の手をひいた。