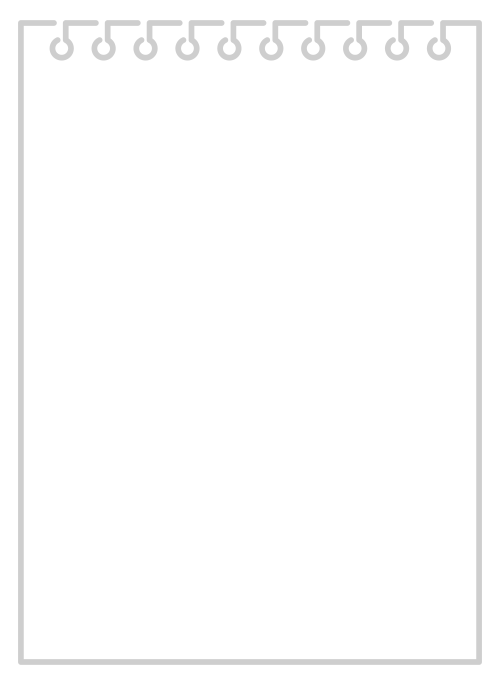嫌々ではあったが、女性は「めんどうくさいから手短にお願いね」と一度扉をしめてチェーンを外した。
泉さんが小さな声で、
「よくやった、切り札」
と、呟く。私は、話を聞くのに顔を見ただけでこの分厚い扉をすこしでも開けてくれるようなそんな存在だったんだろうか。もしかしたら中に入れば、恨みつらみをぶつけられるかもしれない。
少しの恐怖を抱いて私は満尾広菜がいた家へと足を踏み入れた。
足の踏み場もないほどではないが、綺麗とは言い難いそこはあちらこちらにカップ麺のゴミや洋服が散乱している。
そして入ってすぐに気づいた違和感。
「広菜さんは本当にここに住んでたんですか」
泉さんがそう聞いた。
満尾広菜さんの母親とみられるその女性は窓を開けてタバコに火をつける。
煙は外に出ることはなく、私たちを包んだ。
泉さんが言葉に出した疑問は私も感じたことだ。
周りを見渡しても、もう1人住んでいたとは到底思えない。
「時々帰って顔は合わせてたけど、ほとんど荷物取りにきてただけだったわ。それで失踪して自殺なんて言われちゃあね、なんだか他人事みたいだわ」
鼻で笑いながらそう言った女性は露出している肩をずり下がった服を持ち上げて隠した。
そして片手でたばこをもって、窓の外を眺めている。
あまりにも無関心すぎる。本当に、母親なんだろうか。
「なぜ、私のことを知っているんですか」
軽蔑の瞳をその女性に向けながら、私は口を開いた。その女性は窓に向けていた顔をこちらにむけてまた見下すように笑う。
「何言ってんのよ、あんた、あたしになんて言ったか覚えてないの?まだ中学のクソガキがえらそうに説教してきて」
中学生の時。そう言われ、私は過去をなんとか思い出してみる。普通に友達もいて、普通の学校生活を送っていた。そこに、満尾広菜さんがいたかが思い出せない。
顔を合わせれば話すような友達は思い出せるのに、学校の休み時間、放課後、休日は1人で過ごしたような記憶しかない。
記憶は確かにあるはずなのに、それが現実化されているものなのかすら怪しい。自分のことなのに、自分のことが分からない。
「こいつは、あなたになんて言ったんですか」
泉さんが私の代わりに女性にそう聞いた。
すると女性は「ふっ」とまた笑った。
「『あんたは広菜の母親じゃない、鬼め、あんたから広菜は何も教わらない。2度と広菜に母親という武器をふりかざすな』って」
その言葉を私が、この人にぶつけた。その真実を飲み込むにはまだ私は何も知らない。
まるで知らない人が放った言葉のような気さえしてしまう。
泉さんが、「なるほどな」と頷いて部屋を歩きまわりはじめた。
私はそんな泉さんを目で追いかけながら、戸惑いを隠すことなく母親に問いかけた。
「ひ、広菜さんが、家を出て何をしていたか知っていますか」
母親は、近くの灰皿にタバコを押し付け、ため息をついて再び窓の外に顔を向けた。
「体を売ってたわ」
心臓がひりつくような感覚だった。
合ってほしくない答え合わせのように、次々と丸がつけられていく。
「知っててなんでとめなかったんですか」
「とめたところで言うこと聞かないの分かってたし、あたしだってあの子くらいの時からそういう仕事してたわ」
「でも」
「遊び金欲しさに自分を売ってただけじゃない、別にいいでしょ、まあでも高校までいかせてやって売春して退学だなんてバカな子よ」
本当に、本当に満尾広菜さんはそんな浅はかな理由でそんなことをしたんだろうか。
美術部で、絵がうまくて、誰かがいじめられているのを助けるような、そんな子が。
「お金が必要な理由は、他にないんですか。誰かに脅されていたとか、そういう」
「知らないわよそんなの。それにもうあの子は死んだんだし知らなくてもいいことよね?
あたしが母親失格だからってあの子の自殺を私のせいにされても困るわ、勝手に失踪して勝手に死んだくせに」
込み上げる怒りを押さえ込むように拳をぎゅっと強く握る。こんなひどい母親を前にすれば確かに家を出たくなる、その気持ちは分かった気がした。
「…分かりました」
「なら早く帰ってちょうだい、もうあの子のことは忘れたいの」
じゃあ、あなたの広菜さんの記憶を少しでもいいからください。そう言いたかった。
「あなたが、最低な母親ってことは分かりました」
「その目つき、変わらないわね。あたしが最低な母親ってことは、勝手に死んだ広菜は最低な娘ね」
手を振り上げそうになったところで、その手を泉さんが掴んだ。
「っ」
「やめとけ」
振り解くように力を入れるが、泉さんは離さなかった。
「ちょっと来い」
そして引きずるように私を部屋の奥へと引っ張る泉さん。調べろと言われているのに感情的になったことを怒られるんだろうか。
だけど、ぐちゃぐちゃな感情の中でただあの母親を許せないという怒りが突出して今渦巻いている。
ゴミが散乱している中を泉さんが容赦なく進む。
「しゃがめ」
「は?なんで」
「いいから」
奥の部屋のものが積み重なっている角で泉さんが私の頭をつかみそのまま下にむりやり座らせた。
眉間に皺を寄せて泉さんを睨めば、泉さんは顎である場所を見るように促す。
顔を向ければ、物と物の間で倒れていたそれを視界に入れて私は思わず口を手で押さえた。
「こういう母親だ。分かろうとなんてしなくていい」
ーーー骨壷だった。
だがそれは倒れており少し色が変色した粉々の骨が散らばっている。
憎悪と怒りが限度を達し、私は呼吸が早くなる。
突きつけられた現実にみっともなく泣き喚きたくなった。
私はなんとか自分の感情を抑え込みながら、骨を壺の中に戻し壺を戻す。このまま持ち帰ろうと両手に抱えれば泉さんがそれを制した。
「すべて終わってからにしよう。今はダメだ」
泉さんのその言葉に私は持ち上げた骨壷を唇をかみしめて床に戻す。せめてもと周りの物を手で端に寄せていく。ここにいると、すぐに分かるように。絶対に迎えにくるから。
骨壷の近く、使い古しの化粧品やカバンの隙間に1枚の写真が挟まっておりゆっくりとそれを取り出した。
髪は黒髪で肩につかないくらい、片方の髪を耳にかけている。
幾分か幼い顔をしており、公園のブランコに座りカメラに笑顔を向けていた。
「泉さん、満尾広菜さんの顔がやっとみれました」
溢れた涙が、一枚の写真にぽたりと落ちた。