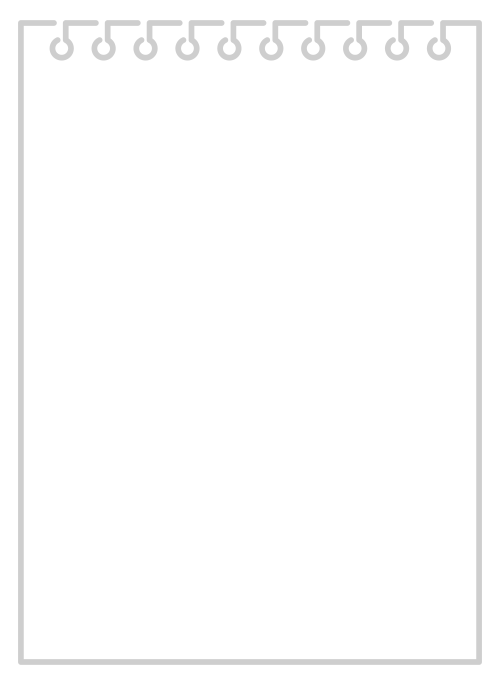着いたのは古いアパートだった。
泉さんが「2階だな」と呟いて、錆が目立つ鉄の階段を登っていく。
私も泉さんのあとを追った。満尾広菜さんは、ここに住んでいた。
彼女と友達だった私は失われた記憶の中でここにきたことはあるのだろうか。
「高橋によると、母親と2人暮らしだったらしいが」
2階の1番端にある扉の前まで行って、そこで泉さんが足を止めた。
そして私の方を振り返る。
「家庭環境はあまりよくなかったらしい」
「…そうだったんですね」
「まあ、自殺した娘をほったらかしてクラブに入り浸るような母親らしいからよ、ちゃんと話聞けるかは分かんねえけど」
「こっちには、お前っていう切り札あるし」とよく分からないことを呟いてインターフォンを鳴らした。
ごくりと唾を飲み込む。ひどい母親とはいえ1人の娘がいじめられて自殺したかもしれなくて、元凶が私かもしれないとすればどんな目に合うかは分からない。
もしかしたら『切り札』とはそういうことなのかもしれない。自分自身で正面から立ち向かえ、と。
これは、現実を受け入れるための答え合わせだ。
待っていても誰かが出てくる気配がなく、泉さんはイラついたようにもう一度インターホンを押した。
「泉さん、留守なんじゃ…」
「いや、いる」
「なんでそんなこと分かるんですか」
「勘だ」
そう言って、拳を握って数回扉にぶつけた。やや強めに叩いたため音が響き渡る。
「すみませーん、記者のものですが満尾広菜さんことでお聞きしたいことがございまして」
廊下に泉さんのそんな声が響き渡る。私は思わず泉さんの腕を掴んだ。
「い、泉さんっ、そんな大きい声ださなくても」
「大きい声で言わねえと聞こえねえだろうが、俺は母親引きずりだすまで帰らないからな」
この家の中に本当に人がいるかも怪しいのに誰か出てくるまでこれをやり続けるのかこの人。
「せめて声のボリューム落としてください」と言ったが、扉を叩く音でそれはかき消される。
しばらくして、中から鍵を開ける音が聞こえた。
「な、いるだろ」と泉さんが得意げに私の方を見る。どう考えても今はドヤ顔するところではないでしょう。
扉にチェーンをかけたまま少しの隙間があく。
怪訝な顔を隙間から覗かせたのは、私の母と同じ歳くらいだろうが化粧は濃く、母とは真逆な雰囲気の女性だった。真っ赤な唇が動いた。
「…誰ですか」
「以前も一度伺いました、記者の泉です。娘さんのことで」
「またあなたですか、何も話すことはないって言ったわよね」
泉さんって敬語使えるんだ。と、そんなことを思っている場合ではないことは分かっていたが、私の母にでさえ掴みかかっていた泉さんにしては少し意外だった。慣れないことをしているのに加え、拒否をされているからか口角のあたりがひくひくと痙攣しており、怒りを抑えられていないけれど。
「あれ、あんた」
女性の瞳が私に向いた。
「広菜とよく一緒にいたわね」
その言葉に目を見開く。
やっぱり、そうだったんだ。「よく一緒にいた」その言葉だけで、私と満尾広菜さんはただの知り合いではないということは嫌でも分かる。
私は泉さんの幾分か後ろにいたが、少しの隙間を閉じられないように一歩前に出て扉を手で掴む。
「詳しい話をききたいので、中に入れてくれませんか」