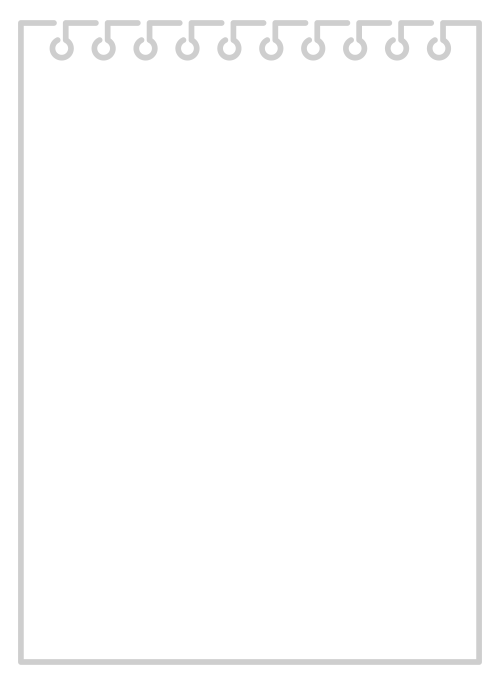耳を塞いだ私に、泉さんは立ち上がった。
そして静かに私の近くまでくると、私の胸ぐらをつかんで引き上げた。
「すぐる!」
慌てたように、高橋さんがとめに入るが泉さんはその手を反対の手で振り払う。
睨みつけるようなその瞳の中に私がうつった。
「てめえだけがつらいと思うなよ」
「っ」
「こっちは、妹が被害に遭ってて、誰かから殺されてるかもしれないって恐怖といつもいつも戦ってんだ。
お前と違って、俺は妹の記憶がしっかり残ってんだよ。
大切な人がずっと頭の中にいるつらさからしたら、忘れてるお前が羨ましくもなる」
泉さんの初めてみせた表情だった。ずっと強気で、私を脅してでも真実を知りたい人。
そんな人が、初めて泣きそうな顔をしていた。
私は何も言えなくなってしまった。
真実に目を向けたのは、私自身だ。
私が強く断っていれば、泉さんはそれ以上は追ってこなかったのかもしれない。今になってみればそう思う。
「もういいだろ、すぐる。手を離せ」
高橋さんがそう言って、泉さんの手を強く掴んだ。
泉さんは舌打ちをして、私から手を離す。
力なく、私は椅子に腰を下ろした。
「すみません」と何にたいしての謝罪かも分からない言葉が吐き出される。
自分が泣いていたことに気づき、手の甲で涙を拭った。
「なくなった記憶の中の私が、少しこわいんです」
「萌香ちゃん…」
高橋さんが泉さんを座るように促した後、心配そうな顔をして私を見つめる。
私は、へらりと笑ってみせた。
「もしかしたら、すべてを知っていたのかもしれないってそう思う時があって。
だから、私は自分で望んで記憶を消したんじゃないかって。泉さんの先程の話を聞いてますます、そう思いました」
記憶を失った時からずっと思っていた。記憶の中にある真実はろくなものじゃないと。
だから平凡に、楽しく過ごすことに無意識にこだわっていたのだと思う。
今だって逃げ出したい、もう何も無かったことにしたいって掴みかけた真実を前にするとどうしても考えてしまう。
そんな自分が嫌だ。
「お前がつらいなら逃げてもいいぞ。俺は実里を探し出すまで調べ続けるけどな。安心しろよ、お前のことは記事にはしねえから」
「…泉さん」
「ただ、都合の悪いことから目を背けて楽しく生きることがお前にとっての『楽』になるとも思えないけど」
そう言って、泉さんはハンカチを私に差し出した。
受け取れずにいると、「まあ」と言葉を続ける泉さん。
「続けるってんなら、お前の罪ごと一緒に背負って地獄に落ちてやるよ。巻き込んだの俺だし」
私は、ゆっくりと手を伸ばして差し出された青色のハンカチを受け取った。
正義のヒーローのような笑みではなかった。ゲームやアニメのラスボスのような不適な笑みを浮かべていた泉さん。私は頬を伝う涙をハンカチで拭いながら小さく笑う。
「何、魔王のプロポーズみたいなこと言ってんだよすぐる」
「はあ!?そういう意味じゃねえわ!」
慌てたように高橋さんに掴み掛かった泉さん。
私はそんな様子をクスクスと笑いながら眺める。
変な縁だとは思うけれど、巻き込んできたのがこの人で少しよかったとさえ思う。
この人でなければ、私は自分の記憶を調べることさえできずに逃げ続けていただろう。
「…私、明日カヨラと繋がりがあるかもしれない真由に話を聞いてきます」
じゃれあっている2人にそう言えば、彼らが顔を見合わせて高橋さんが鞄からUSBを取り出す。
「話をたたむまえに最後にもう一個あって」
高橋さんがそう言った矢先テーブルの上にあるパソコンを開いて、泉さんがUSBをさした。
「すぐるがさっき言った、警察さえも大きな力が働いているかもって話、あながち間違いじゃないかもしれないんだ」
高橋さんがそう言ったあと、泉さんがパソコンの画面をこちらに向けた。「俺はさっき見た」とぶっきらぼうにそう言う。
「これ、は」
「カヨラに多額の寄付をしてる人たちの名簿。萌香ちゃんには分からないかもしれないけど、どいつもこいつも大物ばっかりなんだよね」
画面に出されたそれを私は視界に入れる。
ずらりと縦に並んだ名前の数々。なぜ、そんな怪しい団体に多額の寄付なんてできるの。
見える範囲にはおさまっていないその名簿を画面をマウスでスクロールしてゆっくりと眺めていく。
ふと、私は動きを止めた。
「徳田 達彦…」
「あー、そいつ市議会議員だね。萌香ちゃん知ってる?」
私は断定できないその質問にぎこちなく頷く。
徳田サラは、何かを知っている。そのことは確実で、確か父は議員だという話を本人からきいた覚えがあった。
「娘が同じクラスで、この手紙に出てくる『サラ』と同一人物と思われます」
ーーー『ここまできたら、サラに頼むしかないんじゃないか、お前に残ってる手はそれだけだ、大丈夫、どうせ忘れるんだから』
もしかして、と顔を上げる。そんな私をみて泉さんが小さく頷く。
「この名簿のやつらが売春にかかわっていて、しかもその娘が斡旋してるとしたらこの手紙と満尾広菜のやっていたことの辻褄が合うよな」
「…規模でかすぎて、想像したくないんだけど」
高橋さんがテーブルの上に項垂れた。気持ちは分かる。これって私たちがどうこうできる問題なんだろうか。
そこまで考えて、私はふと満尾広菜さんのことが頭をよぎった。
彼女は失踪をした。記憶は消えていないかもしれない。
記憶が消えていない理由は、調べないと分からないけれど、1つ仮説をたてるとしたら
「満尾広菜さんは、この売春の仕組みを知って死んだ可能性はありませんか」
お金が必要だと、それなりに覚悟をきめてカヨラに入り売春をしていたのだとしたらそれに耐えきれなくなって死を選ぶとは思えない。
記憶がなくなるということより、もっとつらいこと。
「この名簿のことやカヨラの売春の闇を告発しようとしてた、とか」
彼女は、突きつけられた真実に嘆き、どうにかしようとしたけれどダメで、絶望した。
「金が必要って嘆いてたやつがそんなことするか?」
「でも、彼女の記憶は失われなかった。売春の記憶もすべて残ったままです。その中に、この名簿の人が紛れていたとしたら」
そこまで言った後、私のポケットに入っているスマホが揺れて思わず肩を上げる。
取り出して画面を見れば、『母』と表示されていた。
外を見れば日が落ちかけている。
「ひとまず憶測を真実にするには証拠が必要だよね
この多額の寄付をしている人たちはこうやって、調べたら出てくるようになってるけど、これだけで警察が動くとは思えない。もう少し調べよう」
高橋さんが、両手を叩いてそう言った。
私は電話を無視してポケットにスマホを戻す。
そして明日のことを考えた。
先に話すのは真由じゃない、
サラだ。