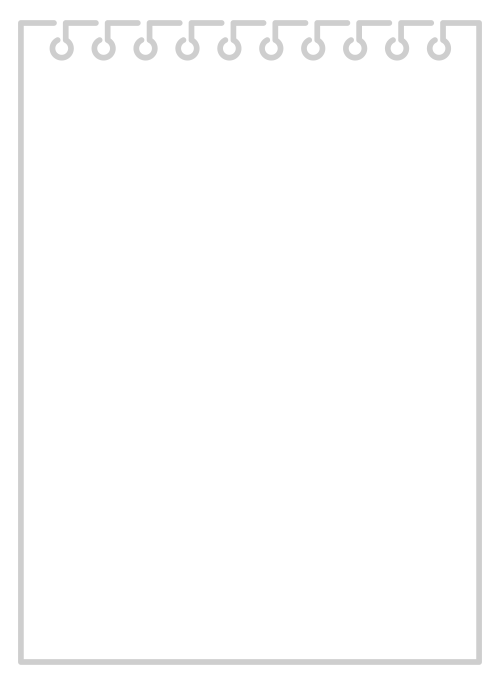一つのテーブルを囲んで3人座れば、泉さんが真ん中に閉じたままのパソコンをおいた。「で」と。
「『みつおひろな』については何か分かったか」
それについてもちろん答えるつもりではいたが、私は隣に座っている高橋さんへ瞳を向ける。
泉さんの知り合いの警察とはこの人のことなのかな。
泉さんと共有していたことに、警察とは言えど見ず知らずの人が介入してくることに少し気が引けていれば、高橋さんが苦笑いを浮かべた。
「すぐる、その前に俺のことちゃんと紹介しろよ」
「前に軽く説明したろ、知り合いの警察だ。妹の件で協力してくれてる」
最低限の情報に私が怪訝な表情を見せれば、泉さんは「なんだよ」と顔を顰めた。
「俺とすぐる、それからすぐるの妹の実里ちゃんは同じ施設で育ったんだ。だから幼馴染みたいなもんで」
「幼馴染…」
「今回の件、連続失踪のことだったり、みつおひろなさんのこと、警察として表立っては動けないのが事実なんだけど、すぐると一緒でやっぱりひっかかることはあるんだよね」
泉さんの言葉足らずに見かねたのか、高橋さんは困ったように笑ってそう言った。
落ち着いた男の人って感じで、泉さんとは真逆だ。
それに、同じ施設で育ったってことはこの2人にも色々あったのだろうか。
「実里ちゃんをなんとか探し出すこともそうだけど、君の記憶のことも俺は何か重要なことを握ってる気がするんだよね」
実里さんのことについては、犯行文のようなものだって送られてきているのに、高橋さんが個人的に動かないといけない理由が気になる。
どうにかして、送った犯人を見つけられないのかな。
「警察が表立って動けないというのは…」
「まず、失踪者の数」
「失踪者の数?」
「そう、この世の中失踪する人なんて数えきれないほどいて、事件性のあるものであれば警察も調べることができるんだけど、こっちが調べてるのは家出の意思を示したあとの失踪。
そんでもって、それが全部つながってるなんて思いもよらないわけ。
警察の見解は一種の流行りのようなものだって、片付けてる」
「そんな…」
「無情にも、家族からの行方不明届が出されることも少ないんだ」
「なんでですか?」
「そういう家庭環境の子が失踪することはよくある」
冷たく聞こえたその言葉。
では、満尾広菜さんもそういうことだったんだろうか。お金が必要で売春に手を出すほど困窮していた。
それで失踪して、未来に希望を抱けずに自殺をしたという憶測で満尾広菜さんの件は片付けられた可能性が高い。
だとすると、泉さんの妹、実里さんの件は話が違ってくる。
「でも、実里さんは自分の意思で失踪したとはいえ、犯行文のようなものが送られてきてますよね。十分事件性があると思いますが」
「そうだよね、なんだけどさ、こいつが」
高橋さんが親指で向けた先には、眉間に皺を寄せて黙って話を聞いていた泉さんがいる。
「警察にも大きい力が働いてるとしたらこの件は容赦なく潰されるだろ、自分で動いた方がましだ」
「って、言うからさ」
苦笑いでそう言った高橋さん。
私は、「そう、ですか」と歯切れ悪く返事をした。
すると、泉さんがせかすように指先でテーブルを鳴らした。
「みつおひろなのこと、分かったことをはやく聞かせろ」
そう言われ、私は少し口がごもって拙い返事をした。
そして小さく息を吐いて、口を開いた。
「私と同じ学年で、2年に進級してすぐ学校を辞めたそうです。それと」
膝の上で、拳をぎゅっと握った。
言ってしまえば、本格的に私の記憶の中の真実が動き始める。なんとなく、そう思った。
「私の思い出せない友達は、『満尾広菜』さんで間違いないと思います」
その言葉に、泉さんの目が大きく開かれた。
そして「そうか」と小さな声で返事をする。なんと声をかけていいのか分からない、というような顔をしていた。この人にもそういう情けみたいな気持ちがあったんだ。
私は、自分の中の確立されつつある真実を他人事のように話し始めた。
「満尾広菜さんには、ある噂があったそうです」
「噂?」と泉さんと高橋さんが首を傾げる。
「売春を、していたという噂です」
泉さんと高橋さんは、静かに顔を見合わせた。
そしてしばらくの沈黙が走ったあと、私は気まずさを誤魔化すように言葉を続けた。
「私は、友達のそんな秘密を知っていたのかどうかさえ思い出せないんです」
みっともなく声は掠れた。
私は知っていて、知った上でどんな言葉を彼女にぶつけていたのだろう、とこわくなる。
「萌香ちゃん」と高橋さんが私を呼んだ
「この前、すぐるから渡されたこれ、調べたんだ」
テーブルの上に出された手紙と私のノート。
私はぱっと顔を上げて、高橋さんを見つめる。
「この手紙は、どちらも萌香ちゃんじゃない」
吐き出された息は震えていた。
ーーー『…お金がいる、そのためには、何をしたらいい、分からない、何も、私には分からない』
ーーー『ここまできたら、サラに頼むしかないんじゃないか、お前に残ってる手はそれだけだ、大丈夫、どうせ忘れるんだから』
安堵した。
でも、それはすぐに不安に変わる。
では、誰が。
お金がいる、と嘆いているのが満尾広菜さんだとして、この返事は誰が書いたものなのだろう。
そこまで考えて、私はなぜか写真にうつる真由が脳裏をよぎった。
彼女は前に、あまり字が綺麗ではないと言っていた。
そして、お世辞にもこの殴り書きのような返事の手紙が綺麗な字とは言い切れなかった。
「それにお前、前に思い出せない友達に失踪する前その意思を伝えていたかもしれないって言っただろ、それも時系列的には不可能だ」
泉さんが静かな口調でそう言う。
私は、「え」と困惑の声をもらした。
泉さんは、頬杖をついて言葉を続ける。
「みつおひろなは、お前が失踪する前には死んでる」
「え?ど、どういう」
「川に死体が浮かんだのが、お前が失踪して記憶抜け落ちて帰ってきた後だったって話」
高橋さんの方をみれば、高橋さんが言葉を付け加えた。
「死亡推定が、君が失踪するちょっと前の5月15日。そして、川で見つかったのが君が帰ってきた後ってことだよ。
死亡解剖や周りの状況からみて、橋から飛び降りた自殺なのは変わりないから、君が殺したとかそういう疑いは自分の中から取り除いて」
そう言われても、拭いきれなかった。
湧き上がる黒いモヤのようなものが、自分の体を締め付けていくような感覚だった。
恐怖をなんとか抑え込むように唇を噛み締める。
「萌香ちゃん、つらいのは分かるんだけど、話を進めよう。真実を調べたいんだろう」
高橋さんはそう言って、テーブルの上に何かを置いた。私は、何度か息を短く吸って、吐いてを繰り返した後それを視界に入れた。
「これ…」
「君たちが、調べようとしてる『カヨラ』のパンフレット」
そう言った瞬間、泉さんがそれを奪い取り一枚一枚めくり始める。
表紙には若い男の人が写っており、空に手を広げている。右手首には薄紫のチェーンブレスレットが光っている。
「このパンフレット、あまり出回ってないらしいんだけど、この宗教団体のやり口なんだろうね、人から人へ紹介する時、その中でもこの人なら確実に入信するって場合にパンフレットが渡されるらしい」
「…おまえ、そんなのどこで調べたんだ」
「まあ、色々裏からね」
意味あるげな笑みを浮かべた高橋さんに、泉さんが小さな舌打ちをした。
そしてしばらく泉さんがそのパンフレットを眺めていると、あるページで動きを止める。
「おい、これみろ」
テーブルの上に再度開かれたそれに、私と高橋さんが覗き込む。
視界に入れた瞬間、心臓が嫌な音を立てる。
知りたくない、真実。
「新しい自分になるために、記憶を消したいあなた
闇の現世から楽しい『記憶』へ」
高橋さんが静かにそれを読み上げる。
その文面の下には、あらゆる説明や信者のインタビューなどがのっているが到底読む気にはなれず私はあげていた腰を椅子に戻した。
「きこえは良いが、やっぱうさんくせぇな『過去のトラウマやPTSDを改善するために存在する画期的な記憶療法』だってよ」
「実際に例ものってるね
『性的被害を受けた女性で社会復帰が難しくなったが、記憶を消し、楽しい記憶で塗り替えたことで働けるようになった』
とか」
泉さんと高橋さんの会話を耳に入れながら、私は自分自身のことについて考えた。
私は、ここで、何か記憶をいじられたのではないのだろうか。
でも、なんで?まさか、満尾広菜さんのことを記憶から消したかったから?
「なあ」
と、泉さんが私の方を向いた。
静かにパンフレットを閉じて、言うのを躊躇うように静かに息を吐いた。
「俺が考えたこのことが、憶測じゃなくて、事実なら、今すぐとっつかまえてこいつら全員、牢屋にぶちこんで欲しいんだが」
ごくりと、泉さんは唾を飲み込む。
「この宗教団体、女に売春させてないよな」
何も言えなくなった私に、高橋さんが「どういうことだよ、すぐる」と泉さんを問い詰める。
「記憶、いくらでも消せるんだろ、だったらそれ利用して売春でもなんでも好き勝手できるんじゃねえのか」
泉さんは、テーブルの上に置かれている手紙を再び引っ張り出して荒々しく私たちに見せた。
「みろ、これ」
ーーー『ここまできたら、サラに頼むしかないんじゃないか、お前に残ってる手はそれだけだ、大丈夫、どうせ忘れるんだから』
「ここに書かれている『お前』はみつおひろなで、みつおひろなは売春をしてたかもしれなくて、
そんで、『どうせ忘れるんだから』って」
ぞっとした。
だとしたら、この手紙に名前が出されているサラは。
「だがみつおひろなは、何かあって記憶がなくならなかったんじゃねえのか」
「っ、泉さん」
「記憶がなくならないってことは、記憶はこびりついて離れない。本人にとってそれは地獄。だから、みつおひろなは」
ーーー自殺した。
「泉さんっ!」
バン、とテーブルの上を手のひらで叩けば、その場が静まり返る。ここまできいても何の記憶も思い出せない。友達が、自殺してその原因の仮説を立てられて、それが真実かもしれなくて。
もう、聞きたくなかった。
「もうやめてよ…知りたくない」