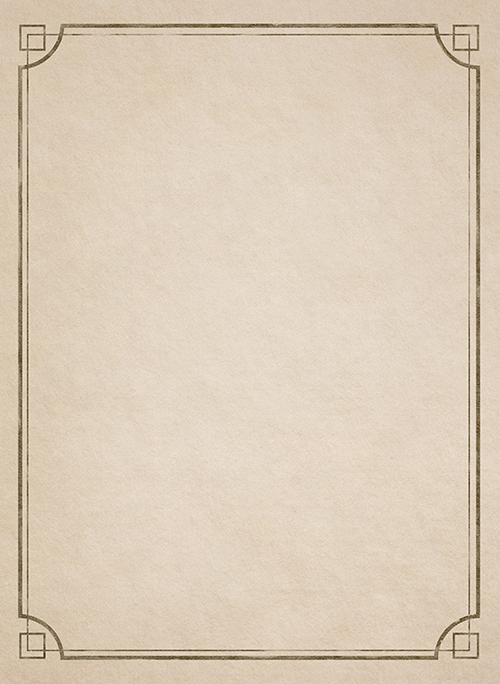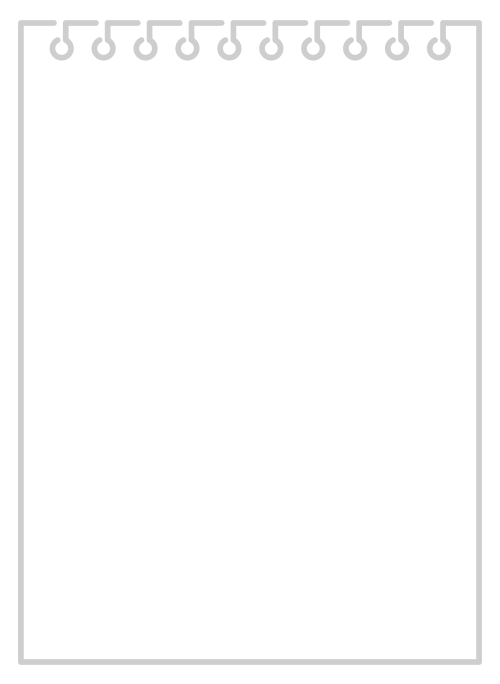静かな空間。
目の前には、ジェンガやトランプ、画用紙などが広げられている。
置かれたホットココアから湯気が出て揺れている。
「自分の記憶を調べてる?」
「はい」
以前まで記憶を思い出したくないと言っていた私の変わりように久松先生はやや渋い顔をした。それはそうだろう、ここに来たくなかった理由だって記憶を思い出したくなかったからなのに。
無理して思い出さなくていい、気持ちが穏やかになるように、前に進めるようにここに来ればいいと何度も久松先生は言ってくれていた。
「前に進むために、調べる必要があると思うんです」
「なるほどねえ、でも思い出すっていうより調べるって感じなのね。それはなんで?」
「思い出せる気がしないからです」
久松先生は少し考えるように瞳を落とした。
指先で積み重なっているジェンガの1つを弾く。
少し揺れたそれは倒れることはなく、綺麗な形を保って私と久松先生の間に立っていた。
「思い出せる気がしないっていうのは、どうして?」
1番安全だと思う、ジェンガの真ん中をひとつ、私は抜き取って上に重ねた。
「なんとなく、そう思うから」
私の小さな声を拾い上げた久松先生が、「そうなのね」と穏やかな笑みを浮かべる。
久松先生はいつもそう。取り乱したり、人の感情に振り回されたりしない。それは久松先生が先生の立場だからなのか、元々こういう人だからなのか。
人にたいして怒ることなどあるのだろうか。
「久松先生は、人の記憶を人工的に消したりできるって思いますか」
「人工的に…?」
久松先生は、少しの沈黙のあと机の上で両手を組んだ。そして『記憶ねえ』と小さく呟く。
「できないことは、ないと思うわ」
『できる』とはっきり言わないのは、私を不安な気持ちにさせないためなんだろう、この人はそういう人だ。久松先生は、少し困ったように笑う。
「それに、記憶が消えるってこと私はそんなに悪いことじゃないと思ってる」
「え…?」
「だって、多かれ少なかれその記憶の中には辛くて苦しいものだってあるでしょう?」
そう問われ、頷いてしまった。
そう思っていたからこそ私は思い出したくないと思っていた。
「萌香ちゃんが自分の記憶を調べたいって思ったのなら調べるべきだけど私の個人的な意見としては」
久松先生が私をまっすぐ見つめた。
「過去を振り返ったって前には進めない」
「っ」
「そう思うわ」
久松先生は、ジェンガがなんとか保たれている1つの軸を動かした。
それによって、それは音を立てて崩れる。
肩をあげた私に、久松先生は「あらごめんなさい、倒しちゃった」と笑った。
「楽しい思い出をこれから先作っていくために、萌香ちゃんはここに来てほしいなって思うけど、調べて何か分かったのなら先生にも共有してほしいな。もちろん詳しいことはきかないから。
萌香ちゃんの力になりたいの」
ふと、原島先輩の言葉を思い出した。
ーーー『大事なこと思い出した時は僕にも教えてね』
聞こえは違うけれど、久松先生が言いたいことはそういうことだ。でも、なんで。
私はそう思いながらも、「はい」と久松先生の言葉に頷く。
「ココアぬるくなっちゃったわね、温めてこようか」
「すみません、お願いします」
久松先生はにこやかに立ち上がって、カウンセリング室の奥の部屋へと入っていった。
倒れたジェンガを端に寄せていれば、ふと先生が毎回書いているカルテに目がいく。
奥の部屋はガラス越しにこちらが見えるようになっているが、久松先生は電子レンジの方に体を向けているため、背中姿しかみえない。
私はおそるおそるカルテに手を伸ばして、自分の方へと引き寄せた。
筆記体のような字で、何かを書いているが読み取れない。
上には日付がかいており、ノートのようにまとめられている。
指先で数ページめくった。日付がどんどん若くなっていく。
「…ん?」
1番古いページに近くなったページをみて、手を止めた。もちろん文面はなんて書いてあるかなんて分からない。疑問なのは日付だ。
私がここに来始めたのは失踪後の6月下旬。
そこに書いてある日付は、5月の初旬であった。
つまり、失踪前にここに来ている。
そんな記憶、ないけど。
と、数枚めくって1番古いページを広げた。
ーーー4月29日。
原島先輩の言葉が再びよぎる。
ーーー『2年にあがってすぐに辞めたから、進級してないようなもんだろうけど』
満尾広菜さんは、あの言い方だと4月ぐらいには学校をやめていることになる。
私が失踪前にここに来ていたということと、満尾広菜さんのことは何か関係がある?
「お待たせ」
急いでカルテをもとあった場所へ戻し、取り繕うように笑った。
「ありがとうございます」
もう、分からないことだらけだ。