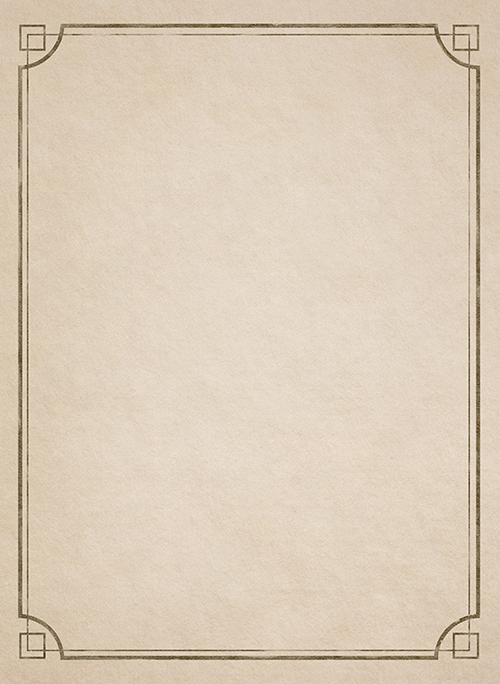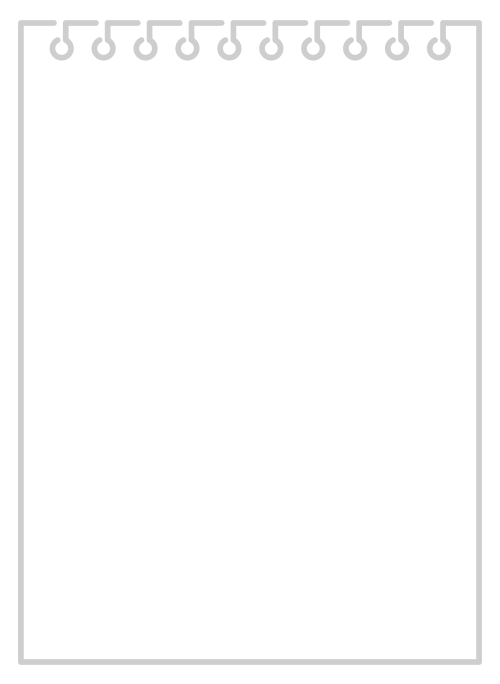「売春、してたって」
聞こえたその言葉に体が硬直する。
満尾広菜さんが『売春』をしていた。
その噂が本当だとしたら、ロッカーに入っていた手紙のやりとりの中のこともなんとなく辻褄は合う。
『お金がいる、そのためには、何をしたらいい、分からない、何も、私には分からない』
あれが満尾広菜さんのものだとしたら、お金が必要で売春に手を出した…?
そして、その返事を書いたのが私だとして『サラに頼むしかない』と言っていたということは、サラはやっぱり何かを知っていて、私はそれを黙認していたということだ。
ーーー私は、そういう人間だったのかもしれない。
湧き上がる自分自身への憎悪みたいなものが私を包んでいく。
「ま、誰も彼女のことを話さないのはそういう子だったからっていうのもあるんじゃないの。学校的にも彼女の存在を抹消した方がイメージ的にも、ね」
「…原島先輩は満尾広菜さんとは面識がありますか」
「美術室で一度」
「美術室?」
「満尾さんは美術部で、絵もかなり上手かったよ。黙々と1人で描いてるのをみて、一度声をかけたんだ」
原島先輩は目を上に向けて、当時なんて話しかけて、どんな会話をしたのか思い出すように言葉をゆっくりと続ける。
「綺麗な絵だねって声をかけた。その時は、2人の少女が公園で遊んでいるような絵だったかな」
私は、自分のスマホを取り出して写真のフォルダからある一枚を原島先輩にみせる。
「これですか?」
原島先輩はそれをしばらく眺めて頷く。
やっぱり、あのロッカーは満尾広菜さんもつかっていた。
それに晴美は同じ美術部だ。
「満尾広菜さんはなんて答えてましたか」
「『過去を、忘れないように描いてるんだ』って言ってたよ」
ーーー過去を、忘れないように。
満尾広菜さんはどういう意図でそれを言ったのだろう。
「まあ、正直見た目も真面目そうだったし、売春に手を出す子とは思えなかったけどね、お金がどうしても必要なら話は別だけど。
もう聞きたいことはない?」
「えっと、満尾広菜さんの髪型って」
「うーん、どうだったかな、髪はこのくらいで片方耳にかけてたかも」
肩につかないくらいで止められた原島先輩の手。
それは以前暴力に合っていた先輩を助けた際にきいた、私と一緒にいたかもしれない友達の特徴と一致していた。
満尾広菜さんは、やっぱり、私と一緒にいたんだ。
だとしたら、泉さんの言うとおり私の友達は死んでいることになる。
思い出せない悔しさと、何もできない不甲斐なさでみっともなく泣きそうになった。せめて、何があったのか突き止めないと。
ふと、原島先輩の右手から、手の甲、腕へと視線を向ければ、腕に傷の跡があるのに気づいた。
少し深い傷なのだろうか、跡がくっきりと残っている。
「…その傷は?」
原島先輩は自分の腕を視界に入れて、反対の手で覆った。そして、へらりと笑う。
「ちょっとした事故だよ」
「たいしたことじゃない」と言って、腕を下におろす。
私は、「そうですか」と静かに返事をして息を吐いた。感情のままに動くのはよくない。
調べて、真実を突き止める。
「ありがとうございました、では」
校舎の中に入っていこうと原島先輩に背中を向けたが、「待って」と少しの挑発を含んだ声色が後ろから聞こえて足を止める。
振り返った私に、原島先輩は傷がある方の手を軽く上げてゆらゆらと揺らす。
「大事なこと思い出した時は僕にも教えてね」