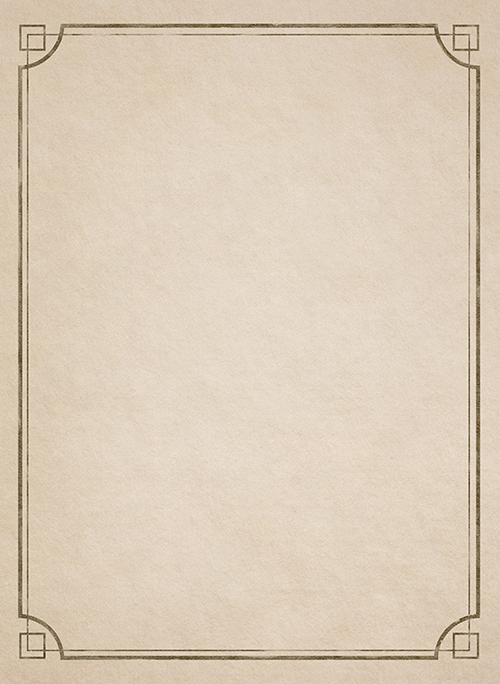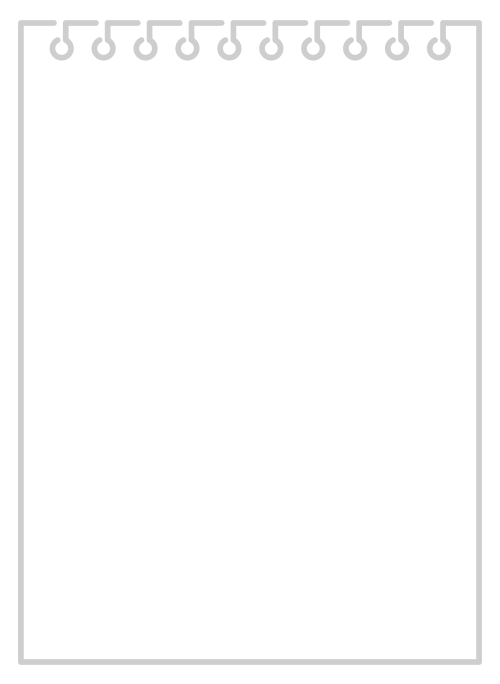「おはよう」
学校の門を潜った時、駆け足で私の隣に並んだその人。私は、「うわ」と声に出して嫌な感情を隠すことなく小さな声で「おはようございます」と返した。
「いやーな感じだね、僕のこと嫌いでしょう」
「はい」
「即答なんだ」
「はは」と軽く笑って、少し飛び跳ねるようにして歩いたあと私の正面に立ったその人、原島先輩は私に手を伸ばす。足を止めざるを得ない状況になり、私は眉間に皺をよせた。
「くま、すごいね」
「人の目元を引き気味に触らないでください」
嫌な人。
その手を払って、再び歩き始めれば原島先輩はまた笑いながら私の横に並ぶ。
「記憶の方はどう?何か思い出した?」
「いえ」
「そっかあ、本当に何も思い出してないの?」
探るように問いかける原島先輩。
私の記憶に何があるのか、知っているようなそんな口ぶり。前に晴美が私にきいたようなことと同じ感じだ。
「…何か知ってるなら教えてください」
「『今』を生きてるから、別に知りたくないんじゃなかったっけ?」
「考えが変わったんです」
「へえ」
シニカルな笑みを浮かべた原島先輩は、遊ばせるようにスクール鞄を揺らす。受験生なのに軽そうだな、なんて思っていれば、私の考えていたことが伝わったのか
「僕、頭いいから推薦で大学行けるんだよね」
「そっ、そんなこと、誰も聞いてないです」
「まあ、親のコネもあるけど」
と嫌味ったらしく声色を変えてそう言った原島先輩。
ため息をついて足を止めた。
靴箱の場所は学年で校舎が分かれており、原島先輩の学年はひとつ隣の校舎へと行かなければならない。
原島先輩の方へ向き直ると原島先輩は「ん?」と首を傾げる。
「聞きたいことが、3つあります」
「結構多いね」
靴箱の人通りが少ない端の方へ寄って、私は3本の指を立てる。
「いいよ、答えられるかは分かんないけどきいてみたら?」と挑発するように身を屈ませた原島先輩。
人差し指をおろした。
「ひとつ目は、この前言っていた『記憶』のことです。人工的に消せたり、改ざんできるというのは本当ですか?」
「本当だよ」
「それが、私が今記憶をなくしていることと関係している可能性は?」
「うん、まあ、あるんじゃない?」
なんとも煮え切らない返事にむっとしながら私は2本目の指をおろした。
「カヨラって団体を知っていますか?」
原島先輩の表情が少し変わった。
目を細めて、原島先輩が頷いた。
「…知ってるけど」
「ホームページを見たところ、『記憶』というページに飛べるようになっています。この団体が失踪のことや記憶のことについて関与してるって可能性は?」
畳み掛けるようにそう言った私に、原島先輩は「うーん」と考え込むように少し唸って顎に手を添える。
「どうだろう、前も言ったけど僕は人の『記憶』にしか興味はないんだよね。
その団体が失踪者を匿って記憶をどうこうってこともあり得なくはないけど、全失踪者がここに入ってたらパンクするでしょ、そんでもって警察も黙ってないだろうし」
「では、なぜカヨラを知ってるんですか?」
「それはお友達に聞いたら?」
「誰のことですか」
「さあ?君にとっての友達って誰なんだろうね」
私にとっての友達。
サラや、真由、晴美、そして思い出せない誰か。
やっぱり、何か知っていてそれゆえに私をからかっているのか、本当に記憶の構造にしか興味がなくて意味のない煽りをしているのか、分からない。
だけど、調べるためにはこの人を協力させるしかない。
3番目の指を下ろす。
「…みつおひろなという人を知っていますか」
原島先輩の瞳が大きく開いた。
そして少し泳いだ瞳が、私を見つめる。
「知ってるよ」
想像していなかった。この学校に知っている人がいる。やっぱり、みつおひろなさんはこの学校にいたのかも。
「どんな人でした?この学校にいたんですよね?漢字はどのように書きますか?学年は?女子であってます?私との面識は?」
「うるさいなあ、近い」
苦笑いを浮かべた原島先輩が、私の額を軽くおして近づいた距離を少し離す。そしてスマホのメモのアプリを開いて『満尾広菜』と書いて私に見せた。
「満尾 広菜さんでしょ、君が失踪する少し前に学校を辞めてる。学年は君と一緒で2年。
つったって、2年にあがってすぐに辞めたから、進級してないようなもんだろうけど」
「学年違うのに、よくそんなこと覚えてますね」
「そりゃあね、色々噂が飛び交ってたし」
噂?と首を傾げる。
3年の原島先輩が知っているのに、サラたちが知らないわけがない。
なんで、彼女たちは嘘をついているんだろう。
「噂ってなんですか」
そう問えば、原島先輩は私の耳元に顔を寄せた。