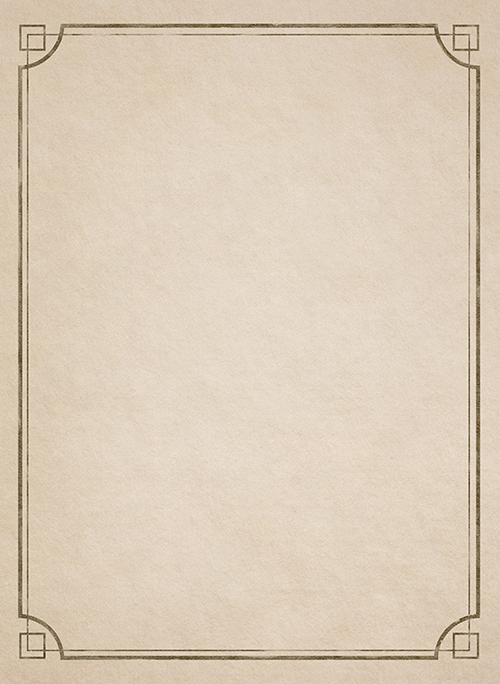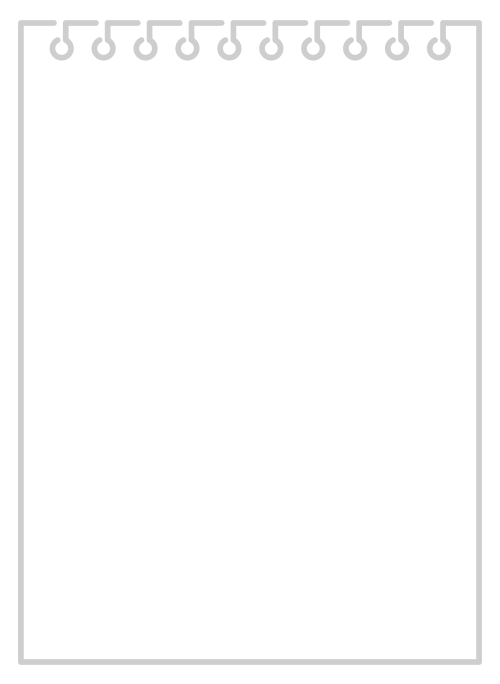笑いを堪えるように顔を背けた泉さんを睨んで言葉を続ける。
「片方がみつおひろなさんだとすると、私とみつおひろなさんは繋がることになります」
泉さんは、私の名前とみつおひろなさんを線で繋いだ。
「そして、これを見てください」
「なんだ」
「手紙の一部です」
ーーー『ここまできたら、サラに頼むしかないんじゃないか、お前に残ってる手はそれだけだ、大丈夫、どうせ忘れるんだから』
泉さんが顔を顰めた。そしてその文の気になるところに人差し指を向ける。
「サラっつーのは」
「友達。おそらく何かを隠してる1人です」
「なるほどな」
そう言って、私の名前と友達を線で繋げた。
そしてもう一度それをまじまじと見つめた。
「この手紙自体をお前のだと仮定して、『お前』と言っている相手は、みつおひろなか」
だとしたら、私はみつおひろなさんを脅していることになる。
気にしないように切り替えるつもりだったけど、心臓が大きく音をたて、向き合いたくないものに向き合わされている時間だと感じてしまう。
振り切るように私は、「そうですね」と返事をした。
「ま、違和感は感じるけどな、字は似てるにしろ、口調が男っぽい」
「失ってる記憶の中の私は、そういう一面があったのかもしれないですよ」
「…あんまりピンとこねえな」
私もですよ。私自身のことなのに、何も分からないんだから。
これが私が書いたものだと証明するにはどうしたらいいんだろう。
しばらく考えて、私は顔を上げた。
「知り合いに警察がいると言っていませんでしたか」
泉さんは何が言いたいのかと顔顰めたあと、気づいたように「あ」と声をもらした。
「筆跡鑑定か」
「はい。正直自分自身でもよく分からないので」
失った記憶の中の自分が、どんな人間だったのかも分からない。思い出すのではなく、調べるために必要なことだと思った。
鞄の中から授業で使っているノートを泉さんの前に差し出す。
「お願いします」
「…分かった。聞いてはみるが期待はすんなよ」
泉さんはそう言って、手紙と差し出したノートを受け取った。
「あとは、俺が前に言った失踪者の共通点だ」
「共通点?」
「俺が調べたかぎり、全員失踪前に家出の意思を誰かに伝えていた、俺の妹もだ」
「はい…」
「お前、どうなんだ」
そう言われ、私は俯いて膝の上で拳を握った。何もなかったと両親からきいているし、サラたちも何も前触れなく私が消えたことに困惑していた。
他に伝えるとしたら、誰に。
「その、思い出せない友達には話していたのかもしれません」
「…振り出しに戻ったな。ひとまず、みつおひろながその友達かどうかを調べるべきか」
「そうですね」と返事をして、私はテーブルの上に転がっているペンを手にとって泉さんが書いた紙を自分の方に引き寄せた。
「あと、おそらく繋がりの中心に何かがあると思っています」
「中心?」
「すべてを繋ぐ、出来事やきっかけ、もしくは失踪者が同じ目的で失踪をしているという可能性です」
円になっている言葉たちの中心に私は『?』を書いて丸で囲んだ。
「だとすると、これもその中心に潜む誰かから送られてきてるってことか」
泉さんが取り出したのは、以前見せてくれた犯行文のようなものだった。そしてそれを取り出した泉さんは怒りを沈めるように息を吐いた。黒い文字、手書きで書かれているそれ。泉さんは悔しそうに紙の端をぐしゃりと掴む。
「正直、無謀なことしてるって自分でも分かってる」
「…泉さん」
「失踪者を調べても調べても、何もでてこねえんだ
妹は、誰かに殺されたかもしれないのに」
そう言って、感情を押し殺すように低い声で「くそ」と呟いた泉さん。
犯行文の一部を視界に入れる。『陽炎に、眠る』
陽炎の中で眠っているということは、私の夢の中にでてくるあの少女のようにだろうか。
これを送った人は、一体なんの目的で?
ふと、テーブルの上にある写真に目がいく。真由と誰かが話している写真だ。
それを手にとった。
あのロッカーの中にあるものは、晴美の隠したい何かが全て詰まっているものと仮定して、この写真は私の記憶と何か繋がっているということになる。
真由の正面に座っている女性、その手には封筒が握られていた。
私は、「泉さん!」とその写真を泉さんの前に差し出した。
「これ、見て欲しいです!」
「なんだよ」
「友達の真由が映っているものなのですが、真由じゃない方のこの人が持っている封筒」
それは、先ほど道端で会った女性が持っていたものと似ていた。
封筒の1番下の部分に青色のバラのようなものが描かれており、その上に文字が書いてある。
あの時、「カ」しか見えなかった。
「カ、ヨ、ラ、って書いてます」
「あ?」
「さっき、私が道端で会った女性もおそらく同じ封筒を持ってて、娘さんがいなくなったと言っていました。
男性にそれをつきつけて『娘を返して』と泣いていたんです、その男性は『僕たちは、人助けをしている』って。
娘さんが、この繋がりに関係あるとしたら」
泉さんは少し考え込むように目を落とし「カヨラ、か」と呟いた後自らのスマホを取り出して何かを調べ出した。
しばらく黙り込んで画面を見つめた泉さん。
おそらく、『カヨラ』を調べているのだろう。聞き馴染みのないその言葉に私は嫌な予感がして唾を飲み込んだ。
画面から顔を上げた泉さんは、ニヤリと笑った。
そして息を吸って、吐き出すのと同時に言葉を放った。
「つながったかもな」