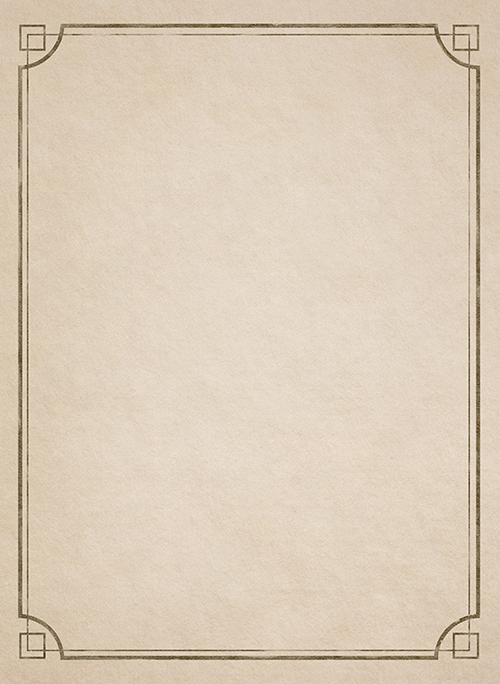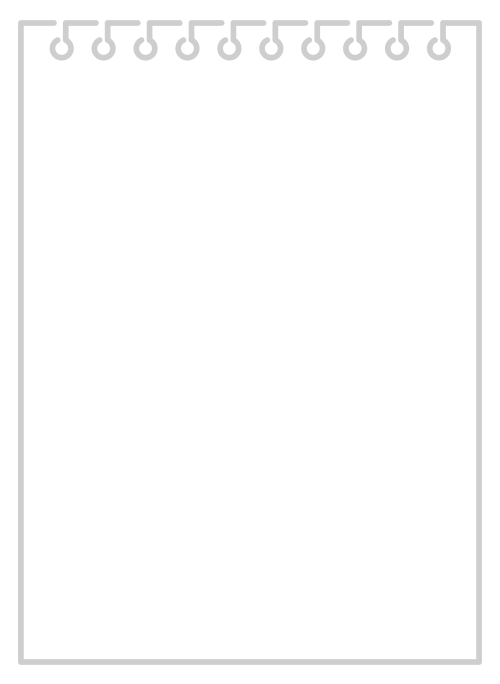場所を変えてやってきたのは、最初に泉さんに強制的に連れてこられたファミレスだった。
あの時の恐怖を少し思い出して私はため息をついた。
感情を読み取ったのか、泉さんが苦笑いを浮かべる。
「あの時は悪かった、何度も言うが俺も必死なんだよ」
「…はい、分かってます」
「なんだよその顔。ほんとに悪いと思ってるって、ほら、今日はなんか頼めや」
メニューを私の前に荒々しく置いた泉さんを少し睨んだあと、私はメニューを視界に入れる。
だけど、心の中を渦巻く葛藤やモヤモヤをはやく吐き出したい気分だった。到底何かを食べる気分ではない。
メニューを端においやり、鞄をテーブルの上に置く。
「先に本題に入りましょう」
「んだよ、俺腹減ってんだけど」
泉さんの言葉を無視して、私は鞄を逆さまにした。
泉さんの顔がぎょっとしているが知ったことか。
テーブルの上に広がった、絵、手紙、そして1枚の写真がその上にひらひらと乗る。
「なんだこれ」
「まず、みつおひろなさんのことはまだよく分かっていませんが、同級生は知らないと。たぶん」
「…たぶんってどういうことだ」
「存在を隠している可能性があるってことです」
「学校の奴らもグルってことか?」
「…それは、分かりません。本当にみつおひろなさんがいたかっていうのも怪しいですし」
「俺を疑ってんのか」
「私を動かすために嘘をついている可能性はあるでしょ」
「殺すぞ、まじで」
取り出されたナイフの先端が私に向く。
この人は、おそらくこういう人なんだろうと理解はしている。だからこそ本気じゃないことは分かっていた。私は向けられたナイフを握りしめた。
「っ、おい」
「私は、なぜ今自分が『あなた』のためにこんなに動いているのか分からなくなる時があります」
手のひらから伝った血が、散らばっている紙に一雫の模様をつくる。
「私は、自分の記憶を知るのがこわい、知りたくないのに、今、人のために自分の記憶を探ってるんです」
「っ」
「『あなた』のために」
正義ぶるつもりなんてなかった。だけど、泉さんがいった人のために自分を探るには、この人をなんとかして信じないといけないと、そう思った。
「あなたに、できる限りの記憶を差し出しますが、あなたも私に嘘はつかないと約束してください」
「っ、分かったから離せ」
ナイフを離せばテーブルの上にナイフが転がる。泉さんはそれを拾い上げるより先に端にあったナプキンを束で掴み取り、私の手のひらに強くあてた。
「アホだろお前、まじで、何考えてんだよ」
「だって泉さん、すぐに脅すから…」
「脅し返してくんなよ、傷残ったらどうすんだよ」
「こんな程度じゃ残りませんよ」
もっと、深く切らないとって。
なんで、そんなこと。
泉さんに掴まれている反対の手を見つめる。なぜか手首を視界に入れる。何もない。
あたりまえじゃない、私はそんなことしないのに。
「なんで俺がこんなことしなきゃなんねえんだよ、めんどくせえな」
顔を上げれば、泉さんは私の傷口をおさえながら少し慌てていた。
困惑している様子が最初抱いていたイメージと違ってなんだか笑えた。