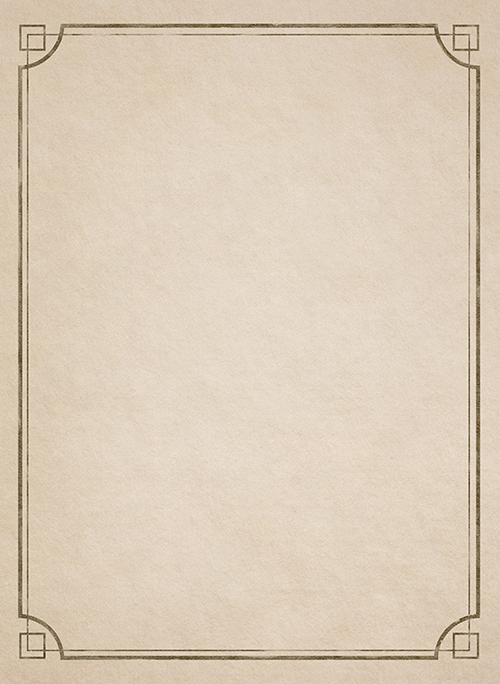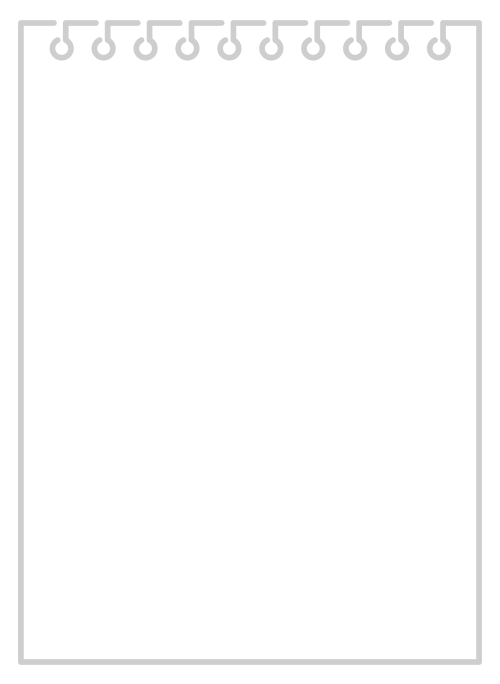「授業サボってる子みっけ」
そんな声がきこえて、私は振り返る。
「原島、先輩」
「お、名前覚えててくれたんだ。嬉しいね」
そう言って仮面のような笑みを浮かべたその人に私は警戒心を隠すことなく一歩足を後ろに下げた。
その分原島先輩は距離を縮めるように私に近づく。
「もしかしてまだ警戒してる?」
「そう思うなら、近づかないで下さい」
「ひどいなあ、俺は君の役にたてると思うんだけど」
やっぱり、この人は何か知っているかもしれない。
離れようとしていた足を止めた。
原島先輩は私の前に立って、試すように私に手を差し出した。
「場所を変えようか」
人目のつかない場所を慣れたように歩く原島先輩の後ろを私は着いていく。
知りたくない。知りたい。
ーーーやっぱり、知りたくない。
足が自然と歩みを止めようとしていた。
知って、どうなるっていうんだろう。
何か良くないことが起こるんじゃないだろうか。
もし、私の隣に誰かがいたとして、じゃあその子は一体誰で、どこで、何をしているんだろう。
陽炎の中で必死にもがいている夢の中の少女は、いつも苦しそうだ。
願うは、彼女ではないこと。誰も、傷ついていませんように。
誰も傷つかない方法を考えてみれば、いま私がやっていることではない気がする。結局消えたものを取り戻したところで…。
「立見さん」
「っ」
歩みを遅くした私に合わせて、幾分か先をいく原島先輩も後ろに手を組んでゆっくりと歩いていた。
優しく問いかけるように私の名を呼んだ。
でも、私の方は振り返らない。
「記憶なんて、結局人間のエゴでできてる」
「えっ…?」
「人はつらいことがあると記憶を都合よく書き換えたり、忘れたりして自分を守ってるんだよ」
ガラリと戸を開けて、私の方に振り向いた原島先輩が中に入るように促す。
私は言われるがままその部屋に入る。
使われていない教室のせいか、少し埃っぽい。
「原島先輩は、何が言いたいんですか」
「君は失踪中のストレスで記憶をなくしている」
電気をつけた原島先輩が戸を閉めたあと、くるりと踊るようにまわって教室を歩き回る。
そして私の前までくると人差し指を上にあげた。
「一般的には、そういう考え方になるだろうね」
「他に、何か理由があるって、そういうことですか」
「うーん、まあ、仮説だけどね。今話題になってる連続失踪は解決していない。君は帰ってこないだろうとみんな思っていた」
無造作に散らばっている机の上に腰を下ろした原島先輩が足を組んで私を見つめる。「だけど」と。
「君は帰ってきた。記憶をなくてしてはいるけれど、ある特定の記憶だけがなくなっている、違う?」
特定の、記憶。
「整理してみるから、今、消えてる記憶をわかる範囲で言葉にしてごらんよ」
そう言われて、私は少し荒くなる息を整えてゆっくりと口を開いた。
「失踪前のこと、失踪中のこと、それから、」
ーーーー『うん、もう1人いた。その子と一緒に暴力振るわれてる俺を助けてくれたよ』
「私の隣にいた、誰か」