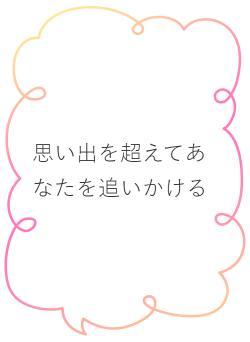五月の大型連休が明け、社会人七年目のくせに未だに毎年発症している五月病と戦いながら、なんとか一週間を生き抜き金曜日の夜を迎えた。最近のマイブームは、溜まったストレスを発散するために仕事帰りにバッティングセンターに寄ること。
国道バイパス沿いの行きつけのバッティングセンターの駐車場に車を停めて車外に出ると、五月の夜にしては暖かさを感じた。スーツの上着を脱いで車内に置き、ワイシャツの袖をまくってふと夜空を見上げると光り輝く満月が目に入ってくる。月を見るたびに脳裏に浮かぶのは、十三、四年前の思い出、俺の最初で最後の恋。
もう忘れよう、思い出さないようにしよう。毎回そう思うのにどうしても忘れられない。二十八年の人生の中で、唯一の甘い記憶。思い出すたびに胸の中で気持ちの良くない感覚がジワリと広がって、自己嫌悪に陥る。
こんなもやもやを打ち払うにもバッティングセンターはちょうどいい。そう思って店内に足を踏み入れると先客が一人だけいた。薄い水色のブラウスにグレーの動きやすそうなロングパンツ、足元はベージュのパンプス。俺と同じく仕事帰りであろう若い女性が、このバッティングセンターで最も遅い球速である八十キロの打席に入ってバットを振っている。
「やあ! てい! くそ!」
肩にかかるくらいの長さの黒髪を振り回し、体は前のめり、体重がまったくバットに伝わらずに手だけで振っているあたりバッティングの経験がないのだろう。それでも腕の力だけでバットを振り回し、たまにバットにボールが当たった際に打球を威嚇するように見る姿から、俺と同じくストレス解消のために来ているということは理解できた。
彼女が打っている打席の側のベンチに腰を下ろし、ネット越しに様子を見守ることにした。ナンパでもするつもりか? と問われれば九割九分違うと答える。残りの一分は今もなお俺の心に残る大きな後悔と、わずかな希望だ。
バットを振り回す姿は見たことはない。そもそも運動はあまり得意ではなかったはずだ。だが、たびたび漏れる声に、ネット越しに見える横顔に、面影を感じずにはいられなかった。
古川月乃。十四年間、思いは変わらないまま、何も行動することができなかった思い出の女の子。中学二年生のたった一年間だけ同じクラスだっただけで、もはや同じ町に住んでいるということ以外に何のつながりもないが、市内のどこかに出かけるたびに、偶然出会えたりしないものかと探してしまうくらいにはまだ好きだった。いっそのこと旦那と歩いていたり、子供を連れている姿でも見かけることができればすっぱりと諦められるのに、そうでないから自分の中のどうしようもない気持ちに決着をつけられないでいる。
そんな彼女に、目の前でバットを振り回す女性は似ている。
彼女に向かってボールを放っていたマシンの上部についているランプの明かりが消えた。息を大きく吐きながら握りしめていたバットを所定の位置に戻した彼女が扉を開けて打席から出てくると、それを見つめていた俺と目が合う。怒り、イラつき、苦悶に満ちていた彼女の表情が和らぎ、あの頃と変わらない穏やかで少しだけいたずらっぽい顔になった。
「覚えてる?」
中学を卒業したあとも何度か偶然再会することはあった。高校の頃の通学路で信号待ちをしていたとき、大学の夏休みに自動車の教習所に通っているとき、社会人二年目に引っ越しやら何やらの手続きのために市役所に行ったとき、俺の顔を見た月乃は決まって今と同じことを聞いた。俺は「うん」と言いながら頷いて、一言か二言だけ言葉を交わして別れてしまっていた。
せめて連絡先を聞いたり、彼氏がいるのか聞いたりしていれば、関係を進展させられるか諦められるかできたのに、臆病な俺は何もできずにいつも脳内で反省会をするだけだった。
五年前にした反省会で決めていた。次に会ったときはもっと話そう。現状の確認をして、可能性が無いなら諦める。可能性があるなら勇気を出す。
「うん」
俺がそう言って頷くと月乃は微笑む。
このまま店の出口に向かうなら声をかけて引き留める。立ち上がるために足に力を入れたが、月乃は俺の隣に座り、中学の頃と同じように気軽に話しかけてきた。
「ここ、よく来るの?」
「うん。仕事帰りにとか、休みの日とか」
「陽君、野球部だったもんね」
陽君という呼び名にドキリとする。物心がついてからから今まで家族や友人に名前を呼ばれたことは数えきれないほどあるが、陽太という名前の俺を陽君と呼んだのは月乃だけだ。
「ふ、つ、月乃は今も市役所?」
月乃が目を見開く。俺は中学の頃、月乃を名前で呼んだことがない。だから驚いているのだろう。ほんの少しだけ勇気を出した。
「うん。前に会ったときからもう五年か。早いね」
「そう、だね」
月乃と最後に会ってもう五年だ。五年間、この日を待ち望んできた。
「前に会ったときは聞けなかったけど、陽君は何のお仕事してるの?」
「高校の教員だよ。理科を教えてるんだ」
「へえ、似合うね。勉強得意だったもんね」
「確かに中学までは結構自信あったけど、高校に入ったら凡人だったことを思い知らされたよ。まあ、自分が凡人だって知ってるから教師が務まってるのかもしれないけど」
「陽君の生徒が羨ましいな。中学の頃、たまに教えてもらうことがあったけど、すごく分かりやすかったから」
「月乃の飲み込みが早かっただけだよ」
月乃はまた微笑んで、俺たちの間に少しの沈黙が流れた。
どうしてこんな時間に一人でこんな場所にいるのか、家庭は持っていないのか、彼氏はいないのか、聞くつもりだった質問はいざ本人を目の前にするとなかなか出てこない。
沈黙を破ったのは月乃だった。
「打たないの?」
「ああ、いや、うん」
「あ、もしかして私を見かけたから会いに来た、とか?」
私がいたからこの係にしたの?
中学三年生の文化祭、俺は音響や照明の係を受け持った。表向きの理由は面白そうだったから。本当の理由は音響機材の扱いに慣れている放送委員長はこの係になることが初めから決まっており、月乃が放送委員長だったから。
係の集まりで集合時間前に二人きりになったときにこう問われ「うん」と言ったつもりだが、曖昧な返事をした気もする。結局すぐに他の人たちが集まってきてそれ以上の会話は続かなかった。
「そうだよ」
今は素直に言える、そんな自分に少しだけ安堵した。
「月乃はどうしてここに? あんまり野球のイメージなかったけど。しかもこんな時間に」
そう尋ねると、月乃は「ふー」と大きく息を吐き、顔と同時に肩を落とした。そして再び顔を上げ、遠くを見るように斜め上の方を見つめる。その切ない視線の先には四十メートルほど先のネットの高さ十五メートルほどの位置に設置された、直径五、六十センチほどのホームランの的と、それに重なるように浮かぶ満月がある。
「私、二十五歳で結婚して、二十八歳の今は娘を一人育てながら、息子を妊娠してる予定だったんだ。今は全然違うけど」
何をおかしなことを、とは思わない。中学二年生で同じクラスだった頃、月乃が最も仲が良かった女子と一緒にそういう人生設計的なことを話していることを知っている。無論、詳細までは知らないが。
「……今は?」
バクバクと気持ち悪いくらいに鼓動が速くなった心臓を無視しながら恐る恐る聞いた。
「結婚する予定だった二十五歳のときに、社会人になってから初めての恋人ができたの。同じ職場で同い年。いい人だった。予定よりは遅くなりそうだけど、この人と結婚するんだろうなって思ってた」
聞かなければよかった。むかむかとする得体の知れない黒い感情に胸の中が支配されていく。
この場を早く立ち去りたい衝動に駆られたが踏みとどまった。すべてを聞かなければ諦めきれない。後悔が残る。
「そのまま三年過ぎて、連休前にお高めのレストランに呼び出されたんだ。やっとプロポーズしてくれるんだ。『愛してるよ。結婚しよう』って言ってくれるんだって思ってた」
胸の中に渦巻く嫌な感情はあっという間に消えた。月乃の声色が悲しみに溢れていて今にも泣きだしそうだったからだ。その言葉通りの展開にはならなかったことは容易に分かる。
「食事を終えて、大事な話があるって言われて、別れようって言われた」
時間が止まったように静寂が訪れる。そばを通るバイパスを走る車の音が鮮明に聞こえて我に返った。我に返ったとしても俺には何も言えなかった。少しだけ喜びが湧いたことに罪悪感を抱いた。
「連休は実家に帰ったり、中学とか高校のときの友達に会って慰めてもらったりして気持ちをリセットしてさ、きっと私にもどこか悪いところはあったとか、よく考えたらあの人のことなんて全然好きじゃなかったとか、運命の人じゃなかったんだとか、色々考えて無理やり納得したんだ」
月乃は「でもね」と言いながら立ち上がり、再び先ほどと同じ打席に入った。バットを掴みながら言葉を続ける。同時に機械に小銭が投入され、マシンの上部のランプが灯る。
「今日、知ったの。あの人、四月に新卒で入った女の子と付き合ってた。そのために私と別れたんだって。中途半端な罪滅ぼしのために最後に高いレストラン奢ってくれたんだって。だから、レストランの自分の分の代金をあの人に押し付けて、こうやって、えい!」
話しながらだったこともあり、二球空振りを続けたのちに三球目を月乃のバットが捉えた。
ハチャメチャなスイングではあるが、怒りや怨念と言った負の感情が乗りまくったその一振りによる打球は一番奥のネットまで届き、ホームランの的よりも十メートルほど低い位置にぶつかった。その後も月乃は声を漏らしながら溜まった感情を吐き出すようにバットを振り続けた。俺は後ろからその姿を見つめる。
月乃の中でプロポーズの言葉は「愛してるよ。結婚しよう」なのだ。先ほど月乃が語った内容を思い返しながら、それを改めて認識する。その言葉は、俺が月乃にかけられたことがある言葉だ。
中学三年生の四月に修学旅行があった。二年生から三年生に上がる際に例年にはなかったクラス替えがあり、慣れない中での旅行だったため二泊三日のうち一日目と二日目は二年生のクラスで、三日目は三年生のクラスで行動することになっていた。
行きの新幹線、俺と月乃は通路を挟んで隣の席だった。スムーズに乗るためにあらかじめ学校で座席を決めていたのだが、俺が決めた後に月乃が隣に来た。男子で決めた班と女子で決めた班をあみだくじでくっつけた班は別々になってしまったが、通路を挟んで話をしたり、月乃の隣や後ろに座っている月乃の仲良しグループの写真を撮ってあげたり、充実した時間だった。
目的地に到着し、自由行動のあと宿泊するホテルに向かうバスの車内で、俺は疲れで眠りそうになっていた。バスの中では二年生の頃のクラスメイト達が大はしゃぎだったが、俺の隣は数少ないおとなしい男子だったので気兼ねなく眠りにつくことができた。ということはなく、大盛り上がりの車内で眠っている不届き者がいればいたずらしたくなるのが中学生の性。俺の耳元で何かを囁く男子もいれば、目をつむっているのに眩しさを感じることもあり、寝顔の写真でも撮られていたのかと思う。
俺は疲れもあったし、文句を言っておふざけに付き合うのも面倒くさいと思って、動きもせず何も話さずそのまま目をつむっていた。
そんなときだった。先ほどの男子とは違う誰かが耳元に近づいてくる気配があった。またいたずらか、と思って無視しようと決め込んでいると、声がした。はっきりと聞こえた。
「愛してるよ。結婚しよう」
俺の耳がおかしくなければあれは月乃の声だった。
あのとき目を開けて声の主を見ていれば。そうでなくても、俺の少し後ろの席のはずだった月乃の様子を見ていれば、今と何かが変わったかもしれない。
でも、あのときの俺は月乃からバレンタインデーにチョコをもらったお礼も言えてなくて、ホワイトデーのお返しも直接渡せずに月乃の友人にお願いして渡してもらったりして、とにかく臆病だった。自分に自信がなかった。だから、過去一番に胸を高鳴らせながら眠ったふりを続けていた。
本当に眠っているかのように見せかけることは成功したようで、何も起きることなくバスはホテルに到着した。
あれが本当に月乃だったのか、そうだとしたら何故あんなことを言ったのか。修学旅行でテンションが上がってしまったからなのか、それとも本心か。その後は月乃と話すことはできず、もやもやを抱えたまま修学旅行は幕を閉じた。
旅行が終わって何日か経った日の休み時間、教室の廊下側の前方に担任の先生が置いてくれていた漢和辞典をなんとなく眺めているときだった。
誰かにトントンと肩を叩かれ、振り返ると人差し指が頬に刺さった。微笑む月乃がいた。もう違うクラスの人間、わざわざ俺に会いに来てくれた。何を話すべきか悩み、狼狽える俺に月乃は一枚の現像された写真を差し出し、俺が受け取るとそのまま自分の教室に戻って行ってしまった。
新幹線で月乃のカメラを使って俺が撮ったのは月乃とその友人の写真。月乃は俺の写真なんか撮っていないはず。斑行動も別々で三日目のクラス行動も別々で、接点なんてほとんどなかったのに、月乃が俺に渡すような写真なんてあるはずもない。
それでも、胸の高鳴りは抑えられなくて周りに誰もいないことを確認して裏返しだったその写真をひっくり返した。
バスの車内で目を閉じて眠っているように見える俺と、そんな俺に顔を寄せて微笑みながら控えめにピースをする月乃。そんな二人が映った写真だった。
それからは学校で顔を合わせるたびにドキドキして、でも何もできなくて言えなくて、そのときはそれでいいと思っていて、月乃と俺の共通の友人は俺の気持ちを察しているような雰囲気がありつつも、結局何もないまま俺たちは卒業して別々の高校に進むことになった。俺は当時まだ携帯電話を持っておらず、連絡先は知らない。
常に月乃の顔が脳裏に浮かんだ。あのときの言葉は耳から離れない。月乃より好きになれる人なんているはずもない。その後の俺は一度も恋をしていない。
大学を卒業して荷物の整理をするとき、大事にとっていたあの写真を処分した。もう社会人になるんだ。いつまでも中学生の頃の恋にしがみついていないで、大人として結婚も考えなければならない。古川月乃は昔好きだった思い出の人。そう決めたのに、忘れられなかった。五年前に再会したときに、気持ちはもっと膨れ上がった。
そんなに好きなのに何故行動しなかったのか。もしタイムマシンがあって過去に戻れるならば、中学生の俺、高校生の俺、大学生の俺、社会人二年目の俺、出会っておきながら何もしなかった俺たちを、殴り倒してでも行動させる。
いつの間にかマシンの明かりが消えていた。
「やっぱり陽君が打つところも見てみたい」
打席から出てくる月乃が言う。
「野球やってるのは知ってたけど、目の前で見たことはなかったから。あ、でもあれは見たよ、高校一年生のときの甲子園。部員九人の進学校の野球部が奇跡の甲子園! って話題になってたよね」
「過去の栄光だよ。もう誰も話題にしないし、そもそも全国放送で一回戦で十五対一で負ける様を晒されて、栄光かどうかも怪しい」
「でも、頑張ってるんだって分かってなんか嬉しかった。陽君はすごいよ」
そう言ってほんの少し目を細め、口角を上げる月乃の顔が昔から好きだった。素直に他人を褒めることができる性格が好きだった。
目の前にいるのは結婚を考えていた恋人に振られたばかりの二十八歳の元同級生の女性。少なくとも嫌われてはいないはずだし、久しぶりの再会でもこうやって昔のように会話ができている。これはチャンスなのだ。俺と付き合わないか? と言えばいい。いきなりが無理でも、中学時代好きだったことを伝えて、思い出を二人で振り返ってその後に言えばいい。頭では分かっている。
「じゃあ、すごいところ見せられるように頑張るよ」
考えたことを実行できていればこの恋の決着は中学時代についていて、今こうして拗らせたりなんかしていない。
格好つけて、気持ちを押し隠して、大人ぶって、そんな成長していない自分に苛立ちと、無力感を覚えながら月乃とは違う打席に入った。
「百二十キロ。そんなに速いの打てるの?」
「このくらいが一番打ちやすいんだよ」
「じゃあ、あれに当てられる?」
月乃が指差したのは満月と重なるホームランの的。あの距離、あの高さまで届くように打つのは難しいことではないが、ピンポイントで的に当てるのはそう簡単ではない。
「できないことはないけど……」
満月のように丸っこくて期待に輝く月乃の瞳に逆らえるはずもない。だが、それは臆病な俺にとって都合のいい後押しとなった。
「もし俺があの的に当てられたら、聞いて欲しいことがあるんだ」
「うん。頑張れ」
そう言ったときにはもうバットを構えて、マシンからボールが出てくる射出口を見つめていたので月乃の表情は見えなかった。ただ、ネットをはさんですぐ後ろで俺のことを見守ってくれている気配だけは感じて、少しでもいいところを見せようとバットを握る手に力が入る。
「惜しい! ああ、あとちょっと! もう少し、頑張って!」
惜しい当たりを打つたびに後ろから月乃の声援が聞こえる。まるで俺にホームランを打ってもらいたいようで、ありもしなかった青春が甦り、涙で目がにじんだ。
俺がもっと勇気を出していれば、高校時代もこうやって月乃が応援してくれる光景がありえたのではないか。もう取り戻せない日々の幻想を打ち払うかのようにバットを振った。
ワイシャツやスラックスが汗でにじんでいくのも、革靴の底がすり減っていくのも気にせずに、たまに休憩をはさみながらボールを打ち続けた。月乃は俺が休憩している間に打席に入ったりしながら、ずっと付き合ってくれた。ホームランの的に重なっていた満月はとっくに位置が変わり、まるで的が二つになったみたいに見える。
午後九時五十五分。バッティングセンターの閉店が午後十時。俺は結局一度もホームランの的に打球を当てられていない。
「次がラストかな」
そう呟きながら打席に入る俺を月乃は祈るように自分の両手を握りしめながら見つめる。
もう言ってしまってもいいんじゃないか。いくら明日が休みの金曜日とはいえ、仕事帰りにこんな時間まで付き合ってくれるのは、少なからず俺に好意を抱いているからではないのか。俺が言おうとしていることを月乃は察していて、それを待っているのではないか。そんな思いをちっぽけなプライドとぬぐい切れない臆病心が邪魔をして、俺は無言でバットを構えた。
何球打ったかも忘れるくらいに集中してバットを振った。
やがてマシンから放たれたボールを俺の振ったバットが完璧に捉え、打球は速度も角度も申し分なく一直線に満月に向かって飛び立つ。
「あ」
月乃が声を上げた。
ボールは満月に当たってネットを揺らした。
当然だがホームランの的に当てたときのファンファーレはならない。
マシンの上部についているランプの明かりが消えた。
取り戻した束の間の青春は終わりを告げる。
俺が打席を出ると、ベンチに座っていた月乃が立ち上がる。
眉を下げて俺を励ますように控えめに「お疲れ様」と声をかけてくれた。
その表情はどんな感情によるものなのか、月乃は何を言いたいのか、俺はそれが分かるほど月乃と濃い関わりを持っていない。
「月乃、俺は……」
「格好良かったよ。陽君が頑張ってる姿を特等席で見られて良かった」
月乃の満月のように丸い瞳がふるふると揺れている。きっと俺の瞳も同じだ。
「またね」
そう言ってあの頃と変わらない笑顔を向けて、小さく手を振って月乃は歩き出す。
バッティングセンターの外に出ようと歩く月乃の背中を見送る。
このまま見送っていいのか。こんな奇跡の出会いはないかもしれない。もう二度と会うことはないかもしれない。
傷つくのが嫌で、恥ずかしい思いをするのが嫌で、気持ちを確かめるのが怖くて、思いばかりを募らせて、何もしなかった中学生時代から俺は何も成長できていない。結局俺は恋愛なんて向いていない人間だったのだ。
月乃が見えなくなって、全てを諦めてベンチに座った。不甲斐ない、意気地なしの自分が嫌いだ。
それなりに勉強して、それなりに部活を頑張って、それなりの実績は出してきた。罪を犯すこともなく、人に迷惑をかけるどころかどちらかと言うと助ける側になることが多かった。友人は多くはないが、周りからはそれなりに信頼は得ていると思う。安定した職に就き、それなりに真面目に働いて、それなりにやりがいはあって、大金は得られないが地方都市で慎ましく暮らすには十分な給料をもらっている。羨ましいと思う人もいるかもしれない、努力の成果だと言ってくれる人もいるかもしれない。でも、心に一か所だけぽっかりと穴が開いていて満たされない。その穴は月乃以外には埋められない。
ずっとこうして生きていくのだろう。叶わなかった恋を後悔し、瑞々しい思い出を糧にして、空白を抱えたまま生きていく。
午後十時を回った。閉店時間のはずだが辺りを見渡しても店員はいない。
だったら最後にもう一度だけ打ってみようか。そう思って打席に入った。
当てられなかったホームランの的。打席から見ると満月との距離はそんなに離れていないように見えるが、実際は何十万キロも離れている。あの的に当てたくらいで月に手が届くと思っていたのが間違いだったのだ。
自虐的に笑ってから、何を馬鹿なことを考えているんだと再びの自己嫌悪に陥る。
マシンからボールが放たれた。
条件反射のようにバットを振った。
打球はまっすぐに的に向かっていく。
あんなに望んでも手に入れられなかったものが簡単に手に入った。
ホームランを知らせる甲高いファンファーレが深い夜に鳴り響く。周りに住宅は少ないが、バイパス沿いのためそちら側には建物が少なく、遠くまで届いて近所迷惑になってしまいそうだ。
俺はその場に座り込んで、マシンから放たれるボールが防球ネットに当たる様を見守った。
ボールの射出が終わりその場に転がったボールを片付けてから打席を出た。
そうだ。俺の人生は意外とうまくいっているんだ。本当に望むことは叶えられていなが、それなりに成功していい思いをしたことは間違いなくあって、だからずっと好きだった人を忘れるくらい、たいしたことじゃない。
「陽君……」
バッティングセンターの出入り口に息を切らした月乃がいた。
「……おめでとう」
駆け寄ってきて、俺のすぐそばで立ち止まり、俺の顔をまっすぐに見つめる月乃に対し、俺の頭は真っ白になって何を言ったのか覚えていない。
ただ、臆病だった自分と袂を分かつことができたことだけは覚えている。
国道バイパス沿いの行きつけのバッティングセンターの駐車場に車を停めて車外に出ると、五月の夜にしては暖かさを感じた。スーツの上着を脱いで車内に置き、ワイシャツの袖をまくってふと夜空を見上げると光り輝く満月が目に入ってくる。月を見るたびに脳裏に浮かぶのは、十三、四年前の思い出、俺の最初で最後の恋。
もう忘れよう、思い出さないようにしよう。毎回そう思うのにどうしても忘れられない。二十八年の人生の中で、唯一の甘い記憶。思い出すたびに胸の中で気持ちの良くない感覚がジワリと広がって、自己嫌悪に陥る。
こんなもやもやを打ち払うにもバッティングセンターはちょうどいい。そう思って店内に足を踏み入れると先客が一人だけいた。薄い水色のブラウスにグレーの動きやすそうなロングパンツ、足元はベージュのパンプス。俺と同じく仕事帰りであろう若い女性が、このバッティングセンターで最も遅い球速である八十キロの打席に入ってバットを振っている。
「やあ! てい! くそ!」
肩にかかるくらいの長さの黒髪を振り回し、体は前のめり、体重がまったくバットに伝わらずに手だけで振っているあたりバッティングの経験がないのだろう。それでも腕の力だけでバットを振り回し、たまにバットにボールが当たった際に打球を威嚇するように見る姿から、俺と同じくストレス解消のために来ているということは理解できた。
彼女が打っている打席の側のベンチに腰を下ろし、ネット越しに様子を見守ることにした。ナンパでもするつもりか? と問われれば九割九分違うと答える。残りの一分は今もなお俺の心に残る大きな後悔と、わずかな希望だ。
バットを振り回す姿は見たことはない。そもそも運動はあまり得意ではなかったはずだ。だが、たびたび漏れる声に、ネット越しに見える横顔に、面影を感じずにはいられなかった。
古川月乃。十四年間、思いは変わらないまま、何も行動することができなかった思い出の女の子。中学二年生のたった一年間だけ同じクラスだっただけで、もはや同じ町に住んでいるということ以外に何のつながりもないが、市内のどこかに出かけるたびに、偶然出会えたりしないものかと探してしまうくらいにはまだ好きだった。いっそのこと旦那と歩いていたり、子供を連れている姿でも見かけることができればすっぱりと諦められるのに、そうでないから自分の中のどうしようもない気持ちに決着をつけられないでいる。
そんな彼女に、目の前でバットを振り回す女性は似ている。
彼女に向かってボールを放っていたマシンの上部についているランプの明かりが消えた。息を大きく吐きながら握りしめていたバットを所定の位置に戻した彼女が扉を開けて打席から出てくると、それを見つめていた俺と目が合う。怒り、イラつき、苦悶に満ちていた彼女の表情が和らぎ、あの頃と変わらない穏やかで少しだけいたずらっぽい顔になった。
「覚えてる?」
中学を卒業したあとも何度か偶然再会することはあった。高校の頃の通学路で信号待ちをしていたとき、大学の夏休みに自動車の教習所に通っているとき、社会人二年目に引っ越しやら何やらの手続きのために市役所に行ったとき、俺の顔を見た月乃は決まって今と同じことを聞いた。俺は「うん」と言いながら頷いて、一言か二言だけ言葉を交わして別れてしまっていた。
せめて連絡先を聞いたり、彼氏がいるのか聞いたりしていれば、関係を進展させられるか諦められるかできたのに、臆病な俺は何もできずにいつも脳内で反省会をするだけだった。
五年前にした反省会で決めていた。次に会ったときはもっと話そう。現状の確認をして、可能性が無いなら諦める。可能性があるなら勇気を出す。
「うん」
俺がそう言って頷くと月乃は微笑む。
このまま店の出口に向かうなら声をかけて引き留める。立ち上がるために足に力を入れたが、月乃は俺の隣に座り、中学の頃と同じように気軽に話しかけてきた。
「ここ、よく来るの?」
「うん。仕事帰りにとか、休みの日とか」
「陽君、野球部だったもんね」
陽君という呼び名にドキリとする。物心がついてからから今まで家族や友人に名前を呼ばれたことは数えきれないほどあるが、陽太という名前の俺を陽君と呼んだのは月乃だけだ。
「ふ、つ、月乃は今も市役所?」
月乃が目を見開く。俺は中学の頃、月乃を名前で呼んだことがない。だから驚いているのだろう。ほんの少しだけ勇気を出した。
「うん。前に会ったときからもう五年か。早いね」
「そう、だね」
月乃と最後に会ってもう五年だ。五年間、この日を待ち望んできた。
「前に会ったときは聞けなかったけど、陽君は何のお仕事してるの?」
「高校の教員だよ。理科を教えてるんだ」
「へえ、似合うね。勉強得意だったもんね」
「確かに中学までは結構自信あったけど、高校に入ったら凡人だったことを思い知らされたよ。まあ、自分が凡人だって知ってるから教師が務まってるのかもしれないけど」
「陽君の生徒が羨ましいな。中学の頃、たまに教えてもらうことがあったけど、すごく分かりやすかったから」
「月乃の飲み込みが早かっただけだよ」
月乃はまた微笑んで、俺たちの間に少しの沈黙が流れた。
どうしてこんな時間に一人でこんな場所にいるのか、家庭は持っていないのか、彼氏はいないのか、聞くつもりだった質問はいざ本人を目の前にするとなかなか出てこない。
沈黙を破ったのは月乃だった。
「打たないの?」
「ああ、いや、うん」
「あ、もしかして私を見かけたから会いに来た、とか?」
私がいたからこの係にしたの?
中学三年生の文化祭、俺は音響や照明の係を受け持った。表向きの理由は面白そうだったから。本当の理由は音響機材の扱いに慣れている放送委員長はこの係になることが初めから決まっており、月乃が放送委員長だったから。
係の集まりで集合時間前に二人きりになったときにこう問われ「うん」と言ったつもりだが、曖昧な返事をした気もする。結局すぐに他の人たちが集まってきてそれ以上の会話は続かなかった。
「そうだよ」
今は素直に言える、そんな自分に少しだけ安堵した。
「月乃はどうしてここに? あんまり野球のイメージなかったけど。しかもこんな時間に」
そう尋ねると、月乃は「ふー」と大きく息を吐き、顔と同時に肩を落とした。そして再び顔を上げ、遠くを見るように斜め上の方を見つめる。その切ない視線の先には四十メートルほど先のネットの高さ十五メートルほどの位置に設置された、直径五、六十センチほどのホームランの的と、それに重なるように浮かぶ満月がある。
「私、二十五歳で結婚して、二十八歳の今は娘を一人育てながら、息子を妊娠してる予定だったんだ。今は全然違うけど」
何をおかしなことを、とは思わない。中学二年生で同じクラスだった頃、月乃が最も仲が良かった女子と一緒にそういう人生設計的なことを話していることを知っている。無論、詳細までは知らないが。
「……今は?」
バクバクと気持ち悪いくらいに鼓動が速くなった心臓を無視しながら恐る恐る聞いた。
「結婚する予定だった二十五歳のときに、社会人になってから初めての恋人ができたの。同じ職場で同い年。いい人だった。予定よりは遅くなりそうだけど、この人と結婚するんだろうなって思ってた」
聞かなければよかった。むかむかとする得体の知れない黒い感情に胸の中が支配されていく。
この場を早く立ち去りたい衝動に駆られたが踏みとどまった。すべてを聞かなければ諦めきれない。後悔が残る。
「そのまま三年過ぎて、連休前にお高めのレストランに呼び出されたんだ。やっとプロポーズしてくれるんだ。『愛してるよ。結婚しよう』って言ってくれるんだって思ってた」
胸の中に渦巻く嫌な感情はあっという間に消えた。月乃の声色が悲しみに溢れていて今にも泣きだしそうだったからだ。その言葉通りの展開にはならなかったことは容易に分かる。
「食事を終えて、大事な話があるって言われて、別れようって言われた」
時間が止まったように静寂が訪れる。そばを通るバイパスを走る車の音が鮮明に聞こえて我に返った。我に返ったとしても俺には何も言えなかった。少しだけ喜びが湧いたことに罪悪感を抱いた。
「連休は実家に帰ったり、中学とか高校のときの友達に会って慰めてもらったりして気持ちをリセットしてさ、きっと私にもどこか悪いところはあったとか、よく考えたらあの人のことなんて全然好きじゃなかったとか、運命の人じゃなかったんだとか、色々考えて無理やり納得したんだ」
月乃は「でもね」と言いながら立ち上がり、再び先ほどと同じ打席に入った。バットを掴みながら言葉を続ける。同時に機械に小銭が投入され、マシンの上部のランプが灯る。
「今日、知ったの。あの人、四月に新卒で入った女の子と付き合ってた。そのために私と別れたんだって。中途半端な罪滅ぼしのために最後に高いレストラン奢ってくれたんだって。だから、レストランの自分の分の代金をあの人に押し付けて、こうやって、えい!」
話しながらだったこともあり、二球空振りを続けたのちに三球目を月乃のバットが捉えた。
ハチャメチャなスイングではあるが、怒りや怨念と言った負の感情が乗りまくったその一振りによる打球は一番奥のネットまで届き、ホームランの的よりも十メートルほど低い位置にぶつかった。その後も月乃は声を漏らしながら溜まった感情を吐き出すようにバットを振り続けた。俺は後ろからその姿を見つめる。
月乃の中でプロポーズの言葉は「愛してるよ。結婚しよう」なのだ。先ほど月乃が語った内容を思い返しながら、それを改めて認識する。その言葉は、俺が月乃にかけられたことがある言葉だ。
中学三年生の四月に修学旅行があった。二年生から三年生に上がる際に例年にはなかったクラス替えがあり、慣れない中での旅行だったため二泊三日のうち一日目と二日目は二年生のクラスで、三日目は三年生のクラスで行動することになっていた。
行きの新幹線、俺と月乃は通路を挟んで隣の席だった。スムーズに乗るためにあらかじめ学校で座席を決めていたのだが、俺が決めた後に月乃が隣に来た。男子で決めた班と女子で決めた班をあみだくじでくっつけた班は別々になってしまったが、通路を挟んで話をしたり、月乃の隣や後ろに座っている月乃の仲良しグループの写真を撮ってあげたり、充実した時間だった。
目的地に到着し、自由行動のあと宿泊するホテルに向かうバスの車内で、俺は疲れで眠りそうになっていた。バスの中では二年生の頃のクラスメイト達が大はしゃぎだったが、俺の隣は数少ないおとなしい男子だったので気兼ねなく眠りにつくことができた。ということはなく、大盛り上がりの車内で眠っている不届き者がいればいたずらしたくなるのが中学生の性。俺の耳元で何かを囁く男子もいれば、目をつむっているのに眩しさを感じることもあり、寝顔の写真でも撮られていたのかと思う。
俺は疲れもあったし、文句を言っておふざけに付き合うのも面倒くさいと思って、動きもせず何も話さずそのまま目をつむっていた。
そんなときだった。先ほどの男子とは違う誰かが耳元に近づいてくる気配があった。またいたずらか、と思って無視しようと決め込んでいると、声がした。はっきりと聞こえた。
「愛してるよ。結婚しよう」
俺の耳がおかしくなければあれは月乃の声だった。
あのとき目を開けて声の主を見ていれば。そうでなくても、俺の少し後ろの席のはずだった月乃の様子を見ていれば、今と何かが変わったかもしれない。
でも、あのときの俺は月乃からバレンタインデーにチョコをもらったお礼も言えてなくて、ホワイトデーのお返しも直接渡せずに月乃の友人にお願いして渡してもらったりして、とにかく臆病だった。自分に自信がなかった。だから、過去一番に胸を高鳴らせながら眠ったふりを続けていた。
本当に眠っているかのように見せかけることは成功したようで、何も起きることなくバスはホテルに到着した。
あれが本当に月乃だったのか、そうだとしたら何故あんなことを言ったのか。修学旅行でテンションが上がってしまったからなのか、それとも本心か。その後は月乃と話すことはできず、もやもやを抱えたまま修学旅行は幕を閉じた。
旅行が終わって何日か経った日の休み時間、教室の廊下側の前方に担任の先生が置いてくれていた漢和辞典をなんとなく眺めているときだった。
誰かにトントンと肩を叩かれ、振り返ると人差し指が頬に刺さった。微笑む月乃がいた。もう違うクラスの人間、わざわざ俺に会いに来てくれた。何を話すべきか悩み、狼狽える俺に月乃は一枚の現像された写真を差し出し、俺が受け取るとそのまま自分の教室に戻って行ってしまった。
新幹線で月乃のカメラを使って俺が撮ったのは月乃とその友人の写真。月乃は俺の写真なんか撮っていないはず。斑行動も別々で三日目のクラス行動も別々で、接点なんてほとんどなかったのに、月乃が俺に渡すような写真なんてあるはずもない。
それでも、胸の高鳴りは抑えられなくて周りに誰もいないことを確認して裏返しだったその写真をひっくり返した。
バスの車内で目を閉じて眠っているように見える俺と、そんな俺に顔を寄せて微笑みながら控えめにピースをする月乃。そんな二人が映った写真だった。
それからは学校で顔を合わせるたびにドキドキして、でも何もできなくて言えなくて、そのときはそれでいいと思っていて、月乃と俺の共通の友人は俺の気持ちを察しているような雰囲気がありつつも、結局何もないまま俺たちは卒業して別々の高校に進むことになった。俺は当時まだ携帯電話を持っておらず、連絡先は知らない。
常に月乃の顔が脳裏に浮かんだ。あのときの言葉は耳から離れない。月乃より好きになれる人なんているはずもない。その後の俺は一度も恋をしていない。
大学を卒業して荷物の整理をするとき、大事にとっていたあの写真を処分した。もう社会人になるんだ。いつまでも中学生の頃の恋にしがみついていないで、大人として結婚も考えなければならない。古川月乃は昔好きだった思い出の人。そう決めたのに、忘れられなかった。五年前に再会したときに、気持ちはもっと膨れ上がった。
そんなに好きなのに何故行動しなかったのか。もしタイムマシンがあって過去に戻れるならば、中学生の俺、高校生の俺、大学生の俺、社会人二年目の俺、出会っておきながら何もしなかった俺たちを、殴り倒してでも行動させる。
いつの間にかマシンの明かりが消えていた。
「やっぱり陽君が打つところも見てみたい」
打席から出てくる月乃が言う。
「野球やってるのは知ってたけど、目の前で見たことはなかったから。あ、でもあれは見たよ、高校一年生のときの甲子園。部員九人の進学校の野球部が奇跡の甲子園! って話題になってたよね」
「過去の栄光だよ。もう誰も話題にしないし、そもそも全国放送で一回戦で十五対一で負ける様を晒されて、栄光かどうかも怪しい」
「でも、頑張ってるんだって分かってなんか嬉しかった。陽君はすごいよ」
そう言ってほんの少し目を細め、口角を上げる月乃の顔が昔から好きだった。素直に他人を褒めることができる性格が好きだった。
目の前にいるのは結婚を考えていた恋人に振られたばかりの二十八歳の元同級生の女性。少なくとも嫌われてはいないはずだし、久しぶりの再会でもこうやって昔のように会話ができている。これはチャンスなのだ。俺と付き合わないか? と言えばいい。いきなりが無理でも、中学時代好きだったことを伝えて、思い出を二人で振り返ってその後に言えばいい。頭では分かっている。
「じゃあ、すごいところ見せられるように頑張るよ」
考えたことを実行できていればこの恋の決着は中学時代についていて、今こうして拗らせたりなんかしていない。
格好つけて、気持ちを押し隠して、大人ぶって、そんな成長していない自分に苛立ちと、無力感を覚えながら月乃とは違う打席に入った。
「百二十キロ。そんなに速いの打てるの?」
「このくらいが一番打ちやすいんだよ」
「じゃあ、あれに当てられる?」
月乃が指差したのは満月と重なるホームランの的。あの距離、あの高さまで届くように打つのは難しいことではないが、ピンポイントで的に当てるのはそう簡単ではない。
「できないことはないけど……」
満月のように丸っこくて期待に輝く月乃の瞳に逆らえるはずもない。だが、それは臆病な俺にとって都合のいい後押しとなった。
「もし俺があの的に当てられたら、聞いて欲しいことがあるんだ」
「うん。頑張れ」
そう言ったときにはもうバットを構えて、マシンからボールが出てくる射出口を見つめていたので月乃の表情は見えなかった。ただ、ネットをはさんですぐ後ろで俺のことを見守ってくれている気配だけは感じて、少しでもいいところを見せようとバットを握る手に力が入る。
「惜しい! ああ、あとちょっと! もう少し、頑張って!」
惜しい当たりを打つたびに後ろから月乃の声援が聞こえる。まるで俺にホームランを打ってもらいたいようで、ありもしなかった青春が甦り、涙で目がにじんだ。
俺がもっと勇気を出していれば、高校時代もこうやって月乃が応援してくれる光景がありえたのではないか。もう取り戻せない日々の幻想を打ち払うかのようにバットを振った。
ワイシャツやスラックスが汗でにじんでいくのも、革靴の底がすり減っていくのも気にせずに、たまに休憩をはさみながらボールを打ち続けた。月乃は俺が休憩している間に打席に入ったりしながら、ずっと付き合ってくれた。ホームランの的に重なっていた満月はとっくに位置が変わり、まるで的が二つになったみたいに見える。
午後九時五十五分。バッティングセンターの閉店が午後十時。俺は結局一度もホームランの的に打球を当てられていない。
「次がラストかな」
そう呟きながら打席に入る俺を月乃は祈るように自分の両手を握りしめながら見つめる。
もう言ってしまってもいいんじゃないか。いくら明日が休みの金曜日とはいえ、仕事帰りにこんな時間まで付き合ってくれるのは、少なからず俺に好意を抱いているからではないのか。俺が言おうとしていることを月乃は察していて、それを待っているのではないか。そんな思いをちっぽけなプライドとぬぐい切れない臆病心が邪魔をして、俺は無言でバットを構えた。
何球打ったかも忘れるくらいに集中してバットを振った。
やがてマシンから放たれたボールを俺の振ったバットが完璧に捉え、打球は速度も角度も申し分なく一直線に満月に向かって飛び立つ。
「あ」
月乃が声を上げた。
ボールは満月に当たってネットを揺らした。
当然だがホームランの的に当てたときのファンファーレはならない。
マシンの上部についているランプの明かりが消えた。
取り戻した束の間の青春は終わりを告げる。
俺が打席を出ると、ベンチに座っていた月乃が立ち上がる。
眉を下げて俺を励ますように控えめに「お疲れ様」と声をかけてくれた。
その表情はどんな感情によるものなのか、月乃は何を言いたいのか、俺はそれが分かるほど月乃と濃い関わりを持っていない。
「月乃、俺は……」
「格好良かったよ。陽君が頑張ってる姿を特等席で見られて良かった」
月乃の満月のように丸い瞳がふるふると揺れている。きっと俺の瞳も同じだ。
「またね」
そう言ってあの頃と変わらない笑顔を向けて、小さく手を振って月乃は歩き出す。
バッティングセンターの外に出ようと歩く月乃の背中を見送る。
このまま見送っていいのか。こんな奇跡の出会いはないかもしれない。もう二度と会うことはないかもしれない。
傷つくのが嫌で、恥ずかしい思いをするのが嫌で、気持ちを確かめるのが怖くて、思いばかりを募らせて、何もしなかった中学生時代から俺は何も成長できていない。結局俺は恋愛なんて向いていない人間だったのだ。
月乃が見えなくなって、全てを諦めてベンチに座った。不甲斐ない、意気地なしの自分が嫌いだ。
それなりに勉強して、それなりに部活を頑張って、それなりの実績は出してきた。罪を犯すこともなく、人に迷惑をかけるどころかどちらかと言うと助ける側になることが多かった。友人は多くはないが、周りからはそれなりに信頼は得ていると思う。安定した職に就き、それなりに真面目に働いて、それなりにやりがいはあって、大金は得られないが地方都市で慎ましく暮らすには十分な給料をもらっている。羨ましいと思う人もいるかもしれない、努力の成果だと言ってくれる人もいるかもしれない。でも、心に一か所だけぽっかりと穴が開いていて満たされない。その穴は月乃以外には埋められない。
ずっとこうして生きていくのだろう。叶わなかった恋を後悔し、瑞々しい思い出を糧にして、空白を抱えたまま生きていく。
午後十時を回った。閉店時間のはずだが辺りを見渡しても店員はいない。
だったら最後にもう一度だけ打ってみようか。そう思って打席に入った。
当てられなかったホームランの的。打席から見ると満月との距離はそんなに離れていないように見えるが、実際は何十万キロも離れている。あの的に当てたくらいで月に手が届くと思っていたのが間違いだったのだ。
自虐的に笑ってから、何を馬鹿なことを考えているんだと再びの自己嫌悪に陥る。
マシンからボールが放たれた。
条件反射のようにバットを振った。
打球はまっすぐに的に向かっていく。
あんなに望んでも手に入れられなかったものが簡単に手に入った。
ホームランを知らせる甲高いファンファーレが深い夜に鳴り響く。周りに住宅は少ないが、バイパス沿いのためそちら側には建物が少なく、遠くまで届いて近所迷惑になってしまいそうだ。
俺はその場に座り込んで、マシンから放たれるボールが防球ネットに当たる様を見守った。
ボールの射出が終わりその場に転がったボールを片付けてから打席を出た。
そうだ。俺の人生は意外とうまくいっているんだ。本当に望むことは叶えられていなが、それなりに成功していい思いをしたことは間違いなくあって、だからずっと好きだった人を忘れるくらい、たいしたことじゃない。
「陽君……」
バッティングセンターの出入り口に息を切らした月乃がいた。
「……おめでとう」
駆け寄ってきて、俺のすぐそばで立ち止まり、俺の顔をまっすぐに見つめる月乃に対し、俺の頭は真っ白になって何を言ったのか覚えていない。
ただ、臆病だった自分と袂を分かつことができたことだけは覚えている。