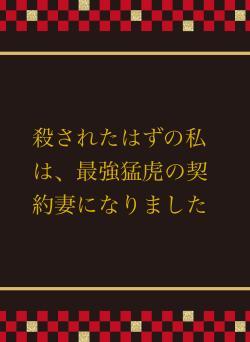一方、ここは後宮内の北側。
人気もなく閑散としたこの場所に、廟がひっそりと建っている。
壁の塗装が剥がれ落ち、瓦も石畳も手入れがされていない。
そんな廟内の狭い一室に、朱璃は閉じ込められていた。
(はあ……伯蓮様、心配するだろうなー)
相変わらず口は布で覆われたまま、廟に到着してからは尚華の侍女らに手足を縄で縛られる。
てっきり尚華の目の前で肉刑の執行がされるか、集団で暴行されるかだろうと思っていた。
しかし身体の自由を奪い、書庫に閉じ込めただけで侍女らは退散していった。
(どうして尚華様は、私を閉じ込めるだけにしたんだろう……)
そんな疑問を残したまま、朱璃は周囲を見渡した。
棚が均等に配置され、書物がいくつも積み上げられている。
埃を被ったまま保管されているのをみると、おそらく書庫なのだろうと推測した。
夜も更けてきたが、誰か立ち寄る様子もない。
聞こえてくるのは、葉擦れの音かアオバズクの鳴き声のみ。
『あんたの命はわたくしが握っているのだから』
尚華に言われたセリフを思い出して、朱璃がふと考える。
今のところ監禁されているだけで、命に危険が迫る感じを受けていない。
もしかして他にも目的があり、処分を後回しにされているのか。
それとも、本気で命を奪ってやろうとは思っていないのか。
(……本当の尚華妃は、もっと違う人柄なのかも)
周囲の侍女や下女にキツく当たるのは、胡家の妃として重圧がかかっているせい。
本当はもっと素直になりたいし、穏やかに過ごしたいと思っているのかもしれない。
孤独を抱える妃を思って、朱璃が救う方法はないかと頭を働かせようとしたとき。
突然、ふっと冷たい空気が流れ込んできて身を震わせた。
(……さ、寒くなってきた)
冷気が入ってくる方に視線を向けると、壁上部にある格子窓が開いていた。
紙を扱う書庫ならば、湿気を発生させないために換気は必要。
しかし冬を間近にした外気は、肌を刺すように冷たい。それが朱璃の頭上から漏れ入ってくる。
徐々に書庫内を冷やしていき、木板の床さえも冷たく感じてきた。
このまま、朝になるまで誰にも発見されなければ、低体温症になってしまう。
そうなれば誰かに直接手をかけられなくても、眠るようにこの命が消えるだろう。
(もしかして、これが目的……?)
朱璃を閉じ込めた侍女らは、きっと口裏を合わせて罪を逃れるはず。
誰に何をされたのか、張本人である朱璃の証言がなければ犯人は不明のままになる。
何者かに攫われ監禁されたのち、寒さに耐えきれずここで命を落としても、尚華を罪に問うことができない。
尚華はやはり、伯蓮との初夜を妨害した朱璃のことを、今でも充分恨んでいるのだと悟った。
(……お父さんお母さん。もう会えなくなるかも)
両親の顔を思い浮かべながら、朱璃が寒さに耐えるため体を丸めた。
ここは後宮内でも誰も近寄ることのない場所だから、誰かが通りかかることは諦めていた。
せめて声が出せたら――そう思って顔を上げた朱璃は、柱に顔を擦り付けて口を塞ぐ巾を外そうと試みる。
すると巾がずるずると外れ、首元にぶら下がった。なんとか自由に声が出せるようになったその時。
「……ミャウ」
「うわ⁉︎ 誰⁉︎」
どこからか猫のような鳴き声が聞こえてきて、朱璃は周囲に目を配る。
すると本棚下のわずかな隙間から、一匹のあやかしが姿を現した。
姿は猫のようで耳は兎のように大きい、空色をした可愛いあやかし。
どこかで見たことのある特徴と容姿に、確信した朱璃は名前を呼んだ。
「流! 伯蓮様のところの流でしょ⁉︎」
「ミャウ⁉︎」
名前を呼ばれて、流がギョッと驚きの表情を浮かべた。
さらに、あやかしが視える人間に出会ったことで、一度身を引っ込めてしまう。
「あ、驚かせてごめんね。私は朱璃。伯蓮様に流の捜索を頼まれていたの」
「ミャ?」
伯蓮の名を聞いて、流が恐る恐る顔を出してきた。
そして朱璃の顔を再度確認して、愛らしく首を傾げる。
「伯蓮様も星も心配しているよ。一緒に蒼山宮に帰ろう?」
朱璃が優しい口調で語りかけると、流は安心したのか少しずつ近づいてきた。
そして座り込む朱璃の足元までやってきたのだが、物言いたげな表情で見上げてくる。
今の不利な状況に気づいた朱璃は、危機感のない笑みを浮かべた。
「あはは、そうだった。私たち閉じ込められてるんだった……」
「ミャウ」
流もコクリと頷いて、監禁されている朱璃を不安げな瞳で見つめる。
どうやら人間の言葉は話せなくても、理解はできているらしい。
しかし、せっかく流を発見できたのに、このままでは伯蓮の元に連れ帰ることができない。
そのことが何より残念で、朱璃は項垂れた。
ただ、ようやく声を出せるようになったのだから、朱璃が今世紀最大の大声で助けを求める。
「すみませーーん! 誰かいませんかーー!」
もちろん廟の周囲には誰もいないし、人の気配もない。
それでも微かに声が届いて、不審に思った誰か近寄ってきてくれるかもしれない。
朱璃は何度も何度も、懸命に大きな声を張り上げる。
出せば出すほど疲労は溜まるが、諦めることなくお腹に空気を溜めて一気に吐き出す。
「閉じ込められてますーー! 助けてくださーーい!」
手足は縛られ体は自由に動かなく、寒くてうまく思考も働かなくなってくる。
流を発見したことを、早く伯蓮に知らせたい朱璃。
けれど徐々に瞼が重たくなってきて、息も絶え絶えになってきた。
すると、足元にいる流が小さな手でトントン叩き起こしてくる。
「はっ、うそ……寝そうだった?」
「ミャ」
朱璃の言葉に、流は叱るような反応を示す。
今寝たら確実に命が危ないと充分わかっている朱璃が、歯を食いしばって苦悩する。
「……そうだ! 流にお願いが」
「ミャウ?」
「私の指を噛んで!」
言いながら流に背中を向けた朱璃は、縛られた両手を見せて指先を動かした。
ここだよ、と主張するようにして、流に噛み付くよう促す。
痛みが走れば眠たくなることもないと思い、そんな提案をしてみた。
どこか納得しないように顔を歪ませた流は、仕方なく朱璃の指先に噛みついた。
「……あまり、痛くない……」
流には鋭い歯はなく、噛まれても目を覚ますほどの激痛は得られなかった。
それどころか、朱璃の指先が異様に冷たくなっていることに流が気づく。
足の指先も同様で、確実に体が冷えに耐えられなくなっていることが表れはじめていた。
「どうしよう、いよいよまずいかも……」
「ミャウミャーウ!」
「……そうだよね。諦めちゃ、ダメだよね……」
鳴き声だけで何を言われているのか理解した朱璃が、力無く微笑んだ。
しかし、その顔は徐々に青ざめ、体全身が氷のように冷たくなる。
朱璃はとうとう、その場に倒れるように横になってしまった。
目の前には流があたふたしながら、朧げな意識の朱璃を見守ることしかできない。
「……流だけでも、出してあげたいのに……」
あやかしは空腹感も寒暖差も感じないと、三々が言っていた。
だから、今すぐ流の命が危険に晒されるという心配はない。
いずれ様子を見にきた尚華の侍女が、きっと扉を開ける。
その時に、流にはこの書庫を抜け出してもらおうと朱璃は考えた。
流だけでも、無事に伯蓮の宮に帰ることができればそれで良い。
薄れる意識の中で、朱璃は最後になるかもしれない言葉を漏らした。
「…………生まれ変わったら、あやかしに、なりたいな……」
朱璃の願いに驚愕した流が、目を見張る。
そんな中、ついに朱璃は眠りについてしまった。
このまま眠り続けていたら、きっと朝までもたない。
「ミャーミャー!」
朱璃を起こそうと大きな声で鳴く流だが、朱璃の瞼はぴくりとも動かない。
あやかしの流にはどうすることもできなくて、横たわる朱璃の体の周りをぐるぐる走る。
その時、外気が漏れてくる格子窓から夜空が見えた。
無数の星々が光り輝く、美しい空。
すると、一筋の光がものすごい速さで夜空を駆ける。
「……ミャウ」
流星を目撃した流は、そっと朱璃の背後に回る。
そして静かに目を閉じて、精神を集中させた。
主人である伯蓮に頼まれ、流を捜索していたと朱璃は言っていた。
あやかしが視えることを隠してきた伯蓮にとって、その秘密を打ち明けること自体が大きな成長。
流と星にとって伯蓮は、あやかしを大切にしてくれる尊敬に値するご主人様。
その伯蓮と同じ心を持つ朱璃は、きっと伯蓮にとって同志のような存在なのだろう。
そう理解した流は、朱璃を守らねばならないという使命に駆られた。
ここで朱璃を死なせてしまうと、伯蓮が悲しむことを容易に想像できたから。
出会ってそんなに時間は経っていないけれど、朱璃の人柄と勇気、強い心は流にも伝わっている。
「…………だから、俺が人肌脱いでやるよ」
突然、得意げな口調の男性の声が聞こえてきた。
眠りの中にいた朱璃は、わずかな意識が働いて瞼をぴくりと動かす。
助けがきたんだと思っていると、手足を縛っていた縄がゆっくり解かれていく感覚がわかった。
安心した朱璃は、一目その姿を確認してお礼を述べたいと、うっすら瞼を開けた。
瞬間、大きな手のひらで視界を覆われてしまう。
「いいから。あんたは眠ったまま休んでろよ」
「……は、い……」
その手の温もりは明らかに人のもので、安心した朱璃は言われるがままに再度眠りにつく。
冷たい床からそっと抱き起こされると、まるで誰かの腕の中で抱えられているような体温を感じた。
朱璃を抱きしめて、その氷のように冷たくなった体を暖めていく一人の男性の影。
その髪色は、人間にしては実に珍しい空色をしていた。