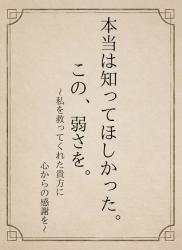「兄さん、それはないでしょ。兄さんの愛は本物だったって、それだけは僕、はっきり言えるよ」
「ちがう。俺なんかより、紅のほうがよっぽど人間だ……」
その時、慧の中で何かが壊れたことだけは分かった。
「っ、兄さんっ!!」
糸が切れたように倒れ込んだ慧を紅が慌てて支える。
「縢雨ちゃん、大丈夫?」
私は、いつの間にか軽くなっていた体で、縢雨ちゃんを抱き起こす。
「氷雨ちゃん……。どうしよう、慧くんが壊れちゃった……っ!」
「縢雨ちゃん、紅もとりあえず、別の部屋に行っててもらえる?」
紅に酷く取り乱す縢雨ちゃんを任せる。
ふたりが部屋を出ていくのを見ると、横たわる慧の真っ白な頬に触れる。
「慧、好き。ずっと、ずっと前から。愛してる。ねぇ、目を開けて。私と話をしよう?」
そっと、唇にキスをひとつ。
「ん……。だ、れ……? ひさ、め……。氷雨?」
「はい。慧、大丈夫ですか?」
「氷雨? ひさ、め……? なんで。俺はニセモノ? ひさめは? この世界は? ……氷雨は俺を……? おれが、俺が……。氷雨は、道具? 世継ぎの、道具……?」
「っ、慧。大丈夫ですか? 慧、けいっ!」
私が喋れば喋るほど慧は混乱したように呟く。
「嫌だ。こわい。なんで、なんで俺は……ぁ、やだ……」
その掠れた悲しそうな声を皮切りに、慧の様子が豹変した。
優しい眼差しは鳴りをひそめ、代わりに冷たい視線が向けられた。
これが、覚醒のとき。
「ちがう。俺なんかより、紅のほうがよっぽど人間だ……」
その時、慧の中で何かが壊れたことだけは分かった。
「っ、兄さんっ!!」
糸が切れたように倒れ込んだ慧を紅が慌てて支える。
「縢雨ちゃん、大丈夫?」
私は、いつの間にか軽くなっていた体で、縢雨ちゃんを抱き起こす。
「氷雨ちゃん……。どうしよう、慧くんが壊れちゃった……っ!」
「縢雨ちゃん、紅もとりあえず、別の部屋に行っててもらえる?」
紅に酷く取り乱す縢雨ちゃんを任せる。
ふたりが部屋を出ていくのを見ると、横たわる慧の真っ白な頬に触れる。
「慧、好き。ずっと、ずっと前から。愛してる。ねぇ、目を開けて。私と話をしよう?」
そっと、唇にキスをひとつ。
「ん……。だ、れ……? ひさ、め……。氷雨?」
「はい。慧、大丈夫ですか?」
「氷雨? ひさ、め……? なんで。俺はニセモノ? ひさめは? この世界は? ……氷雨は俺を……? おれが、俺が……。氷雨は、道具? 世継ぎの、道具……?」
「っ、慧。大丈夫ですか? 慧、けいっ!」
私が喋れば喋るほど慧は混乱したように呟く。
「嫌だ。こわい。なんで、なんで俺は……ぁ、やだ……」
その掠れた悲しそうな声を皮切りに、慧の様子が豹変した。
優しい眼差しは鳴りをひそめ、代わりに冷たい視線が向けられた。
これが、覚醒のとき。