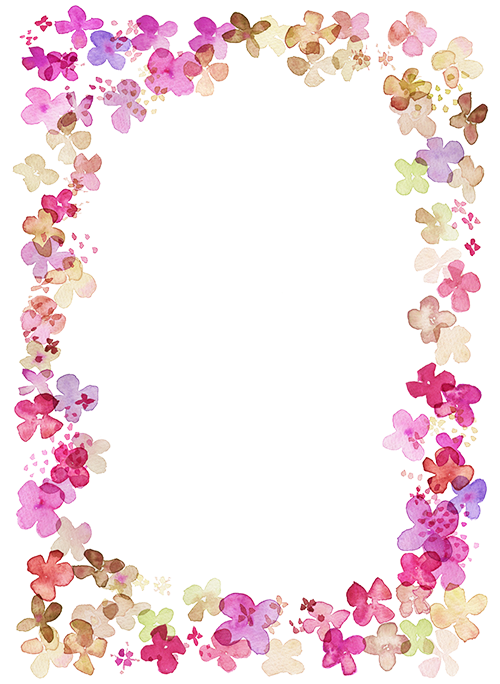時を忘れたくなる時、いつも俺が立ち寄る場所がある。
職場から各駅停車の電車で二駅分、そこから徒歩十五分。格別の娯楽施設もビルもない小さな街に、ひっそりと佇む白い教会がある。
教会に隣接した、中世の酒場のような独特の雰囲気の店が目的だ。
古めかしい木造りの建物で、淡い赤茶色の照明が浮く。耳を澄ませないとわからないくらいの小音量で音楽がかかる程度で、客もぼそぼそとした声でしか話さない。飲み屋だというのに不思議と静粛な気分になってしまう。
ここに来ると現代の日本にいることを忘れそうになる。
カウンターでビールを頼もうとした時、俺は微かな空気の流れを感じて振り向く。
壁紙でもめくるように、ぺらりと空がはがれた。
何もない空中から、眩しいほどの長い銀髪と銀色の目をした少女が抜け出てくる。ステッキを片手に、マジシャンのような燕尾服をひらめかせて。
「え?」
俺は自分の目が信じられずに瞬きをする。
トン、とカウンターに何かが置かれた音で、俺は幻覚から目覚めた。
いつ来たのか、俺の隣の席には高校生ほどの少女が座っていた。ショートカットの黒髪に黒い瞳で、涼やかな目元をした綺麗な子だった。
ただまさか燕尾服など着ておらず、ステッキも持っていなかった。
「こんばんは」
俺が見ているのに気付いたのか、少女は愛想よく微笑んで挨拶してきた。
彼女の手元には黒いシルクハットが置かれている。先ほどの音はこの帽子を置いた音だったらしい。
「私、どこか変ですか?」
柔らかな声音で問いかけてきたので、俺ははっとして現在の自分を取り戻す。
「いや。変わった帽子だな、と」
「ああ。時代外れの形でしたか」
彼女は帽子を手にとって小さく頷く。
「うっかりしていました。今到着したばかりなもので」
「君、日本の人じゃないね」
流暢な日本語を話しているが、どこか違和感がある。黒髪黒目だが、日本人の顔立ちではない。
「旅行者なんです。テラといいます」
「それは名字? 名前?」
「名前です」
「そう。テラさん。早速だが、君は未成年じゃないか?」
彼女はメニュー表を物色しながら苦笑する。
「そういうあなたは、警察の方ではありませんか?」
「いい勘をしているが、俺は検事なんだ」
「一杯だけ見逃してもらえませんか?」
テラと名乗った少女は目を細めて赤茶色の店内を見上げる。
「ここのビールがおいしいと聞いて遠くから来たのです」
「まあ、いいよ。旅行だものね」
補導は俺の職務ではないし、第一今は職務時間外だ。
俺とテラさんは一杯ずつビールを注文した。まもなく、木のジョッキに入ったビールが出される。
ひと口飲んで、俺は何気なく口を開く。
「ここのビールは隣の教会が作っているらしいよ」
「そうらしいですね」
「教会と酒場という組み合わせは多少違和感があるね。何か悪いことをしているような気持ちにさせられる」
入口に掲げられた十字架を見やって、テラさんは首を傾げる。
「そうですか? 西洋には教会で作っているワインやビールも多いですよ。元々、信仰の中にお酒が組み込まれているんですから」
「そのはずなんだがね。不思議なことだ」
仏教はともかく、神道では酒と馴染みがないわけではないのにと、俺は首を傾げる。
「ふうん。今の日本ではお酒を飲むことが悪いことなんですね」
「いや、そういうわけではないよ」
「では、悪いことって何でしょう?」
「法に反することさ」
即答した俺に、テラさんはにっこりと笑った。
「何か?」
「いいえ。ところで」
悪意のまるで見えない無邪気な表情を浮かべて彼女は言う。
「最近、この辺りで人は死んでいますか?」
微笑を浮かべながら口にする言葉ではないと、俺は首の後ろが冷たくなる思いがする。
「そりゃ、毎日のようにいるよ。交通事故や、病気や」
「殺人や?」
「物騒だな?」
俺は思わず眉をひそめる。
「不愉快でしたらすみません。ただ私も好きでこんなことをお聞きしているのではないのです。仕事ですから、仕方なく」
「仕事?」
マスコミ関係者だろうか。だとしたら、このような質問がぽんと出てくる理由に思い当りがある。
「ちまたの「正義の刃」でも記事にしようっていうのかな?」
「「正義の刃」とは?」
「ああ、外国までは知られていないのか。日本ではけっこう騒がれているんだがね」
「よろしければ、どんな話か聞かせて頂けますか」
「君の興味のある、人の殺される話だよ」
皮肉をこめた俺の言葉に、彼女は頷く。
「それが聞きたいんです」
仕事といいながらいたく乗り気じゃないか。俺は目を細める。
まあいい。俺が話せることといえば、日本のマスコミで散々報道されている程度のことだ。
「ここ五年での連続殺人事件のことだよ。わかっている限りで二十三件。被害者はいずれも心臓を一突きにされて即死している。だが手掛かりのほとんどが不明なんだ」
「どうしてです? 現代の科学を持ってすれば、一本の髪の毛のような小さなものからでも犯人を辿れるはずでしょう。そして人間ならば、痕跡を全く残さないことは不可能のはず」
「ありすぎてわからないんだ」
俺はジョッキを置いて告げる。
「被害者は公衆の面前で殺されてる。人通りの多い大通りやラッシュ時の駅、真昼の遊園地なんてのもある。もちろん警察も現場を封鎖して調べたが、人も物も多すぎて犯人にかかわるものか特定できない。おそらく人にまぎれて逃げてしまったんだろう」
手を組みかえて、俺はその上にあごをつく。
「でも大量の目撃者たちは被害者が死んだ所を見ているが、誰も人が殺される所を見ていない」
「というと?」
「皆、こう言う。「被害者がいきなり胸から血を噴き出して倒れた」と」
胸から血が噴き出す瞬間は刃物を抜いた時のはずだ。人通りの多いところでそんな派手なことをすれば、誰かの目に止まる。そうでなくとも、前後に不自然な動きをしている人間を見ていておかしくない。
「殺しのプロなのでは?」
「そう言われていた。だがある時、駅構内での事件で、監視カメラに事件の瞬間が映っていたんだ」
俺もその映像を見た。そしてこの事件の異常性を目の当たりにすることになったのだ。
「本当に、いきなり被害者が血を噴いて倒れたんだ。カメラは千分の一秒までコマ割りできるが、どの瞬間にも被害者が刺される瞬間は映っていなかった」
「それなら殺人ではなく、事故死や病死なのでは?」
「次にそう騒がれたさ。凶器はみつかってないんだからな」
被害者の病歴や薬の服用状態、当時の現場の空気の成分分析まで、科学で出来る限りの分析をしたと聞く。
「それでも、被害者の死因は間違いなく心臓に外部から空いた穴によるものだそうだ。自然発生や病気ではない」
「銃とか?」
「ゼロ距離からの刺突だそうだ」
単純で確実に人を殺せる手段だ。それがますます事態を渦に引き込む。
「凶器が特定できない。いつまで経っても、「刃物のようなもの」としか」
「失礼ですが、あなたは検事と仰いましたよね」
俺が頷くと、テラさんは不思議そうに問いかけた。
「あなたなら、毎日とはいわずとも、犯人や凶器のわからないだけの事件など、数多く扱っているのではないですか?」
俺は肯定しなかったが否定もしなかった。
いくら科学が発達しようと綿密な捜査をしようと、拾いきれないことはある。ただそれを仕方ないことだと片付けるわけにはいかなかった。
「なぜそれらの殺人事件を、「正義の刃」というのですか?」
核心部分を摘みあげられて、俺は小さく息をつく。
「……被害者が全員、人を殺した者なんだ」
テラさんと目が合った。
「裁かれなかった者だけ。正当防衛で釈放されていたり、事件当時心神喪失者だったり、逃亡中だったり」
「つまり、法では裁けない殺人者を裁く、正義のような存在だと」
俺は奥歯に力が入るのを感じた。
「馬鹿げてる。法で裁かれないのはそう社会で決めたからだ。独断で死を与えるなんて許されない」
「けれどマスコミや世間では、「正義の刃」というのですね?」
俺の不快感を察したようで、彼女は少し黙った。
日本の外から今着いたばかりの年若い旅行者にはどう見えるのだろう。ふいに気になって、俺は訊いてみることにした。
「率直に、君はどう思う」
彼女は軽く頷いてすんなりと答えた。
「生きた人間以外のものが起こしている事件なのでしょう」
「動物ということ?」
「魔物」
一瞬彼女の黒い瞳が底知れぬ暗黒のように見えて、俺は知らず息を呑む。
ふっと彼女は表情を緩めて首を傾けた。
「なんていうのはどうでしょう。格別の想像力もないので、こんな陳腐な発想になってしまいますが」
「……いや」
俺は気づかない内に熱くなっていた頭がクールダウンしていくのを感じた。
「きっとそうなんだろう。人を殺すという狂気に取りつかれた何者かが、犯人なんだろうな」
それを魔物と表現することも間違ってはいないはずだ。
しばらく二人、無言でビールを飲んでいた。
「からんで申し訳ない」
「いいえ」
にこやかに彼女は相槌を打った。
「あなたは特別、その事件に思い入れがあるように見受けられました」
「個人的に追っているんだ」
「どうして?」
話してみてもいいかもしれない。手掛かりは、どんな些細なものでも欲しいのだ。
「……生きていれば君くらいの年だな」
ため息と共に言葉を零して、俺は懐から手帳を取り出す。
「世間では五年前からだといわれているが、俺はこの事件の始まりは十年前だと思っている。……俺の母と妻が何者かに殺された」
テラさんは気の毒そうな素振りも、驚く様子も見せなかった。全くの傍観者としての態度を見て、俺はかえって話しやすくなる。
「そのとき、俺の一人娘が行方不明になった」
身の側から離したことのない、小さな娘の写真を取り出して見せる。
「氷牙正子。当時八歳だ」
とびきり元気で、悪戯っ子で、そしてかわいかった娘。肩車した時のぬくもりも、おとうさんと呼ぶ声も、どんな出来事だって昨日のことのように思い出せるのに、現実に掴むことができない。
身代金ならいくらでも出す覚悟だった。警察が諦めた後も手を尽くして探しまわった。けれど事件から十年たった今でも正子はみつからない。
「どんなことでもする。正子が無事に帰ってくるなら」
どこかで生きていると信じている。信じずにはいられない。あの子の亡きがらなんて見た日には、俺は今度こそ気が狂う。
「……そして必ず犯人を法の裁きにかける」
十年前のあの日から、その時のためだけに俺は生きている。
少し世間話をしていた。最近の日本のニュース、流行の帽子の形なんて話も出た。正直若い人の流行はわかりかねたが、知っている限りで話に乗った。
約束通りビールを一杯飲み終わったところで、テラさんは立ち上がる。
「お話ありがとうございます。少々失礼しますね。今晩の宿の交渉に行ってまいりますので」
「宿も決めてないのか?」
夜も更けてきている。ビジネスホテルでも一杯かもしれない。
「大丈夫です。あてはあります」
テラさんは代金を払って、人波の中を滑るように歩いていく。
俺は二杯目のビールを頼もうかと思っていると、入り口の方が騒がしいことに気付く。
「ん?」
あの二人組は俺の良く知る警官だ。いぶかしんで目を細めると、二人組は俺に気づいて歩いてくる。
二人は俺の前で立ち止まった。
「氷牙貴正。三十八歳。職業、地検の検事」
「年齢は言わないでくれ。これでも若いつもりでいるんだから」
嫌な予感はしたが、俺は少しだけ口の端を上げた。
警官の二人組は警察手帳を見せて言う。
「署まで御同行願えるか」
俺はゆっくりと問う。
「夜遅くまで職務ご苦労だが、どのような用件だろうか?」
「二時間ほど前、山根愛理の遺体が発見された」
さすがに俺は瞬時に眉を寄せた。
「……山根が?」
「そう。お前のかつての同僚で愛人が殺された」
片方の刑事が皮肉げに言うのを、もう片方がたしなめるように見やる。
俺は呆然としたが、すぐに直感が頭をよぎる。
「もしかして、容疑者は「刃」か?」
最近では警察内部でも、一連の「正義の刃」連続殺人の犯人のことをそう呼ぶ。
黙っていた方の警官が目を動かす。俺はそれで、刃と関係があることに気付いた。
「お前は母親と妻を殺したのが彼女だと考えていたそうじゃないか。娘を帰してくれとずいぶん迫ったとも聞く」
「確かに俺は彼女を責めた」
それは事実だ。母は人格者で知られていたし、妻は大人しい女だった。誰でも故人をそういうものだが、二人を恨むような者はそう思いつかなかった。
「だが俺は山根と愛人関係だったことはないし、責めたのも一時だけで後はほとんど縁が切れていた」
「言いわけをするな!」
年かさの警官の方が怒声を響かせた。
「あまり騒がないでくれ。ここは静かに酒を飲む場所なんだ」
俺とて十数年この業界で仕事をしている。手で制して立ち上がろうとした。
「何事ですか」
声を聞き咎めたのか、凛とした声が俺たちの間に割って入る。
不機嫌に振り返った警官たちの息を呑む音が聞こえた。
光沢のあるブロンドの髪を後ろで縛っていて、細工物を思わせるほどに整った目鼻立ちをした少年がそこにいた。
「ここは神の血を頂く場所ですよ」
年若くして神父である彼は、教会の信者たちに神の作った芸術品だと崇拝されている。身につけているのは質素な黒いスータンに過ぎないのに、立っているだけで光が溢れるような錯覚を持つ。彼の声に、天使を思う。
「平穏を乱す者は出て行きなさい」
静寂そのものをまとって、彼は言葉を失った警官に告げる。
「この場合は出ていくのは俺の方だな、聖也君」
俺は立ちあがって手を上げる。
「いいんだ。ちょうど行こうとしていたところだから」
代金を置いて、俺は鞄を取る。聖也君は、宝石のような青い目でじっと警官たちを見ていた。
「署へ同行しよう」
事件の情報も入るかもしれない。かつての同僚の死すら手段に代えてしまう自分に嫌気を覚えるが、やめようとは思わない。
待っていてくれ、正子。父さんは必ずお前を助け出す。
「正義の刃」などという馬鹿げた殺人鬼は、俺がこの手で法の裁きにかけてみせるから。
店の出口を踏み越えようとした時、俺は耳元で囁く声を聞いた。
「お気をつけて。正義の刃は、正しいものを貫くまで終わりませんから」
思わず振り返ると、シルクハットを被った少女の姿が人波に消えるのが見えた。
あんな遠くから声が聞こえるわけがない。幻覚といい、俺は少々疲れているらしいと首を横に振る。
すっかり日の落ちた暗闇の中に、俺は一歩足を踏み出した。
職場から各駅停車の電車で二駅分、そこから徒歩十五分。格別の娯楽施設もビルもない小さな街に、ひっそりと佇む白い教会がある。
教会に隣接した、中世の酒場のような独特の雰囲気の店が目的だ。
古めかしい木造りの建物で、淡い赤茶色の照明が浮く。耳を澄ませないとわからないくらいの小音量で音楽がかかる程度で、客もぼそぼそとした声でしか話さない。飲み屋だというのに不思議と静粛な気分になってしまう。
ここに来ると現代の日本にいることを忘れそうになる。
カウンターでビールを頼もうとした時、俺は微かな空気の流れを感じて振り向く。
壁紙でもめくるように、ぺらりと空がはがれた。
何もない空中から、眩しいほどの長い銀髪と銀色の目をした少女が抜け出てくる。ステッキを片手に、マジシャンのような燕尾服をひらめかせて。
「え?」
俺は自分の目が信じられずに瞬きをする。
トン、とカウンターに何かが置かれた音で、俺は幻覚から目覚めた。
いつ来たのか、俺の隣の席には高校生ほどの少女が座っていた。ショートカットの黒髪に黒い瞳で、涼やかな目元をした綺麗な子だった。
ただまさか燕尾服など着ておらず、ステッキも持っていなかった。
「こんばんは」
俺が見ているのに気付いたのか、少女は愛想よく微笑んで挨拶してきた。
彼女の手元には黒いシルクハットが置かれている。先ほどの音はこの帽子を置いた音だったらしい。
「私、どこか変ですか?」
柔らかな声音で問いかけてきたので、俺ははっとして現在の自分を取り戻す。
「いや。変わった帽子だな、と」
「ああ。時代外れの形でしたか」
彼女は帽子を手にとって小さく頷く。
「うっかりしていました。今到着したばかりなもので」
「君、日本の人じゃないね」
流暢な日本語を話しているが、どこか違和感がある。黒髪黒目だが、日本人の顔立ちではない。
「旅行者なんです。テラといいます」
「それは名字? 名前?」
「名前です」
「そう。テラさん。早速だが、君は未成年じゃないか?」
彼女はメニュー表を物色しながら苦笑する。
「そういうあなたは、警察の方ではありませんか?」
「いい勘をしているが、俺は検事なんだ」
「一杯だけ見逃してもらえませんか?」
テラと名乗った少女は目を細めて赤茶色の店内を見上げる。
「ここのビールがおいしいと聞いて遠くから来たのです」
「まあ、いいよ。旅行だものね」
補導は俺の職務ではないし、第一今は職務時間外だ。
俺とテラさんは一杯ずつビールを注文した。まもなく、木のジョッキに入ったビールが出される。
ひと口飲んで、俺は何気なく口を開く。
「ここのビールは隣の教会が作っているらしいよ」
「そうらしいですね」
「教会と酒場という組み合わせは多少違和感があるね。何か悪いことをしているような気持ちにさせられる」
入口に掲げられた十字架を見やって、テラさんは首を傾げる。
「そうですか? 西洋には教会で作っているワインやビールも多いですよ。元々、信仰の中にお酒が組み込まれているんですから」
「そのはずなんだがね。不思議なことだ」
仏教はともかく、神道では酒と馴染みがないわけではないのにと、俺は首を傾げる。
「ふうん。今の日本ではお酒を飲むことが悪いことなんですね」
「いや、そういうわけではないよ」
「では、悪いことって何でしょう?」
「法に反することさ」
即答した俺に、テラさんはにっこりと笑った。
「何か?」
「いいえ。ところで」
悪意のまるで見えない無邪気な表情を浮かべて彼女は言う。
「最近、この辺りで人は死んでいますか?」
微笑を浮かべながら口にする言葉ではないと、俺は首の後ろが冷たくなる思いがする。
「そりゃ、毎日のようにいるよ。交通事故や、病気や」
「殺人や?」
「物騒だな?」
俺は思わず眉をひそめる。
「不愉快でしたらすみません。ただ私も好きでこんなことをお聞きしているのではないのです。仕事ですから、仕方なく」
「仕事?」
マスコミ関係者だろうか。だとしたら、このような質問がぽんと出てくる理由に思い当りがある。
「ちまたの「正義の刃」でも記事にしようっていうのかな?」
「「正義の刃」とは?」
「ああ、外国までは知られていないのか。日本ではけっこう騒がれているんだがね」
「よろしければ、どんな話か聞かせて頂けますか」
「君の興味のある、人の殺される話だよ」
皮肉をこめた俺の言葉に、彼女は頷く。
「それが聞きたいんです」
仕事といいながらいたく乗り気じゃないか。俺は目を細める。
まあいい。俺が話せることといえば、日本のマスコミで散々報道されている程度のことだ。
「ここ五年での連続殺人事件のことだよ。わかっている限りで二十三件。被害者はいずれも心臓を一突きにされて即死している。だが手掛かりのほとんどが不明なんだ」
「どうしてです? 現代の科学を持ってすれば、一本の髪の毛のような小さなものからでも犯人を辿れるはずでしょう。そして人間ならば、痕跡を全く残さないことは不可能のはず」
「ありすぎてわからないんだ」
俺はジョッキを置いて告げる。
「被害者は公衆の面前で殺されてる。人通りの多い大通りやラッシュ時の駅、真昼の遊園地なんてのもある。もちろん警察も現場を封鎖して調べたが、人も物も多すぎて犯人にかかわるものか特定できない。おそらく人にまぎれて逃げてしまったんだろう」
手を組みかえて、俺はその上にあごをつく。
「でも大量の目撃者たちは被害者が死んだ所を見ているが、誰も人が殺される所を見ていない」
「というと?」
「皆、こう言う。「被害者がいきなり胸から血を噴き出して倒れた」と」
胸から血が噴き出す瞬間は刃物を抜いた時のはずだ。人通りの多いところでそんな派手なことをすれば、誰かの目に止まる。そうでなくとも、前後に不自然な動きをしている人間を見ていておかしくない。
「殺しのプロなのでは?」
「そう言われていた。だがある時、駅構内での事件で、監視カメラに事件の瞬間が映っていたんだ」
俺もその映像を見た。そしてこの事件の異常性を目の当たりにすることになったのだ。
「本当に、いきなり被害者が血を噴いて倒れたんだ。カメラは千分の一秒までコマ割りできるが、どの瞬間にも被害者が刺される瞬間は映っていなかった」
「それなら殺人ではなく、事故死や病死なのでは?」
「次にそう騒がれたさ。凶器はみつかってないんだからな」
被害者の病歴や薬の服用状態、当時の現場の空気の成分分析まで、科学で出来る限りの分析をしたと聞く。
「それでも、被害者の死因は間違いなく心臓に外部から空いた穴によるものだそうだ。自然発生や病気ではない」
「銃とか?」
「ゼロ距離からの刺突だそうだ」
単純で確実に人を殺せる手段だ。それがますます事態を渦に引き込む。
「凶器が特定できない。いつまで経っても、「刃物のようなもの」としか」
「失礼ですが、あなたは検事と仰いましたよね」
俺が頷くと、テラさんは不思議そうに問いかけた。
「あなたなら、毎日とはいわずとも、犯人や凶器のわからないだけの事件など、数多く扱っているのではないですか?」
俺は肯定しなかったが否定もしなかった。
いくら科学が発達しようと綿密な捜査をしようと、拾いきれないことはある。ただそれを仕方ないことだと片付けるわけにはいかなかった。
「なぜそれらの殺人事件を、「正義の刃」というのですか?」
核心部分を摘みあげられて、俺は小さく息をつく。
「……被害者が全員、人を殺した者なんだ」
テラさんと目が合った。
「裁かれなかった者だけ。正当防衛で釈放されていたり、事件当時心神喪失者だったり、逃亡中だったり」
「つまり、法では裁けない殺人者を裁く、正義のような存在だと」
俺は奥歯に力が入るのを感じた。
「馬鹿げてる。法で裁かれないのはそう社会で決めたからだ。独断で死を与えるなんて許されない」
「けれどマスコミや世間では、「正義の刃」というのですね?」
俺の不快感を察したようで、彼女は少し黙った。
日本の外から今着いたばかりの年若い旅行者にはどう見えるのだろう。ふいに気になって、俺は訊いてみることにした。
「率直に、君はどう思う」
彼女は軽く頷いてすんなりと答えた。
「生きた人間以外のものが起こしている事件なのでしょう」
「動物ということ?」
「魔物」
一瞬彼女の黒い瞳が底知れぬ暗黒のように見えて、俺は知らず息を呑む。
ふっと彼女は表情を緩めて首を傾けた。
「なんていうのはどうでしょう。格別の想像力もないので、こんな陳腐な発想になってしまいますが」
「……いや」
俺は気づかない内に熱くなっていた頭がクールダウンしていくのを感じた。
「きっとそうなんだろう。人を殺すという狂気に取りつかれた何者かが、犯人なんだろうな」
それを魔物と表現することも間違ってはいないはずだ。
しばらく二人、無言でビールを飲んでいた。
「からんで申し訳ない」
「いいえ」
にこやかに彼女は相槌を打った。
「あなたは特別、その事件に思い入れがあるように見受けられました」
「個人的に追っているんだ」
「どうして?」
話してみてもいいかもしれない。手掛かりは、どんな些細なものでも欲しいのだ。
「……生きていれば君くらいの年だな」
ため息と共に言葉を零して、俺は懐から手帳を取り出す。
「世間では五年前からだといわれているが、俺はこの事件の始まりは十年前だと思っている。……俺の母と妻が何者かに殺された」
テラさんは気の毒そうな素振りも、驚く様子も見せなかった。全くの傍観者としての態度を見て、俺はかえって話しやすくなる。
「そのとき、俺の一人娘が行方不明になった」
身の側から離したことのない、小さな娘の写真を取り出して見せる。
「氷牙正子。当時八歳だ」
とびきり元気で、悪戯っ子で、そしてかわいかった娘。肩車した時のぬくもりも、おとうさんと呼ぶ声も、どんな出来事だって昨日のことのように思い出せるのに、現実に掴むことができない。
身代金ならいくらでも出す覚悟だった。警察が諦めた後も手を尽くして探しまわった。けれど事件から十年たった今でも正子はみつからない。
「どんなことでもする。正子が無事に帰ってくるなら」
どこかで生きていると信じている。信じずにはいられない。あの子の亡きがらなんて見た日には、俺は今度こそ気が狂う。
「……そして必ず犯人を法の裁きにかける」
十年前のあの日から、その時のためだけに俺は生きている。
少し世間話をしていた。最近の日本のニュース、流行の帽子の形なんて話も出た。正直若い人の流行はわかりかねたが、知っている限りで話に乗った。
約束通りビールを一杯飲み終わったところで、テラさんは立ち上がる。
「お話ありがとうございます。少々失礼しますね。今晩の宿の交渉に行ってまいりますので」
「宿も決めてないのか?」
夜も更けてきている。ビジネスホテルでも一杯かもしれない。
「大丈夫です。あてはあります」
テラさんは代金を払って、人波の中を滑るように歩いていく。
俺は二杯目のビールを頼もうかと思っていると、入り口の方が騒がしいことに気付く。
「ん?」
あの二人組は俺の良く知る警官だ。いぶかしんで目を細めると、二人組は俺に気づいて歩いてくる。
二人は俺の前で立ち止まった。
「氷牙貴正。三十八歳。職業、地検の検事」
「年齢は言わないでくれ。これでも若いつもりでいるんだから」
嫌な予感はしたが、俺は少しだけ口の端を上げた。
警官の二人組は警察手帳を見せて言う。
「署まで御同行願えるか」
俺はゆっくりと問う。
「夜遅くまで職務ご苦労だが、どのような用件だろうか?」
「二時間ほど前、山根愛理の遺体が発見された」
さすがに俺は瞬時に眉を寄せた。
「……山根が?」
「そう。お前のかつての同僚で愛人が殺された」
片方の刑事が皮肉げに言うのを、もう片方がたしなめるように見やる。
俺は呆然としたが、すぐに直感が頭をよぎる。
「もしかして、容疑者は「刃」か?」
最近では警察内部でも、一連の「正義の刃」連続殺人の犯人のことをそう呼ぶ。
黙っていた方の警官が目を動かす。俺はそれで、刃と関係があることに気付いた。
「お前は母親と妻を殺したのが彼女だと考えていたそうじゃないか。娘を帰してくれとずいぶん迫ったとも聞く」
「確かに俺は彼女を責めた」
それは事実だ。母は人格者で知られていたし、妻は大人しい女だった。誰でも故人をそういうものだが、二人を恨むような者はそう思いつかなかった。
「だが俺は山根と愛人関係だったことはないし、責めたのも一時だけで後はほとんど縁が切れていた」
「言いわけをするな!」
年かさの警官の方が怒声を響かせた。
「あまり騒がないでくれ。ここは静かに酒を飲む場所なんだ」
俺とて十数年この業界で仕事をしている。手で制して立ち上がろうとした。
「何事ですか」
声を聞き咎めたのか、凛とした声が俺たちの間に割って入る。
不機嫌に振り返った警官たちの息を呑む音が聞こえた。
光沢のあるブロンドの髪を後ろで縛っていて、細工物を思わせるほどに整った目鼻立ちをした少年がそこにいた。
「ここは神の血を頂く場所ですよ」
年若くして神父である彼は、教会の信者たちに神の作った芸術品だと崇拝されている。身につけているのは質素な黒いスータンに過ぎないのに、立っているだけで光が溢れるような錯覚を持つ。彼の声に、天使を思う。
「平穏を乱す者は出て行きなさい」
静寂そのものをまとって、彼は言葉を失った警官に告げる。
「この場合は出ていくのは俺の方だな、聖也君」
俺は立ちあがって手を上げる。
「いいんだ。ちょうど行こうとしていたところだから」
代金を置いて、俺は鞄を取る。聖也君は、宝石のような青い目でじっと警官たちを見ていた。
「署へ同行しよう」
事件の情報も入るかもしれない。かつての同僚の死すら手段に代えてしまう自分に嫌気を覚えるが、やめようとは思わない。
待っていてくれ、正子。父さんは必ずお前を助け出す。
「正義の刃」などという馬鹿げた殺人鬼は、俺がこの手で法の裁きにかけてみせるから。
店の出口を踏み越えようとした時、俺は耳元で囁く声を聞いた。
「お気をつけて。正義の刃は、正しいものを貫くまで終わりませんから」
思わず振り返ると、シルクハットを被った少女の姿が人波に消えるのが見えた。
あんな遠くから声が聞こえるわけがない。幻覚といい、俺は少々疲れているらしいと首を横に振る。
すっかり日の落ちた暗闇の中に、俺は一歩足を踏み出した。