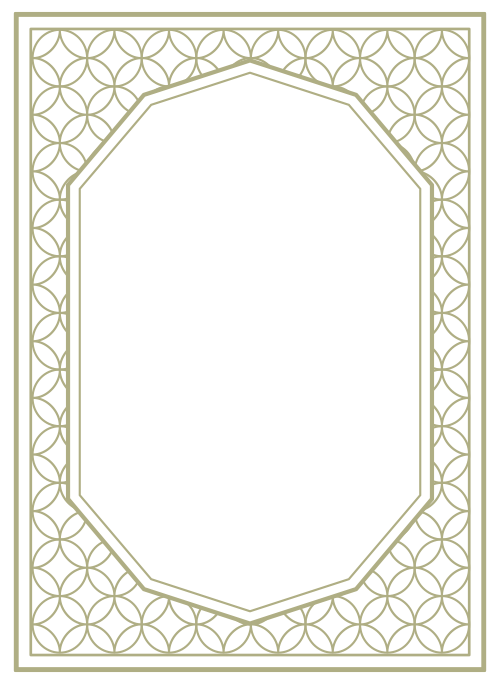*
玲人が転校してきて、あっという間に九月は過ぎ去った。相変わらず玲人があかねを頼りに学校生活を送る日々は続き、あかねの高校生活は一気に薔薇色に彩られた。推しに頼られているという事実が、あかねを高揚させる。
マイスクールライフイズソーハピー!!
あかねがそう脳内で連呼し、ファンファーレが鳴り響く日々は続いた。
十月に入り、文化祭が来月に控える中、今日はクラスで文化祭の出し物の選定だ。体育祭は運動の得手不得手で生徒の受け止め方が異なるが、文化祭はお祭りなので、基本的にみんな乗り気だ。このクラスメイトたちとどんな思い出を作ろうかと、皆で知恵を出し合って考える。
「あのう」
ひとりの女子が挙手をして立ち上がる。文化祭委員が意見を求めると、その女子は笑顔でこう言った。
「折角暁くんと小林くんが居るんだから、二人をリーダーにして執事喫茶とかだと盛り上がりそうだし、お客さんもたくさん来てくれると思います」
女子の発言に、クラス中が色めきだった。
もともと光輝は女子の中で支持率の高い男子だったし(あかねが光輝と一緒に居てやっかみを受けなかったのは、その玲人への崇拝と、光輝に対する圧倒的な関心のなさからだった)、玲人はといえば、未だに休み時間に彼の顔を見ようと、他のクラスの女子たちが廊下に鈴なりになっている状態だ。それを思えば、彼らを祭り上げるだけで集客効果はばっちりだろう。
その考えはクラス中に共有されたらしく、いいね! とか、じゃあ二人以外の執事も厳選して、なんて言葉が飛び交う。そんな中、玲人は恐縮した様子で笑っていたが、あかねには玲人が考えていることが分かってしまった。
……玲人は『FTF』のリーダーに推薦されたときも遠慮していた。みんなでリーダーの気持ちを持ってやっていけば良いじゃないか、という思想の持ち主だった。自分一人だけが目立つのではなく、皆で輝きたい、そういう思考の持ち主だった。だからこそ、あかねはそんな玲人を敬愛し、推しとして崇め奉ることを厭わなかった。
玲人は人格者だ。それ故、入ったばかりのこのクラスでは波風立てないようにみんなの意見に反対しないだろう。それが玲人の『普通の高校生になりたい』という希望に適っていなくてもだ。
そう思ったら、あかねは自然と挙手していた。
「はい、高橋さん」
文化祭委員があかねを挿し、あかねは椅子から立ち上がった。
「……特定の人を祭り上げるのはどうかなと思います。もっと……、皆でクラスを盛り上げることが大事だと思います」
あかねの心臓は、ドッキンバックンと鳴っていた。クラスの八割が賛成しているような状況で、反対意見を言うのは勇気が要った。でも、玲人がこのままお祭りに祭り上げられてしまうのは見過ごせなかったのだ。
玲人たちをリーダーとする執事喫茶で盛り上がっていたクラスメイトたちがしん、としてあかねを見た。いたたまれなくて俯いたが、クラスにカッコつけと後ろ指をさされても、(光輝は兎も角)玲人の願いを守りたかった。
しん、と静まり返った教室に、声が響く。
「あの」
すいっと、あかねの隣の席の玲人が挙手した。
「僕、いいですよ。文化祭って思い出に残るものでしょう? 僕で良ければ、皆の力になりたいです」
あかねは玲人の言葉に息をのんだ。
(ああ、玲人くんはやっぱり素敵だ……。自分の自由を犠牲にしてまでもクラスに貢献しようだなんて……。もしかして『FTF』でも、そうやってみんなを引っ張ってたのかな……。それだとしたら、凄く疲れただろうな……。それなのに五年も嫌な顔一つせずに、私たちに夢を見させてくれた玲人くんは、やっぱり凄いよ……。せめて高校(ここ)では、そういうことと無縁になればいいのに……)
あかねはそう思ったが、それでも着席する間際に玲人があかねを見て微笑んでくれたから、あかねの気持ちは伝わった……、のかもしれない。光輝も挙手して立ち上がる。
「俺はそもそも楽しい事好きだから、乗り気です。このクラスで思い出に残ることしたいから」
クラスの筆頭イケメン二人が案に参加する意思を表明したところで、出し物はそのまま執事喫茶に決まった。ホームルームが終わり、教室がざわめく中、玲人は隣のあかねに声をかけてくれた。
「高橋さん、僕のことも考えてくれてありがとう」
「ううん……。光輝は兎も角、暁くんが構わないんだったらいいんだけど、……本当に良かったの?」
万に一つでも玲人が無理をしているのだったら、それは『普通の高校生』を楽しめていないことになる。今なら、もう一度話し合いの場を持つことだって可能かもしれない。そう思って確認すると、本当にいいんだよ、と玲人が楽しそうに微笑んだ。
「僕、前の学校のままだったら、準備に時間のかかる文化祭なんて体験できなかったからさ。だから、みんなと文化祭の準備が出来るのが、凄く嬉しいんだ」
そうか。玲人が楽しんでいるのならもう何も言わない。あかねも笑って、そうなんだね、と応えた。
「高橋さんはやさしいよね。授業の遅れの事気にしてくれたり、こんな経歴の僕が目立つみたいになることを気にしてくれたり」
でも、疑いのない純粋なまなざしで目を見られると、ちょっと心臓に針がぶすっと刺さったみたいに痛い。あかねは力なく、ううん、そんなことないよ、と言って俯くしかなかった。あかねの罪悪感を払しょくするように玲人があかねの顔を覗き込んで言った。
「僕、席が高橋さんの隣で良かったな。高橋さんと友達になれて良かったよ」
間近で見る推しの顔は爆裂的にきれいで美しくて世の中の全てを浄化するような微笑みだった。バクン! と心臓が拍動を打って、そのまま体中を疾走する。ぶわあーっと顔が赤くなったのを自覚した。ほっぺたがめちゃくちゃ熱い。
「あ、近かった?」
ごめんね、距離感分からなくて。
照れてそう言う玲人は、でもあかねの顔を覗き込んだまま、こう言った。
――――「今日、一緒に駅まで帰らない?」