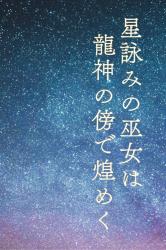ラジオ企画の放送は、オンタイムでスタートした。放送室では、俺と部長が隣合って座っている。
オープニングのBGMが流れると、部長がマイクに語りかけた。
「みなさま、十六時になりました。ここからは、ビートボクサーの瀬尾くんをお招きして、楽しくお喋りしていきたいと思います」
どこかの局のパーソナリティに寄せたダンディな口調に、思わず苦笑してしまう。部長は、完全に役に入りきっているようだ。
事前の打ち合わせでは、部長と俺の対談形式でビートボックスの歴史について語り、中盤から俺が単独でパフォーマンスする流れになっていた。だけど部長に頼んで、急遽進行を変えてもらった。
「ビートボックスを披露していただく前に、瀬尾くんが伝えたいことがあるそうです。なんでしょう、気になりますね~。ぜひともお話してもらいましょう」
みんなの前で明かすのは怖い。上手く喋れる自信もない。
だけど、入江に聞いてもらうには、この方法しか思いつかなかった。意を決してマイクと向き合う。
「こんにちは、瀬尾です。パフォーマンスの前に、少しだけお話に付き合っていただけると嬉しいです。実は先日、友達……いえ、友達になりかけていた人と喧嘩をしてしまいました」
「ほう、喧嘩ですか~。それは穏やかじゃないですねぇ」
ひとり語りにならないように、部長が聞き役として入ってきてくれる。そのアシストは、ありがたかった。
「はい。俺は普段、人と深く関わらないように、広く浅くの関係を心がけてきました。過去に強い言葉で友達を傷つけてしまった経験があるからです」
「なるほど~。その結果、孤高のビートボクサーが爆誕したわけですね」
不意に孤高弄りをされて、ずっこけそうになる。部長までそれを言うのか……。本番で弄ってくるなんて反則だぞ。
だけど、まあ、いいか。今更格好なんてつかないんだ。ありのままを曝け出そう。
「そういうことです。ずっと孤高を気取ってきましたが、二学期になってからある人と出会いました。彼は、俺とは違って人との輪を大切にする人です。優しくて、真っすぐで、そんな性格だから時には利用されることもあって……。彼が傷ついているのを見ているとこっちまで痛くなるから、勢い余って傷つけるようなことを言ってしまったんです。それが彼にとっての致命傷になると分かっていながら……」
語っているうちにも、真っ赤な顔をした入江を思い出して、キリッと胸が痛んだ。
「要するに、瀬尾くんは、傷つけてしまった彼と仲直りしたいと」
「はい」
一拍置いてから、俺は校舎のどこかで俯いている入江に伝えた。
「あの時は、酷い言葉を浴びせて申し訳ありませんでした。俺の言葉選びが下手くそ過ぎました。本当に伝えたかったのは、あんな言葉じゃないんです」
入江の奏でる優しい音色を思い出しながら訴えた。
「無理に合わせなくたっていい。言いたいことは、はっきり言っていい。それで切れるような繋がりなんて、その程度だったんだ」
本当の気持ちを隠して、その場しのぎの浅い会話だけを繰り返す関係に、俺は『友達』と名付けられなかった。
俺から見れば、黒田たちとの関係なんて偽物だ。いままでの俺たちの関係だって……。
「俺は、お前と本当の友達になりたい。最初は音楽を通して繋がっていれば十分だと思っていたけど、今はもうそれだけじゃ物足りないんだ。もっと深い所で繋がっていたい」
俺は小さく息を吐き出してから、願いを伝えた。
「俺のことを許してくれるなら、もう一度セッションしよう」
これが俺の、嘘偽りない言葉だ。入江にも届くと信じて――。
沈黙が流れる。ラジオとしては致命的だ。
その場を取りなすように、部長が慌ててマイクに身を寄せた。
「えー、瀬尾くんの想いが、彼にも届くといいですね。ここからは、お待ちかねのビートボックスを披露していただきましょう。アツイビートを刻んでください」
ぎゅっと心臓が縮こまる。
……そうだよな。そういう進行で予定していたんだもんな。部長は何も悪くない。
もの寂しさを感じながら、俺はマイクを引き寄せた。
歯の隙間から息を吐き出して、シューッと蒸気のように音を鳴らす。そこからエンジンをかけたように、16ビートで激しくリズムを刻んだ。
入江と合わせている時よりも音数が多いはずなのに、叩けば叩くほど虚しくなってくる。今まではビートボックス単体でも、かっこよく思えたのに、今は不完全さが際立っていた。
足りない。足りない。俺だけじゃ駄目なんだ。
心が空っぽになっていくのを感じながら、無心でビートを刻み続けた。
あと、どれくらい続ければいいんだろう? 机に置かれたタイマーに視線を向けようとした時、放送室の外からバタバタと足音が聞こえた。
なんだ?
パフォーマンスを中断して振り返ると、扉を突き破りそうな勢いで誰かが入ってくる。
それは、待ち望んでいた人物だった。
「入江……」
ギターを抱えた入江が、放送室に飛び込んできた。ダッシュしてきたのか、呼吸は乱れている。入江は汗で張り付いた前髪をかきあげてから、清々しい笑顔を浮かべた。
「瀬尾、俺も交ぜて!」
ラジオ企画と後夜祭のリハーサルは、時間が被っていたはずだ。入江は、黒田たちのバンドを抜け出して、ここに駆けつけてきてくれたということか?
サプライズゲストの登場で、部長のテンションも上がる。
「なんと! 思いを伝えた彼が、この場に駆けつけてくれました! これはアツイ展開になりましたよ~。ささ、お隣へどうぞ」
部長が席を譲ると、入江は俺の隣に座る。すると、不完全だったパズルのピースが揃ったようにしっくりきた。
入江は呼吸を落ち着かせてから、マイクを握る。
「俺も、瀬尾に伝えたいことがあります。初めて会った日から、瀬尾には感謝していました。ギターの音を聞くと、悲しいことや惨めなことを思い出すから、もう弾くのはやめようと思っていたけど、瀬尾と合わせてギターの楽しさを思い出したんです」
やっぱりあの時、入江はギターをやめようと思っていたのか。その場にタイミングよく居合わせたのは、いま考えればラッキーだったのかもしれない。
「瀬尾には、痛い所を突かれました。自分の弱さを見透かされて、恥ずかしくて、情けなくて……」
入江は当時を思い返すように、拳を握って俯く。その頬は、保健室で見た時のように赤く染まっていた。フォローしようと口を開きかけた時、入江はバッと勢いよく顔を上げた。
「だけど、あの日の言葉は、俺を貶めようとしていたわけじゃない。弱い俺に、喝を入れようとしてくれたんだって分かったんです。あんなにアツくなって真正面からぶつかってくるのは、瀬尾が初めてだ」
思いがけない言葉に放心していると、隣に座った入江が手を差し伸べる。
「俺も、瀬尾との繋がりを“その程度”で終わらせたくない。仲直りして、友達になりたい」
差し伸べられた手をじっと見つめる。その手に触れてもいいのだろうか?
「……俺、言葉選びが下手くそだから、また傷つけるかもしれないよ?」
この場に及んで躊躇している情けない俺の手を、入江は強く掴んだ。
「いいよ、それでも。次、言われたら、はっきり言い返すから」
そう宣言する入江は、いつになく強気な顔をしていた。
目頭が熱くなってくる。マズイ。泣きそうだ。歯を食いしばって泣くのを堪えていると、後ろで待機していた部長が腕時計を指さす。
タイマーを見ると、残り時間は七分になっていた。入江の得意なバラードなら演奏できる。
「入江、いけるか? 三曲目のバラード」
涙を振り切るように威勢よく尋ねると、入江は初めてセッションした時のように目を輝かせた。
「うん!」
大丈夫だ。俺たちは、ここからやり直せる。
互いの意思確認をするように頷いてから、俺たちは演奏を始めた。
スピーカーを通して、二人の音色が校内に響き渡る。アコースティックギターの優しい音色に寄り添うように、俺はビートを刻んだ。
不完全だった音が、ようやく完成した。二人で奏でる音色が、戻ってきた瞬間だった。
ビートを刻みながら、この穏やかで心地よい時間が永遠に続けばいいと願っていた。
最後の一音を奏でると、放送室の外から盛大な拍手が聞こえてくる。
俺たちの演奏を、他の誰かに聴いてもらったのは初めてだ。嬉しいけど、ちょっと気恥ずかしい。
俺たちは照れくさそうに顔を見合わせて笑っていた。
オープニングのBGMが流れると、部長がマイクに語りかけた。
「みなさま、十六時になりました。ここからは、ビートボクサーの瀬尾くんをお招きして、楽しくお喋りしていきたいと思います」
どこかの局のパーソナリティに寄せたダンディな口調に、思わず苦笑してしまう。部長は、完全に役に入りきっているようだ。
事前の打ち合わせでは、部長と俺の対談形式でビートボックスの歴史について語り、中盤から俺が単独でパフォーマンスする流れになっていた。だけど部長に頼んで、急遽進行を変えてもらった。
「ビートボックスを披露していただく前に、瀬尾くんが伝えたいことがあるそうです。なんでしょう、気になりますね~。ぜひともお話してもらいましょう」
みんなの前で明かすのは怖い。上手く喋れる自信もない。
だけど、入江に聞いてもらうには、この方法しか思いつかなかった。意を決してマイクと向き合う。
「こんにちは、瀬尾です。パフォーマンスの前に、少しだけお話に付き合っていただけると嬉しいです。実は先日、友達……いえ、友達になりかけていた人と喧嘩をしてしまいました」
「ほう、喧嘩ですか~。それは穏やかじゃないですねぇ」
ひとり語りにならないように、部長が聞き役として入ってきてくれる。そのアシストは、ありがたかった。
「はい。俺は普段、人と深く関わらないように、広く浅くの関係を心がけてきました。過去に強い言葉で友達を傷つけてしまった経験があるからです」
「なるほど~。その結果、孤高のビートボクサーが爆誕したわけですね」
不意に孤高弄りをされて、ずっこけそうになる。部長までそれを言うのか……。本番で弄ってくるなんて反則だぞ。
だけど、まあ、いいか。今更格好なんてつかないんだ。ありのままを曝け出そう。
「そういうことです。ずっと孤高を気取ってきましたが、二学期になってからある人と出会いました。彼は、俺とは違って人との輪を大切にする人です。優しくて、真っすぐで、そんな性格だから時には利用されることもあって……。彼が傷ついているのを見ているとこっちまで痛くなるから、勢い余って傷つけるようなことを言ってしまったんです。それが彼にとっての致命傷になると分かっていながら……」
語っているうちにも、真っ赤な顔をした入江を思い出して、キリッと胸が痛んだ。
「要するに、瀬尾くんは、傷つけてしまった彼と仲直りしたいと」
「はい」
一拍置いてから、俺は校舎のどこかで俯いている入江に伝えた。
「あの時は、酷い言葉を浴びせて申し訳ありませんでした。俺の言葉選びが下手くそ過ぎました。本当に伝えたかったのは、あんな言葉じゃないんです」
入江の奏でる優しい音色を思い出しながら訴えた。
「無理に合わせなくたっていい。言いたいことは、はっきり言っていい。それで切れるような繋がりなんて、その程度だったんだ」
本当の気持ちを隠して、その場しのぎの浅い会話だけを繰り返す関係に、俺は『友達』と名付けられなかった。
俺から見れば、黒田たちとの関係なんて偽物だ。いままでの俺たちの関係だって……。
「俺は、お前と本当の友達になりたい。最初は音楽を通して繋がっていれば十分だと思っていたけど、今はもうそれだけじゃ物足りないんだ。もっと深い所で繋がっていたい」
俺は小さく息を吐き出してから、願いを伝えた。
「俺のことを許してくれるなら、もう一度セッションしよう」
これが俺の、嘘偽りない言葉だ。入江にも届くと信じて――。
沈黙が流れる。ラジオとしては致命的だ。
その場を取りなすように、部長が慌ててマイクに身を寄せた。
「えー、瀬尾くんの想いが、彼にも届くといいですね。ここからは、お待ちかねのビートボックスを披露していただきましょう。アツイビートを刻んでください」
ぎゅっと心臓が縮こまる。
……そうだよな。そういう進行で予定していたんだもんな。部長は何も悪くない。
もの寂しさを感じながら、俺はマイクを引き寄せた。
歯の隙間から息を吐き出して、シューッと蒸気のように音を鳴らす。そこからエンジンをかけたように、16ビートで激しくリズムを刻んだ。
入江と合わせている時よりも音数が多いはずなのに、叩けば叩くほど虚しくなってくる。今まではビートボックス単体でも、かっこよく思えたのに、今は不完全さが際立っていた。
足りない。足りない。俺だけじゃ駄目なんだ。
心が空っぽになっていくのを感じながら、無心でビートを刻み続けた。
あと、どれくらい続ければいいんだろう? 机に置かれたタイマーに視線を向けようとした時、放送室の外からバタバタと足音が聞こえた。
なんだ?
パフォーマンスを中断して振り返ると、扉を突き破りそうな勢いで誰かが入ってくる。
それは、待ち望んでいた人物だった。
「入江……」
ギターを抱えた入江が、放送室に飛び込んできた。ダッシュしてきたのか、呼吸は乱れている。入江は汗で張り付いた前髪をかきあげてから、清々しい笑顔を浮かべた。
「瀬尾、俺も交ぜて!」
ラジオ企画と後夜祭のリハーサルは、時間が被っていたはずだ。入江は、黒田たちのバンドを抜け出して、ここに駆けつけてきてくれたということか?
サプライズゲストの登場で、部長のテンションも上がる。
「なんと! 思いを伝えた彼が、この場に駆けつけてくれました! これはアツイ展開になりましたよ~。ささ、お隣へどうぞ」
部長が席を譲ると、入江は俺の隣に座る。すると、不完全だったパズルのピースが揃ったようにしっくりきた。
入江は呼吸を落ち着かせてから、マイクを握る。
「俺も、瀬尾に伝えたいことがあります。初めて会った日から、瀬尾には感謝していました。ギターの音を聞くと、悲しいことや惨めなことを思い出すから、もう弾くのはやめようと思っていたけど、瀬尾と合わせてギターの楽しさを思い出したんです」
やっぱりあの時、入江はギターをやめようと思っていたのか。その場にタイミングよく居合わせたのは、いま考えればラッキーだったのかもしれない。
「瀬尾には、痛い所を突かれました。自分の弱さを見透かされて、恥ずかしくて、情けなくて……」
入江は当時を思い返すように、拳を握って俯く。その頬は、保健室で見た時のように赤く染まっていた。フォローしようと口を開きかけた時、入江はバッと勢いよく顔を上げた。
「だけど、あの日の言葉は、俺を貶めようとしていたわけじゃない。弱い俺に、喝を入れようとしてくれたんだって分かったんです。あんなにアツくなって真正面からぶつかってくるのは、瀬尾が初めてだ」
思いがけない言葉に放心していると、隣に座った入江が手を差し伸べる。
「俺も、瀬尾との繋がりを“その程度”で終わらせたくない。仲直りして、友達になりたい」
差し伸べられた手をじっと見つめる。その手に触れてもいいのだろうか?
「……俺、言葉選びが下手くそだから、また傷つけるかもしれないよ?」
この場に及んで躊躇している情けない俺の手を、入江は強く掴んだ。
「いいよ、それでも。次、言われたら、はっきり言い返すから」
そう宣言する入江は、いつになく強気な顔をしていた。
目頭が熱くなってくる。マズイ。泣きそうだ。歯を食いしばって泣くのを堪えていると、後ろで待機していた部長が腕時計を指さす。
タイマーを見ると、残り時間は七分になっていた。入江の得意なバラードなら演奏できる。
「入江、いけるか? 三曲目のバラード」
涙を振り切るように威勢よく尋ねると、入江は初めてセッションした時のように目を輝かせた。
「うん!」
大丈夫だ。俺たちは、ここからやり直せる。
互いの意思確認をするように頷いてから、俺たちは演奏を始めた。
スピーカーを通して、二人の音色が校内に響き渡る。アコースティックギターの優しい音色に寄り添うように、俺はビートを刻んだ。
不完全だった音が、ようやく完成した。二人で奏でる音色が、戻ってきた瞬間だった。
ビートを刻みながら、この穏やかで心地よい時間が永遠に続けばいいと願っていた。
最後の一音を奏でると、放送室の外から盛大な拍手が聞こえてくる。
俺たちの演奏を、他の誰かに聴いてもらったのは初めてだ。嬉しいけど、ちょっと気恥ずかしい。
俺たちは照れくさそうに顔を見合わせて笑っていた。