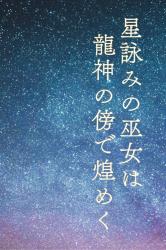秋も深まった十一月中旬。ついに文化祭当日がやってきた。
普段は男子ばかりの校舎に、女子の姿もある。そんな非日常な光景に、生徒たちは浮足立っていた。
「たこ焼き、いかがですか~! 焼きたてで美味しいですよ~」
「その二人、ぜひ二年三組に寄っていって!」
黒地に『漢』と書かれたTシャツを着たクラスメイトが、大声で呼び込みをしている。はりきって接客をするクラスメイトをパーテーションの奥から眺めながら、俺は黙々とたこ焼きの生地を作っていた。
二年三組の出し物は、漢のたこ焼き屋だ。通常よりも一回り大きいたこ焼きを作って提供している。
出し物を決める時、『飲食は当日忙しくなるからやめておけ』と反対意見があがっていたが、今はその忙しさに救われている。じっとしていたら、嫌なことばかり思い出してしまうからだ。こういう時は、単調な作業をしている方が気が紛れる。
調理スペースでひたすら生地を混ぜていると、接客をしていたクラスメイトが覗きに来る。
「瀬尾、オープンしてからずっと生地作ってんじゃん。代ろうか?」
「あー、平気、平気。接客はダルイから、裏方の方がいいし」
接客がやりたくないというのは事実だ。万が一、中学の部活のメンバーと鉢合わせたら、余計に抉られる。隠れ蓑にするにも、このパーテーションは最適だった。
「そっか。あと四十分で午前のシフトは終わるから、それまでは頼んだ」
「ういー」
軽く手を挙げて返事をすると、俺は再びたこ焼き生地製造マシーンになった。
午前中のシフトが終われば、いったんフリーになる。そして十六時からは、例のラジオ企画だ。
入江に断られた日、放送部の部室に赴いて出演を断ろうとしたが、既にプログラムを載せたパンフレットを刷ってしまったから、枠を空けるのは勘弁してほしいと部長から頼み込まれた。話し合った結果、放送部の部長と俺で、ビートボックスについてトークした後で、単独でパフォーマンスすることになった。
入江が出なければ出演する意義はないのだけれど、ここまできたらやるしかない。
午前中のシフトが終わると、クラスメイトからたこ焼きを渡された。ありがたく頂いて、静かに食べられる場所はないかと彷徨っていると、いつぞや訪れた外階段に辿り付く。
この場所は、文化祭の最中でも閑散としていてお祭りムードを感じさせない。退避場所としてはちょうど良かった。
ラジオ企画で話す内容を考えながら腹を満たしていると、階段下から複数人の足音が聞こえてくる。
なんだか、こんなシチュエーション、前にもあったぞ……。
最後のたこ焼きを口に放り込んでから、手すりから身を乗り出して下を覗いた。
下にいる面子を見て、「げっ」と顔をしかめる。そこにいたのは、黒田たちだった。見たところ、入江は一緒ではないようだ。
ここはあいつらの溜まり場だったのか? それならもう近寄らないでおこう。
そそくさと立ち去ろうとしたところで、聞き捨てならない会話が聞こえてくる。
「後夜祭のバンド、清水出れるって。さっきチャットきてた」
「マジで? 出る気あったんだ」
「みたいよ。彼女と模擬店まわってるから、十六時のリハーサルは出れないみたいだけど」
黒田が説明をすると、二人は「勝手すぎんだろ」と失笑していた。
「で、どうする? 正直、清水が出た方が目立つよなぁ。あいつイケメンだし、歌も上手いし」
「分かる。ポテンシャル高いから、練習不足でもそれなりの演奏はできるだろうし」
「上手くいけば、他校の女子とも繋がり持てるかも」
この猿どもが、と心の中で毒づく。二人が賛成すると、黒田はニタァといやらしく笑った。
「じゃあ、リハまでは入江に出てもらって、本番は清水に出てもらうか。入江には、リハが終わってから伝えればいいよな」
……は? なんだよ、それ。
最低すぎる計画に、バチンッと脳内で火花が弾ける。
黒田のお仲間は、まるで悪いとは思っていないようで「それが良い~」と笑いながら賛同していた。
意見が一致すると、黒田はくくっと口元を押さえながら満足そうに笑う。
「それにしても、入江って都合いいよな。なんだかんだ言いながらも戻って来てくれたし」
「そうそう、瀬尾と組んだって聞いた時は、は?、って思ったけど」
「俺らを裏切って、別の奴と組むとかありえねえよなー」
先に裏切ったのはそっちだろ。そう怒鳴ってやりたかったが、どうにか堪えた。
黒田たちは、俺の存在には気付かず、話を続ける。
「なんかそういうの、ラノベで流行ってるよな。追放系だっけ?」
「あー、知ってる、知ってる。ギルドを追放されて、ざまあする奴でしょ?」
「そうそう! それと同じ感じで、俺らよりも上手い演奏をして、ざまあしたかったのかもなぁ」
黒田の言葉で、二人は腹を抱えてゲラゲラ笑いだす。
「痛すぎんだろ、リアルでそれやろうとすんの」
「別に俺ら、あいつらの演奏が上手くてもなんとも思わねえし。無だわ、無」
勝手に妄想を膨らませるな。入江にお前らを貶めようなんて意図があるわけないだろ。いつも一緒にいるくせに、そんなことも分からないのか?
むしゃくしゃしていると、黒田は「ふっ」と小馬鹿にするように鼻で笑った。
「大体さぁ、こっちはたかが文化祭のバンドで高度な演奏をしようなんて思ってないし。恥かかない程度に演奏して、注目されればそれで十分」
たかが文化祭のバンド。その一言で、俺の中で何かが壊れた。
今までは、他人を刺さないように気を付けていた。だけど今は刺したくて仕方がない。
入江は、音楽が好きで、地道に練習を重ねてきた。そんな人間を都合よく扱おうとしているのは許せなかった。
黒田たちの吐く言葉は、一撃で致命傷を負わせるような鋭いものではない。仲良しごっこをしながら、相手が自由に動けなくなるように縛り付ける言葉だ。そして都合が悪くなったら、あっさりと谷底に突き落としていく。
そんな関係は、友達とは呼ばない。呼んでやるものか。こいつらは、入江にとって敵だ。
もう、我慢するのはやめた。
全身の血液が煮えたぎりそうになりながら、一段飛ばしで外階段を駆け下りる。カンカンッと迫る金属音で、黒田たちも人の気配に気付いた。
地上まで降りてきてから、黒田たちを鋭く睨みつける。
「あのさ、入江を都合よく扱うのやめろよ」
突如部外者が現れたことで、黒田はぴたっと固まる。後ろにいた二人は、顔を引きつらせてたじろいでいた。
「は? な、なんだよ、急に?」
黒田は小馬鹿にするように笑っていたが、その瞳には明らかに動揺が滲んでいる。多分、本気でぶつかり合うような喧嘩に慣れていないのだろう。
俺には、こいつらの弱い部分が見えている。そこを狙って刺しにいく。
「都合が悪くなったら切り捨てるような付き合い方をしていると、いつか自分が切られるぞ?」
黒田の顔から笑顔が消える。「ああ?」と眉間にしわを寄せて不快感を露わにした。
思った通りだ。狙いは正しかった。刺したところを、ぐりぐりと抉ってやろう。
「分かってんの? 入江を切り捨てたら、お前ら三人じゃん。体育のペアだって、ひとりあぶれることになる。相手探しでうろうろ動き回るのは、お前らにとって一番屈辱的なんじゃねーの?」
にやりと笑いながら挑発すると、黒田は顔を真っ赤に染めた。
「そんなのどーでもいいしっ! いちいち気にしてるなんて根暗すぎんだろ!」
「ふーん。じゃあ次の体育では、お前が抜けんだー。あぶれても気にしないなら、いいよなー。相手探し、がんばってー」
わざとらしく拳を握って見せると、黒田はぐっと言葉を詰まらせる。他の二人は、黒田が攻撃されても後ろで縮こまっているだけだった。
おおかた、一連の騒動を黒田に擦り付けて、切り捨てようとしているのだろう。なんて脆い関係なんだ。
彼らのグループに二対一で薄っすら線引きしたところで、真っ赤な顔をした黒田に睨まれる。
「お前、孤高のビートボクサーとか呼ばれて調子乗ってんだろ? 俺はお前らとは違います~みたいな。そういうのうぜえんだよ!」
……え? 俺、陰では『孤高のビートボクサー』なんて呼ばれてんの?
うわっ、恥ずかしっ! 今のは結構刺さったぞ。
これ以上、そのネタを引っ張られたら、こっちが負傷する。さっさと片を付けよう。
「とにかく。これ以上、入江を都合よく扱ったら許さねえからな。入江は俺の――」
――友達なんだ。
その一言は、喉の奥でつっかえて出てこなかった。俺が黙り込んだ所で、黒田は「へっ」と笑う。
「もう行こうぜ。あいつらキショイわ。できてんじゃねーの?」
黒田はそう吐き捨てると、早足で校舎裏から立ち去る。残された二人も遠慮がちに追いかけていった。
取り残された俺は、強く拳を握る。
「そんなんじゃねーよ……」
俺はただ、入江が悲しむのを見たくないだけだ。
◇
黒田たちが立ち去った後、俺は外階段で項垂れていた。
――友達なんだ。
黒田にはっきりそう言えなかったのが、ショックだった。入江と喧嘩する前だったら、堂々と宣言できていただろうか?
……いや、きっと俺は躊躇っていたと思う。人と深く関わることを避けて、入江から差し伸べられた手に、気付かないふりをしてしまったのだから。
だけど結局、俺は入江の弱いところを刺してしまった。このまま何もしなければ、入江との関係は終わってしまうだろう。放課後の空き教室で、セッションしていた時間もなかったことになる。
「やだなぁ……」
入江の優しい音色を聴けなくなることも、その音でビートを刻めなくなることも、堪らなく惜しい。時を戻してでも、あの空間に飛んでいきたかった。
もう俺たちは、弱いところを見せるくらい深く繋がってしまったんだ。今更切り捨てることなんてできない。
入江とは、音楽を通して繋がっていられたら十分だと思っていたけど、今はそれだけでは足りなく感じている。
入江と、ちゃんと話そう。耳障りのいい言葉ではなく、本当の言葉で。
――今度こそ、入江と友達になりたい。
本当の思いは、言葉にしなければ伝わらないんだ。
普段は男子ばかりの校舎に、女子の姿もある。そんな非日常な光景に、生徒たちは浮足立っていた。
「たこ焼き、いかがですか~! 焼きたてで美味しいですよ~」
「その二人、ぜひ二年三組に寄っていって!」
黒地に『漢』と書かれたTシャツを着たクラスメイトが、大声で呼び込みをしている。はりきって接客をするクラスメイトをパーテーションの奥から眺めながら、俺は黙々とたこ焼きの生地を作っていた。
二年三組の出し物は、漢のたこ焼き屋だ。通常よりも一回り大きいたこ焼きを作って提供している。
出し物を決める時、『飲食は当日忙しくなるからやめておけ』と反対意見があがっていたが、今はその忙しさに救われている。じっとしていたら、嫌なことばかり思い出してしまうからだ。こういう時は、単調な作業をしている方が気が紛れる。
調理スペースでひたすら生地を混ぜていると、接客をしていたクラスメイトが覗きに来る。
「瀬尾、オープンしてからずっと生地作ってんじゃん。代ろうか?」
「あー、平気、平気。接客はダルイから、裏方の方がいいし」
接客がやりたくないというのは事実だ。万が一、中学の部活のメンバーと鉢合わせたら、余計に抉られる。隠れ蓑にするにも、このパーテーションは最適だった。
「そっか。あと四十分で午前のシフトは終わるから、それまでは頼んだ」
「ういー」
軽く手を挙げて返事をすると、俺は再びたこ焼き生地製造マシーンになった。
午前中のシフトが終われば、いったんフリーになる。そして十六時からは、例のラジオ企画だ。
入江に断られた日、放送部の部室に赴いて出演を断ろうとしたが、既にプログラムを載せたパンフレットを刷ってしまったから、枠を空けるのは勘弁してほしいと部長から頼み込まれた。話し合った結果、放送部の部長と俺で、ビートボックスについてトークした後で、単独でパフォーマンスすることになった。
入江が出なければ出演する意義はないのだけれど、ここまできたらやるしかない。
午前中のシフトが終わると、クラスメイトからたこ焼きを渡された。ありがたく頂いて、静かに食べられる場所はないかと彷徨っていると、いつぞや訪れた外階段に辿り付く。
この場所は、文化祭の最中でも閑散としていてお祭りムードを感じさせない。退避場所としてはちょうど良かった。
ラジオ企画で話す内容を考えながら腹を満たしていると、階段下から複数人の足音が聞こえてくる。
なんだか、こんなシチュエーション、前にもあったぞ……。
最後のたこ焼きを口に放り込んでから、手すりから身を乗り出して下を覗いた。
下にいる面子を見て、「げっ」と顔をしかめる。そこにいたのは、黒田たちだった。見たところ、入江は一緒ではないようだ。
ここはあいつらの溜まり場だったのか? それならもう近寄らないでおこう。
そそくさと立ち去ろうとしたところで、聞き捨てならない会話が聞こえてくる。
「後夜祭のバンド、清水出れるって。さっきチャットきてた」
「マジで? 出る気あったんだ」
「みたいよ。彼女と模擬店まわってるから、十六時のリハーサルは出れないみたいだけど」
黒田が説明をすると、二人は「勝手すぎんだろ」と失笑していた。
「で、どうする? 正直、清水が出た方が目立つよなぁ。あいつイケメンだし、歌も上手いし」
「分かる。ポテンシャル高いから、練習不足でもそれなりの演奏はできるだろうし」
「上手くいけば、他校の女子とも繋がり持てるかも」
この猿どもが、と心の中で毒づく。二人が賛成すると、黒田はニタァといやらしく笑った。
「じゃあ、リハまでは入江に出てもらって、本番は清水に出てもらうか。入江には、リハが終わってから伝えればいいよな」
……は? なんだよ、それ。
最低すぎる計画に、バチンッと脳内で火花が弾ける。
黒田のお仲間は、まるで悪いとは思っていないようで「それが良い~」と笑いながら賛同していた。
意見が一致すると、黒田はくくっと口元を押さえながら満足そうに笑う。
「それにしても、入江って都合いいよな。なんだかんだ言いながらも戻って来てくれたし」
「そうそう、瀬尾と組んだって聞いた時は、は?、って思ったけど」
「俺らを裏切って、別の奴と組むとかありえねえよなー」
先に裏切ったのはそっちだろ。そう怒鳴ってやりたかったが、どうにか堪えた。
黒田たちは、俺の存在には気付かず、話を続ける。
「なんかそういうの、ラノベで流行ってるよな。追放系だっけ?」
「あー、知ってる、知ってる。ギルドを追放されて、ざまあする奴でしょ?」
「そうそう! それと同じ感じで、俺らよりも上手い演奏をして、ざまあしたかったのかもなぁ」
黒田の言葉で、二人は腹を抱えてゲラゲラ笑いだす。
「痛すぎんだろ、リアルでそれやろうとすんの」
「別に俺ら、あいつらの演奏が上手くてもなんとも思わねえし。無だわ、無」
勝手に妄想を膨らませるな。入江にお前らを貶めようなんて意図があるわけないだろ。いつも一緒にいるくせに、そんなことも分からないのか?
むしゃくしゃしていると、黒田は「ふっ」と小馬鹿にするように鼻で笑った。
「大体さぁ、こっちはたかが文化祭のバンドで高度な演奏をしようなんて思ってないし。恥かかない程度に演奏して、注目されればそれで十分」
たかが文化祭のバンド。その一言で、俺の中で何かが壊れた。
今までは、他人を刺さないように気を付けていた。だけど今は刺したくて仕方がない。
入江は、音楽が好きで、地道に練習を重ねてきた。そんな人間を都合よく扱おうとしているのは許せなかった。
黒田たちの吐く言葉は、一撃で致命傷を負わせるような鋭いものではない。仲良しごっこをしながら、相手が自由に動けなくなるように縛り付ける言葉だ。そして都合が悪くなったら、あっさりと谷底に突き落としていく。
そんな関係は、友達とは呼ばない。呼んでやるものか。こいつらは、入江にとって敵だ。
もう、我慢するのはやめた。
全身の血液が煮えたぎりそうになりながら、一段飛ばしで外階段を駆け下りる。カンカンッと迫る金属音で、黒田たちも人の気配に気付いた。
地上まで降りてきてから、黒田たちを鋭く睨みつける。
「あのさ、入江を都合よく扱うのやめろよ」
突如部外者が現れたことで、黒田はぴたっと固まる。後ろにいた二人は、顔を引きつらせてたじろいでいた。
「は? な、なんだよ、急に?」
黒田は小馬鹿にするように笑っていたが、その瞳には明らかに動揺が滲んでいる。多分、本気でぶつかり合うような喧嘩に慣れていないのだろう。
俺には、こいつらの弱い部分が見えている。そこを狙って刺しにいく。
「都合が悪くなったら切り捨てるような付き合い方をしていると、いつか自分が切られるぞ?」
黒田の顔から笑顔が消える。「ああ?」と眉間にしわを寄せて不快感を露わにした。
思った通りだ。狙いは正しかった。刺したところを、ぐりぐりと抉ってやろう。
「分かってんの? 入江を切り捨てたら、お前ら三人じゃん。体育のペアだって、ひとりあぶれることになる。相手探しでうろうろ動き回るのは、お前らにとって一番屈辱的なんじゃねーの?」
にやりと笑いながら挑発すると、黒田は顔を真っ赤に染めた。
「そんなのどーでもいいしっ! いちいち気にしてるなんて根暗すぎんだろ!」
「ふーん。じゃあ次の体育では、お前が抜けんだー。あぶれても気にしないなら、いいよなー。相手探し、がんばってー」
わざとらしく拳を握って見せると、黒田はぐっと言葉を詰まらせる。他の二人は、黒田が攻撃されても後ろで縮こまっているだけだった。
おおかた、一連の騒動を黒田に擦り付けて、切り捨てようとしているのだろう。なんて脆い関係なんだ。
彼らのグループに二対一で薄っすら線引きしたところで、真っ赤な顔をした黒田に睨まれる。
「お前、孤高のビートボクサーとか呼ばれて調子乗ってんだろ? 俺はお前らとは違います~みたいな。そういうのうぜえんだよ!」
……え? 俺、陰では『孤高のビートボクサー』なんて呼ばれてんの?
うわっ、恥ずかしっ! 今のは結構刺さったぞ。
これ以上、そのネタを引っ張られたら、こっちが負傷する。さっさと片を付けよう。
「とにかく。これ以上、入江を都合よく扱ったら許さねえからな。入江は俺の――」
――友達なんだ。
その一言は、喉の奥でつっかえて出てこなかった。俺が黙り込んだ所で、黒田は「へっ」と笑う。
「もう行こうぜ。あいつらキショイわ。できてんじゃねーの?」
黒田はそう吐き捨てると、早足で校舎裏から立ち去る。残された二人も遠慮がちに追いかけていった。
取り残された俺は、強く拳を握る。
「そんなんじゃねーよ……」
俺はただ、入江が悲しむのを見たくないだけだ。
◇
黒田たちが立ち去った後、俺は外階段で項垂れていた。
――友達なんだ。
黒田にはっきりそう言えなかったのが、ショックだった。入江と喧嘩する前だったら、堂々と宣言できていただろうか?
……いや、きっと俺は躊躇っていたと思う。人と深く関わることを避けて、入江から差し伸べられた手に、気付かないふりをしてしまったのだから。
だけど結局、俺は入江の弱いところを刺してしまった。このまま何もしなければ、入江との関係は終わってしまうだろう。放課後の空き教室で、セッションしていた時間もなかったことになる。
「やだなぁ……」
入江の優しい音色を聴けなくなることも、その音でビートを刻めなくなることも、堪らなく惜しい。時を戻してでも、あの空間に飛んでいきたかった。
もう俺たちは、弱いところを見せるくらい深く繋がってしまったんだ。今更切り捨てることなんてできない。
入江とは、音楽を通して繋がっていられたら十分だと思っていたけど、今はそれだけでは足りなく感じている。
入江と、ちゃんと話そう。耳障りのいい言葉ではなく、本当の言葉で。
――今度こそ、入江と友達になりたい。
本当の思いは、言葉にしなければ伝わらないんだ。