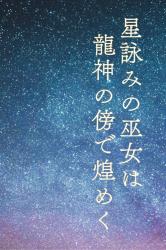文化祭一週間前になると、学校のいたるところで文化祭の装飾が見られるようになった。
正門に建てられた入場ゲート。美術部が描いた階段アート。各クラスの出し物を宣伝するポスターも、廊下のあちこちに貼り出された。校内が華やかになっていく一方で、俺の中では焦燥感が加速していった。
ラジオ企画の本番は、刻一刻と迫っている。それなのに入江は、最近練習を休むことが増えた。
【ごめん! 今日も外せない用事ができちゃって】
放課後にそのメッセージを見た時、「またか……」とがっかりしてしまった。
理由は何となく察している。だけど、あえて気付かないふりをした。
【了解】と端的に送ったメッセージには、苛立ちまでも乗っかってしまった気がした。
入江は来ないと分かっていたが、そのまま帰る気にはなれずに、空き教室で自主練をしていた。
二曲目の見せ場であるボイストランペットは、まだ上手く吹けない。レクチャー動画を繰り返し視聴しながら練習したが、理想とする音は出せなかった。
動画を停止して、ため息をつく。
一人でいる教室は、暗く、冷たい。いつの間にか夏は過ぎ去って、秋の色が深まっていた。
翌日の五時間目は、一・二・三組合同の体育だ。二学期はハンドボールの授業をしている。グラウンドに出ると、つい二組の入江の姿を探してしまった。
入江は、黒田たちに囲まれながら、穏やかに微笑んでいる。その姿をぼんやり見ていると、不意に目が合った。
入江は申し訳なさそうに視線を巡らせた後、黒田たちに視線を戻す。嫌われているわけではないのだろうけど、微妙な空気だ。
多分、入江は練習を休んだことを後ろめたく思っているのだろう。「そんなの気にすんな」と明るくフォローできたら入江の気も楽になるんだろうけど、あえてそれはしなかった。
入江とは深く関わらない。その掟を守るには、このくらいの距離感でちょうどいいんだ。
準備体操を終えると、ペアを作ってキャッチボールをするように指示された。続々とペアが組まれていく様子を眺めていると、隅っこで大人しそうな三人組の男子が浮かない顔で話し合いをしていた。
今日はあそこだな。
三人のもとに駆け寄ると、警戒心を解くようににっと微笑む。
「俺、まだペアいないから、誰か一緒に組もー」
こういう時、悲壮感を滲ませると向こうも惨めな気分になる。わざとらしいほど明るく振舞ってお願いをした。
三人は顔を見合わせる。僅かな沈黙が生まれた中、一番背の低い男子がおずおずと手を挙げた。
「うん、じゃあ、お願いします」
へらりと力なく笑う顔を見て、俺は察した。
多分、こいつは入江と同じタイプだ。輪を乱さないために、自ら貧乏くじを引きに行ったんだ。
ごめんね、相手が俺で。心の中で謝りながら、二人でボールを取りに行った。
ふと、二組のコートに視線を向けると、入江は黒田とペアになっていた。
入江があぶれていなくて安心したけど、相手が黒田というのは複雑だ。俺はなるべく、その二人を視界に入れないようにした。
しばらくゆるーいキャッチボールを続けていると、背後から黒田の吠えるような声が聞こえた。
「おいっ! 入江! 大丈夫か!?」
入江と聞いて、すぐさま振り返る。数メートル先では、入江がグラウンドにうつ伏せで倒れていた。俺の足は、無意識で動きだす。
「どういう状況? 頭にボールが当たったとか?」
すぐさま尋ねると、黒田は自分は悪くないと主張するように首を振る。
「違う! 普通にキャッチボールしてたら、急に倒れて」
外的要因がないとするなら、体調不良か? 俺はその場でしゃがみ込んで、入江の肩を叩いた。
「大丈夫? どっか痛い?」
入江はふるふると首を左右に振りながら、ゆっくりと起き上がる。その顔は、血の気が引いて真っ青だった。
「大丈夫。ちょっと、立ち眩みがしただけ……」
入江はぎこちなく笑うと、地面に手をついて立ち上がろうとする。しかしすぐに力が抜けたようにへたり込んでしまった。
このまま授業に出るのは無理だろう。俺は入江の前で背を向けてしゃがんだ。
「背中に乗って」
「え、でも」
「いいから!」
強い口調で促すと、入江は観念したように肩に手を回した。
「ごめん、重いでしょ?」
「全然。よゆー」
振り返ってにっと笑ってみせると、入江の顔に少しだけ血が通ったような気がした。
「保健室連れてくから、先生に報告しといて」
「あ、ああ、分かった……」
戸惑う黒田に報告を頼んでから、俺は入江を背負って校舎に向かった。
入江の病状は気になるが、今は保健室に運ぶのが優先だ。早足で歩いていると、入江が背中でもぞもぞ動き出した。
「あ、やばっ……瀬尾、降ろして」
「どうした?」
「おなか、押されて、吐きそ……」
そこで事情を察した。すぐさま歩くペースを緩める。
「大丈夫。吐いても怒らないから」
体操着だし、着替えれば平気だ。部室棟にはシャワーだってある。問題ないとアピールすると、入江は「くぅ」と唸った。
「それは流石に、申しわけなさすぎるよぉ」
結局、入江はフゥフゥ唸りながらも、どうにかトイレまで持ちこたえてくれた。それから保健室まで連れて行く。
タイミングが悪く、養護教諭は不在だった。二つあるベッドはどちらも開いていたから、窓側のベッドを使わせてもらうことにした。
「調子悪かったの? 風邪?」
「ううん、多分、寝不足……」
ベッドで横たわる入江は、申し訳なさそうに視線を落とす。それから、悪事を白状する子供のように続けた。
「実は今、六曲弾けるように練習しているんだ。それでしばらくちゃんと寝てなくて……」
六曲と聞いて、力が抜けていく。
黒田とのやりとりを目撃した日から、入江がバンドに引き戻されたのは薄々感じていた。俺との練習に来られない日は、黒田たちの練習に参加していたのだろう。
生真面目な入江のことだから、必死に練習していたことは容易に想像できる。だけど、六曲はあんまりだ。
「こんなになってまで練習する必要ある?」
「あっちの曲は俺の知らない間にロックになってたから、いちから練習するしかなくて」
「そうじゃなくて!」
入江の言葉を遮って、じっと瞳を見据える。
「黒田たちのバンドは断れば良かったじゃん。キャパ的に無理だって」
言葉尻がきつくなる。入江も怯えたように、顔を強張らせていた。
これ以上はやめろと危険信号が点滅しているのに、止まれない。
「なんで、無理して出ようとすんだよ?」
憤りが滲んだ声を発した瞬間、入江の瞳にじわりと涙が滲む。それを隠すかのように、手の甲で目元を覆った。
「だって、そうしないと、また仲間外れにされるからぁ」
覆った目元から、ボロボロと涙がこぼれていく。寝不足と体調不良で、メンタルまでやられているんだろう。
入江は、俺に弱い部分を晒している。そこは刺してはいけない場所だ。頭ではそう分かっているのに、俺の悪い口は止まらなかった。
「そんなんだから、舐められるし、ハブられるんだよ」
言葉にした瞬間、それが入江にとっての致命傷になっていることに気付いた。
入江は目元を覆った手を離す。驚いていた顔は、みるみるうちに赤く燃え上がった。
「そんなの、言われなくても分かってるよ!」
普段の入江からは想像できないような感情的な声だ。入江はフゥフゥと肩を上下させていたが、すぐに取り乱したことに気付いた。
「ごめん、怒鳴って……」
入江はこれ以上のやりとりを拒むように、布団を頭から被った。
これ以上、口を開いたら、もっと入江を追い詰めてしまうかもしれない。俺は、唇を固く縫い合わせた。
時計の音が、カチカチと規則正しく響く。俺の心音は、それよりも早いリズムで刻んでいた。多分、BPM200は超えている。
沈黙が続いた後、入江は布団を被りながら告げた。
「ごめん。瀬尾の言うように、六曲はキツイ。俺、後夜祭のバンド一本に集中するから、ラジオ企画には出ない。誘ってくれたのに、ごめんね」
がつんと頭を殴られたような衝撃に襲われる。
そうか、入江は黒田たちではなく、俺を切り捨てたんだ。
当然か。あんなひどいことを言ったんだし。
「分かった」
そう返事をするのが、精一杯だった。俺は入江から顔を背けて、保健室から飛び出した。
扉を閉めると、ヘナヘナと力が抜けて廊下にへたり込む。
この感覚は、久々に味わったな。友達を失くすのは、結構痛い。
正門に建てられた入場ゲート。美術部が描いた階段アート。各クラスの出し物を宣伝するポスターも、廊下のあちこちに貼り出された。校内が華やかになっていく一方で、俺の中では焦燥感が加速していった。
ラジオ企画の本番は、刻一刻と迫っている。それなのに入江は、最近練習を休むことが増えた。
【ごめん! 今日も外せない用事ができちゃって】
放課後にそのメッセージを見た時、「またか……」とがっかりしてしまった。
理由は何となく察している。だけど、あえて気付かないふりをした。
【了解】と端的に送ったメッセージには、苛立ちまでも乗っかってしまった気がした。
入江は来ないと分かっていたが、そのまま帰る気にはなれずに、空き教室で自主練をしていた。
二曲目の見せ場であるボイストランペットは、まだ上手く吹けない。レクチャー動画を繰り返し視聴しながら練習したが、理想とする音は出せなかった。
動画を停止して、ため息をつく。
一人でいる教室は、暗く、冷たい。いつの間にか夏は過ぎ去って、秋の色が深まっていた。
翌日の五時間目は、一・二・三組合同の体育だ。二学期はハンドボールの授業をしている。グラウンドに出ると、つい二組の入江の姿を探してしまった。
入江は、黒田たちに囲まれながら、穏やかに微笑んでいる。その姿をぼんやり見ていると、不意に目が合った。
入江は申し訳なさそうに視線を巡らせた後、黒田たちに視線を戻す。嫌われているわけではないのだろうけど、微妙な空気だ。
多分、入江は練習を休んだことを後ろめたく思っているのだろう。「そんなの気にすんな」と明るくフォローできたら入江の気も楽になるんだろうけど、あえてそれはしなかった。
入江とは深く関わらない。その掟を守るには、このくらいの距離感でちょうどいいんだ。
準備体操を終えると、ペアを作ってキャッチボールをするように指示された。続々とペアが組まれていく様子を眺めていると、隅っこで大人しそうな三人組の男子が浮かない顔で話し合いをしていた。
今日はあそこだな。
三人のもとに駆け寄ると、警戒心を解くようににっと微笑む。
「俺、まだペアいないから、誰か一緒に組もー」
こういう時、悲壮感を滲ませると向こうも惨めな気分になる。わざとらしいほど明るく振舞ってお願いをした。
三人は顔を見合わせる。僅かな沈黙が生まれた中、一番背の低い男子がおずおずと手を挙げた。
「うん、じゃあ、お願いします」
へらりと力なく笑う顔を見て、俺は察した。
多分、こいつは入江と同じタイプだ。輪を乱さないために、自ら貧乏くじを引きに行ったんだ。
ごめんね、相手が俺で。心の中で謝りながら、二人でボールを取りに行った。
ふと、二組のコートに視線を向けると、入江は黒田とペアになっていた。
入江があぶれていなくて安心したけど、相手が黒田というのは複雑だ。俺はなるべく、その二人を視界に入れないようにした。
しばらくゆるーいキャッチボールを続けていると、背後から黒田の吠えるような声が聞こえた。
「おいっ! 入江! 大丈夫か!?」
入江と聞いて、すぐさま振り返る。数メートル先では、入江がグラウンドにうつ伏せで倒れていた。俺の足は、無意識で動きだす。
「どういう状況? 頭にボールが当たったとか?」
すぐさま尋ねると、黒田は自分は悪くないと主張するように首を振る。
「違う! 普通にキャッチボールしてたら、急に倒れて」
外的要因がないとするなら、体調不良か? 俺はその場でしゃがみ込んで、入江の肩を叩いた。
「大丈夫? どっか痛い?」
入江はふるふると首を左右に振りながら、ゆっくりと起き上がる。その顔は、血の気が引いて真っ青だった。
「大丈夫。ちょっと、立ち眩みがしただけ……」
入江はぎこちなく笑うと、地面に手をついて立ち上がろうとする。しかしすぐに力が抜けたようにへたり込んでしまった。
このまま授業に出るのは無理だろう。俺は入江の前で背を向けてしゃがんだ。
「背中に乗って」
「え、でも」
「いいから!」
強い口調で促すと、入江は観念したように肩に手を回した。
「ごめん、重いでしょ?」
「全然。よゆー」
振り返ってにっと笑ってみせると、入江の顔に少しだけ血が通ったような気がした。
「保健室連れてくから、先生に報告しといて」
「あ、ああ、分かった……」
戸惑う黒田に報告を頼んでから、俺は入江を背負って校舎に向かった。
入江の病状は気になるが、今は保健室に運ぶのが優先だ。早足で歩いていると、入江が背中でもぞもぞ動き出した。
「あ、やばっ……瀬尾、降ろして」
「どうした?」
「おなか、押されて、吐きそ……」
そこで事情を察した。すぐさま歩くペースを緩める。
「大丈夫。吐いても怒らないから」
体操着だし、着替えれば平気だ。部室棟にはシャワーだってある。問題ないとアピールすると、入江は「くぅ」と唸った。
「それは流石に、申しわけなさすぎるよぉ」
結局、入江はフゥフゥ唸りながらも、どうにかトイレまで持ちこたえてくれた。それから保健室まで連れて行く。
タイミングが悪く、養護教諭は不在だった。二つあるベッドはどちらも開いていたから、窓側のベッドを使わせてもらうことにした。
「調子悪かったの? 風邪?」
「ううん、多分、寝不足……」
ベッドで横たわる入江は、申し訳なさそうに視線を落とす。それから、悪事を白状する子供のように続けた。
「実は今、六曲弾けるように練習しているんだ。それでしばらくちゃんと寝てなくて……」
六曲と聞いて、力が抜けていく。
黒田とのやりとりを目撃した日から、入江がバンドに引き戻されたのは薄々感じていた。俺との練習に来られない日は、黒田たちの練習に参加していたのだろう。
生真面目な入江のことだから、必死に練習していたことは容易に想像できる。だけど、六曲はあんまりだ。
「こんなになってまで練習する必要ある?」
「あっちの曲は俺の知らない間にロックになってたから、いちから練習するしかなくて」
「そうじゃなくて!」
入江の言葉を遮って、じっと瞳を見据える。
「黒田たちのバンドは断れば良かったじゃん。キャパ的に無理だって」
言葉尻がきつくなる。入江も怯えたように、顔を強張らせていた。
これ以上はやめろと危険信号が点滅しているのに、止まれない。
「なんで、無理して出ようとすんだよ?」
憤りが滲んだ声を発した瞬間、入江の瞳にじわりと涙が滲む。それを隠すかのように、手の甲で目元を覆った。
「だって、そうしないと、また仲間外れにされるからぁ」
覆った目元から、ボロボロと涙がこぼれていく。寝不足と体調不良で、メンタルまでやられているんだろう。
入江は、俺に弱い部分を晒している。そこは刺してはいけない場所だ。頭ではそう分かっているのに、俺の悪い口は止まらなかった。
「そんなんだから、舐められるし、ハブられるんだよ」
言葉にした瞬間、それが入江にとっての致命傷になっていることに気付いた。
入江は目元を覆った手を離す。驚いていた顔は、みるみるうちに赤く燃え上がった。
「そんなの、言われなくても分かってるよ!」
普段の入江からは想像できないような感情的な声だ。入江はフゥフゥと肩を上下させていたが、すぐに取り乱したことに気付いた。
「ごめん、怒鳴って……」
入江はこれ以上のやりとりを拒むように、布団を頭から被った。
これ以上、口を開いたら、もっと入江を追い詰めてしまうかもしれない。俺は、唇を固く縫い合わせた。
時計の音が、カチカチと規則正しく響く。俺の心音は、それよりも早いリズムで刻んでいた。多分、BPM200は超えている。
沈黙が続いた後、入江は布団を被りながら告げた。
「ごめん。瀬尾の言うように、六曲はキツイ。俺、後夜祭のバンド一本に集中するから、ラジオ企画には出ない。誘ってくれたのに、ごめんね」
がつんと頭を殴られたような衝撃に襲われる。
そうか、入江は黒田たちではなく、俺を切り捨てたんだ。
当然か。あんなひどいことを言ったんだし。
「分かった」
そう返事をするのが、精一杯だった。俺は入江から顔を背けて、保健室から飛び出した。
扉を閉めると、ヘナヘナと力が抜けて廊下にへたり込む。
この感覚は、久々に味わったな。友達を失くすのは、結構痛い。