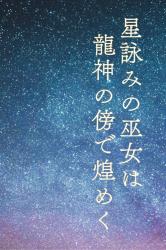『お前さ、いつもラクしようとしてるから、肝心な時にきめられないんだよ』
――痛い。
『試合に負けたの、お前のせいだから』
――痛い、痛い。
『もうお前には、ボール回さない』
――痛い、痛い、痛い。
『瀬尾! それは言いすぎたろ!』
『言って良いことと悪いことの区別もつかねえのかよ!』
――その通りだ。俺は、言ってはいけないことを言ってしまった。
『もう黙れ、なにアツくなってんだよ?』
その言葉を発したのは、かつてのチームメイトなのか、過去の自分なのか、区別がつかなかった。
◇
ハッと目を覚ますと、いつも通りの天井が視界に入った。カーテンの隙間から覗いた空は薄暗く、瑠璃色に染まっている。
「夢、か……」
浅い呼吸を繰り返しながら、暴れまわる心臓を押さえる。Tシャツは、汗でじっとり湿っていて気持ちが悪かった。
深く息を吐いてから、ベッドから起き上がる。そのまま風呂場に直行した。
ぬるいシャワーを頭から浴びながら、俺は過去に犯した失態を思い返していた。
中学時代、俺はバレー部に所属していた。
ポジションはセッター。アタッカーが打ちやすいようにトスを回すポジションだ。
『瀬尾は周りがよく見えているから適任だ』と顧問から推薦された時は、自分の長所を見つけてもらえたようで嬉しかった。
セッターは、味方の状況や敵の守備を確認して、誰にトスを出すか瞬時に判断しなければならない。その影響で、これまで以上に人に目を向けるようになった。
おかげで洞察力が研ぎ澄まされ、チームメイトの異変にいち早く気付けるようになった。だけど、良いことばかりでもない。人の嫌な部分や弱い部分にまで、目がいってしまった。
あまり親しくない間柄だったら、何を見ても黙っていられる。だけど相手が深く関わってきた人だと、見過ごしてはおけなかった。
バレー部に原田という男子がいた。背が高くて、力も強くて、アタッカーとしては恵まれた身体を持っている。チームメイトや顧問からも期待されていた。
しかし原田は、隙を見てサボる癖があった。ランニングの周回数や筋トレの回数をちょろまかすことは日常茶飯事。注意をしても、ヘラヘラ笑いながらはぐらかされてしまった。
『瀬尾、そんなにアツくなんなよ、たかが部活ごときで』
確かにその通りだけど、当時熱心に部活に取り組んでいた俺にとっては、“たかが”なんて言葉で片付けてほしくなかった。なんだか、自分自身まで否定された気がして、やるせなさを感じた。
そして、中二の秋に行われた試合で、ついに我慢の限界が訪れた。
その日の試合相手は、地元では強豪校と知られているチーム。1セット目は落としたが、2セット目ではチームメイトのファインプレイが続き見事勝利した。
勝負の分かれ道の3セット目。勢いが衰えることなく、俺たちは強豪校の怒涛の攻撃にくらいついていった。
24-21。相手はマッチポイントを取っているが、まだ勝機はある。緊張感に包まれる中、相手チームからの力強いサーブが飛んできた。
チームメイトがレシーブで上手く受ける。ボールは俺のもとに綺麗な放物線を描いて飛んできた。
この局面で誰に打たせるか。ちょうど原田へのマークが手薄になっていることに気付き、軽やかにトスを回した。
――お前の強烈なアタックで圧倒してやれ。
そう期待していたものの、原田はジャンプのタイミングを見誤った。力強く打たれたボールはネットに引っかかり、原田の足元に転がる。
ホイッスルが鳴る。試合終了。俺たちの負けだ――。
コートを出た直後、悔しくて、泣いた。抑えきれない感情をぶつけるように、俺は鋭い言葉で原田を刺してしまったんだ。
『お前さ、いつもラクしようとしてるから、肝心な時にきめられないんだよ』
『試合に負けたの、お前のせいだから』
『もうお前には、ボール回さない』
原田だって、あの局面できめられなかったことを悔いていた。目を真っ赤にしていたのが、その証拠だ。
それなのに、俺は優しい言葉で励ますのではなく、鋭い言葉で罵倒してしまった。そこを刺せば、原田に致命傷を与えることも分かっていながら。
その後、原田は部活をやめた。学校でも避けられまくって、謝ることすらできずに卒業した。
中学時代の出来事を思い出すと、つくづく痛感する。
言葉は人を励ますこともあれば、深く傷つけることもある。使い方が下手くそ奴は、黙っておけばいい。
もう、同じ失敗は繰り返したくない。人と深く関わるから、相手の嫌な部分や弱い部分が気になってしまうんだ。
それなら浅い付き合いで、薄っぺらい会話だけしていればいい。そうすれば、誰も傷つけることはないのだから。
ふと、音楽室で見た入江の泣き顔を思い出す。
俺は、入江の弱い部分を見つけてしまった。深く関わり過ぎた証拠だ。
時を戻すことも、記憶を消すこともできないのなら、口を噤めばいい。
俺の鋭利な言葉で、優しい入江を傷つけたくなかった。
――痛い。
『試合に負けたの、お前のせいだから』
――痛い、痛い。
『もうお前には、ボール回さない』
――痛い、痛い、痛い。
『瀬尾! それは言いすぎたろ!』
『言って良いことと悪いことの区別もつかねえのかよ!』
――その通りだ。俺は、言ってはいけないことを言ってしまった。
『もう黙れ、なにアツくなってんだよ?』
その言葉を発したのは、かつてのチームメイトなのか、過去の自分なのか、区別がつかなかった。
◇
ハッと目を覚ますと、いつも通りの天井が視界に入った。カーテンの隙間から覗いた空は薄暗く、瑠璃色に染まっている。
「夢、か……」
浅い呼吸を繰り返しながら、暴れまわる心臓を押さえる。Tシャツは、汗でじっとり湿っていて気持ちが悪かった。
深く息を吐いてから、ベッドから起き上がる。そのまま風呂場に直行した。
ぬるいシャワーを頭から浴びながら、俺は過去に犯した失態を思い返していた。
中学時代、俺はバレー部に所属していた。
ポジションはセッター。アタッカーが打ちやすいようにトスを回すポジションだ。
『瀬尾は周りがよく見えているから適任だ』と顧問から推薦された時は、自分の長所を見つけてもらえたようで嬉しかった。
セッターは、味方の状況や敵の守備を確認して、誰にトスを出すか瞬時に判断しなければならない。その影響で、これまで以上に人に目を向けるようになった。
おかげで洞察力が研ぎ澄まされ、チームメイトの異変にいち早く気付けるようになった。だけど、良いことばかりでもない。人の嫌な部分や弱い部分にまで、目がいってしまった。
あまり親しくない間柄だったら、何を見ても黙っていられる。だけど相手が深く関わってきた人だと、見過ごしてはおけなかった。
バレー部に原田という男子がいた。背が高くて、力も強くて、アタッカーとしては恵まれた身体を持っている。チームメイトや顧問からも期待されていた。
しかし原田は、隙を見てサボる癖があった。ランニングの周回数や筋トレの回数をちょろまかすことは日常茶飯事。注意をしても、ヘラヘラ笑いながらはぐらかされてしまった。
『瀬尾、そんなにアツくなんなよ、たかが部活ごときで』
確かにその通りだけど、当時熱心に部活に取り組んでいた俺にとっては、“たかが”なんて言葉で片付けてほしくなかった。なんだか、自分自身まで否定された気がして、やるせなさを感じた。
そして、中二の秋に行われた試合で、ついに我慢の限界が訪れた。
その日の試合相手は、地元では強豪校と知られているチーム。1セット目は落としたが、2セット目ではチームメイトのファインプレイが続き見事勝利した。
勝負の分かれ道の3セット目。勢いが衰えることなく、俺たちは強豪校の怒涛の攻撃にくらいついていった。
24-21。相手はマッチポイントを取っているが、まだ勝機はある。緊張感に包まれる中、相手チームからの力強いサーブが飛んできた。
チームメイトがレシーブで上手く受ける。ボールは俺のもとに綺麗な放物線を描いて飛んできた。
この局面で誰に打たせるか。ちょうど原田へのマークが手薄になっていることに気付き、軽やかにトスを回した。
――お前の強烈なアタックで圧倒してやれ。
そう期待していたものの、原田はジャンプのタイミングを見誤った。力強く打たれたボールはネットに引っかかり、原田の足元に転がる。
ホイッスルが鳴る。試合終了。俺たちの負けだ――。
コートを出た直後、悔しくて、泣いた。抑えきれない感情をぶつけるように、俺は鋭い言葉で原田を刺してしまったんだ。
『お前さ、いつもラクしようとしてるから、肝心な時にきめられないんだよ』
『試合に負けたの、お前のせいだから』
『もうお前には、ボール回さない』
原田だって、あの局面できめられなかったことを悔いていた。目を真っ赤にしていたのが、その証拠だ。
それなのに、俺は優しい言葉で励ますのではなく、鋭い言葉で罵倒してしまった。そこを刺せば、原田に致命傷を与えることも分かっていながら。
その後、原田は部活をやめた。学校でも避けられまくって、謝ることすらできずに卒業した。
中学時代の出来事を思い出すと、つくづく痛感する。
言葉は人を励ますこともあれば、深く傷つけることもある。使い方が下手くそ奴は、黙っておけばいい。
もう、同じ失敗は繰り返したくない。人と深く関わるから、相手の嫌な部分や弱い部分が気になってしまうんだ。
それなら浅い付き合いで、薄っぺらい会話だけしていればいい。そうすれば、誰も傷つけることはないのだから。
ふと、音楽室で見た入江の泣き顔を思い出す。
俺は、入江の弱い部分を見つけてしまった。深く関わり過ぎた証拠だ。
時を戻すことも、記憶を消すこともできないのなら、口を噤めばいい。
俺の鋭利な言葉で、優しい入江を傷つけたくなかった。