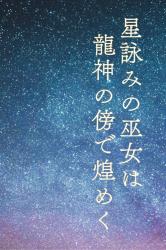昼休みのチャイムが鳴ったと同時に、俺は教室から飛び出して購買に走った。
今日は十月十五日。月に一度、ホイップ苺ロールパンが販売される日だ。
先月は、ラスト1個のところで卓球部の男子に奪われた。だから今月こそは、絶対にゲットしたい。
購買でもみくちゃになりながらも、どうにかお目当ての品をゲットする。優越感に浸りながら教室に戻ろうとしていると、二組の教室からやけに喧しい声が聞こえてきた。
耳にギンギン響くような声で喚いているのは黒田だ。鬱陶しく思いながらも視線を向けると、黒田たちが教室の後方でたむろしていた。その中心には、入江がいる。
あいつら、まだ仲良かったのか……?
驚いていたものの、入江が背中を丸めて小さくなっているのを見て、また良くないことが起ころうとしていると察した。
「入江、頼む! やっぱり後夜祭のバンド、出てくんね? 清水とバンド組んだんだけど、あいつ最近他校の女子と付き合いだしたらしくて、全然練習に顔出さないんだよ。このままじゃマズいから、戻ってきてくんね?」
黒田が両手を合わせながら、大声で頼み込んでいる。自分から切り捨てておいて、今更都合が良すぎだろ。
しかもやり口も汚い。切り捨てる時は校舎裏でこっそり頼んでいたくせに、引き戻す時は教室で堂々と頼んでいる。入江が断りずらいシチュエーションを作っているようにしか思えなかった。
こんな誘い、さっさと断ってやれ。そう思っていたが、入江は人の良さそうな顔で笑っていた。
「うーん、ちょっと考えさせて?」
思わず「は?」と声を出してしまう。
考えさせて? 何を言ってるんだ。断るだろ、フツー。
曖昧な態度に苛立ちを覚えていると、入江が笑顔を保ったまま言葉を続けた。
「実は今、三組の瀬尾と組んでるんだ」
「瀬尾? あいつ楽器弾けるの?」
「楽器じゃなくてビートボックス。俺と瀬尾で、アコギとビートボックスのセッションをするんだ。文化祭では、放送部のラジオ企画に出る予定。だから、ね……」
“だから”の先は明言しなかったけど、俺にはちゃんと分かる。忙しいからお前らに構っている暇はない。そう言いたいのだろう。
入江に予定があると知ると、黒田を含めた三人は顔を見合わせる。それから示し合わせたように、「ぷっ」と笑った。
「へー、凄いじゃん。ちなみにそのラジオ企画って何時から?」
「十六時からだけど」
「ならいけるって! 後夜祭は十八時からだから、出れるじゃん」
いやいや、タイムテーブルは被らないけど、準備が間に合わない。そっちのバンドに出るなら、曲だって練習しないといけないだろうし。
入江だってそんなことは分かっているはずだ。その証拠に、困ったように眉を下げていた。
「うーん、でも……」
「頼む! 俺ら一年の時から出ようって約束したじゃん!」
パンッと両手を合わせて大声で懇願する。黒田の大袈裟なパフォーマンスのせいで、二組の教室にいる生徒のほとんどが彼らのやりとりに注目していた。
これ以上は見ていられない。助け船を出そう。そう決意した時、入江は目を伏せながら頷いた。
「……うん、考えておく」
入江がそう口にした途端、黒田がニタァと笑う。その“考えておく”を、黒田は都合よく受け取ったようだ。
「ありがとー! 入江!」
バシバシと入江の肩を叩く。顔を上げた入江は、戸惑ったように黒田を見つめていた。肩を叩かれるたびに、感謝を押し売りされているようだ。
一部始終を廊下から見ていた俺は、思わず舌打ちをする。
黒田たちが図々しいのは言うまでもないが、入江も入江だ。無理ならはっきり断れば良かったんだ。曖昧な態度を取るから、あいつらに付け入れられる。
あー、もう、むしゃくしゃする! 俺は怒りに任せて、二組の教室に入った。
「入江っ!」
大声で呼ぶと、入江の肩がビクンッと跳ねる。入江は悪事がバレた子供のように、瞳を揺らがせながら俺を見つめていた。
俺はズカズカと教室に入ると、入江の腕を掴む。
「来い。一緒に昼飯食うぞ」
そんな約束はしていない。今、俺が勝手に決めたことだ。入江も突然の誘いに困惑していた。
「あ、えっと……」
「行くぞ」
入江の言葉を聞かずに、腕を引っ張って教室から連れ出す。入江は戸惑っていたが、素直に付いて来てくれた。
廊下に出ると、入江の腕を掴んだまま、ずんずん歩く。入江は背後をチラチラ気にしながら、俺の後に続いていた。
「あの、瀬尾……。俺の弁当、教室なんだけど……」
笑顔を浮かべながらも、困ったような目をする入江を見て、パッと手を離す。
「あ、ごめん……。急に連れ出して」
「それはいいけど……」
「俺と食うのが嫌だったら、黒田たちと食っていいよ」
咄嗟に逃げ道を作ってしまう。入江は腕を押さえながら、ふるふると首を振った。
「ううん。瀬尾と食べる」
即答してくれたことで、怒りのボルテージは少し下がった。
パタパタと走っていく背中を眺めていると、入江にぶつけたい言葉が溢れてくる。
なんで黒田たちの誘いをちゃんと断らないんだよ。三曲でも大変だって言ってたのに、あいつらのバンド曲まで練習する時間ないだろ。優し過ぎるんだよ。そんなんだから―――。
ハッと言葉を呑み込む。それを口にしたら、入江を傷つけてしまう。そこは刺してはいけない場所だ。
落ち着け、落ち着け、と念じながら、額を押さえる。
そうだ。入江が戻って来たら、楽しい話をしよう。音楽の話でもいい。犬の話でもいい。とにかく、さっきの出来事から気をそらすんだ。
ふと左手を見ると、握りしめていたホイップ苺ロールパンはぺしゃんこに潰れていた。
今日は十月十五日。月に一度、ホイップ苺ロールパンが販売される日だ。
先月は、ラスト1個のところで卓球部の男子に奪われた。だから今月こそは、絶対にゲットしたい。
購買でもみくちゃになりながらも、どうにかお目当ての品をゲットする。優越感に浸りながら教室に戻ろうとしていると、二組の教室からやけに喧しい声が聞こえてきた。
耳にギンギン響くような声で喚いているのは黒田だ。鬱陶しく思いながらも視線を向けると、黒田たちが教室の後方でたむろしていた。その中心には、入江がいる。
あいつら、まだ仲良かったのか……?
驚いていたものの、入江が背中を丸めて小さくなっているのを見て、また良くないことが起ころうとしていると察した。
「入江、頼む! やっぱり後夜祭のバンド、出てくんね? 清水とバンド組んだんだけど、あいつ最近他校の女子と付き合いだしたらしくて、全然練習に顔出さないんだよ。このままじゃマズいから、戻ってきてくんね?」
黒田が両手を合わせながら、大声で頼み込んでいる。自分から切り捨てておいて、今更都合が良すぎだろ。
しかもやり口も汚い。切り捨てる時は校舎裏でこっそり頼んでいたくせに、引き戻す時は教室で堂々と頼んでいる。入江が断りずらいシチュエーションを作っているようにしか思えなかった。
こんな誘い、さっさと断ってやれ。そう思っていたが、入江は人の良さそうな顔で笑っていた。
「うーん、ちょっと考えさせて?」
思わず「は?」と声を出してしまう。
考えさせて? 何を言ってるんだ。断るだろ、フツー。
曖昧な態度に苛立ちを覚えていると、入江が笑顔を保ったまま言葉を続けた。
「実は今、三組の瀬尾と組んでるんだ」
「瀬尾? あいつ楽器弾けるの?」
「楽器じゃなくてビートボックス。俺と瀬尾で、アコギとビートボックスのセッションをするんだ。文化祭では、放送部のラジオ企画に出る予定。だから、ね……」
“だから”の先は明言しなかったけど、俺にはちゃんと分かる。忙しいからお前らに構っている暇はない。そう言いたいのだろう。
入江に予定があると知ると、黒田を含めた三人は顔を見合わせる。それから示し合わせたように、「ぷっ」と笑った。
「へー、凄いじゃん。ちなみにそのラジオ企画って何時から?」
「十六時からだけど」
「ならいけるって! 後夜祭は十八時からだから、出れるじゃん」
いやいや、タイムテーブルは被らないけど、準備が間に合わない。そっちのバンドに出るなら、曲だって練習しないといけないだろうし。
入江だってそんなことは分かっているはずだ。その証拠に、困ったように眉を下げていた。
「うーん、でも……」
「頼む! 俺ら一年の時から出ようって約束したじゃん!」
パンッと両手を合わせて大声で懇願する。黒田の大袈裟なパフォーマンスのせいで、二組の教室にいる生徒のほとんどが彼らのやりとりに注目していた。
これ以上は見ていられない。助け船を出そう。そう決意した時、入江は目を伏せながら頷いた。
「……うん、考えておく」
入江がそう口にした途端、黒田がニタァと笑う。その“考えておく”を、黒田は都合よく受け取ったようだ。
「ありがとー! 入江!」
バシバシと入江の肩を叩く。顔を上げた入江は、戸惑ったように黒田を見つめていた。肩を叩かれるたびに、感謝を押し売りされているようだ。
一部始終を廊下から見ていた俺は、思わず舌打ちをする。
黒田たちが図々しいのは言うまでもないが、入江も入江だ。無理ならはっきり断れば良かったんだ。曖昧な態度を取るから、あいつらに付け入れられる。
あー、もう、むしゃくしゃする! 俺は怒りに任せて、二組の教室に入った。
「入江っ!」
大声で呼ぶと、入江の肩がビクンッと跳ねる。入江は悪事がバレた子供のように、瞳を揺らがせながら俺を見つめていた。
俺はズカズカと教室に入ると、入江の腕を掴む。
「来い。一緒に昼飯食うぞ」
そんな約束はしていない。今、俺が勝手に決めたことだ。入江も突然の誘いに困惑していた。
「あ、えっと……」
「行くぞ」
入江の言葉を聞かずに、腕を引っ張って教室から連れ出す。入江は戸惑っていたが、素直に付いて来てくれた。
廊下に出ると、入江の腕を掴んだまま、ずんずん歩く。入江は背後をチラチラ気にしながら、俺の後に続いていた。
「あの、瀬尾……。俺の弁当、教室なんだけど……」
笑顔を浮かべながらも、困ったような目をする入江を見て、パッと手を離す。
「あ、ごめん……。急に連れ出して」
「それはいいけど……」
「俺と食うのが嫌だったら、黒田たちと食っていいよ」
咄嗟に逃げ道を作ってしまう。入江は腕を押さえながら、ふるふると首を振った。
「ううん。瀬尾と食べる」
即答してくれたことで、怒りのボルテージは少し下がった。
パタパタと走っていく背中を眺めていると、入江にぶつけたい言葉が溢れてくる。
なんで黒田たちの誘いをちゃんと断らないんだよ。三曲でも大変だって言ってたのに、あいつらのバンド曲まで練習する時間ないだろ。優し過ぎるんだよ。そんなんだから―――。
ハッと言葉を呑み込む。それを口にしたら、入江を傷つけてしまう。そこは刺してはいけない場所だ。
落ち着け、落ち着け、と念じながら、額を押さえる。
そうだ。入江が戻って来たら、楽しい話をしよう。音楽の話でもいい。犬の話でもいい。とにかく、さっきの出来事から気をそらすんだ。
ふと左手を見ると、握りしめていたホイップ苺ロールパンはぺしゃんこに潰れていた。