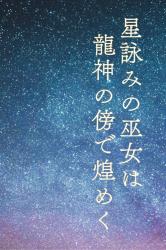「あのさ、入江。文化祭のラジオ企画って興味ない?」
入江と組んでから一週間が経った頃、練習中にそれとなく話題にあげてみた。案の定、入江はきょとんと目を丸くしている。
「ラジオ企画? なにそれ?」
「毎年放送部がやっている企画なんだけど、ゲストを呼んでトークをしたり、音楽を流したりするんだって。後夜祭のステージは、枠が埋まってて申し込めなかったけど、そっちはまだ空きがあるらしい。アコギとビートボックスなら生演奏しても構わないって言われたから、どうかなって」
入江は後夜祭に出ることを目標に練習に励んできた。それならどこかで演奏を披露できる場があった方がいいだろう。本番があった方が、練習のしがいもある。
あちこちでリサーチをした結果、一番しっくりきたのが放送部のラジオ企画だった。
アコースティックギターとビートボックスのセッションは、バンドと比べると見た目の華やかさはない。だから講堂や外ステージを使った見せるライブよりも、音だけで聴かせるラジオの方が向いているように思えた。
「うん、いいんじゃないかな!」
入江は目を輝かせて賛同してくれた。その反応を見て、ほっとする。
「じゃあ、放送部の部長に参加希望を出しておくよ。ひと枠20分って聞いたから、三曲できたらベストだけど」
「三曲かぁ……。本番まで二ヶ月ちょっと。いけるかな?」
あまり時間があるわけではない。だけど入江の実力なら、ギリギリいけそうな気がした。
俺たちはこの一週間で三回顔を合わせて練習していたけど、入江はその都度曲を変えていた。多分、譜読みも早い方なのだろう。
俺の方は、どうとでも合わせられる。もともと楽譜は使わずに、フィーリングでやっていたんだ。三曲だったら対応できる。
とはいえ、無理はさせたくない。入江に負担がかからないように、足並みは揃えるつもりだ。
「無理そうだったら、二曲でもいいよ。最悪一曲でもいいし」
放送部の部長からは、尺が短くなる分には構わないと言っていた。余った時間は、トークで繋ぐそうだ。
入江は少し考えこんでいたが、覚悟を決めたように「よし」と頷く。
「三曲やろう。やるからにはベストを尽くしたい」
「おお、アツイな」
「うん。俺、今燃えてるよ。目標が決まって、すっごくやる気になっているんだ。瀬尾と合わせるのも楽しいし」
純粋で真っすぐな思いをぶつけられると、照れくさくなってくる。
「……俺も、楽しいよ。入江とセッションしてるの」
恥ずかしさで顔を背けながらも本音を伝えると、教室の温度がちょっと上がった気がした。
シャツの胸元をパタパタさせて扇いでいると、入江はぐっと机から身を乗り出す。
「で、曲はなにやる? 俺、やりたい曲はいっぱいあるんだ」
目を輝かせながらうずうずしている。その姿を見て、自然と笑みが零れた。
そうだよな。どの曲をやるか決める時間が、一番楽しいんだ。
「色々曲を聴きながら、候補をあげていこうか」
俺はスマホを取り出して、動画配信サイトを開いた。
散々悩んだ結果、当日に演奏する三曲が決定した。
一曲目はアップテンポの青春ソング。一発目でみんなに興味を持ってもらえるように、高校生にも人気の曲をチョイスした。明るい曲調だから、聴いている方も弾いている方も楽しくなるに違いない。
二曲目は、一昔前に流行ったアニメのテーマソングだ。スパイが主人公のハードボイルドな作品で、曲はミステリアスでカッコいい。ボイストランペットで見せ場を作れることも決め手になった。
三曲目は、しっとりとしたバラードだ。切ない失恋ソングではなく、優しさと幸せを煮詰めたような曲だった。
この曲は、入江によく似合う。優しいギターの音色を最大限引き出せる曲だ。
20分という枠の中で、聴き手を飽きさせないようにバラエティーに富んだ曲をチョイスした。
「うんうん、良い選曲なんじゃない? さっそく帰ったら練習してみるよ」
テンションが上がっている入江を見て、ほっこりする。
「曲も決まったことだし、そろそろ帰ろうか」
「だねー」
片付けを終えると、俺たちは教室をあとにした。
空はすっかり暗くなっている。真夏と比べると、陽が沈むのが早くなったような気がした。
街灯に照らされた歩道を、ギターを背負った入江と並んで歩く。
「遅くなったけど、親、大丈夫?」
「これくらいなら平気。遅くなるって連絡入れたし」
「そっか、なら良かった」
マメに連絡を入れているのは入江らしい。多分、親とも普通に仲が良いんだろう。
家の話題があがったところで、入江は「そうだっ」と声を弾ませる。
「今度さ、うちにおいでよ。母さんも瀬尾のビートボックス、聴いてみたいって」
入江の家というのは、ちょっと興味がある。一体どんな豪邸に住んでいるんだ? 例のラフコリー(名前はローレンというらしい。貴族っぽい)にも会ってみたい。
文化祭が終わったらお邪魔しようかな、なんて考えていたところで、ふと我に返った。
人と深く関わるのはやめよう。そう決めたはずなのに、俺は自ら深みにはまろうとしている。
やめておけ、と脳内で黄色い危険信号が引っ切りなしに点滅していた。
入江とは、波長が合うから油断してしまった。多分、今がギリギリだ。これ以上近付いたら、見たくないものまで見えてしまう。
入江とは、音楽を通してだけ繋がっていればいい。これ以上深く関わったら、また傷つけてしまう。
今ならまだ引き返せる。踏み込み過ぎるな。
「あー、うん……。そのうちね。それよりさ――」
入江家へのお呼ばれの話はスルーして、別の話題に切り変える。幸い入江には不審がられなかった。
隣で無邪気に笑う入江を見て、ほっと息をつく。
これでいい。これでいいんだ。
入江と組んでから一週間が経った頃、練習中にそれとなく話題にあげてみた。案の定、入江はきょとんと目を丸くしている。
「ラジオ企画? なにそれ?」
「毎年放送部がやっている企画なんだけど、ゲストを呼んでトークをしたり、音楽を流したりするんだって。後夜祭のステージは、枠が埋まってて申し込めなかったけど、そっちはまだ空きがあるらしい。アコギとビートボックスなら生演奏しても構わないって言われたから、どうかなって」
入江は後夜祭に出ることを目標に練習に励んできた。それならどこかで演奏を披露できる場があった方がいいだろう。本番があった方が、練習のしがいもある。
あちこちでリサーチをした結果、一番しっくりきたのが放送部のラジオ企画だった。
アコースティックギターとビートボックスのセッションは、バンドと比べると見た目の華やかさはない。だから講堂や外ステージを使った見せるライブよりも、音だけで聴かせるラジオの方が向いているように思えた。
「うん、いいんじゃないかな!」
入江は目を輝かせて賛同してくれた。その反応を見て、ほっとする。
「じゃあ、放送部の部長に参加希望を出しておくよ。ひと枠20分って聞いたから、三曲できたらベストだけど」
「三曲かぁ……。本番まで二ヶ月ちょっと。いけるかな?」
あまり時間があるわけではない。だけど入江の実力なら、ギリギリいけそうな気がした。
俺たちはこの一週間で三回顔を合わせて練習していたけど、入江はその都度曲を変えていた。多分、譜読みも早い方なのだろう。
俺の方は、どうとでも合わせられる。もともと楽譜は使わずに、フィーリングでやっていたんだ。三曲だったら対応できる。
とはいえ、無理はさせたくない。入江に負担がかからないように、足並みは揃えるつもりだ。
「無理そうだったら、二曲でもいいよ。最悪一曲でもいいし」
放送部の部長からは、尺が短くなる分には構わないと言っていた。余った時間は、トークで繋ぐそうだ。
入江は少し考えこんでいたが、覚悟を決めたように「よし」と頷く。
「三曲やろう。やるからにはベストを尽くしたい」
「おお、アツイな」
「うん。俺、今燃えてるよ。目標が決まって、すっごくやる気になっているんだ。瀬尾と合わせるのも楽しいし」
純粋で真っすぐな思いをぶつけられると、照れくさくなってくる。
「……俺も、楽しいよ。入江とセッションしてるの」
恥ずかしさで顔を背けながらも本音を伝えると、教室の温度がちょっと上がった気がした。
シャツの胸元をパタパタさせて扇いでいると、入江はぐっと机から身を乗り出す。
「で、曲はなにやる? 俺、やりたい曲はいっぱいあるんだ」
目を輝かせながらうずうずしている。その姿を見て、自然と笑みが零れた。
そうだよな。どの曲をやるか決める時間が、一番楽しいんだ。
「色々曲を聴きながら、候補をあげていこうか」
俺はスマホを取り出して、動画配信サイトを開いた。
散々悩んだ結果、当日に演奏する三曲が決定した。
一曲目はアップテンポの青春ソング。一発目でみんなに興味を持ってもらえるように、高校生にも人気の曲をチョイスした。明るい曲調だから、聴いている方も弾いている方も楽しくなるに違いない。
二曲目は、一昔前に流行ったアニメのテーマソングだ。スパイが主人公のハードボイルドな作品で、曲はミステリアスでカッコいい。ボイストランペットで見せ場を作れることも決め手になった。
三曲目は、しっとりとしたバラードだ。切ない失恋ソングではなく、優しさと幸せを煮詰めたような曲だった。
この曲は、入江によく似合う。優しいギターの音色を最大限引き出せる曲だ。
20分という枠の中で、聴き手を飽きさせないようにバラエティーに富んだ曲をチョイスした。
「うんうん、良い選曲なんじゃない? さっそく帰ったら練習してみるよ」
テンションが上がっている入江を見て、ほっこりする。
「曲も決まったことだし、そろそろ帰ろうか」
「だねー」
片付けを終えると、俺たちは教室をあとにした。
空はすっかり暗くなっている。真夏と比べると、陽が沈むのが早くなったような気がした。
街灯に照らされた歩道を、ギターを背負った入江と並んで歩く。
「遅くなったけど、親、大丈夫?」
「これくらいなら平気。遅くなるって連絡入れたし」
「そっか、なら良かった」
マメに連絡を入れているのは入江らしい。多分、親とも普通に仲が良いんだろう。
家の話題があがったところで、入江は「そうだっ」と声を弾ませる。
「今度さ、うちにおいでよ。母さんも瀬尾のビートボックス、聴いてみたいって」
入江の家というのは、ちょっと興味がある。一体どんな豪邸に住んでいるんだ? 例のラフコリー(名前はローレンというらしい。貴族っぽい)にも会ってみたい。
文化祭が終わったらお邪魔しようかな、なんて考えていたところで、ふと我に返った。
人と深く関わるのはやめよう。そう決めたはずなのに、俺は自ら深みにはまろうとしている。
やめておけ、と脳内で黄色い危険信号が引っ切りなしに点滅していた。
入江とは、波長が合うから油断してしまった。多分、今がギリギリだ。これ以上近付いたら、見たくないものまで見えてしまう。
入江とは、音楽を通してだけ繋がっていればいい。これ以上深く関わったら、また傷つけてしまう。
今ならまだ引き返せる。踏み込み過ぎるな。
「あー、うん……。そのうちね。それよりさ――」
入江家へのお呼ばれの話はスルーして、別の話題に切り変える。幸い入江には不審がられなかった。
隣で無邪気に笑う入江を見て、ほっと息をつく。
これでいい。これでいいんだ。