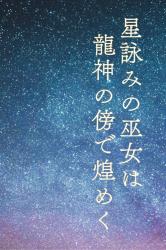人と深く関わるのはやめよう。
高校に入学した時にそう決意したはずなのに、俺は入江に声をかけてしまった。軽率に誘ってしまったことを、今更ながら後悔している。
「あー……」
放課後の空き教室で、がしがしと頭をかきながら項垂れていた。
窓の外からは、野球部員の声が聞こえてくる。「遅い、遅い、遅いっ」と叫ぶ野太い声は、俺までも叱責されているように思えた。
今更後悔しても遅いんだ。他でもない俺自身が、碇をあげてしまったんだから。船に乗るかどうかは、入江が決めることだ。その決断を、これから聞く。
俺と組もうと誘った時、入江は驚いたように固まっていた。そんな提案をされるとは思わなかっただのだろう。
しばらく沈黙が続いた後、入江は『少し、考えさせてほしい』と目を伏せた。そして二日後の今日、入江の決断を聞かせてもらう約束をしている。
生真面目そうだからすっぽかされることはないだろうけど、断られる可能性は大いにある。入江とはこれまで接点がなかった。知らない奴から急に誘われても困るだろう。もし俺が同じ立場なら、速攻断る。
そわそわしながら白球を追いかける野球部員を眺めていると、ガラリと教室のドアが開く。
「ごめん、待たせて。帰りがけに先生に頼まれ事をして」
「あ、うん、全然、いい、よ……」
振り返って入江の姿を見た途端、どきりと心臓が跳ねた。入江が、ギターケースを背負っていたからだ。
俺と組む気になったのか? いや、まだ確定したわけじゃない。まずは話し合いだ。
「とりあえず、そこ座れよ」
「うん」
前の席を指さすと、入江は朗らかに微笑んで頷く。心なしか、二日前に会った時よりも、顔色がよく見えた。
入江が正面に座ると、妙に緊張する。気まずくならないように、俺は会話のとっかかりを探した。
「悪いな、時間作ってもらって。忙しくなかった? 部活とかバイトとか」
「部活もバイトもやってないから平気だよ。放課後は、ギター弾いてるか、犬の散歩をしてるかだし」
「へえ、犬飼ってるんだ。犬種なに?」
「ラフコリー。賢くて、優しいんだよ」
ほら、と見せられたスマホのロック画面には、白と薄茶色が混ざった毛足の長い大型犬が映っていた。俺の想像していた飼い犬よりも、だいぶデカイ。
多分、こいつん家、金持ちだ。都内で大型犬を飼えるなんて、裕福な家に違いない。平々凡々なサラリーマン家庭に生まれた俺とは、住む世界が違うのかもしれない。
早々に怖気づいてしまったが、入江は何食わぬ顔で「ん?」と首を傾げるばかり。その顔と仕草は、スマホに映るラフコリーとよく似ていた。
「あー……。犬待たせたら悪いから、本題に入ろう」
どんな本題の持っていき方だよ、なんて心の中で突っ込みを入れてしまったが、正面の入江は「今日は弟に任せてるから平気だよー」なんて呑気に笑っていた。気を取り直して、本題に入る。
「えーっと、俺と組もうって言ったのは、アコースティックギターとビートボックスのセッションをやろうってこと」
「一昨日、音楽室で合わせたやつだよね。メンバーは俺と瀬尾の二人?」
「そのつもり」
「ボーカルは?」
「ボーカルなしのインストバンドでやろうと思っている」
入江は歌苦手って言ってたから、と付け足そうとしたがやめておいた。校舎裏での会話を盗み聞きしていたのは、俺にとっては後ろめたいことだからだ。
入江は納得したように、ふんふんと頷く。
「なるほどねー。だけどギターとビートボックスっていうのは結構珍しいんじゃない。あれから俺も色々調べてみたけど、瀬尾がやってたのって、アカペラバンドのリズム隊なんでしょ? ボイスパーカッションっていうんだっけ?」
「そうだね。アカペラだとボイスパーカッションって呼ばれている。ビートボックスは、ヒップホップ由来のものだから、バンドのパーカスの役割を果たすものじゃないんだけど……まあ、その辺はそんなに気にしなくていいよ」
ビートボックスのことになると、うっかり喋りすぎてしまいそうだから自重した。
入江は心配そうな眼差しで、じっとこちらを見つめる。
「ギターとも合わせられるの?」
「音楽に縛りなんてないでしょ。どんな楽器でも、やり方次第でいくらでも合わせられる」
そう言い切ると、入江は驚いたように目を見開く。変なこと言ったか、とビビっていると、入江はへなへなと机に突っ伏した。
「かぁっこいいなぁ、瀬尾は」
「……は?」
想像の斜め上をいく反応をされて、間の抜けた声が出る。入江はへにゃりと緩んだ表情で、こちらを見上げた。
「実はさ、ビートボックスだけじゃなくて、瀬尾のこともちょっと調べたんだ。……あ、変な意味じゃないよ。どんな人なのか知りたくて、友達にそれとなく聞いてみたの」
調べたと言われて肝が冷える。後ろめたいことは、知られていないはずだ。それを知っている人間は、この学校にはいないのだから。
内心では動揺していたものの、入江が耳にした情報はまたしても俺の想像の斜め上をいくものだった。
「瀬尾ってさ、特定の人とつるむんじゃなくて、誰とでも対等に話せるんだってね。グループに所属しているわけじゃないけど、孤立しているわけじゃない。その場、その場で、自在にコミュニケーションがとれる。そういうのって大人っぽくって、かっこいいなぁって思ったんだ」
「…………別に、そんな大層なもんじゃないよ」
俺はただ、人と深く関わることを避けているだけだ。だから広く、浅くの関係を心がけている。知り合ったばかりの相手に、話す内容ではないけど。
「この間も、さりげなく優しくしてくれたし。……実は結構モテるでしょ? 背も高いし、顔も爽やかでかっこいいし、清潔感あるし」
「モテねーよ。ここ男子校だぞ」
「あはっ、確かにー。共学だったら即彼女できていたタイプだろうね。男子校でざーんねんっ」
入江は、突っ伏しながらくすくす笑っていた。
入江から恋愛絡みの話が出てくるのは、ちょっと意外だった。ゆるふわフェアリーくんかと思っていたけど、案外普通の男子高校生なのかもしれない。その方が、俺としては付き合いやすいけど。
「そういう入江は、彼女いるの?」
「彼女はいないけど、婚約者はいるよ」
「え? マジ?」
さすがお坊ちゃん、なんて真に受けてしまったが、入江はふふっと肩を震わせて笑いだした。
「ごめん。冗談。彼女も婚約者もいないよ」
「なんだ、冗談か、びっくりしたぁ」
今時高校生で婚約者がいるとかありえないよな。そこらへんも俺と同じ普通の男子高校生で安心した。
入江はひとしきり笑うと、むくりと身体を起こす。
「決めた。瀬尾と組むよ」
「……マジで?」
「うん。ビートボックスと上手く合わせられるかは分からないけど、瀬尾となら上手くいきそう」
真っすぐ俺を捉えた入江の瞳には、光が宿っていた。新たな一歩を踏み出す、期待に満ちた眼差しだ。
今の会話のどこが決め手になったのかは分からないが、こっちを信用してくれたのは嬉しかった。
入江と話すまでは、うかつに誘ってしまったことに後悔していたけど、もう迷いはない。これなら堂々とオールを漕げる。二人乗りの小さな船は、航海を始めようとしていた。
「ありがとう、入江! じゃあ、さっそく練習する?」
「うん!」
入江は弾んだ声で返事をしてから、いそいそとギターケースからアコースティックギターを取り出した。
入江はギターを抱えると、ポロンと優しく弦を弾く。いくつかコードを確認してから、演奏を始めた。
今日の音色は、前回よりも優しく聞こえる。ギターの音色に寄り添うように、俺はビートを刻んだ。
音を通して、入江の人柄が伝わってくる。優しさや、純粋さや、繊細さが。少し目を伏せながら穏やかな眼差しで弾く姿を見つめていると、顔を上げた入江が目を細めて微笑んだ。
――楽しいね。
そう言われているような気がした。それに返すように、俺は小さく頷く。
俺たちは、言葉を交わすことなく、音楽で対話をしている。こんなやり方で人と繋がれるなんて思わなかった。言葉の使い方が下手くそな俺には、このやり方がちょうどいいのかもしれない。
入江を誘って良かった。この優しい音色が、いつまでも消えないようにと願っていた。
高校に入学した時にそう決意したはずなのに、俺は入江に声をかけてしまった。軽率に誘ってしまったことを、今更ながら後悔している。
「あー……」
放課後の空き教室で、がしがしと頭をかきながら項垂れていた。
窓の外からは、野球部員の声が聞こえてくる。「遅い、遅い、遅いっ」と叫ぶ野太い声は、俺までも叱責されているように思えた。
今更後悔しても遅いんだ。他でもない俺自身が、碇をあげてしまったんだから。船に乗るかどうかは、入江が決めることだ。その決断を、これから聞く。
俺と組もうと誘った時、入江は驚いたように固まっていた。そんな提案をされるとは思わなかっただのだろう。
しばらく沈黙が続いた後、入江は『少し、考えさせてほしい』と目を伏せた。そして二日後の今日、入江の決断を聞かせてもらう約束をしている。
生真面目そうだからすっぽかされることはないだろうけど、断られる可能性は大いにある。入江とはこれまで接点がなかった。知らない奴から急に誘われても困るだろう。もし俺が同じ立場なら、速攻断る。
そわそわしながら白球を追いかける野球部員を眺めていると、ガラリと教室のドアが開く。
「ごめん、待たせて。帰りがけに先生に頼まれ事をして」
「あ、うん、全然、いい、よ……」
振り返って入江の姿を見た途端、どきりと心臓が跳ねた。入江が、ギターケースを背負っていたからだ。
俺と組む気になったのか? いや、まだ確定したわけじゃない。まずは話し合いだ。
「とりあえず、そこ座れよ」
「うん」
前の席を指さすと、入江は朗らかに微笑んで頷く。心なしか、二日前に会った時よりも、顔色がよく見えた。
入江が正面に座ると、妙に緊張する。気まずくならないように、俺は会話のとっかかりを探した。
「悪いな、時間作ってもらって。忙しくなかった? 部活とかバイトとか」
「部活もバイトもやってないから平気だよ。放課後は、ギター弾いてるか、犬の散歩をしてるかだし」
「へえ、犬飼ってるんだ。犬種なに?」
「ラフコリー。賢くて、優しいんだよ」
ほら、と見せられたスマホのロック画面には、白と薄茶色が混ざった毛足の長い大型犬が映っていた。俺の想像していた飼い犬よりも、だいぶデカイ。
多分、こいつん家、金持ちだ。都内で大型犬を飼えるなんて、裕福な家に違いない。平々凡々なサラリーマン家庭に生まれた俺とは、住む世界が違うのかもしれない。
早々に怖気づいてしまったが、入江は何食わぬ顔で「ん?」と首を傾げるばかり。その顔と仕草は、スマホに映るラフコリーとよく似ていた。
「あー……。犬待たせたら悪いから、本題に入ろう」
どんな本題の持っていき方だよ、なんて心の中で突っ込みを入れてしまったが、正面の入江は「今日は弟に任せてるから平気だよー」なんて呑気に笑っていた。気を取り直して、本題に入る。
「えーっと、俺と組もうって言ったのは、アコースティックギターとビートボックスのセッションをやろうってこと」
「一昨日、音楽室で合わせたやつだよね。メンバーは俺と瀬尾の二人?」
「そのつもり」
「ボーカルは?」
「ボーカルなしのインストバンドでやろうと思っている」
入江は歌苦手って言ってたから、と付け足そうとしたがやめておいた。校舎裏での会話を盗み聞きしていたのは、俺にとっては後ろめたいことだからだ。
入江は納得したように、ふんふんと頷く。
「なるほどねー。だけどギターとビートボックスっていうのは結構珍しいんじゃない。あれから俺も色々調べてみたけど、瀬尾がやってたのって、アカペラバンドのリズム隊なんでしょ? ボイスパーカッションっていうんだっけ?」
「そうだね。アカペラだとボイスパーカッションって呼ばれている。ビートボックスは、ヒップホップ由来のものだから、バンドのパーカスの役割を果たすものじゃないんだけど……まあ、その辺はそんなに気にしなくていいよ」
ビートボックスのことになると、うっかり喋りすぎてしまいそうだから自重した。
入江は心配そうな眼差しで、じっとこちらを見つめる。
「ギターとも合わせられるの?」
「音楽に縛りなんてないでしょ。どんな楽器でも、やり方次第でいくらでも合わせられる」
そう言い切ると、入江は驚いたように目を見開く。変なこと言ったか、とビビっていると、入江はへなへなと机に突っ伏した。
「かぁっこいいなぁ、瀬尾は」
「……は?」
想像の斜め上をいく反応をされて、間の抜けた声が出る。入江はへにゃりと緩んだ表情で、こちらを見上げた。
「実はさ、ビートボックスだけじゃなくて、瀬尾のこともちょっと調べたんだ。……あ、変な意味じゃないよ。どんな人なのか知りたくて、友達にそれとなく聞いてみたの」
調べたと言われて肝が冷える。後ろめたいことは、知られていないはずだ。それを知っている人間は、この学校にはいないのだから。
内心では動揺していたものの、入江が耳にした情報はまたしても俺の想像の斜め上をいくものだった。
「瀬尾ってさ、特定の人とつるむんじゃなくて、誰とでも対等に話せるんだってね。グループに所属しているわけじゃないけど、孤立しているわけじゃない。その場、その場で、自在にコミュニケーションがとれる。そういうのって大人っぽくって、かっこいいなぁって思ったんだ」
「…………別に、そんな大層なもんじゃないよ」
俺はただ、人と深く関わることを避けているだけだ。だから広く、浅くの関係を心がけている。知り合ったばかりの相手に、話す内容ではないけど。
「この間も、さりげなく優しくしてくれたし。……実は結構モテるでしょ? 背も高いし、顔も爽やかでかっこいいし、清潔感あるし」
「モテねーよ。ここ男子校だぞ」
「あはっ、確かにー。共学だったら即彼女できていたタイプだろうね。男子校でざーんねんっ」
入江は、突っ伏しながらくすくす笑っていた。
入江から恋愛絡みの話が出てくるのは、ちょっと意外だった。ゆるふわフェアリーくんかと思っていたけど、案外普通の男子高校生なのかもしれない。その方が、俺としては付き合いやすいけど。
「そういう入江は、彼女いるの?」
「彼女はいないけど、婚約者はいるよ」
「え? マジ?」
さすがお坊ちゃん、なんて真に受けてしまったが、入江はふふっと肩を震わせて笑いだした。
「ごめん。冗談。彼女も婚約者もいないよ」
「なんだ、冗談か、びっくりしたぁ」
今時高校生で婚約者がいるとかありえないよな。そこらへんも俺と同じ普通の男子高校生で安心した。
入江はひとしきり笑うと、むくりと身体を起こす。
「決めた。瀬尾と組むよ」
「……マジで?」
「うん。ビートボックスと上手く合わせられるかは分からないけど、瀬尾となら上手くいきそう」
真っすぐ俺を捉えた入江の瞳には、光が宿っていた。新たな一歩を踏み出す、期待に満ちた眼差しだ。
今の会話のどこが決め手になったのかは分からないが、こっちを信用してくれたのは嬉しかった。
入江と話すまでは、うかつに誘ってしまったことに後悔していたけど、もう迷いはない。これなら堂々とオールを漕げる。二人乗りの小さな船は、航海を始めようとしていた。
「ありがとう、入江! じゃあ、さっそく練習する?」
「うん!」
入江は弾んだ声で返事をしてから、いそいそとギターケースからアコースティックギターを取り出した。
入江はギターを抱えると、ポロンと優しく弦を弾く。いくつかコードを確認してから、演奏を始めた。
今日の音色は、前回よりも優しく聞こえる。ギターの音色に寄り添うように、俺はビートを刻んだ。
音を通して、入江の人柄が伝わってくる。優しさや、純粋さや、繊細さが。少し目を伏せながら穏やかな眼差しで弾く姿を見つめていると、顔を上げた入江が目を細めて微笑んだ。
――楽しいね。
そう言われているような気がした。それに返すように、俺は小さく頷く。
俺たちは、言葉を交わすことなく、音楽で対話をしている。こんなやり方で人と繋がれるなんて思わなかった。言葉の使い方が下手くそな俺には、このやり方がちょうどいいのかもしれない。
入江を誘って良かった。この優しい音色が、いつまでも消えないようにと願っていた。