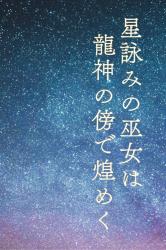放課後は早く帰りたかったのに、数学のノートを全員分回収して、職員室に運ばなければならなかった。
九月七日だから、9と7を足した出席番号16番、瀬尾颯真。数学教師は、そいつに仕事を命じた。俺だ。
シンプルに7番にしとけよ、なんて思ったが、口には出さず。ちゃっちゃかノートを回収して、職員室に運んだ。
ひと仕事終えて音楽室の前を通りかかった時、ポン、ポン、ポン、と透き通ったアルペジオが聞こえた。
気になって足を止める。この音は、アコースティックギターか?
音の出どころは、音楽室だ。うちの学校には軽音楽部はないから、ギターを弾いている奴は珍しい。十一月に控えた文化祭に向けて、練習をしているのか?
文化祭とギター。その単語が並んだ所で、昼休みに目撃した追放騒動を思い出す。
……まさかな。そんな偶然はあるはずがない。
関係ないと思いつつも、気になってしまった。俺はそっと音楽室の扉を押し開けて、中を覗いた。
扉の向こうには、背を向けて椅子に座る男子生徒がいる。そのつむじは、昼休みに目撃した入江のものと一致していた。
やっぱり、入江だったのか……。予想が当たって嬉しいような、悲しいような。
入江は身体を前後に揺らしながら、丁寧に音を紡いでいる。窓から差し込んだ夕日に照らされて、入江の背中が透き通って見えた。
嘘みたいに綺麗だ。俺は息を呑んで、入江が演奏する姿を脳裏に焼き付けていた。
音が止むと、入江はふぅと息をつく。それから気分を切り替えるように曲を弾き始めた。
前奏を聞いただけで分かった。少し前に流行った、バラード調の失恋ソングだ。泣ける映画の主題歌だった気がする。
しっとりしたアコースティックギターの音色を聴いていると、ぎゅっと胸が締め付けられる。歌詞に引きずられているわけではない。入江の奏でる音色から、切なさが滲み出ていた。
気を緩めたら泣きそうだ。切なさを振り払うように頭を揺らしてから、曲に集中した。
それにしても、入江は安定感のある演奏をする。途中で詰まることもなければ、テンポが乱れることはない。プロ並みとは言い難いが、普通に上手かった。
きっとそれなりの年月をかけて練習してきたのだろう。ギターは素人の俺だけど、入江の演奏は上手いと思えた。
音楽を聴いていると、ビートを刻みたくなる。ビートボックスの動画を観るようになってから、俺も練習していた。
ゆったりとした曲だから、8ビートで刻めばいい。最初はドッドッと重低音で響くバスドラムを鳴らし、慣れてきたらツッと舌で弾くようなハイハットを加えてみる。さらにカッとドラムの淵を叩くようにリムショットも交えてみた。
三つの音を組み合わせれば、ボイスパーカッションとしての役割を十分果たせた。
自分以外の音が交ざっていることに、入江も気付く。すんっと鼻をすするように肩を上下させた後、ゆっくりと振り返った。
ああ、まただ……。入江は、泣いている。瞳の中に涙を溜めて、目尻は朱色に染まっていた。
入江は目を見開いた後、ごしごしと目元と拭ってから、作り笑いを浮かべる。
「あれ、昼休みに会った……」
「瀬尾颯真。二年三組の」
ボイスパーカッションを止めて、自己紹介をする。反応から察するに、向こうも俺の名前は知らなかったようだ。
「あ、あー、瀬尾くん? どうしたの? 音楽室に用事あった?」
入江は、あちらこちらに視線を巡らせながら用件を尋ねる。
忘れ物して~、とか適当に誤魔化せばよかったものの、俺は正直に答えてしまった。
「ギターの音がしたから気になって」
「あー、そっか、そうだよね。うん……」
笑顔を取り繕っていた入江は、しぼんだ風船のように小さくなっていく。なんだかもう、色々誤魔化しが効かなくなったことを悟ったのかもしれない。
恥をかかせているのは分かっている。ここで何事もなかったように立ち去るのが優しさだと思う。だけど俺は、入江の奏でる音色に未練があった。
「続けて」
「え?」
「さっきみたいに、ビート刻むから」
入江は、ぽかんと口を開けて固まっている。目の前の男が、何を企んでいるか分からないからだろう。ボロボロになった彼は、少しの刺激も恐れているように見えた。
これは俺が先にやるしかない。腹の奥まで息を吸い込むと、先ほどと同じように8ビートでリズムを刻んだ。
何やってんだ、と呆れられてしまうかもしれない。だけど、彼が音楽に未練があるなら、この誘いに乗ってきてくれるような気がした。
案の定、入江は乗ってきた。
悪い事をしているかのように、目を伏せながら弦を弾く。先ほどよりもぎこちない演奏だ。人に見られながら演奏することに慣れていないのかもしれない。
AメロからBメロに変わったタイミングで、少しリズムの刻み方を変えてみる。バスドラム、ハイハット、リムショット、ハイハットの順でループしていたリズムに、プシッと軽やかに響くスネアドラムを加えてみた。
入江はふっと顔を上げる。それは先ほどまでの悲し気な表情とは異なり、物珍しいものを見るような眼差しだった。
興味を持ってもらえたようだ。目を細めて笑ってみせると、入江の表情も柔らかくなった。
弦を弾く手に力がこもる。その瞬間からバラバラだった音色が、糸を束ねるように合わさった。
サビに入る直前に、変則的に叩くフィルインでアクセントを入れてみる。そこから盛り上がるように刻み方を変えていくと、入江もリズムに押し負けないように力を込めて弾いた。
音楽室に響いているのは、切なげなメロディーではない。芯を持った優しいメロディーだ。
誰かと音を共有することが、こんなにも楽しいことだとは思わなかった。
この時間が終わってほしくない。二人で奏でる音色に酔いしれていた。
曲は次第に終わりに近付いている。入江はラストのサビで目一杯盛り上げてから、力強く最後の一音を鳴らした。その余韻を残すように、俺はクラッシュシンバルを鳴らす。練習不足なせいで、ぷしゅーっと気の抜けた音になってしまったけど。
音が止むと、静寂が訪れる。オレンジ色に染まった音楽室の真ん中で、入江は目を輝かせた。
「凄いね! それ、なんていうんだっけ? ボイスパーカッション?」
「あー、俺が好きなのはビートボックスだけど、今のはボイスパーカッションかな」
入江は、はて、と首を傾げていたけど、すぐに瞳の輝きを取り戻す。
「凄いね! 瀬尾くんにそんな特技があったなんて知らなかったよ。口だけでいろんな音が出せるなんて、ほんと凄い」
「瀬尾でいいよ。俺は始めて一年くらいしか経ってないから、そんなに上手くないし。まだまだ練習中。入江こそ、ギター上手いじゃん。昔からやってたの?」
「俺も一年前くらいからギター始めたんだ。去年の後夜祭で先輩たちのバンドに感動して、来年は俺たちも出ようぜってみんなで約束、した、から……」
意気揚々と語っていた入江だったが、うっかり痛い所に触れてしまったようだ。
入江の言う“みんな”とは、黒田たちのことだろう。去年の文化祭で約束をしてから、入江は地道に練習してきたんだ。
一年であれだけ弾けるようになったのだから、相当練習したに違いない。入江の生真面目な性格がひしひしと伝わってきた。
入江は沈んだ空気を切り替えるように、へらりと力なく笑う。
「まあ、あんなことがあったから、お披露目する機会はなくなっちゃったけどね。もう学校では弾かないから、音楽準備室に保管していたギターを取りにきたんだ」
入江は膝に乗せたギターをそっと抱き寄せる。辛うじて笑っているけど、やるせなさが滲んできた。
「最後に、楽しく弾けて良かった……」
入江の口にした“最後”という言葉に引っかかる。
「ギター、もうやめるの?」
「うーん、どうだろうねえ……」
入江はギターを見つめながら、歯切れの悪い返事をする。伏せた目元から覗く長い睫毛は、やけに繊細に見えた。
入江がギターをやめる。それはもったいないことだ。一年であんなに上達したのに、こんなところでやめるなんて……。
それに入江とセッションした時、今までにはない高揚感を味わった。あんな感覚は、初めてだ。
ビートボックスは、ひとりでも楽しめる。誰かと合わせなくたっていい。だから俺ものめり込んだ。
だけど今日は、合わせた。成り行きだったけど、楽しかった。ひとりで練習している時よりもずっと――。
また、合わせてみたい。あの高揚感を、もう一度味わいたい。
押し寄せる欲望は、理性という固い砦をあっという間に飲み込んだ。
「あのさ、入江。もしよければ、俺と組まない?」
九月七日だから、9と7を足した出席番号16番、瀬尾颯真。数学教師は、そいつに仕事を命じた。俺だ。
シンプルに7番にしとけよ、なんて思ったが、口には出さず。ちゃっちゃかノートを回収して、職員室に運んだ。
ひと仕事終えて音楽室の前を通りかかった時、ポン、ポン、ポン、と透き通ったアルペジオが聞こえた。
気になって足を止める。この音は、アコースティックギターか?
音の出どころは、音楽室だ。うちの学校には軽音楽部はないから、ギターを弾いている奴は珍しい。十一月に控えた文化祭に向けて、練習をしているのか?
文化祭とギター。その単語が並んだ所で、昼休みに目撃した追放騒動を思い出す。
……まさかな。そんな偶然はあるはずがない。
関係ないと思いつつも、気になってしまった。俺はそっと音楽室の扉を押し開けて、中を覗いた。
扉の向こうには、背を向けて椅子に座る男子生徒がいる。そのつむじは、昼休みに目撃した入江のものと一致していた。
やっぱり、入江だったのか……。予想が当たって嬉しいような、悲しいような。
入江は身体を前後に揺らしながら、丁寧に音を紡いでいる。窓から差し込んだ夕日に照らされて、入江の背中が透き通って見えた。
嘘みたいに綺麗だ。俺は息を呑んで、入江が演奏する姿を脳裏に焼き付けていた。
音が止むと、入江はふぅと息をつく。それから気分を切り替えるように曲を弾き始めた。
前奏を聞いただけで分かった。少し前に流行った、バラード調の失恋ソングだ。泣ける映画の主題歌だった気がする。
しっとりしたアコースティックギターの音色を聴いていると、ぎゅっと胸が締め付けられる。歌詞に引きずられているわけではない。入江の奏でる音色から、切なさが滲み出ていた。
気を緩めたら泣きそうだ。切なさを振り払うように頭を揺らしてから、曲に集中した。
それにしても、入江は安定感のある演奏をする。途中で詰まることもなければ、テンポが乱れることはない。プロ並みとは言い難いが、普通に上手かった。
きっとそれなりの年月をかけて練習してきたのだろう。ギターは素人の俺だけど、入江の演奏は上手いと思えた。
音楽を聴いていると、ビートを刻みたくなる。ビートボックスの動画を観るようになってから、俺も練習していた。
ゆったりとした曲だから、8ビートで刻めばいい。最初はドッドッと重低音で響くバスドラムを鳴らし、慣れてきたらツッと舌で弾くようなハイハットを加えてみる。さらにカッとドラムの淵を叩くようにリムショットも交えてみた。
三つの音を組み合わせれば、ボイスパーカッションとしての役割を十分果たせた。
自分以外の音が交ざっていることに、入江も気付く。すんっと鼻をすするように肩を上下させた後、ゆっくりと振り返った。
ああ、まただ……。入江は、泣いている。瞳の中に涙を溜めて、目尻は朱色に染まっていた。
入江は目を見開いた後、ごしごしと目元と拭ってから、作り笑いを浮かべる。
「あれ、昼休みに会った……」
「瀬尾颯真。二年三組の」
ボイスパーカッションを止めて、自己紹介をする。反応から察するに、向こうも俺の名前は知らなかったようだ。
「あ、あー、瀬尾くん? どうしたの? 音楽室に用事あった?」
入江は、あちらこちらに視線を巡らせながら用件を尋ねる。
忘れ物して~、とか適当に誤魔化せばよかったものの、俺は正直に答えてしまった。
「ギターの音がしたから気になって」
「あー、そっか、そうだよね。うん……」
笑顔を取り繕っていた入江は、しぼんだ風船のように小さくなっていく。なんだかもう、色々誤魔化しが効かなくなったことを悟ったのかもしれない。
恥をかかせているのは分かっている。ここで何事もなかったように立ち去るのが優しさだと思う。だけど俺は、入江の奏でる音色に未練があった。
「続けて」
「え?」
「さっきみたいに、ビート刻むから」
入江は、ぽかんと口を開けて固まっている。目の前の男が、何を企んでいるか分からないからだろう。ボロボロになった彼は、少しの刺激も恐れているように見えた。
これは俺が先にやるしかない。腹の奥まで息を吸い込むと、先ほどと同じように8ビートでリズムを刻んだ。
何やってんだ、と呆れられてしまうかもしれない。だけど、彼が音楽に未練があるなら、この誘いに乗ってきてくれるような気がした。
案の定、入江は乗ってきた。
悪い事をしているかのように、目を伏せながら弦を弾く。先ほどよりもぎこちない演奏だ。人に見られながら演奏することに慣れていないのかもしれない。
AメロからBメロに変わったタイミングで、少しリズムの刻み方を変えてみる。バスドラム、ハイハット、リムショット、ハイハットの順でループしていたリズムに、プシッと軽やかに響くスネアドラムを加えてみた。
入江はふっと顔を上げる。それは先ほどまでの悲し気な表情とは異なり、物珍しいものを見るような眼差しだった。
興味を持ってもらえたようだ。目を細めて笑ってみせると、入江の表情も柔らかくなった。
弦を弾く手に力がこもる。その瞬間からバラバラだった音色が、糸を束ねるように合わさった。
サビに入る直前に、変則的に叩くフィルインでアクセントを入れてみる。そこから盛り上がるように刻み方を変えていくと、入江もリズムに押し負けないように力を込めて弾いた。
音楽室に響いているのは、切なげなメロディーではない。芯を持った優しいメロディーだ。
誰かと音を共有することが、こんなにも楽しいことだとは思わなかった。
この時間が終わってほしくない。二人で奏でる音色に酔いしれていた。
曲は次第に終わりに近付いている。入江はラストのサビで目一杯盛り上げてから、力強く最後の一音を鳴らした。その余韻を残すように、俺はクラッシュシンバルを鳴らす。練習不足なせいで、ぷしゅーっと気の抜けた音になってしまったけど。
音が止むと、静寂が訪れる。オレンジ色に染まった音楽室の真ん中で、入江は目を輝かせた。
「凄いね! それ、なんていうんだっけ? ボイスパーカッション?」
「あー、俺が好きなのはビートボックスだけど、今のはボイスパーカッションかな」
入江は、はて、と首を傾げていたけど、すぐに瞳の輝きを取り戻す。
「凄いね! 瀬尾くんにそんな特技があったなんて知らなかったよ。口だけでいろんな音が出せるなんて、ほんと凄い」
「瀬尾でいいよ。俺は始めて一年くらいしか経ってないから、そんなに上手くないし。まだまだ練習中。入江こそ、ギター上手いじゃん。昔からやってたの?」
「俺も一年前くらいからギター始めたんだ。去年の後夜祭で先輩たちのバンドに感動して、来年は俺たちも出ようぜってみんなで約束、した、から……」
意気揚々と語っていた入江だったが、うっかり痛い所に触れてしまったようだ。
入江の言う“みんな”とは、黒田たちのことだろう。去年の文化祭で約束をしてから、入江は地道に練習してきたんだ。
一年であれだけ弾けるようになったのだから、相当練習したに違いない。入江の生真面目な性格がひしひしと伝わってきた。
入江は沈んだ空気を切り替えるように、へらりと力なく笑う。
「まあ、あんなことがあったから、お披露目する機会はなくなっちゃったけどね。もう学校では弾かないから、音楽準備室に保管していたギターを取りにきたんだ」
入江は膝に乗せたギターをそっと抱き寄せる。辛うじて笑っているけど、やるせなさが滲んできた。
「最後に、楽しく弾けて良かった……」
入江の口にした“最後”という言葉に引っかかる。
「ギター、もうやめるの?」
「うーん、どうだろうねえ……」
入江はギターを見つめながら、歯切れの悪い返事をする。伏せた目元から覗く長い睫毛は、やけに繊細に見えた。
入江がギターをやめる。それはもったいないことだ。一年であんなに上達したのに、こんなところでやめるなんて……。
それに入江とセッションした時、今までにはない高揚感を味わった。あんな感覚は、初めてだ。
ビートボックスは、ひとりでも楽しめる。誰かと合わせなくたっていい。だから俺ものめり込んだ。
だけど今日は、合わせた。成り行きだったけど、楽しかった。ひとりで練習している時よりもずっと――。
また、合わせてみたい。あの高揚感を、もう一度味わいたい。
押し寄せる欲望は、理性という固い砦をあっという間に飲み込んだ。
「あのさ、入江。もしよければ、俺と組まない?」