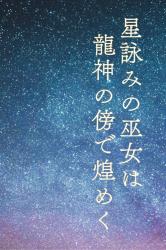文化祭が終わると、生徒たちは熱気に包まれたまま、後夜祭が行われる体育館に移動していた。
俺と入江は、その流れに逆らって、空き教室に向かう。窓際の席で向かい合って座ると、いつもの空気が戻ってきた。
「あーあ、リハもサボっちゃったし、本番もサボっちゃった。黒田たち、怒っているよねー」
入江は机に突っ伏しながら、窓の外を眺めている。嘆いているような口ぶりだが、その表情はどこか晴れやかだ。
「気にすんな。あっちはあっちでどうにかするだろ。失敗しても、ざまあって笑っとけ」
「ふふっ、そうだね」
入江は椅子から立ち上がると、窓辺に立つ。校舎の窓から見える体育館を一瞥した後、境界線を引くようにシャーッとカーテンを閉めた。
すぐに席に戻ってくると思いきや、入江は背を向けたまま立ち尽くしている。どうしたんだと眉を顰めていると、入江は緊張感を漂わせながら話を切り出した。
「あのさ、瀬尾。ずっと言えなかったこと、言って良い?」
改まってなんだ? 入江の顔が見えないから、良い話か悪い話か判別がつかない。
「……うん、いいけど」
身構えながらも話を聞く姿勢になると、入江は背を向けたまま告げた。
「俺さ、好きだよ」
「え?」
「瀬尾のビートボックス」
ぱちぱちと瞬きをしてから、ようやく理解が追い付く。
あ、あー、ビートボックスか……。一瞬、告白されたかと思ってびっくりした。
無駄に暴れまわった心臓を押さえていると、入江は俯き加減で言葉を続ける。
「これを言ったら気を悪くするかもしれないけどさ、音楽室で瀬尾と合わせた日の晩、ビートボックスバトルの動画を観てみたんだ。だけど、なんというか……ちょっと怖いなって思ったんだ」
「怖い?」
「うん、音の暴力っていうのかな? 荒々しくて、喧嘩っぽくって、穏やかじゃないなって……」
まあ、確かに、ビートボックスバトルだと、雰囲気に圧倒されるのも分かる。音はパワフルだし、会場の熱気も凄い。
だけど、それを凌駕するほどの感動と情熱が~、なんて語りたくなったが、思いとどまった。まずは入江の話を聞こう。
「だけど、瀬尾の出す音は、優しいなって思ったんだ。こっちの音に寄り添って、支えてくれるような音に聞こえた」
優しい音なんて、初めて言われた。優しい音を出すのは入江であって、俺は別に……。
戸惑っていると、入江はくるりと振り返って、穏やかに微笑んだ。
「多分さ、瀬尾は一人でいるよりも、みんなの輪の中にいる方が向いていると思う。瀬尾の優しさに救われる人は、大勢いるはずだから」
さらりと飛んできた言葉は、凍えていたもう一人の自分をそっと包み込んだ。
俺は、もう誰も傷つけないように、誰とも深く繋がらないように心掛けてきた。だけど、本心は違う。
本当は、誰かと繋がっていたかったんだ。ひとりでも構わないと思い込んでいたけど、心の奥底では誰とも深く繋がれない日々を退屈に思っていた。
そんな俺の本音を、入江は見抜いていた。言葉ではなく、音楽を通して。
誰にも気付かれないようにしまっていた感情を、取り出されてしまったようだ。
きっと入江は、勇気を出して伝えてくれたに違いない。緊張しながら話を切り出していたのが、その証拠だ。
音楽を通して受け取った思いを、きちんと言葉にして返してくれた。その勇気に、俺は救われていた。
目頭が熱くなる。こんな所で、湿っぽい空気にする気はなかったのに勘弁してくれ。
込み上げてくる涙を遠ざけるように、俺は頭を揺らす。
「……優しいだけじゃ、ないから」
「ん?」
「かっこいい音も出せる」
まるで子供のような主張だなと呆れてしまったが、入江は「へえ」と興味を持ってくれた。
「ボイストランペットは、それなりにかっこよく吹けるようになった。聴きたい?」
「うん、聴きたい!」
入江は即答する。そう言ってくれると思った。
俺が前の席を指さすと、入江は壁に立てかけたギターを掴んで椅子に座った。
「入江だって一曲しか弾けてなくて不完全燃焼なんだろ? ここで演奏しよう。こっちのバンドの三曲と、あいつらのバンドの三曲。六曲連続で」
「向こうの曲は、瀬尾知らないじゃん。ロックだよ? テンポも速いよ?」
「見くびんなよ? 俺はどんな曲でも即興で合わせられる」
にっと笑いながら大口を叩くと、入江は目を細めてくすくすと笑いだした。
「やっぱり瀬尾は、かっこいいね」
顔を見合わせてひとしきり笑った後、入江はポロンと優しく弦を弾く。
「じゃあ、やろっか。二人だけの後夜祭」
「だなっ!」
カーテンの向こうからは、ロックバンドの激しい演奏が聞こえる。
その音に被せるように、俺はハイハットを三つ叩いてカウントを取った。
【fin】
俺と入江は、その流れに逆らって、空き教室に向かう。窓際の席で向かい合って座ると、いつもの空気が戻ってきた。
「あーあ、リハもサボっちゃったし、本番もサボっちゃった。黒田たち、怒っているよねー」
入江は机に突っ伏しながら、窓の外を眺めている。嘆いているような口ぶりだが、その表情はどこか晴れやかだ。
「気にすんな。あっちはあっちでどうにかするだろ。失敗しても、ざまあって笑っとけ」
「ふふっ、そうだね」
入江は椅子から立ち上がると、窓辺に立つ。校舎の窓から見える体育館を一瞥した後、境界線を引くようにシャーッとカーテンを閉めた。
すぐに席に戻ってくると思いきや、入江は背を向けたまま立ち尽くしている。どうしたんだと眉を顰めていると、入江は緊張感を漂わせながら話を切り出した。
「あのさ、瀬尾。ずっと言えなかったこと、言って良い?」
改まってなんだ? 入江の顔が見えないから、良い話か悪い話か判別がつかない。
「……うん、いいけど」
身構えながらも話を聞く姿勢になると、入江は背を向けたまま告げた。
「俺さ、好きだよ」
「え?」
「瀬尾のビートボックス」
ぱちぱちと瞬きをしてから、ようやく理解が追い付く。
あ、あー、ビートボックスか……。一瞬、告白されたかと思ってびっくりした。
無駄に暴れまわった心臓を押さえていると、入江は俯き加減で言葉を続ける。
「これを言ったら気を悪くするかもしれないけどさ、音楽室で瀬尾と合わせた日の晩、ビートボックスバトルの動画を観てみたんだ。だけど、なんというか……ちょっと怖いなって思ったんだ」
「怖い?」
「うん、音の暴力っていうのかな? 荒々しくて、喧嘩っぽくって、穏やかじゃないなって……」
まあ、確かに、ビートボックスバトルだと、雰囲気に圧倒されるのも分かる。音はパワフルだし、会場の熱気も凄い。
だけど、それを凌駕するほどの感動と情熱が~、なんて語りたくなったが、思いとどまった。まずは入江の話を聞こう。
「だけど、瀬尾の出す音は、優しいなって思ったんだ。こっちの音に寄り添って、支えてくれるような音に聞こえた」
優しい音なんて、初めて言われた。優しい音を出すのは入江であって、俺は別に……。
戸惑っていると、入江はくるりと振り返って、穏やかに微笑んだ。
「多分さ、瀬尾は一人でいるよりも、みんなの輪の中にいる方が向いていると思う。瀬尾の優しさに救われる人は、大勢いるはずだから」
さらりと飛んできた言葉は、凍えていたもう一人の自分をそっと包み込んだ。
俺は、もう誰も傷つけないように、誰とも深く繋がらないように心掛けてきた。だけど、本心は違う。
本当は、誰かと繋がっていたかったんだ。ひとりでも構わないと思い込んでいたけど、心の奥底では誰とも深く繋がれない日々を退屈に思っていた。
そんな俺の本音を、入江は見抜いていた。言葉ではなく、音楽を通して。
誰にも気付かれないようにしまっていた感情を、取り出されてしまったようだ。
きっと入江は、勇気を出して伝えてくれたに違いない。緊張しながら話を切り出していたのが、その証拠だ。
音楽を通して受け取った思いを、きちんと言葉にして返してくれた。その勇気に、俺は救われていた。
目頭が熱くなる。こんな所で、湿っぽい空気にする気はなかったのに勘弁してくれ。
込み上げてくる涙を遠ざけるように、俺は頭を揺らす。
「……優しいだけじゃ、ないから」
「ん?」
「かっこいい音も出せる」
まるで子供のような主張だなと呆れてしまったが、入江は「へえ」と興味を持ってくれた。
「ボイストランペットは、それなりにかっこよく吹けるようになった。聴きたい?」
「うん、聴きたい!」
入江は即答する。そう言ってくれると思った。
俺が前の席を指さすと、入江は壁に立てかけたギターを掴んで椅子に座った。
「入江だって一曲しか弾けてなくて不完全燃焼なんだろ? ここで演奏しよう。こっちのバンドの三曲と、あいつらのバンドの三曲。六曲連続で」
「向こうの曲は、瀬尾知らないじゃん。ロックだよ? テンポも速いよ?」
「見くびんなよ? 俺はどんな曲でも即興で合わせられる」
にっと笑いながら大口を叩くと、入江は目を細めてくすくすと笑いだした。
「やっぱり瀬尾は、かっこいいね」
顔を見合わせてひとしきり笑った後、入江はポロンと優しく弦を弾く。
「じゃあ、やろっか。二人だけの後夜祭」
「だなっ!」
カーテンの向こうからは、ロックバンドの激しい演奏が聞こえる。
その音に被せるように、俺はハイハットを三つ叩いてカウントを取った。
【fin】