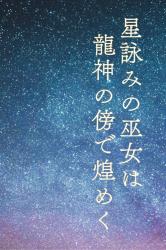夏休みが終わっても、すぐに秋が訪れるわけではない。
うんざりするほど聞いてきた蝉の声をBGMに、俺は外階段に座ってツナサンドを齧っていた。
冷房の効いた教室で昼飯を食べた方が快適だけど、今は一人になりたかった。推しのビートボクサーの生配信があるからだ。
しかも今日は、ずっと楽しみにしていた豪華なコラボ回。ビートボックス界の神とも言われているTAKATAさんとビートボックスバトルが行われる。
推しVS神。このバトルを見届けないわけにはいかないだろ。アーカイブでも見られるだろうけど、リアルタイムで視聴したかった。
配信まであと5分。期待で胸を弾ませながらその時を待っていると、階段下から複数人の足音が聞こえてきた。
俺の推し活を邪魔する奴は誰だ? 喧嘩なら余所でやってくれ。
残りのツナサンドを口に放り込んでから、手すりから身を乗り出して下を覗いた。
俺のいる外階段は、校舎裏に繋がっている。教室ではできない話をするのに、うってつけの場所だ。下にいる連中を見るに、あまり穏やかな雰囲気ではなさそうだ。
わらわらと校舎裏に集まって来たのは、四人の男子生徒。そのうち一人は、去年同じクラスだった黒田だ。やたらと声がデカイ奴で、入学式での自己紹介ではベースをやっていると得意げに話していた。他の面子も見覚えがあるから、みんな俺と同じ二年だろう。
みんな黒髪で、制服も校則通りに着こなしている。派手に喧嘩をするタイプには見えないが、三人の後を追うように歩いてきた色白で線の細い男子だけは浮かない顔をしている。
多分、これから彼にとって良くないことが起こるのだろう。
気になって様子を窺っていると、黒田がぼりぼりと頭をかきながら話を切り出す。
「あー、えっとさ、後夜祭の出し物のバンドだけど、ギターは入江じゃなくて、一組の清水を入れようと思ってるんだ。あいつ、ギター上手いし、歌も超上手いんだよ。だから、さ」
“だから”の先は明言しなかったが、続く言葉は外野の俺でも想像がついた。
要するに、現メンバーに代わって新メンバーを入れたいから、抜けろと言いたいのだろう。そして脱退を促されている入江は、あの浮かない顔をした男子だ。
入江も、黒田の言わんとしていることを察したようで、へらりと力なく笑う。
「そっか、なら仕方ないね。俺、歌はあんまり上手くないし」
随分物分かりのいい反応をするから驚いてしまった。こいつらとのバンドに未練はないのか?
入江の真意は分からないが、黒田をはじめとした三人は、ほっとしたように顔を見合わせていた。
「悪いな、入江」
「今度カラオケ奢るから、それで許して」
「時間があったらでいいから、俺らのライブも観に来てくれよな」
最後の一人がライブに誘うと、他の二人が「ブホォ」と噴き出す。そんな些細な言動だけでも、彼らの悪意が滲み出ていた。
多分、黒田たちは、入江のことを舐めているんだろう。だからあっさりと切り捨てたんだ。
用件が済むと、黒田たちはそそくさと校舎裏から去っていく。取り残された入江は、悲壮感を漂わせながら俯いていた。
なんだか、胸糞悪い現場を見てしまった。ライトノベルでありがちな追放シーンと似たような状況じゃないか。
もしここがライトノベルの世界なら、この後登場する三人くらい美少女とバンドを組んでハーレムライフが始まるんだろうけど、残念ながらうちの学校では起こりえない。男子校だからだ。
残念だったな、入江。
同情しながら彼のつむじを見つめていると、入江は空を見上げるように顔を上げた。
その瞬間、外階段にいた俺と目が合う。色素の薄い瞳には、涙の膜が張っていた。
やばっ、見つかった! しかも半泣きのところを目撃してしまった! これは向こうとしては結構痛いぞ……。
とはいえ、今更隠れるわけにもいかず。「あ、ども」なんて白々しい挨拶をするしかなかった。
入江は、シャツの袖で目元を拭うと、もう一度顔を上げる。
「ごめんね。変なところ見せちゃったね。忘れてー」
穏やかな口調。柔らかな笑み。その言動だけで、彼の温厚な性格が伝わってきた。
学校生活では、優しくて、穏やかな人が、貧乏くじを引きがちなことを知っている。彼もそういうタイプなのだろう。
「いや、むしろ覗き見してごめん。わざとじゃなかったんだけど……」
その後に続く言葉が見つからずに口ごもっていると、入江は再び微笑んだ。
「暑くて汗かいてきちゃったから、そろそろ戻るね」
話を終わらせようとする入江。俺はすかさず階段に置いた未開封のコーヒー牛乳を拾い上げた。
「あのさ、これやるよ」
ぽーんとコーヒー牛乳を放り投げる。入江は「え、え」と驚きながらも、落下するコーヒー牛乳をキャッチした。
俺とコーヒー牛乳を交互に見つめる入江に、にっこりと笑いかける。
「甘いの飲んで、元気出して」
自販機で買った110円のコーヒー牛乳では、彼の心の傷は癒せない。これは、恥ずかしい現場を盗み見てしまった罪滅ぼしだ。
入江はコーヒー牛乳をじっと見つめている。次に顔を上げた時、夏空のような晴れやかな笑顔を浮かべていた。
「ありがとう!」
弾んだ声でお礼を言うと、入江は校舎裏から去っていった。
蝉の声が、やけに煩く聞こえる。俺はずるずるとしゃがみ込みながら、額に滲んだ汗を拭った。
「あ、配信……」
推しの生配信は、既に始まっている。だけど、あんな悲しい現場を見てしまった後では、ビートボックスバトルを楽しめそうになかった。
アーカイブで見よう。そう決めてから、俺は教室に戻った。
うんざりするほど聞いてきた蝉の声をBGMに、俺は外階段に座ってツナサンドを齧っていた。
冷房の効いた教室で昼飯を食べた方が快適だけど、今は一人になりたかった。推しのビートボクサーの生配信があるからだ。
しかも今日は、ずっと楽しみにしていた豪華なコラボ回。ビートボックス界の神とも言われているTAKATAさんとビートボックスバトルが行われる。
推しVS神。このバトルを見届けないわけにはいかないだろ。アーカイブでも見られるだろうけど、リアルタイムで視聴したかった。
配信まであと5分。期待で胸を弾ませながらその時を待っていると、階段下から複数人の足音が聞こえてきた。
俺の推し活を邪魔する奴は誰だ? 喧嘩なら余所でやってくれ。
残りのツナサンドを口に放り込んでから、手すりから身を乗り出して下を覗いた。
俺のいる外階段は、校舎裏に繋がっている。教室ではできない話をするのに、うってつけの場所だ。下にいる連中を見るに、あまり穏やかな雰囲気ではなさそうだ。
わらわらと校舎裏に集まって来たのは、四人の男子生徒。そのうち一人は、去年同じクラスだった黒田だ。やたらと声がデカイ奴で、入学式での自己紹介ではベースをやっていると得意げに話していた。他の面子も見覚えがあるから、みんな俺と同じ二年だろう。
みんな黒髪で、制服も校則通りに着こなしている。派手に喧嘩をするタイプには見えないが、三人の後を追うように歩いてきた色白で線の細い男子だけは浮かない顔をしている。
多分、これから彼にとって良くないことが起こるのだろう。
気になって様子を窺っていると、黒田がぼりぼりと頭をかきながら話を切り出す。
「あー、えっとさ、後夜祭の出し物のバンドだけど、ギターは入江じゃなくて、一組の清水を入れようと思ってるんだ。あいつ、ギター上手いし、歌も超上手いんだよ。だから、さ」
“だから”の先は明言しなかったが、続く言葉は外野の俺でも想像がついた。
要するに、現メンバーに代わって新メンバーを入れたいから、抜けろと言いたいのだろう。そして脱退を促されている入江は、あの浮かない顔をした男子だ。
入江も、黒田の言わんとしていることを察したようで、へらりと力なく笑う。
「そっか、なら仕方ないね。俺、歌はあんまり上手くないし」
随分物分かりのいい反応をするから驚いてしまった。こいつらとのバンドに未練はないのか?
入江の真意は分からないが、黒田をはじめとした三人は、ほっとしたように顔を見合わせていた。
「悪いな、入江」
「今度カラオケ奢るから、それで許して」
「時間があったらでいいから、俺らのライブも観に来てくれよな」
最後の一人がライブに誘うと、他の二人が「ブホォ」と噴き出す。そんな些細な言動だけでも、彼らの悪意が滲み出ていた。
多分、黒田たちは、入江のことを舐めているんだろう。だからあっさりと切り捨てたんだ。
用件が済むと、黒田たちはそそくさと校舎裏から去っていく。取り残された入江は、悲壮感を漂わせながら俯いていた。
なんだか、胸糞悪い現場を見てしまった。ライトノベルでありがちな追放シーンと似たような状況じゃないか。
もしここがライトノベルの世界なら、この後登場する三人くらい美少女とバンドを組んでハーレムライフが始まるんだろうけど、残念ながらうちの学校では起こりえない。男子校だからだ。
残念だったな、入江。
同情しながら彼のつむじを見つめていると、入江は空を見上げるように顔を上げた。
その瞬間、外階段にいた俺と目が合う。色素の薄い瞳には、涙の膜が張っていた。
やばっ、見つかった! しかも半泣きのところを目撃してしまった! これは向こうとしては結構痛いぞ……。
とはいえ、今更隠れるわけにもいかず。「あ、ども」なんて白々しい挨拶をするしかなかった。
入江は、シャツの袖で目元を拭うと、もう一度顔を上げる。
「ごめんね。変なところ見せちゃったね。忘れてー」
穏やかな口調。柔らかな笑み。その言動だけで、彼の温厚な性格が伝わってきた。
学校生活では、優しくて、穏やかな人が、貧乏くじを引きがちなことを知っている。彼もそういうタイプなのだろう。
「いや、むしろ覗き見してごめん。わざとじゃなかったんだけど……」
その後に続く言葉が見つからずに口ごもっていると、入江は再び微笑んだ。
「暑くて汗かいてきちゃったから、そろそろ戻るね」
話を終わらせようとする入江。俺はすかさず階段に置いた未開封のコーヒー牛乳を拾い上げた。
「あのさ、これやるよ」
ぽーんとコーヒー牛乳を放り投げる。入江は「え、え」と驚きながらも、落下するコーヒー牛乳をキャッチした。
俺とコーヒー牛乳を交互に見つめる入江に、にっこりと笑いかける。
「甘いの飲んで、元気出して」
自販機で買った110円のコーヒー牛乳では、彼の心の傷は癒せない。これは、恥ずかしい現場を盗み見てしまった罪滅ぼしだ。
入江はコーヒー牛乳をじっと見つめている。次に顔を上げた時、夏空のような晴れやかな笑顔を浮かべていた。
「ありがとう!」
弾んだ声でお礼を言うと、入江は校舎裏から去っていった。
蝉の声が、やけに煩く聞こえる。俺はずるずるとしゃがみ込みながら、額に滲んだ汗を拭った。
「あ、配信……」
推しの生配信は、既に始まっている。だけど、あんな悲しい現場を見てしまった後では、ビートボックスバトルを楽しめそうになかった。
アーカイブで見よう。そう決めてから、俺は教室に戻った。