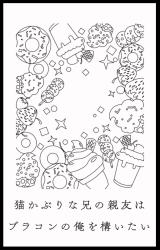家に入ると、縁はすぐに俺を自分の部屋へと連れて行ってくれた。
以前の部屋は、子供部屋の延長線のようなカラフルな内装。けれど、この数ヶ月来ないだけで全く違う雰囲気に変わっていた。
勉強机は小学生から使っていた学習机からシンプルな黒い机に変わっていたし、椅子はゲーミングチェア。本棚も黒のラックになり、カーテンもベッドのシーツもダークグレーに。
なぜか、黙っている時の縁に似ていると思った。やけに大人っぽい。
「縁の部屋……前と違うね」
そう言った瞬間、縁がくるっと振り返って「当真」と呼んだ。
俺をまっすぐ見つめるその目は、何というか、いつにも増して色気があって、吸い込まれてしまいそうだ。
本当に後輩なんだっけ? って疑いたくなるくらい、縁は大人っぽい。
「俺のこと……好き?」
縁が俺に一歩近づいてきて、頰に触れてくる。俺の顔を覗き込むように少しだけ背を丸めてくるものだから、顔の距離が近くなった。
「好きって……さっきも言ったよ?」
「でも、もっかい聞きたい。だめ? 俺、年下なんだぞ? 甘えさせてくれよ」
「こういう時は後輩なんだ?」
「悪いかよ。こんな俺は嫌いか?」
「……好き。だけど……縁……あの、ちょっとね、顔、近すぎると思うんだよね」
そう言ったら、縁は口元を緩めた。
「ははっ。当真が好きでたまんねぇんだよ。いつも、我慢してたんだ。当真も俺のこと好きなら、許してくれ」
縁はそう言って、俺の頰に軽くキスをしてきた。
たったそれだけなのに、俺の顔は一瞬にして熱を帯びる。
でも、俺はひとつ、やり残したことがあることに気づいて、「縁、あのね」と口を開いた。
「俺……縁のこと、凄く……好きだよ。だけど、今から、傷つけること言う」
「ん? なんだ?」
「あ……あの、俺……いつから縁と恋人なのか、知らないんだ」
縁を傷つけることが怖くて、ぎゅっと目を瞑ってしまった。
だけど、俺の心配ごとはどうやら、縁にとっては痛くも痒くもなかったらしい。
「あははっ」
縁の笑い声がして、俺は瞼をあげた。
「当真。悪い。しらねぇの、当たり前」
「当たり前……?」
「俺が中三の時、当真が俺の勉強見てくれてたろ? あの時に『俺が当真と同じ高校に行けたら、俺と付き合って』って言ったんだよ」
「……俺、それ知らない」
「そりゃそうだろ。当真は寝ぼけてたし。もうほぼ寝ながら『うん』って返事してさ」
縁はくくっと笑う。
「え……っと。じゃあ、ほんとは……付き合ってないの?」
「ん? いや。約束には違いねぇし。俺は高校入学と同時に当真と付き合ったということにして、形から落とすことにした。当真、流されやすいし。自分から付き合ってないとか言いださねぇだろ? なら、思う存分溺愛して、俺ナシで生きられないようにしてやろーって」
縁は悪びれもなくそう言うものだから、俺は開いたくちが塞がらなかった。
でも、それを聞いても怒ろうとは思えないのは、目の前にいる縁が愛おしくて。可愛く見えるからだ。
「……とんでもない彼氏に捕まっちゃったね」
笑みをこぼしたら、縁がまた俺の頰を撫でた。
「なぁ、当真」
「……ん?」
「もう、いいよな? キスしても。両思いだし」
縁は俺の返事を聞く間もなく、俺の顎をくいっと上向かせる。そうかと思えば、唇に柔らかいものが当たった。
ちゅっ、ちゅっと軽いキスが繰り返されるたびに、心臓は大騒ぎだ。頭の中まで、ドクドクとうるさくたまらない。
ややあって、終わったと思ったら、縁はまだ足りなかったようだ。
「当真。もっと欲しい」
縁の甘い声に、俺の頭はくらくらしてしまう。
「ほら。ちょっとだけ口、開けて」
「くち……?」
なんて言って少し唇を開いたら、縁の舌が俺の口に侵入してしまった。
唇が触れただけでも、頭はぼんやりした。それなのに、舌が絡みとられるなんて、呼吸もままならない。
息継ぎなんてどうしたらいいか分からなくて、もう死んでしまうかと思った。
しばらくして、ようやく縁の唇が俺から離れた。
はぁはぁと荒い呼吸を繰り返す自分が、すごくいやらしい存在になったように思えて、今だけは縁に見られたくなる。
でも、縁は俺の顎を押さえて、顔を逸らさせてはくれない。
「当真。かわいい。……すげぇ、かわいい」
そう言いながら、軽く俺の唇をまた奪ってしまった。
やっぱり、縁は色気が凄い。
艶のある目で見てくるものだから、もう本当に心臓に悪い。
見つめられるだけで、心臓も何もかも自分のものじゃなくなってしまうようだった。
「かわいいは……嬉しくないよ」
「ははっ。じゃあ、すげぇきれい。ほんと、綺麗だよ。世界でいちばん」
縁は吐息がかかる距離でそう言って、再び俺にキスをしてくれた。そして、愛おしそうに俺の頬を撫でてから、首筋にキスを落としてくる。一回、二回、三回と首筋に唇を這わせた。
そんな風に俺に触れながら、縁の手が俺の腹に伸ばされた。ピクッと体が反応してしまって、俺は縁の頭に手を伸ばす。
(縁……俺にいつも顔が良いっていうけど、縁だって、顔も色気もすごすぎるよ)
俺はもう限界に達していた。
「縁……俺、初めてだから。もう、これ以上は無理」
「俺だって初めてだし。……てか、何? 当真は俺が他のやつと遊んでるとでも思って──って、当真! 鼻血出てきてんじゃねぇか!」
縁が俺を見上げて、目を見開いた。
「え……?」
なんか生温いものが鼻の奥に感じるなと思ったら、鼻血が出ているとは。
鼻に触れてみると、手にべっとりと赤い血がついていた。
***
やっぱり、俺の幼なじみは過保護だ。
ただちょっと鼻血が出ただけなのに、縁は顔面蒼白になってしまうし、手厚い看病をされてしまった。
鼻血が止まった今だって、縁は俺を横抱きにして膝の上に乗せてくれている。ちなみに、縁の手には練習中だという、たまごサンドがある。
「ほら、当真、あーんしろよ」
「……恥ずかしい」
「これまで散々、俺に食べさせられてるくせに、今更すぎるだろ」
ほぼ毎日のように縁に餌付けされてるのを思い出して、俺はおずおずと口を開ける。
縁は「よしよし」と言って、俺の口の中に手作りたまごサンドを運んでくれた。
ぱくりと口に入れて、俺は目を見開く。
(なに……これ! すごく美味しすぎる……!)
購買のたまごサンドがこれまでの俺のトップに君臨していたのだけど、縁のはそれを凌駕するくらい、美味しくてたまらなかった。
ちょうどいい塩梅のからしマヨネーズに、黒胡椒。さらにここに、俺の好きな刻みピクルス。たまごペーストが格段にランクアップしていた。
もぐもぐと咀嚼して、ごくっと飲み込んだ俺は思わず縁の頰にキスをしていた。
「縁最高! これ! これ! すっごい美味しい……! 今まで食べたやつで一番好き!」
「そりゃ、当真の好みを熟知した俺が改良に改良を重ねたやつだからな。ご褒美にいくらでも作ってやるよ」
「ほんと? 嬉しい!」
こうして俺の彼氏は、がっつり俺の胃袋まで掴んでしまったのだった。
***
縁と初めてキスした日から、一週間と少しが過ぎた。
昼休みに縁の教室に向かおうとしたら、一人の女子生徒に「有馬先輩、あの──」と、呼び止められてしまった。
その手には、購買のたまごサンド。
でも、俺はもうそれには釣られない。
「ごめんね。もう俺、そういうのはやめたんだ」
そう言うと、彼女は「あ……そうですか」と少し残念そうに言った。でも、そのあとすぐに「すみませんでしたぁぁぁぁっ!」と、急に大声を出して、その場から立ち去っていく。
なんでかいきなり逃げ出したものだから、俺は驚いて瞬きを繰り返した。
(あれ? なんか、今の子、ほんの少し怯えた顔を一瞬だけしたような? 俺、そんなに怖い顔してたかな)
頬っぺたをむにむにと触りながら、俺は小首を傾げる。すると、俺の目の前にたまごサンドがぬっと現れた。
背後から手が伸びていて、俺は「縁だ」と後ろを振り向く。
縁は満足そうな顔をしながら「当真はもう、俺特製の当真専用たまごサンドしか食べねぇもんな?」と、言ってきた。
「見てたんだ?」
「俺の彼氏がちゃーんと断れるかなぁって気になって」
「縁のご褒美があるし、縁を悲しませたくないからもうしないよ」
「わかってるならよろしい」
縁は俺の頭をくしゃくしゃと撫でてくれる。
「早くそれ食べたい」
「わかったよ。じゃ、行くか」
縁はそう言いながら、俺の手を握る。
俺にはもう、俺専用特製たまごサンドに代わる味なんて、どこにもない。
大好きな彼氏のご褒美が、一番なのだから。
以前の部屋は、子供部屋の延長線のようなカラフルな内装。けれど、この数ヶ月来ないだけで全く違う雰囲気に変わっていた。
勉強机は小学生から使っていた学習机からシンプルな黒い机に変わっていたし、椅子はゲーミングチェア。本棚も黒のラックになり、カーテンもベッドのシーツもダークグレーに。
なぜか、黙っている時の縁に似ていると思った。やけに大人っぽい。
「縁の部屋……前と違うね」
そう言った瞬間、縁がくるっと振り返って「当真」と呼んだ。
俺をまっすぐ見つめるその目は、何というか、いつにも増して色気があって、吸い込まれてしまいそうだ。
本当に後輩なんだっけ? って疑いたくなるくらい、縁は大人っぽい。
「俺のこと……好き?」
縁が俺に一歩近づいてきて、頰に触れてくる。俺の顔を覗き込むように少しだけ背を丸めてくるものだから、顔の距離が近くなった。
「好きって……さっきも言ったよ?」
「でも、もっかい聞きたい。だめ? 俺、年下なんだぞ? 甘えさせてくれよ」
「こういう時は後輩なんだ?」
「悪いかよ。こんな俺は嫌いか?」
「……好き。だけど……縁……あの、ちょっとね、顔、近すぎると思うんだよね」
そう言ったら、縁は口元を緩めた。
「ははっ。当真が好きでたまんねぇんだよ。いつも、我慢してたんだ。当真も俺のこと好きなら、許してくれ」
縁はそう言って、俺の頰に軽くキスをしてきた。
たったそれだけなのに、俺の顔は一瞬にして熱を帯びる。
でも、俺はひとつ、やり残したことがあることに気づいて、「縁、あのね」と口を開いた。
「俺……縁のこと、凄く……好きだよ。だけど、今から、傷つけること言う」
「ん? なんだ?」
「あ……あの、俺……いつから縁と恋人なのか、知らないんだ」
縁を傷つけることが怖くて、ぎゅっと目を瞑ってしまった。
だけど、俺の心配ごとはどうやら、縁にとっては痛くも痒くもなかったらしい。
「あははっ」
縁の笑い声がして、俺は瞼をあげた。
「当真。悪い。しらねぇの、当たり前」
「当たり前……?」
「俺が中三の時、当真が俺の勉強見てくれてたろ? あの時に『俺が当真と同じ高校に行けたら、俺と付き合って』って言ったんだよ」
「……俺、それ知らない」
「そりゃそうだろ。当真は寝ぼけてたし。もうほぼ寝ながら『うん』って返事してさ」
縁はくくっと笑う。
「え……っと。じゃあ、ほんとは……付き合ってないの?」
「ん? いや。約束には違いねぇし。俺は高校入学と同時に当真と付き合ったということにして、形から落とすことにした。当真、流されやすいし。自分から付き合ってないとか言いださねぇだろ? なら、思う存分溺愛して、俺ナシで生きられないようにしてやろーって」
縁は悪びれもなくそう言うものだから、俺は開いたくちが塞がらなかった。
でも、それを聞いても怒ろうとは思えないのは、目の前にいる縁が愛おしくて。可愛く見えるからだ。
「……とんでもない彼氏に捕まっちゃったね」
笑みをこぼしたら、縁がまた俺の頰を撫でた。
「なぁ、当真」
「……ん?」
「もう、いいよな? キスしても。両思いだし」
縁は俺の返事を聞く間もなく、俺の顎をくいっと上向かせる。そうかと思えば、唇に柔らかいものが当たった。
ちゅっ、ちゅっと軽いキスが繰り返されるたびに、心臓は大騒ぎだ。頭の中まで、ドクドクとうるさくたまらない。
ややあって、終わったと思ったら、縁はまだ足りなかったようだ。
「当真。もっと欲しい」
縁の甘い声に、俺の頭はくらくらしてしまう。
「ほら。ちょっとだけ口、開けて」
「くち……?」
なんて言って少し唇を開いたら、縁の舌が俺の口に侵入してしまった。
唇が触れただけでも、頭はぼんやりした。それなのに、舌が絡みとられるなんて、呼吸もままならない。
息継ぎなんてどうしたらいいか分からなくて、もう死んでしまうかと思った。
しばらくして、ようやく縁の唇が俺から離れた。
はぁはぁと荒い呼吸を繰り返す自分が、すごくいやらしい存在になったように思えて、今だけは縁に見られたくなる。
でも、縁は俺の顎を押さえて、顔を逸らさせてはくれない。
「当真。かわいい。……すげぇ、かわいい」
そう言いながら、軽く俺の唇をまた奪ってしまった。
やっぱり、縁は色気が凄い。
艶のある目で見てくるものだから、もう本当に心臓に悪い。
見つめられるだけで、心臓も何もかも自分のものじゃなくなってしまうようだった。
「かわいいは……嬉しくないよ」
「ははっ。じゃあ、すげぇきれい。ほんと、綺麗だよ。世界でいちばん」
縁は吐息がかかる距離でそう言って、再び俺にキスをしてくれた。そして、愛おしそうに俺の頬を撫でてから、首筋にキスを落としてくる。一回、二回、三回と首筋に唇を這わせた。
そんな風に俺に触れながら、縁の手が俺の腹に伸ばされた。ピクッと体が反応してしまって、俺は縁の頭に手を伸ばす。
(縁……俺にいつも顔が良いっていうけど、縁だって、顔も色気もすごすぎるよ)
俺はもう限界に達していた。
「縁……俺、初めてだから。もう、これ以上は無理」
「俺だって初めてだし。……てか、何? 当真は俺が他のやつと遊んでるとでも思って──って、当真! 鼻血出てきてんじゃねぇか!」
縁が俺を見上げて、目を見開いた。
「え……?」
なんか生温いものが鼻の奥に感じるなと思ったら、鼻血が出ているとは。
鼻に触れてみると、手にべっとりと赤い血がついていた。
***
やっぱり、俺の幼なじみは過保護だ。
ただちょっと鼻血が出ただけなのに、縁は顔面蒼白になってしまうし、手厚い看病をされてしまった。
鼻血が止まった今だって、縁は俺を横抱きにして膝の上に乗せてくれている。ちなみに、縁の手には練習中だという、たまごサンドがある。
「ほら、当真、あーんしろよ」
「……恥ずかしい」
「これまで散々、俺に食べさせられてるくせに、今更すぎるだろ」
ほぼ毎日のように縁に餌付けされてるのを思い出して、俺はおずおずと口を開ける。
縁は「よしよし」と言って、俺の口の中に手作りたまごサンドを運んでくれた。
ぱくりと口に入れて、俺は目を見開く。
(なに……これ! すごく美味しすぎる……!)
購買のたまごサンドがこれまでの俺のトップに君臨していたのだけど、縁のはそれを凌駕するくらい、美味しくてたまらなかった。
ちょうどいい塩梅のからしマヨネーズに、黒胡椒。さらにここに、俺の好きな刻みピクルス。たまごペーストが格段にランクアップしていた。
もぐもぐと咀嚼して、ごくっと飲み込んだ俺は思わず縁の頰にキスをしていた。
「縁最高! これ! これ! すっごい美味しい……! 今まで食べたやつで一番好き!」
「そりゃ、当真の好みを熟知した俺が改良に改良を重ねたやつだからな。ご褒美にいくらでも作ってやるよ」
「ほんと? 嬉しい!」
こうして俺の彼氏は、がっつり俺の胃袋まで掴んでしまったのだった。
***
縁と初めてキスした日から、一週間と少しが過ぎた。
昼休みに縁の教室に向かおうとしたら、一人の女子生徒に「有馬先輩、あの──」と、呼び止められてしまった。
その手には、購買のたまごサンド。
でも、俺はもうそれには釣られない。
「ごめんね。もう俺、そういうのはやめたんだ」
そう言うと、彼女は「あ……そうですか」と少し残念そうに言った。でも、そのあとすぐに「すみませんでしたぁぁぁぁっ!」と、急に大声を出して、その場から立ち去っていく。
なんでかいきなり逃げ出したものだから、俺は驚いて瞬きを繰り返した。
(あれ? なんか、今の子、ほんの少し怯えた顔を一瞬だけしたような? 俺、そんなに怖い顔してたかな)
頬っぺたをむにむにと触りながら、俺は小首を傾げる。すると、俺の目の前にたまごサンドがぬっと現れた。
背後から手が伸びていて、俺は「縁だ」と後ろを振り向く。
縁は満足そうな顔をしながら「当真はもう、俺特製の当真専用たまごサンドしか食べねぇもんな?」と、言ってきた。
「見てたんだ?」
「俺の彼氏がちゃーんと断れるかなぁって気になって」
「縁のご褒美があるし、縁を悲しませたくないからもうしないよ」
「わかってるならよろしい」
縁は俺の頭をくしゃくしゃと撫でてくれる。
「早くそれ食べたい」
「わかったよ。じゃ、行くか」
縁はそう言いながら、俺の手を握る。
俺にはもう、俺専用特製たまごサンドに代わる味なんて、どこにもない。
大好きな彼氏のご褒美が、一番なのだから。