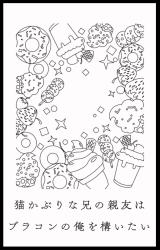週末、作戦決行日。俺は秋吉先輩と一緒に、縁と小松先輩を少し離れた場所から見守ることになった。
場所は、俺たちの高校からほど近い、公園だ。この日はちょうど雨が止んでいたけれど、広々とした園内の東屋に縁と小松先輩はいた。
ベンチに座って待つ小松先輩と、その横に立つ縁。一言も喋る気配はない。
二人の顔が見える木陰から見守っていたのだけど、縁がちゃんと恋人みたいに振る舞えるのか、心配だった。
しばらくして、小松先輩の元カレらしき人がやって来た。
小松先輩の横にいる縁を見て、露骨に嫌そうな顔をするのが分かる。
でも、縁はその場に立っているだけだった。
というのも、縁は黙っているだけで、すごく怖く見えるからだ。いや、女子と話す時は攻撃性が増すから、それはそれで怖いんだけども。黙っていると、強面の美形彼氏っていうコンセプトでいくらしい。
ただ、役だと分かっているのに、小松先輩が縁の腕に手を絡めたのは、いただけない。なんか、それを見てすごくもやっとした。
なんでこうなっているのか。胃のあたりがぎゅってするし、見てるだけで歯軋りしたくなる感覚だ。
そんな感覚に俺が苛まれている時だった。
小松先輩が何かを口にしたように見えた瞬間、その元カレは、縁の胸ぐらを掴んだのが俺の目に映った。
その時、俺は学校の屋上で、宮田に胸元を掴まれて殴られそうになった自分のことを鮮明に思い出した。
自然と胸を押さえていて、心臓がじりじりと痛みを放ち始める。
別に、あの日の出来事がトラウマになったわけじゃない。自分が殴られるのは嫌だけど、あの時の俺は殴られても仕方がないことをしたから。
でも、俺は今、目頭が物凄く熱くて、涙がこぼれ落ちそうだった。
お願いだから、縁にそんなことしないで。やめて。縁を殴ろうとしないで。縁が何をしたって言うんだよ。
縁が殴られるって思ったら、縁が雑に扱われているのを見たら、体の内側からズタズタに引き裂かれていくかのような感覚に陥っていく。
でも、それ以上に苦しい原因があることに、俺はようやく気づいた。
俺が見ている今の縁は、抵抗するそぶりも何も見せずに、殴られてもいいとでも言いたげな顔をしているのだ。
殴られそうになっているのは、もちろん苦しいし、今にも飛びかかって助けたくなる。けど、縁が「自分を大事にしろ」って言うのに、今の縁こそ自分を大事にしているように思えないことが、余計に苦しさを助長しているような気がした。
誰よりも、大事だと思える人が、自分をおざなりにする姿を見ることが、これほど辛いなんて思わなくて。胸が痛くて、たまらなかった。
「……有馬くん、泣いてる?」
隣にいた秋吉先輩が声をかけて来て、俺は慌てて目尻に浮かんだ涙を手の甲で拭った。
「俺……ずっと、縁にこんな思いさせてたんですかね?」
「え?」
「俺、縁が……痛い思いするの、嫌なんです。誰かに傷つけられてしまうかもって思ったら、怖い。それなのに……縁には、同じことを平気でさせてた。俺、ずっと、自分を大事にできてなかった。縁はずっと、この気持ちを味わってたんだって思ったら……苦しい」
ぽろぽろと涙がこぼれ落ちてくる。
「久世くんも有馬くんも、お互いのことが凄く大切なんだね」
秋吉先輩の言葉に、俺はこくりと頷く。
「でも、たぶん大丈夫だと思うよ。きっと久世くんなら、痛い思いはしないと思う。見てよ、あの体格差」
秋吉先輩はふふっと笑って、指差す。
言われてみれば、縁は平均身長をはるかに超えている。対して相手は、俺よりももしかしたら少し小さいかもしれない。胸ぐらを掴んではいるけれど、圧倒的に縁の方が強そうだった。
しかも、縁は面倒くさそうに、耳をほじり始める。それはまるで、相手をあえて挑発しているようにも見えた。
次の瞬間、縁の顔に男の握り拳が飛んでいく。
先輩は大丈夫って言ったけど、俺は「縁っ!」と呼んで、立ち上がっていた。
だけど、縁は俺の心配なんてよそに、その手を捻りあげるように捕まえた。挙句、もう片方の手で、小松先輩の元カレの腹を殴ってしまっていた。
(あ……痛そう)
相手は一発KOだった。その場にうずくまるのが見えた。
そこまでしなくても……なんて思う俺は、甘いのかな。
俺が見ていることはわかっているはずなのに、縁は容赦なく男の首根っこを押さえた。さらには地面に顔を近づけるように押し倒して、その背に乗っかる。その姿は小学生の頃にいじめっ子たちを返り討ちしていた時の、悪魔のような縁と重なって見えた。
そして、小松先輩が男の前に紙を突き出した。
作戦会議で、「今後一切接触しないこと」「違反時は法的措置を取ること」と、念書を書かせるって言っていた。きっと、その紙だろう。
縁が男の背から降りると、地べたに這いつくばりながら紙を受け取った。男は慌てたように何かを書いていく。
縁たちが男に何を言っているかは、分からない。けれど、縁は男を脅しているのか。相手の男が明らかに縁を恐れているように思えた。
「じゃあ、二人のところに行こっか」
ややあって、小松先輩の元カレが立ち去ってから、秋吉先輩に声をかけられた。「そうですね」と返事して、縁と小松先輩のもとに向かう。
でも、二人の近くに来た時、なんだか最初の二人の様子とは少し違うように思えた。小松先輩が縁を見る目が、表情が、縁が俺を見るときのようなそんなものに見える。
(縁は、かっこいい……。それはわかってるけど……なんか、嫌だな。縁は俺の彼氏なのに)
なんとも言えない、もやもやとした感情が、また腹の中に渦巻く。その感覚に戸惑いながら、俺はその辺りのシャツをギュッと握った。
思わず、俯いたその時、縁が「当真?」と俺を呼んでくれた。俺を気にかけるように、頬を触ってくれる。
「どうした、当真。何かあったか?」
縁の指先が優しく頰を触れる度に、俺の瞳から涙がぽろぽろとこぼれ落ちる。次いで、自然と言葉が飛び出していた。
「縁は……俺の。俺のだよ。俺の彼氏」
「ははっ。どうした? そうだよ、俺は当真のだよ。なに、やっと実感したのかよ?」
縁は俺の目尻を指で拭いながら、顔を覗き込んでくる。
先輩たちの前で何してるんだろうって思うけど、今口にした言葉で、はっきりと分かった。
俺は縁が好きで、縁を誰にもとられたくない。誰の目にも触れさせたくないくらい、好きなんだって。
縁を傷つけたくないのも、全部縁が大好きだからなんだって。
「俺以外が縁に触れるのも、縁が他の誰かに見られるのもイヤだよ。縁が他の人のために危険な目に遭うのも、イヤ。縁が……言ってたこと、ようやくわかった。心臓が痛いよ。俺……縁が大好きみたい」
「当真……それ、ほんと?」
「え?」
「もう一回、言って。俺のことどう思ってるか」
「好き。……縁が好きだよ?」
「やった! やっと当真が俺のこと、本気で好きって言ってくれた!」
縁は俺の身体をひょいと持ち上げてしまう。
「えっ? えぇっ……?」
俺はこれまで、縁に何度も好きだよって言っていたはずだ。なのに、これまで以上に物凄く喜ばれてしまって、妙な違和感を覚えた。
でも、テンションの上がった縁は、もう誰も止められない。
そのまま担がれてしまって、縁はくるっと秋吉先輩と小松先輩の方を見た。
秋吉先輩が「そのまま担いで帰るのはさすがに……」と言ったけれど、縁は「いつも当真、担いでるから平気です」とさらっと暴露してしまって恥ずかしい。
俺がソファで寝落ちしたときとか、外で足くじいたときとか、縁はしょっちゅう俺をこうして担ぐ。もう俺は慣れているので、何も言わなかった。
(恥ずかしいけど……むしろ、縁にこうされるの、好きだったりする)
「じゃ、失礼します」
縁は颯爽と駆けだす。
遠くから秋吉先輩が「お幸せにー!」と言う声がする。
縁に担がれたまま、二人の方を見たら、小松先輩も手を振ってくれていた。
***
先輩たちと別れた後、マンションから近いとはいえ、このまま帰るのは憚られた。
途中で「下ろして」と言ったら、縁もさすがに近所の人に見られたら駄目だと思ったんだろう。マンションが見え始めたところで、俺を地面に降ろしてくれた。
ただ、俺たちはそのあとすぐに手を握った。何度も、互いの温もりを確かめるように、握り返しながら。
でも、そんなことをしながらも、俺たちは随分、緊張していた。
少し前を歩く縁の耳は、物凄く赤い。
いつもの道のりなのに、俺の心臓の音もうるさくて仕方がなかった。
そして、マンションのエレベーターの中にいる今。二人きりで乗るなんて毎日しているのに、縁の顔を見ることができない。
でも、しょうがないと思う。
だって、俺はこれが初恋だ。
エレベーターが最上階に着いて、チンと鳴る音ですら、ぴくっと身体が反応してしまうくらい緊張していた。
「当真。今日は俺の家に来る? 今日、父さんも母さんもいないんだけど」
縁の声も、少し緊張しているようだった。
そんな縁は、ほぼ毎日のように俺の家に来る。だけど、俺はたぶん、縁の家に行くのは数ヶ月ぶりだ。
最後に行ったのは、縁の受験前日。勉強を見てあげていたとき以来。
今の縁と部屋に入ったら、どうなるのかは分からない。
でも、俺はもう縁が好きだ。
胸を張って、縁が好きだって言える。だから。
「縁の部屋……久々だね」
呟くような小さな声だったけど、縁の耳にはちゃんと届いたみたいだ。
「じゃ、決まり」
縁は目元を緩めて、俺の手を引いた。
でも、そんな優しさとは裏腹に、家の鍵を開けた縁は、力強く俺を家の中へ引き入れた。
まるで、待ちきれないって言っているみたいで。もしかしたら俺は、選択を間違えたのかもしれないって、ちょっとだけ後悔した。
場所は、俺たちの高校からほど近い、公園だ。この日はちょうど雨が止んでいたけれど、広々とした園内の東屋に縁と小松先輩はいた。
ベンチに座って待つ小松先輩と、その横に立つ縁。一言も喋る気配はない。
二人の顔が見える木陰から見守っていたのだけど、縁がちゃんと恋人みたいに振る舞えるのか、心配だった。
しばらくして、小松先輩の元カレらしき人がやって来た。
小松先輩の横にいる縁を見て、露骨に嫌そうな顔をするのが分かる。
でも、縁はその場に立っているだけだった。
というのも、縁は黙っているだけで、すごく怖く見えるからだ。いや、女子と話す時は攻撃性が増すから、それはそれで怖いんだけども。黙っていると、強面の美形彼氏っていうコンセプトでいくらしい。
ただ、役だと分かっているのに、小松先輩が縁の腕に手を絡めたのは、いただけない。なんか、それを見てすごくもやっとした。
なんでこうなっているのか。胃のあたりがぎゅってするし、見てるだけで歯軋りしたくなる感覚だ。
そんな感覚に俺が苛まれている時だった。
小松先輩が何かを口にしたように見えた瞬間、その元カレは、縁の胸ぐらを掴んだのが俺の目に映った。
その時、俺は学校の屋上で、宮田に胸元を掴まれて殴られそうになった自分のことを鮮明に思い出した。
自然と胸を押さえていて、心臓がじりじりと痛みを放ち始める。
別に、あの日の出来事がトラウマになったわけじゃない。自分が殴られるのは嫌だけど、あの時の俺は殴られても仕方がないことをしたから。
でも、俺は今、目頭が物凄く熱くて、涙がこぼれ落ちそうだった。
お願いだから、縁にそんなことしないで。やめて。縁を殴ろうとしないで。縁が何をしたって言うんだよ。
縁が殴られるって思ったら、縁が雑に扱われているのを見たら、体の内側からズタズタに引き裂かれていくかのような感覚に陥っていく。
でも、それ以上に苦しい原因があることに、俺はようやく気づいた。
俺が見ている今の縁は、抵抗するそぶりも何も見せずに、殴られてもいいとでも言いたげな顔をしているのだ。
殴られそうになっているのは、もちろん苦しいし、今にも飛びかかって助けたくなる。けど、縁が「自分を大事にしろ」って言うのに、今の縁こそ自分を大事にしているように思えないことが、余計に苦しさを助長しているような気がした。
誰よりも、大事だと思える人が、自分をおざなりにする姿を見ることが、これほど辛いなんて思わなくて。胸が痛くて、たまらなかった。
「……有馬くん、泣いてる?」
隣にいた秋吉先輩が声をかけて来て、俺は慌てて目尻に浮かんだ涙を手の甲で拭った。
「俺……ずっと、縁にこんな思いさせてたんですかね?」
「え?」
「俺、縁が……痛い思いするの、嫌なんです。誰かに傷つけられてしまうかもって思ったら、怖い。それなのに……縁には、同じことを平気でさせてた。俺、ずっと、自分を大事にできてなかった。縁はずっと、この気持ちを味わってたんだって思ったら……苦しい」
ぽろぽろと涙がこぼれ落ちてくる。
「久世くんも有馬くんも、お互いのことが凄く大切なんだね」
秋吉先輩の言葉に、俺はこくりと頷く。
「でも、たぶん大丈夫だと思うよ。きっと久世くんなら、痛い思いはしないと思う。見てよ、あの体格差」
秋吉先輩はふふっと笑って、指差す。
言われてみれば、縁は平均身長をはるかに超えている。対して相手は、俺よりももしかしたら少し小さいかもしれない。胸ぐらを掴んではいるけれど、圧倒的に縁の方が強そうだった。
しかも、縁は面倒くさそうに、耳をほじり始める。それはまるで、相手をあえて挑発しているようにも見えた。
次の瞬間、縁の顔に男の握り拳が飛んでいく。
先輩は大丈夫って言ったけど、俺は「縁っ!」と呼んで、立ち上がっていた。
だけど、縁は俺の心配なんてよそに、その手を捻りあげるように捕まえた。挙句、もう片方の手で、小松先輩の元カレの腹を殴ってしまっていた。
(あ……痛そう)
相手は一発KOだった。その場にうずくまるのが見えた。
そこまでしなくても……なんて思う俺は、甘いのかな。
俺が見ていることはわかっているはずなのに、縁は容赦なく男の首根っこを押さえた。さらには地面に顔を近づけるように押し倒して、その背に乗っかる。その姿は小学生の頃にいじめっ子たちを返り討ちしていた時の、悪魔のような縁と重なって見えた。
そして、小松先輩が男の前に紙を突き出した。
作戦会議で、「今後一切接触しないこと」「違反時は法的措置を取ること」と、念書を書かせるって言っていた。きっと、その紙だろう。
縁が男の背から降りると、地べたに這いつくばりながら紙を受け取った。男は慌てたように何かを書いていく。
縁たちが男に何を言っているかは、分からない。けれど、縁は男を脅しているのか。相手の男が明らかに縁を恐れているように思えた。
「じゃあ、二人のところに行こっか」
ややあって、小松先輩の元カレが立ち去ってから、秋吉先輩に声をかけられた。「そうですね」と返事して、縁と小松先輩のもとに向かう。
でも、二人の近くに来た時、なんだか最初の二人の様子とは少し違うように思えた。小松先輩が縁を見る目が、表情が、縁が俺を見るときのようなそんなものに見える。
(縁は、かっこいい……。それはわかってるけど……なんか、嫌だな。縁は俺の彼氏なのに)
なんとも言えない、もやもやとした感情が、また腹の中に渦巻く。その感覚に戸惑いながら、俺はその辺りのシャツをギュッと握った。
思わず、俯いたその時、縁が「当真?」と俺を呼んでくれた。俺を気にかけるように、頬を触ってくれる。
「どうした、当真。何かあったか?」
縁の指先が優しく頰を触れる度に、俺の瞳から涙がぽろぽろとこぼれ落ちる。次いで、自然と言葉が飛び出していた。
「縁は……俺の。俺のだよ。俺の彼氏」
「ははっ。どうした? そうだよ、俺は当真のだよ。なに、やっと実感したのかよ?」
縁は俺の目尻を指で拭いながら、顔を覗き込んでくる。
先輩たちの前で何してるんだろうって思うけど、今口にした言葉で、はっきりと分かった。
俺は縁が好きで、縁を誰にもとられたくない。誰の目にも触れさせたくないくらい、好きなんだって。
縁を傷つけたくないのも、全部縁が大好きだからなんだって。
「俺以外が縁に触れるのも、縁が他の誰かに見られるのもイヤだよ。縁が他の人のために危険な目に遭うのも、イヤ。縁が……言ってたこと、ようやくわかった。心臓が痛いよ。俺……縁が大好きみたい」
「当真……それ、ほんと?」
「え?」
「もう一回、言って。俺のことどう思ってるか」
「好き。……縁が好きだよ?」
「やった! やっと当真が俺のこと、本気で好きって言ってくれた!」
縁は俺の身体をひょいと持ち上げてしまう。
「えっ? えぇっ……?」
俺はこれまで、縁に何度も好きだよって言っていたはずだ。なのに、これまで以上に物凄く喜ばれてしまって、妙な違和感を覚えた。
でも、テンションの上がった縁は、もう誰も止められない。
そのまま担がれてしまって、縁はくるっと秋吉先輩と小松先輩の方を見た。
秋吉先輩が「そのまま担いで帰るのはさすがに……」と言ったけれど、縁は「いつも当真、担いでるから平気です」とさらっと暴露してしまって恥ずかしい。
俺がソファで寝落ちしたときとか、外で足くじいたときとか、縁はしょっちゅう俺をこうして担ぐ。もう俺は慣れているので、何も言わなかった。
(恥ずかしいけど……むしろ、縁にこうされるの、好きだったりする)
「じゃ、失礼します」
縁は颯爽と駆けだす。
遠くから秋吉先輩が「お幸せにー!」と言う声がする。
縁に担がれたまま、二人の方を見たら、小松先輩も手を振ってくれていた。
***
先輩たちと別れた後、マンションから近いとはいえ、このまま帰るのは憚られた。
途中で「下ろして」と言ったら、縁もさすがに近所の人に見られたら駄目だと思ったんだろう。マンションが見え始めたところで、俺を地面に降ろしてくれた。
ただ、俺たちはそのあとすぐに手を握った。何度も、互いの温もりを確かめるように、握り返しながら。
でも、そんなことをしながらも、俺たちは随分、緊張していた。
少し前を歩く縁の耳は、物凄く赤い。
いつもの道のりなのに、俺の心臓の音もうるさくて仕方がなかった。
そして、マンションのエレベーターの中にいる今。二人きりで乗るなんて毎日しているのに、縁の顔を見ることができない。
でも、しょうがないと思う。
だって、俺はこれが初恋だ。
エレベーターが最上階に着いて、チンと鳴る音ですら、ぴくっと身体が反応してしまうくらい緊張していた。
「当真。今日は俺の家に来る? 今日、父さんも母さんもいないんだけど」
縁の声も、少し緊張しているようだった。
そんな縁は、ほぼ毎日のように俺の家に来る。だけど、俺はたぶん、縁の家に行くのは数ヶ月ぶりだ。
最後に行ったのは、縁の受験前日。勉強を見てあげていたとき以来。
今の縁と部屋に入ったら、どうなるのかは分からない。
でも、俺はもう縁が好きだ。
胸を張って、縁が好きだって言える。だから。
「縁の部屋……久々だね」
呟くような小さな声だったけど、縁の耳にはちゃんと届いたみたいだ。
「じゃ、決まり」
縁は目元を緩めて、俺の手を引いた。
でも、そんな優しさとは裏腹に、家の鍵を開けた縁は、力強く俺を家の中へ引き入れた。
まるで、待ちきれないって言っているみたいで。もしかしたら俺は、選択を間違えたのかもしれないって、ちょっとだけ後悔した。