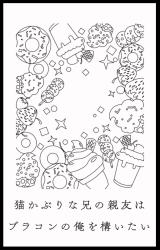屋上に続く扉の向こうから、雨音がしとしとと聞こえてくる。
中間テストが終わってから、早一ヶ月。制服も中間服から夏服に切り替わって、すっかりじめじめとした梅雨に突入していた。
「あー、うぜぇ。なんなんだよ、あの人ら」
階段の踊り場であぐらをかく縁は、不機嫌そうに紙パックのストローを口にくわえた。
あの人らというのは、たまごサンドの先輩二人組のことだ。
一ヶ月前のあの日以降、彼女たちは事あるごとにたまごサンドを持って、俺の前に現れるようになった。昼休みはもちろん、放課後は靴箱で待ち伏せされることもある。
ただ、たまごサンド好きなのに、俺は一度も彼女たちから、受け取ってはいない。
今、俺の手にあるたまごサンドは、縁がご褒美としてくれたものだ。
──当真。この人らからたまごサンドもらわねぇならさ、俺がご褒美にやるよ。
先輩たちの提案を断った翌日。再びやってきた彼女たちの前で、縁もまたまたたまごサンドをちらつかせながら、意地悪そうな笑みを浮かべて言った。
先輩たちからしたら、生意気な後輩なんだと思う。
でも、それからというものの、縁は俺の盾になってあの人たちを追い払ってくれているから、俺は先輩たちから全く受け取らずに済んでいる。
まぁ、縁の懐事情がすごく気になるところではあるんだけど。俺がたまごサンド受け取ると、ふにゃりと可愛く笑ってくれるし、「小遣いたんまりもらってっから気にすんな。いつも勉強教えてもらってるし、それでチャラ」って言われるから、縁からは素直に受け取ることにした。せっかく買ってきてくれるのに、食べないほうがもったいないし。
ただ、このところ、縁はずっとイライラもしている。今日も眉間のしわが随分と深い。
(俺のせいで縁が嫌な思いするの……それはなんか、嫌だなぁ)
たまごサンドを持つ手に、ついきゅっと力が入ってしまった。中身が飛び出して、ボトッと俺のズボンに落ちる。
「あっ、おい。当真! 何してんだよ、ほんともう。……今日も年上とは思えねぇ、ぼけっと具合だなぁ」
縁はポケットティッシュを制服のズボンから取り出して、すぐにたまごペーストを拭い取ってくれる。
俺の方が先輩なのに、何から何までダメダメすぎる。ほんと自分が、嫌になる。
「ごめん」
「いや、別に……謝る必要ねぇけど。……って、あー……もしかしてさ、俺のせい?」
「え?」
「当真ってさ、平和主義だろ。俺がイライラしてるの……嫌なんだろなって。ほら、昔、俺が近所のやつと喧嘩したときと……同じ顔、してんなって」
縁は購買のビニール袋に汚れたティッシュを入れながら、心配げに俺を見た。
「あー……えっと、まぁ。縁が俺のために怒ってくれてるのは、嬉しいよ。でも……うん。そうだね。俺のせいで、縁がイライラしちゃうのは、嫌だなぁって。それに……」
俺は少し気になることがあって、途中で口をつぐんだ。
先輩たちがなんであんなに必死になって頼み事をしに来るのか、それが不思議だった。
「俺の杞憂だったらいいんだけどさ……。当真さ、あの人らの話聞こうって思ってねぇ?」
縁には何でもお見通しみたいだ。
俺は目を伏せて「ちょっと……気になって」と口にした。
「そんなに気になるもん? 俺は当真が搾取されんのが、すげぇ嫌なんだけど。そのお人好しもどうかと思う」
「でも、もし本当に困ってたら? これまでみたいに、誰かにヤキモチ妬かせたいってだけなら、一か月も……普通なら、しないよね?」
「そうかもしんねぇけど……」
「深刻な何かがあって助けを求めてるとしたら、俺は放っておけないよ」
「あー、もう」
縁は呆れたように息を吐いて、後ろ頭をぐしゃぐしゃと掻いた。そして、あまり納得してはいないようだったけど「わかったよ」と言ってくれる。
「話聞いてみるだけなら、いい。でも、絶対に当真一人では行かせねぇし、当真が泣かされるようなことがあったら、相手が女でも先輩でも容赦しねぇよ」
縁は真剣な目で、俺の方をまっすぐ見てきた。
俺たちはこの一ヶ月、これといった進展はない。でも、俺の気持ちは少しずつだけど、変わってきている。
「縁が隣にいてくれるなら、怖くないよ」
「何かあったら抱えて逃げるからな? 子ども扱いするなって言っても、聞かねぇから」
「……ふふっ。お願い」
俺は過保護なこの恋人を愛おしく思いながら、残っていたたまごサンドを口に運んだ。
ふわふわのパンに、からしの効いたマヨネーズ。後から、ピリッと黒胡椒が香る、学校の購買に置くには少しパンチの効いたサンドイッチ。その味は、俺を守ろうとしてくれる縁の強さと、どこか似ている。
食べるたびになんだか安心するから、俺は自然と笑みをこぼしていた。
もしかしたら、高校に入学してすぐ、一人で心細かったから、この味を求めるようになったのかも──なんて思ったのは、縁には絶対に秘密だ。
***
翌日の昼休み、俺と縁は早速、先輩たちの話を聞くことにした。
ただ、周囲にはあまり聞かせたくない話らしい。彼女たちの指定で、人のいない空き教室で話をすることになった。
俺が少しだけ緊張しているのを、縁は感じとったのだろうか。教室まで迎えに来てくれた時からずっと、俺の肩を抱いてくれている。
三年生の校舎にある空き教室にショートヘアの秋吉先輩と、ロングヘアの小松先輩が先に入っていく。二人に続いて、俺たちも中に入った。
「で、話ってなんなんですか?」
教室に入るなり、縁はすぐに先輩たちに話を振った。
椅子に座ろうとしていた先輩たちは、背もたれに触れたところで、その手を止める。
「まずはちょっと、座ってからにしない?」
小松先輩は少しだけ困ったように肩をすくめて、座るよう促してきた。
縁は「長話になるのか」とボソッと呟く。仕方なさそうに先輩たちから少し離れた席の椅子を引いて、俺を見てきた。
「当真、ここに座れ」
「あ……うん」
俺は縁が引いてくれた椅子に座った。
すると、縁は隣の椅子を俺のすぐそばに置いて、俺を守る番犬みたいに腰を下ろす。
先に口を開いたのは、小松先輩だった。
「えっと……あの、頼みたいことなんだけど。実は……私の恋人のフリをしてほしくて」
まさかの言葉が飛び出して、すぐに縁が「はぁ?」と、低い声をあげた。
俺はさすがに女の子相手に喧嘩腰になる縁が心配になって、慌てて「駄目だよ」と肩をたたく。
ここ最近気づいたことだけど、縁はどうやら女子が苦手らしい。俺の友達や縁のクラスメイト、委員会が同じ先輩とか、男子に対する態度とは天と地の差がある。
人好きする性格だと思っていたのは俺だけだったみたいで、秋吉先輩も小松先輩も、顔を引き攣らせていた。
「だって、この先輩が意味わかんねぇこと言うからだろ。なんで当真がそんなことしなきゃなんねぇんだよ。意味わかんねぇ」
縁がそう言った瞬間、秋吉先輩が「あ、あのっ……」と声をかけてくる。
「有馬くんがだめなら……久世くんでもいいよ」
秋吉先輩は声を震わせながら、縁の方を見た。
「うわ。そういうのが、すげぇむかつく。当真を蔑ろにするやつ、マジでむ──」
「縁。お口チャック」
これ以上、縁が口を開けば何を言い出すか分からなくて、俺は人差し指を縁の唇に当てた。すると、縁は目をぱちくりさせて、黙ってくれた。
俺が先輩たちの方に向き直ると、小松先輩は「ごめんね」と言った。
「悪いとは思ってるの……でも、元カレに、ストーカーされてて」
声を震わせる小松先輩は、今にも消えてなくなりそうなくらい小さく見えた。
隣に座る秋吉先輩は、そんな小松先輩の手に自分の手を重ねて、俺たちの方を見る。
「この子の元カレ、大学生なんだけど……もう束縛が凄くて、別れたんだよね。でも……別れたはずなのに、ずっと付き纏ってて」
「それで、なんで俺や当真が彼氏のフリしなきゃなねーんすか? ストーカーなら、警察の仕事でしょ」
縁は冷たく言い放った。
秋吉先輩はそんな風に強く言われるとは思ってもみなかったように、一瞬だけ固まる。
でも、すぐに「ふぅ」と息を吐いた。
「警察は動いてくれなかったの。一度だけ相談したけど、証拠不十分って」
「なら、証拠集めたらいいじゃねーっすか」
「それができたら……頼んでないよ。皆、警察警察言うけど……あの人たち簡単には動いてくれないんだから……」
警察に頼んだけど、何かあったんだろうか。秋吉先輩はやるせないように唇を噛み締めた。
隣に座る小松先輩は、今にも泣き出しそうな顔をしている。
何か言ってあげたいけれど、俺はどうしたらいいかわからなかった。男の俺は、そんな経験もなくて、言葉だけ寄り添ってあげても、彼女たちの不安は拭えないに決まっている。
「それに……凛子の元カレ、ビジュ重視の人間なの。自分より顔がいい相手に対しては、コンプレックス拗らせてて、何にも言えない感じなんだよね」
秋吉先輩は、俺と縁を交互に見た。
「だから、うちの学校でも目立つ有馬くんに助けを求めようって……私が、凛子に言ったの。有馬くん、たまごサンドあげたら、大概の頼まれごと引き受けてくれるって聞いて」
そう言い終えると、秋吉先輩は申し訳なさそうに眉尻を下げる。
そんな顔をされてしまうと、放っておけなくなる。助けてあげた方がいいんじゃって、思った。でも、そんな俺を縁はお見通しみたいだ。
俺が返事をする前に「あのー……だからって、それ、当真が巻き込まれていい話っすか?」と、冷たい声で言った。
「でも、もう誰にも頼れなくて……! このままだと、凛子が……」
「秋吉先輩からすれば、小松先輩は大事な友達なのかもしんねぇけど。こっちだってな、同じなんすよ。当真は……人が良いし、ぼけぼけで……その上、クソ食いしん坊だから、これまでどんだけ搾取されてきたか」
「それは……」
秋吉先輩は俺の方を見て、次の言葉が出てこないかのように目を伏せた。
「縁……俺なら、大丈夫だよ。ほら、これまでのとはまたちょっと違う気がするし。それに、ストーカーって深刻でしょ」
「……違うって何が? また俺は、当真が殴られそうになるのを見なきゃいけないのかよ?」
「そうなるって決まったわけじゃ──」
「あーもう、いい分かった。俺がやるわ、その役。俺なら、ガタイがいいし、なんとかなるだろ」
縁はこれ以上話をしても無駄というように、面倒くさそうに言った。
なんでいつも、縁はそうなんだろう。
俺を思うがゆえの言動なのは分かる。けど、縁が代わりになろうとするなんて嫌だった。
縁の方がずっとずっと体格もいいのは分かってるけど、縁を危険に晒したくなかった。
「それは……駄目だよ」
俺が断るとは思ってなかったのか。縁は目を丸くした。
「はぁ? 当真が行くより、俺の方がいいだろ。ぽやぽやしてる当真が行ったところで、なんになんだよ」
「俺だって男だよ。ちょっと頼りないかもしれないけど、俺だって彼氏のフリくらいできる。それに、縁は後輩だ。こういうことは、先輩の俺が行くべきだと思う」
俺ははっきりと口にした。
だって、彼氏のフリくらい、できる自信があったから。
実際、俺は今、縁を騙しているのだ。
付き合ってる自覚なんてないまま、ずっとそばにいて。傷つけるなら言う必要ないかなって、今も縁に「俺たち付き合ってるの?」なんて言えないままいる。うまく、隠してる。だから、彼氏役くらい簡単だって思った。
でも、縁からすれば、俺はよほど弱っちいみたいだ。
「先輩とか後輩とか、関係ねぇだろ。つーか、こんな時だけ先輩ヅラすんな。当真は大人しく俺に守られとけよ」
縁の言葉は鋭いナイフのように、俺に刺さった。
反論しようと思うのに、ほんとこんな時だけ先輩みたいに振る舞うなんて……って、都合がいい話だ。自分に呆れてしまう。それに。
「当真、お願いだからさ……少しは俺の言うこと聞いてくれよ。俺は、当真が傷つくことが一番つらいんだよ」
縁にそんな風に言われてしまったら、もう何も言えない。
縁がつらいと思うことは、俺もしたくない。
縁を傷つけることだけは、したくなかった。
ぐっと言葉を詰まらせる俺の頭を、縁はぐしゃぐしゃと撫でてくれる。
「てことで、俺は何したらいい?」
縁が先輩たちに向けたその言葉を聞きながら、俺は唇を噛み締めて俯いた。
中間テストが終わってから、早一ヶ月。制服も中間服から夏服に切り替わって、すっかりじめじめとした梅雨に突入していた。
「あー、うぜぇ。なんなんだよ、あの人ら」
階段の踊り場であぐらをかく縁は、不機嫌そうに紙パックのストローを口にくわえた。
あの人らというのは、たまごサンドの先輩二人組のことだ。
一ヶ月前のあの日以降、彼女たちは事あるごとにたまごサンドを持って、俺の前に現れるようになった。昼休みはもちろん、放課後は靴箱で待ち伏せされることもある。
ただ、たまごサンド好きなのに、俺は一度も彼女たちから、受け取ってはいない。
今、俺の手にあるたまごサンドは、縁がご褒美としてくれたものだ。
──当真。この人らからたまごサンドもらわねぇならさ、俺がご褒美にやるよ。
先輩たちの提案を断った翌日。再びやってきた彼女たちの前で、縁もまたまたたまごサンドをちらつかせながら、意地悪そうな笑みを浮かべて言った。
先輩たちからしたら、生意気な後輩なんだと思う。
でも、それからというものの、縁は俺の盾になってあの人たちを追い払ってくれているから、俺は先輩たちから全く受け取らずに済んでいる。
まぁ、縁の懐事情がすごく気になるところではあるんだけど。俺がたまごサンド受け取ると、ふにゃりと可愛く笑ってくれるし、「小遣いたんまりもらってっから気にすんな。いつも勉強教えてもらってるし、それでチャラ」って言われるから、縁からは素直に受け取ることにした。せっかく買ってきてくれるのに、食べないほうがもったいないし。
ただ、このところ、縁はずっとイライラもしている。今日も眉間のしわが随分と深い。
(俺のせいで縁が嫌な思いするの……それはなんか、嫌だなぁ)
たまごサンドを持つ手に、ついきゅっと力が入ってしまった。中身が飛び出して、ボトッと俺のズボンに落ちる。
「あっ、おい。当真! 何してんだよ、ほんともう。……今日も年上とは思えねぇ、ぼけっと具合だなぁ」
縁はポケットティッシュを制服のズボンから取り出して、すぐにたまごペーストを拭い取ってくれる。
俺の方が先輩なのに、何から何までダメダメすぎる。ほんと自分が、嫌になる。
「ごめん」
「いや、別に……謝る必要ねぇけど。……って、あー……もしかしてさ、俺のせい?」
「え?」
「当真ってさ、平和主義だろ。俺がイライラしてるの……嫌なんだろなって。ほら、昔、俺が近所のやつと喧嘩したときと……同じ顔、してんなって」
縁は購買のビニール袋に汚れたティッシュを入れながら、心配げに俺を見た。
「あー……えっと、まぁ。縁が俺のために怒ってくれてるのは、嬉しいよ。でも……うん。そうだね。俺のせいで、縁がイライラしちゃうのは、嫌だなぁって。それに……」
俺は少し気になることがあって、途中で口をつぐんだ。
先輩たちがなんであんなに必死になって頼み事をしに来るのか、それが不思議だった。
「俺の杞憂だったらいいんだけどさ……。当真さ、あの人らの話聞こうって思ってねぇ?」
縁には何でもお見通しみたいだ。
俺は目を伏せて「ちょっと……気になって」と口にした。
「そんなに気になるもん? 俺は当真が搾取されんのが、すげぇ嫌なんだけど。そのお人好しもどうかと思う」
「でも、もし本当に困ってたら? これまでみたいに、誰かにヤキモチ妬かせたいってだけなら、一か月も……普通なら、しないよね?」
「そうかもしんねぇけど……」
「深刻な何かがあって助けを求めてるとしたら、俺は放っておけないよ」
「あー、もう」
縁は呆れたように息を吐いて、後ろ頭をぐしゃぐしゃと掻いた。そして、あまり納得してはいないようだったけど「わかったよ」と言ってくれる。
「話聞いてみるだけなら、いい。でも、絶対に当真一人では行かせねぇし、当真が泣かされるようなことがあったら、相手が女でも先輩でも容赦しねぇよ」
縁は真剣な目で、俺の方をまっすぐ見てきた。
俺たちはこの一ヶ月、これといった進展はない。でも、俺の気持ちは少しずつだけど、変わってきている。
「縁が隣にいてくれるなら、怖くないよ」
「何かあったら抱えて逃げるからな? 子ども扱いするなって言っても、聞かねぇから」
「……ふふっ。お願い」
俺は過保護なこの恋人を愛おしく思いながら、残っていたたまごサンドを口に運んだ。
ふわふわのパンに、からしの効いたマヨネーズ。後から、ピリッと黒胡椒が香る、学校の購買に置くには少しパンチの効いたサンドイッチ。その味は、俺を守ろうとしてくれる縁の強さと、どこか似ている。
食べるたびになんだか安心するから、俺は自然と笑みをこぼしていた。
もしかしたら、高校に入学してすぐ、一人で心細かったから、この味を求めるようになったのかも──なんて思ったのは、縁には絶対に秘密だ。
***
翌日の昼休み、俺と縁は早速、先輩たちの話を聞くことにした。
ただ、周囲にはあまり聞かせたくない話らしい。彼女たちの指定で、人のいない空き教室で話をすることになった。
俺が少しだけ緊張しているのを、縁は感じとったのだろうか。教室まで迎えに来てくれた時からずっと、俺の肩を抱いてくれている。
三年生の校舎にある空き教室にショートヘアの秋吉先輩と、ロングヘアの小松先輩が先に入っていく。二人に続いて、俺たちも中に入った。
「で、話ってなんなんですか?」
教室に入るなり、縁はすぐに先輩たちに話を振った。
椅子に座ろうとしていた先輩たちは、背もたれに触れたところで、その手を止める。
「まずはちょっと、座ってからにしない?」
小松先輩は少しだけ困ったように肩をすくめて、座るよう促してきた。
縁は「長話になるのか」とボソッと呟く。仕方なさそうに先輩たちから少し離れた席の椅子を引いて、俺を見てきた。
「当真、ここに座れ」
「あ……うん」
俺は縁が引いてくれた椅子に座った。
すると、縁は隣の椅子を俺のすぐそばに置いて、俺を守る番犬みたいに腰を下ろす。
先に口を開いたのは、小松先輩だった。
「えっと……あの、頼みたいことなんだけど。実は……私の恋人のフリをしてほしくて」
まさかの言葉が飛び出して、すぐに縁が「はぁ?」と、低い声をあげた。
俺はさすがに女の子相手に喧嘩腰になる縁が心配になって、慌てて「駄目だよ」と肩をたたく。
ここ最近気づいたことだけど、縁はどうやら女子が苦手らしい。俺の友達や縁のクラスメイト、委員会が同じ先輩とか、男子に対する態度とは天と地の差がある。
人好きする性格だと思っていたのは俺だけだったみたいで、秋吉先輩も小松先輩も、顔を引き攣らせていた。
「だって、この先輩が意味わかんねぇこと言うからだろ。なんで当真がそんなことしなきゃなんねぇんだよ。意味わかんねぇ」
縁がそう言った瞬間、秋吉先輩が「あ、あのっ……」と声をかけてくる。
「有馬くんがだめなら……久世くんでもいいよ」
秋吉先輩は声を震わせながら、縁の方を見た。
「うわ。そういうのが、すげぇむかつく。当真を蔑ろにするやつ、マジでむ──」
「縁。お口チャック」
これ以上、縁が口を開けば何を言い出すか分からなくて、俺は人差し指を縁の唇に当てた。すると、縁は目をぱちくりさせて、黙ってくれた。
俺が先輩たちの方に向き直ると、小松先輩は「ごめんね」と言った。
「悪いとは思ってるの……でも、元カレに、ストーカーされてて」
声を震わせる小松先輩は、今にも消えてなくなりそうなくらい小さく見えた。
隣に座る秋吉先輩は、そんな小松先輩の手に自分の手を重ねて、俺たちの方を見る。
「この子の元カレ、大学生なんだけど……もう束縛が凄くて、別れたんだよね。でも……別れたはずなのに、ずっと付き纏ってて」
「それで、なんで俺や当真が彼氏のフリしなきゃなねーんすか? ストーカーなら、警察の仕事でしょ」
縁は冷たく言い放った。
秋吉先輩はそんな風に強く言われるとは思ってもみなかったように、一瞬だけ固まる。
でも、すぐに「ふぅ」と息を吐いた。
「警察は動いてくれなかったの。一度だけ相談したけど、証拠不十分って」
「なら、証拠集めたらいいじゃねーっすか」
「それができたら……頼んでないよ。皆、警察警察言うけど……あの人たち簡単には動いてくれないんだから……」
警察に頼んだけど、何かあったんだろうか。秋吉先輩はやるせないように唇を噛み締めた。
隣に座る小松先輩は、今にも泣き出しそうな顔をしている。
何か言ってあげたいけれど、俺はどうしたらいいかわからなかった。男の俺は、そんな経験もなくて、言葉だけ寄り添ってあげても、彼女たちの不安は拭えないに決まっている。
「それに……凛子の元カレ、ビジュ重視の人間なの。自分より顔がいい相手に対しては、コンプレックス拗らせてて、何にも言えない感じなんだよね」
秋吉先輩は、俺と縁を交互に見た。
「だから、うちの学校でも目立つ有馬くんに助けを求めようって……私が、凛子に言ったの。有馬くん、たまごサンドあげたら、大概の頼まれごと引き受けてくれるって聞いて」
そう言い終えると、秋吉先輩は申し訳なさそうに眉尻を下げる。
そんな顔をされてしまうと、放っておけなくなる。助けてあげた方がいいんじゃって、思った。でも、そんな俺を縁はお見通しみたいだ。
俺が返事をする前に「あのー……だからって、それ、当真が巻き込まれていい話っすか?」と、冷たい声で言った。
「でも、もう誰にも頼れなくて……! このままだと、凛子が……」
「秋吉先輩からすれば、小松先輩は大事な友達なのかもしんねぇけど。こっちだってな、同じなんすよ。当真は……人が良いし、ぼけぼけで……その上、クソ食いしん坊だから、これまでどんだけ搾取されてきたか」
「それは……」
秋吉先輩は俺の方を見て、次の言葉が出てこないかのように目を伏せた。
「縁……俺なら、大丈夫だよ。ほら、これまでのとはまたちょっと違う気がするし。それに、ストーカーって深刻でしょ」
「……違うって何が? また俺は、当真が殴られそうになるのを見なきゃいけないのかよ?」
「そうなるって決まったわけじゃ──」
「あーもう、いい分かった。俺がやるわ、その役。俺なら、ガタイがいいし、なんとかなるだろ」
縁はこれ以上話をしても無駄というように、面倒くさそうに言った。
なんでいつも、縁はそうなんだろう。
俺を思うがゆえの言動なのは分かる。けど、縁が代わりになろうとするなんて嫌だった。
縁の方がずっとずっと体格もいいのは分かってるけど、縁を危険に晒したくなかった。
「それは……駄目だよ」
俺が断るとは思ってなかったのか。縁は目を丸くした。
「はぁ? 当真が行くより、俺の方がいいだろ。ぽやぽやしてる当真が行ったところで、なんになんだよ」
「俺だって男だよ。ちょっと頼りないかもしれないけど、俺だって彼氏のフリくらいできる。それに、縁は後輩だ。こういうことは、先輩の俺が行くべきだと思う」
俺ははっきりと口にした。
だって、彼氏のフリくらい、できる自信があったから。
実際、俺は今、縁を騙しているのだ。
付き合ってる自覚なんてないまま、ずっとそばにいて。傷つけるなら言う必要ないかなって、今も縁に「俺たち付き合ってるの?」なんて言えないままいる。うまく、隠してる。だから、彼氏役くらい簡単だって思った。
でも、縁からすれば、俺はよほど弱っちいみたいだ。
「先輩とか後輩とか、関係ねぇだろ。つーか、こんな時だけ先輩ヅラすんな。当真は大人しく俺に守られとけよ」
縁の言葉は鋭いナイフのように、俺に刺さった。
反論しようと思うのに、ほんとこんな時だけ先輩みたいに振る舞うなんて……って、都合がいい話だ。自分に呆れてしまう。それに。
「当真、お願いだからさ……少しは俺の言うこと聞いてくれよ。俺は、当真が傷つくことが一番つらいんだよ」
縁にそんな風に言われてしまったら、もう何も言えない。
縁がつらいと思うことは、俺もしたくない。
縁を傷つけることだけは、したくなかった。
ぐっと言葉を詰まらせる俺の頭を、縁はぐしゃぐしゃと撫でてくれる。
「てことで、俺は何したらいい?」
縁が先輩たちに向けたその言葉を聞きながら、俺は唇を噛み締めて俯いた。