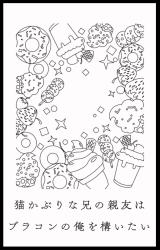中間考査一日目、帰りのホームルームを終えてすぐに、俺はトイレに向かった。
手洗い場の鏡に映る自分は、いつになく顔色が悪くて、ため息がこぼれる。
ほんと、最悪だ。なんとか無事に一日目を終えたけど、問題を解きながら、何度も朝の縁のことを思い出してしまった。おかげで、ほとんど見直しができずにどの試験も終わったから、今回のテストは成績を落としてしまったかもしれない。
(ケアレスミス……ないといいけど)
俺は手洗いを済ませると、気分を沈ませたまま、トイレから廊下に出た。
すると、ちょうどトイレの前で、俺の友達二人──三春くんと志筑くんに、ばったり遭遇した。二人はちょうど帰るところだったみたいだ。
縁に『ほわほわ三人衆』と呼ばれるだけあって、彼らは「当真、またね〜」「僕たち、もう帰るね〜」と、ふにゃふにゃした笑顔を浮かべて手を振ってくれる。
俺も「うん、また明日〜」と、笑って返す。
でも、二人を見送った俺の足取りは、すぐに重くなった。
(あぁ……早く帰って、明日の勉強しなきゃなあ。……縁のせいでダメだったって、言い訳するのよくない。これは、俺のせいだ……)
はぁとため息をつきながら、教室に向かって歩き始めた時だった。
「あっ……あれ、有馬くんじゃない⁉」
「ほんとだ……。いたっ!」
前方から、俺のことを探していたらしい女子の声が聞こえた。
見覚えのないショートヘアとロングヘアの女子二人組が俺のクラスの前にいて、「おーい、有馬くーん」と手を挙げている。
「え……? 誰?」
知らない女子生徒に、俺は戸惑ってしまった。
けれど、彼女たちは、あっという間に俺の元に駆け寄ってくる。
そんな彼女たちの中間服のネクタイは、深緑色だ。ということは、この二人は三年生らしい。
どうしたんだろう……? と首をひねる俺に対して、先輩たちは「初めて生で見たけど、ビジュえぐいね?」とか「肌キレイ過ぎない? なんの化粧水使ってるの?」とか聞いてくる。
でも、俺はその問いかけに、答えられなかった。
残念ながら、俺は皆と違って自分の容姿がいいなんて思わないし、化粧水は縁と一緒に使ってるから、メーカーが分からない。
そんな俺を、先輩たちはじろじろと品定めするように見てから、二人は顔を見合わせる。そして、大きく頷いた。
(……何? どういうこと?)
俺は少しだけ不安になって、身構えてしまった。
すると、ショートヘアの先輩が「お願い! 頼みがあるの!」と、俺に向かって両手を合わせる。
「ここにたまごサンドあるよ! 購買のやつ!」
もう一人のロングヘアの先輩はそう言って、手に持っていた購買のたまごサンドを俺に見せてきた。
(たまごサンド……!)
見ただけで、じゅるりとヨダレが口の中に溢れてくる。食べたい。そう思ったら、手が伸びそうになった。
けれど、屋上で殴られそうになった日の夜に、縁から言われた言葉が鮮明に耳に蘇った。
──当真。もう、二度と当て馬なんかするなよ。
──当真が誰かに消費されるの、俺は見たくねぇ。
──当真は俺にとって、世界一番大事なヤツなんだからな。
あの日、縁は俺の部屋に泊まって、俺を抱きしめながらそう言った。布団の中で、優しく言い聞かせるように、俺の背中を撫でながら。
あの時の俺は、縁が彼氏って知って驚きもあったけど……宝物みたいに思ってくれてるんだって知って、初めて自分が尊い存在のように思えた。
そんな縁の言葉を思い出したら、すぐに俺は正気に戻ることができた。だめだ、だめだと首を振って、俺は伸ばしかけた手を引っ込める。
「あ……えっと、すみません。受け取れない、です」
そう伝えたら、先輩たちは顔を見合わせて、「えぇ〜! 嘘でしょ?」「有馬くん、たまごサンド好きって言ってたよね?」なんて言いながら、困ったように肩をすくめた。
でも、諦める気はないらしい。
「あ、あのね。とりあえず、話を聞いてくれるだけでいいの。それだけで、このたまごサンドあげる」
「そうそう。それで、その話を聞いたうえで、有馬くんがOKしてくれたら、たまごサンド一か月分でどうかな?」
先輩たちは、さらなる提案をしてくる。
魅力的な提案だ。一ヶ月も、たまごサンドを食べられるなんて。
でも、これを受け入れたら、縁との約束を破ることになってしまう。
躊躇いながらも、俺は断ろうとした。だけど、俺が言葉を発する前に、ショートヘアの先輩から腕を掴まれてしまった。
「お願いっ! 有馬くんにしか頼めないの!」
その声は大きくて、廊下を通りかかった同級生たちの視線が向くのを視界の端に捉える。
目の前の先輩も、あまりに必死な形相だ。断ることに、じわじわと罪悪感を覚えてしまう。
(話を聞くだけなら……別にいいんじゃないのかな? 凄く、困ってるみたいだし。何か頼まれたら、断ればいいわけだもんね……)
仕方なく、俺はその頼みを受け入れようと、口を開いた。
「わかりま──」
「お断りしまーす」
俺の返事に、やや低めの柔らかな声が重なる。その声が響いた瞬間、廊下が静まり返って、俺は後ろを向いた。
「当真。たまごサンドなら、俺が買ってきてやったから、んな話に乗んなよ」
後輩なのに、圧倒的な存在感を放つ幼なじみ──いや、恋人は、たまごサンドを顔の横に掲げてみせた。
「でも、困ってそうで」
「そんなもん、知らねーわ。俺らに関係ねぇ。話なんか聞く必要ねぇ」
縁ははっきり言い放つと、「ほらよ」と、俺の手にたまごサンドを乗せてくれる。
そんな俺の背後で、先輩たちはこそこそと声を潜めて、話し合いを始めていた。
「ねぇ、どうする?」
「どうしようもできなくない?」
「てか、こっちの子ってあの久世くんだよね?」
「うん。そうだと思う。写真で見るよりビジュが爆発してるわ」
「有馬くんだめなら、久世くんに頼む?」
「いや、無理だよ。こわい。イン◯タのDM送った子が速攻でブロックされたって言ってたし」
何の話なのかは分からないけど、先輩たちはもはや俺ではなく、縁の方を見ているようだった。
俺じゃなくても良い──そう言われているようで、話を聞こうとしていた自分が、なぜか恥ずかしくなってくる。
「はっ……。さっきは当真にしか頼めねぇって言っときながら、それかよ」
俯きそうになった時、縁がボソッと呟いた。
縁を見上げれば、軽蔑したような目で、俺の後ろを見ている。
でも、縁の視線に気づくと、大丈夫だよとでも言うように目を細めて、俺の肩を抱いてくれた。
「じゃ、先輩方。これから、当真は俺に愛でられまくる予定なんで、失礼しまーす」
縁はそう言って先輩たちを放置して、何食わぬ顔で俺を教室へ連れて行こうとする。
でも、縁は物凄く腹を立てていたみたいだ。
「あー、ふざけんなよ。……当真は、誰かの代わりになるようなやつじゃねぇし」
声に憤りを滲ませる縁の手に、力が入るのが分かった。
ほんの少し、掴まれた肩が痛い。
けれど、縁の言葉が嬉しくて、そんな痛みなんてどうでもよくなった。
縁は俺を、俺だけを見てくれる。
こうして、俺を宝物みたいに大事にしてくれる。
その事実が、俺の沈みかけた心を軽くしてくれた。
だけど、ごめんね、ありがとう──その言葉さえも、声を詰まらせてしまって、口にできない。
俺が何も言えずにいると、肩を掴んでいたはずの縁の手が離れて、そっと俺の頭を撫でた。
「ここで待ってっから。荷物取ってこいよ」
俺を教室に送り出してくれるその手が、温かくて。
同じ気持ちを返せていないことが、何よりも心苦しく思えた。
なんで俺は、縁のことを好きじゃないんだろう。
***
「当真。今日はどうする? 一緒に寝るか?」
明日の試験科目の勉強を終えると、縁に声をかけられた。顔を上げてみれば、縁はソファで心配そうにクッションを抱えている。
今夜、俺の父さんは留守だ。近くの県立病院で勤務医として働いているから、週に一、二回の当直がある。今日も、その日。
俺はテーブルの上に広げた教科書とノートを一つにまとめながら、首を振った。
「大丈夫だよ。一緒に寝ると狭いし。試験前に悪いよ」
「なーに言ってんだよ。俺は当真の彼氏だぞ? 遠慮すんな」
「でも」
「でもじゃねぇよ。今日、おじさんいないなら、一人にさせんの、俺が嫌なんだよ。……昼のこともあったし」
縁は過保護だ。本当に、過保護。
マンションの隣の部屋で、何かあったらすぐ駆けつけられる距離なのに。
「縁はなんで、そんなに俺を大事にしてくれるの」
ずっと気になっていたことを口にしたら、縁は笑いながら手を広げた。こっちに来いっていう意味だろう。
俺はゆっくり立ち上がって、縁のもとに行く。
「そんなの、当真が好きだからだろ」
縁は俺を抱きしめて、膝の上に乗せてくれた。
「好きだけで……?」
「そうだよ。好きだから、大切にしてぇって思うよ」
「そうなんだ」
「そうなんだって冷てぇな」
縁はくすっと笑いながら、俺の頭を撫でてくれる。
「ごめん」
「いーよ。俺はな、もう小さい頃からずっと……当真だけを見てきたんだ。当真のおばさんが亡くなってからは、余計に当真への気持ちが抑えられなくなってさ。年下だって分かってっけど、どれだけ当真を守ってやりてぇって思うようになったか」
「そ……そうなの?」
「ああ。だからさ、やっと、当真に気持ち伝えられて、付き合ってもらえてんのに。大事にしなくてどうすんだよって話だ」
縁の言葉で、俺はぐっと言葉を詰まらせた。
縁はこんなに俺を想ってくれているのに、なんで付き合ってることに気づいていなかったんだろう。
いつから付き合っているのか、知らないんだろう。
せめて、今言えることだけは伝えておきたくて、俺は縁からそっと身体を離した。
「……縁。あの、俺の方こそ……俺ばっかり、縁にもらってばかりだ」
縁をまっすぐ見つめて、そう口にする。
すると、縁は驚いたように、目を丸くした。でも、すぐに破顔する。
「ははっ。そう思ってくれてんなら、よかったわ。当真を幸せにしてやりたくて、たまんねぇんだから」
優しい声音でそう言って、愛おしそうに、俺の頬っぺたに唇を落としてくれる。
朝はキスをされて戸惑っていたのに、なぜか今はとても心地が良かった。
俺もちゃんと『好き』って気持ちを、縁に返せたらいいのに。
そしたら、縁はどんな反応をするんだろう。
今の俺はまだ、縁に同じ好きを渡せてないから、早く、縁を好きになりたくて。
俺はそっと、縁の肩に腕を回した。
縁はあったかくて、心がホッとする。俺はいつまでもこの腕の中にいたいと、そう願いながら目を閉じた。