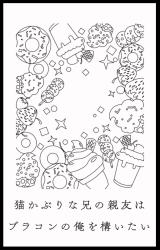──縁って、いつの間に俺の彼氏になったの?
そう確認するタイミングを逃してしまってから、一週間と少し。
ソファで映画を観ながら膝枕をしてくれたり、風呂上がりに髪を乾かしてくれたり。事あるごとに柔らかな目をして「好き」「かわいい」なんて甘い言葉を吐く縁を前にしたら、いくら疎い俺でも、単なる幼なじみじゃないんだなって、理解した。
中間考査を明日に控えた日曜のこの日も、そうだった。俺の家に来た縁は、先程から目の前の勉強よりも俺に夢中らしい。
「何……? 俺の顔に何かついてる?」
リビングのローテーブルで数IIの問題集を解いていた俺は、その手を止めて、向かいに座る縁を見た。
俺たちは、部屋着代わりに、大体いつも中学の体操服を着ている。ゼッケンにでかでかと久世と書かれたそれを着る縁は、顔を綻ばせながら俺を見ていた。
「んー? ついてねぇよ」
「じゃあ、なんでずっと俺を見てるの?」
「なんでって、当真見ながら英単語覚えてんの」
縁は手元の英単語帳をほれ、と持ち上げてみせる。
「えぇ……? 俺見て覚えられるわけないよ」
「それができるんだなー。俺、当真で連想しながら覚えたら、ぜってぇ忘れねぇから」
「それは……すごいね?」
「だろ? やっぱ彼氏の力って偉大だわ」
縁はそう言って幸せそうに笑うものだから、俺は何も言えなくなる。
いや、知らないうちに幼なじみが彼氏になってるとかおかしな話だし、本当は「いつから付き合ってるんだっけ?」とか、「縁はいつから俺が好きなの?」とか、聞きたいことは山ほどある。
でも、それが出来ないのは、縁が物凄く俺が好きなんだなぁって伝わってくるから。
それに、縁の隣にいることは、これまでと変わらない。なら、わざわざ傷つけることはしなくてもいいのかなぁって、気持ちになっている。
この関係、崩したくないし。
(まぁ……ただちょっとだけ、ベタベタ距離が近いっていうのが困るところだけど)
今も縁は「なんだよ、当真」なんて言いながら、俺の右手に触れてくる。
俺は縁が『彼氏』だって知ってから、気づいた。
縁はとにかく、俺に触りたがるって。かなりの、スキンシップ過多。
「縁。俺は縁と違って右利きだし、触るなら左手にして? 問題ちょっと解きにくい」
「ははっ。分かったよ」
縁はそう言いながら、今度は右手を俺の左手に重ねてきた。嬉しそうに目を細めて「これでいいか?」と、聞いてくる。
(縁ってほんと……なんか、甘い。いつから、こうなんだっけ……)
俺はふと、これまでの縁のことを思い返すことにした。
母さんが生きていた時から、縁は俺が熱を出すと必ず、うちに泊まりにきてくれていた。
親たちがダメだって言うのに、縁は風邪が移るのもお構い無し。こっそり隠れて自分の布団を持ってきて、俺のベッドの下に敷いていた。
──当真。俺がついてるから、もう大丈夫だぞ。
なんて言いながら、俺が眠るまでずっと手を握ってくれていたっけ。
それに、中学に上がった頃からは、おばあちゃんがよく俺の家に来てくれてたんだけど、縁もほぼ毎日夕飯作りを手伝ってくれるようになった。うちのおばあちゃんに一緒になって料理を習って、その度に、俺に味見させてくれるようになって。今も昔も変わらず「ほら、当真。あーんしろよ」って口に運んでくれている。
それだけじゃなくて、いつの間にか自分の布団持って、しょっちゅう俺の家に泊まってくれるようになったんだけど。ホラー映画とかちょっと俺の苦手なものを観たり、俺が沈んでてなかなか寝付けなかったりする時は必ず、気づいてくれる。
──当真? 眠れねぇの? ほら、来いよ。
って、腕を広げてくれて、俺をぎゅっと抱きしめて眠ってくれるんだよね。
そういえば、他にもあった。去年の冬なんて、縁は受験生だったのに、俺が学校に行く時にマフラーしてなかったからって、放課後学校近くまで来てくれたっけ。
──当真。風邪ひくだろ。
なんて、自分のマフラーを俺に巻いてくれたの、凄く嬉しかったな。
(あれ……? よく考えてみれば、俺、もしかしてずっと縁に甘やかされて育った? ……そもそも、彼氏じゃない時から、ずっと甘い? ていうか、ほんと縁っていつから彼氏なんだ?)
ぼんやり縁のことを考えていると、縁が「おーい、当真」と、目の前で左手を振り始めて、俺はハッと我に返った。
「な、何」
「当真さぁ……俺の前でぼんやりしたらさ、その都度、キスしていい?」
「なっ! ……キスって、縁ってば変だよ」
「何でだよ。付き合ってんだし、良いじゃん」
「よ、よくないと思う。それは」
「なんで?」
縁は膝立ちになって、俺の方に近づいてくる。
(だって……俺はまだ、縁をそういう意味で好きなのかって、分からない。幼なじみとしては、大好きだけど。たぶん、縁が感じているものとは違う)
縁には申し訳なくて、俺は目を伏せた。
「生徒手帳に不純異性交遊はダメって書いてたよ」
「俺たち同性」
すぐさま返されて、俺は「それでもっ」と視線を縁に戻した。
すると、縁はにんまり笑って、右手は俺の手に触れたまま、左手で俺の頰に触れてくる。
一瞬だけ、俺の身体はぴくっと跳ねてしまった。
指先が触れるだけで反応をしてしまう自分が恥ずかしくて、俺はもう一度、縁から目を背けた。
「当真さぁ。もしかして……ようやく、俺のこと意識してくれた感じ?」
「してない」
「ふーん? じゃあ、なんで生徒手帳の内容なんか知ってんだよ。ぽやぽやした当真が、んなこと知ってると思えないんだけど〜」
縁に突っ込まれて、俺はギクッとした。
縁から『彼氏だ』って言われた日の夜。縁が恋人なんだと知ってしまったら、なんだかやけに落ち着かなくなって、生徒手帳の校則を読み返していた。
(だって……俺、誰とも付き合ったことないし。急に付き合ってるって言われたら……なんか、校則とか破ってないかなって、気になったんだよ……)
そんな慌てた俺の行動がバレているような気がして、頰がかあっと熱くなってくる。
「た……たまたまだよ」
「へぇ。それじゃあ、俺の方見ないのはなんで?」
そう言われて、俺は仕方なくまた、縁の方を見る。
「見たよ」
「当真。今さ、すげぇ顔、赤いの分かってる? 俺のことで赤くしてくれる当真、めちゃくちゃかわいい」
甘ったるい縁に、なんでだろう。情緒が乱されそうになる。俺は息を呑んで──でも、明日は中間考査だってのを思い出して。
「……もう何言ってるの。勉強しなよ」
そう言うのが、精一杯だった。
***
翌日。朝ごはんを食べ終えた後、縁はいつも通り、俺の身の回りを整えてくれた。
一緒に家を出て、マンションから徒歩五分の学校に向かうのだけど。なんか今日も今日とて、やっぱり距離が近い。
もう五月下旬なのもあって、カーディガンはなくなり、俺たちは長袖一枚だ。縁は学校までの道中ずっと俺の肩を抱いていて、触れる障害物が一つなくなるだけで、体温がより伝わってくる。
(縁が高校入ってきてから、もうずーっとこんな感じでの登校なんだよね。……縁は何を考えて、こんな風に俺に触れて来るんだろう? 恋人って、そんなにペタペタ触れたくなるものなのかな?)
そう思いながら歩いていたら、縁に「当真」と呼ばれて、ようやく現実に戻った。
気づいたら、もう学校の昇降口前だった。
「あ、ごめん」
慌てて謝ると、縁はいつもの俺の髪ではなく、頰を撫でた。
「当真。俺、言ったよな? ぼんやりしてたら、キスしてもいいかって」
「え?」
縁を見上げた時には、もう遅かった。
この前は額にキスをされたけど、今度は頬──ほとんど唇の近くに柔らかな感触がした。
けれど、すぐに縁は俺から離れて、その感触は消える。
(え……?)
俺は戸惑いながら、ゆっくりと唇のすぐ横に触れた。
どこからか「見た⁉︎」「見ちゃった!」「キスしてたよね⁉︎」とか、俺たちのことを言っているような女子の声が聞こえる。
「ほんとはさ、女子が当真にたまごサンド持って来ねぇように、ここにキスマークつけてぇんだけど。さすがに当真が可哀想だし、これで許してやるよ」
縁は俺の首元をとんとんと指先でつきながら、そう言う。
俺はずっと、縁のことを世話焼きな幼なじみだって思っていた。
だけど、本当は彼氏だった。
そんな相手から、あまりにストレートな言葉を投げられて、キスまでされたら、いくら俺でも動揺する。
あっという間に、全身が熱くなるのがわかって「縁のばか!」と、逃げるように靴箱の方に向かった。
(……どうしよう。縁とはもう、幼なじみじゃいられない?)
頰が熱くて、たまらない。パタパタと手で仰いでも、なかなかこの熱は引いてくれそうにない。
周囲の視線から逃れるように、俺は自分の頼りない細腕で、顔を隠すしかなかった。