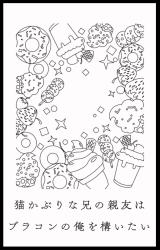逃げるようにして縁に連れて来られた先は、屋上の階段から降りてすぐ。三階の社会科資料室だった。
俺は一度だけ来たことがあるけど、大多数の生徒は存在すら知らないような部屋だ。だから、普段は鍵がかかっているはずなのに、縁はすんなりドアを開けて、俺を押し込んだ。
淡い光が差し込む狭い室内には、古い棚が並ぶ。
埃っぽさと、ほんの少しのカビ臭さがあって、相変わらずほとんど人が来ないのも、頷ける。
(でも、なんで縁はここの鍵を持っているんだろう……?)
縁を見れば、すぐに内側から鍵をかけて、俺の方を向いた。
「……当真さぁ。ほんと勘弁してくれよ。最初、当真のことだし、ここに閉じ込められてっかもって、鍵まで借りてきたんだからな。……なのに、屋上って、マジで心臓止まるかと思った」
はぁ、とため息をこぼした縁は、背を丸めて、俺を力強く抱きしめた。どこか甘えるように俺の首筋に顔を擦り寄せてくる。
(鍵まで借りてきたって……そんなに俺のこと、心配してくれてたんだ)
「ごめんね……心配かけて」
「ほんと心配させんな。……GPS入れてんのにさ、階数まではわかんねぇし、めちゃくちゃ走り回ったし。……昼休み迎え行くって言ったの、ちゃんと守れよ」
縁は俺の存在を確かめるように、後ろ頭を優しく押さえてくる。
そういえば、去年の春、高校に一人でちゃんと通えるのかを心配して、縁は俺のスマホにGPSアプリを入れてくれてたんだっけ。
まさか、校内で使われることになるなんて、思いもしなかった。
「ごめん……」
「ごめんじゃすまねぇ。こちとら学年ちげーし、昼休みも放課後も、当真がちゃんと教室いるか気が気じゃねーってのに。ちゃんと言うこときけよ、ばか」
縁は俺を抱きしめたまま、拗ねたような声を上げる。縁の吐息が俺の首筋を撫でてきて、ちょっとくすぐったい。
「……ばかってひどい」
俺は縁の爽やかなシャンプーの香りを感じながら、ほんと過保護だなぁって思って、少しだけ笑った。
「あー……ばかって言って、ごめん。……てか、なんで屋上にいたんだよ」
縁はすぐに謝ると、急に俺の肩から顔を離して、真面目な表情でじっと見つめてきた。
「なんでって……たまごサンドくれるって言ったから」
「……は?」
「あ、えっと、佐々木さんに『たまごサンドあげるから、ついて来て』って言われて。……俺、ただ立ってただけなんだけど、ちょっと巻き込まれちゃった」
縁が眉間にしわを寄せて怖い顔をするので、俺は少しでもその心配を和らげようと、へらりと笑ってみせた。だけど、それは逆効果だったみたいだ。
俺を見る縁の表情は、みるみるうちに元気を無くす。
眉尻を下げて、まるで自分が何かを言われて傷ついてしまったかのように、悲しげだ。そんな顔をされたら、俺の胸までズキッと痛みを放ち始めてしまう。
「縁……もしかして、泣きそう?」
俺はそっと縁の頬に手を伸ばした。指先が肌に触れると、縁がぴくっと反応する。でも、縁は昔から、どんな時も俺の手だけは拒まない。
俺が触ることを許すように、そっと目を伏せてくれる。
「違う。怒ってんだよ。……心臓いくらあっても足んねぇ。当真……もっと自分を大事にしてくれ」
「ん? 大事にしてるよ? 俺、すごく健康だし」
「そういう意味じゃねぇわ」
縁はほんの少し、むすっとした表情を浮かべて、言葉を続けた。
「昨日……クラスの女子から、当真が『当て馬先輩』って呼ばれてるの聞いた。ほんと……もうさ、なんでそんな扱いされてんだよ。意味わかんねぇよ」
縁は苦しそうに言葉を吐き出した。
でも、俺は何をそんなに縁が怒るのか、よく分からなかった。むしろ、俺はなかなかのネーミングセンスに、感動を覚えていたくらいだ。
「でも、縁。そのあだ名つけた人、すごいよ?」
少しでも縁にこの感動を伝えたくてそう言ったのだけど、縁の眉がぴくりと動いた。
「……何がだよ」
「何がって、俺の真ん中の二つの漢字を逆にしたら、当て馬って言葉に──」
「それ、絶対違げぇから」
俺はちょっとした発見だと思ったのに、縁は表情をさらに曇らせて、力強く言葉を遮った。
「えっ、これがあだ名の由来じゃない感じ?」
「違う。そうじゃなくて──」
縁はためらうように口をつぐんで、くしゃりと自分の前髪を掴む。
そんな縁の指先は、震えている。苛立ちを我慢するようなその様子を見てようやく、俺は縁が本気で怒っていることに気がついた。
でも、すぐに縁は手を下ろして、深呼吸をひとつしてから、再び開口した。
「当真にもうこんなことさせたくないから言うわ。……女子たちが、当真の顔使って彼氏とか、好きな相手にヤキモチ妬かせてんだよ」
「え? 俺の顔使う? どういうこと?」
縁の言うことが意味わからなくて、俺の頭にははてながいくつも浮かぶ。
縁は「当真さぁ、自分の顔がやたらいいこと自覚してねぇのもどうかと思うわ」と言いながら、そんな俺の顎をガシッと掴んできた。
縁は俺を触る時、いつも加減をしてくれている。だから全く痛くはない。けど、身動きがとれなくなって、少し困った。
「当真が女子と話したり、笑ったりするだけで、その子を好きな男はモヤモヤすんだよ。盗られるんじゃねぇかって」
「……ほふなの?(そうなの?)」
縁の手で口が上手く開かなくて、俺の声がくぐもる。
すると、縁は俺の目をじっと見ながら「そうなんだよ」と言って、ようやく手を離してくれた。
俺は軽く顎をさすって、縁ってば過保護なのか雑なのか、よくわかんないなぁと思いながら、口を尖らせた。
でも、縁もよく言ってくれるけど、俺の顔って、そんなに良いのだろうか。
鏡を見るたびに、目が大きいなとか、肌が白いなとか、思うことはある。
けど、殴られたら一発KOしそうな頼りない見た目だ。
たまに「写真撮っていいですか?」ってカメラ向けられる時あるけど、怖くて逃げちゃうような俺が、女の子に騒がれる理由がわからない。
それより、縁みたいに骨格がしっかりしてて、厳ついピアスも似合う容姿の方が、絶対かっこいいのに。
そんなことを考えながら、俺は縁が何をそんなに怒ってるのか、まだよく分かっていなくて、「へぇ……」と、気の抜けた相槌をした。
だから、次の瞬間。
「と〜う〜ま〜! ほんとにちゃんとわかってんのかよ?」
また縁からグッと顎を掴まれて、俺の心臓が止まるかと思った。
「よく聞けよ?」
「ひゃい(はい)」
「当真がその気無くても、好きな奴が異性と話してるだけで気に食わねぇって奴はいっぱいいる」
「ひゃい(はい)」
「特に当真は顔が良いから、立ってるだけで『当て馬役』になるって……相手の気持ちを確かめたくて、当真使ってんの。たまごサンドを餌に女子に利用されてんだよ。クソ腹立つ」
縁は顔をしかめて、俺ではない誰かに対して、嫌悪感を露わにした。
俺も、まさかのそういう風に見られていたなんて、全然知らなかった。ようやく知った今、事の深刻さに手が震えてくる。
(俺と話して、彼氏や好きな人にヤキモチ妬かせたかった……って。俺、他の男子が嫌がることしてたんだ……。だから、宮田くんもあんなに怒って。縁にも、心配かけた)
考えただけで、申し訳なくて、鼻の奥がつんと痛くなってくる。
たぶん、まだ涙は出ていない。
でも、縁は俺の顎から手を離すと、またギュッと抱きしめてくれた。自分がいるから大丈夫とでも、言ってくれているように。
「ごめんな。当真。もうぜってぇ、当真がそんな扱いされねぇようにするから。あと、顎も掴んでごめん。痛かったよな」
縁の身体は温かくて、俺を全身で包み込んでくれる。まるで俺の心ごと抱きしめようとしているようだ。
俺は泣きそうになるのをぎゅっと堪えながら、縁の背中に手を回した。
縁は昔から、俺よりも俺のことで心を痛めてくれる。
小学生の頃の俺は、よく女の子と間違えられてたから、近所の子から「おとこおんな〜」なんて言われていた。だけど、その時も俺以上に縁が怒っていたっけ。
それに、中学に上がる前に、俺の母さんが亡くなった時だって……泣けない俺の代わりに泣いてくれて。俺も、釣られて泣けるようになったんだっけ。
たぶん、俺は縁が怒ったり、泣いたり、いろんな感情を出してくれるから、傷ついても、ちゃんと前を向けるようになるんだと思う。一緒になって悲しんでくれたり、苦しんでくれたり、気持ちを共有してくれるから、安心できる。
「……縁、ありがと」
「ありがとうなんか言うな。まだ、守れてねぇんだ」
「えぇ? 十分だよ?」
そう言うと、縁は少し離れるように腕をほどいて、俺をまっすぐ見た。
「どこがだよ。……つーか、当真の友達も、なんで誰も言ってやらねぇんだよ。俺しか気づいてねぇのか?」
「んー……皆、俺と似てるから?」
少し首を傾げながら言ったら、縁は黙り込んだ。
なんかだんだん、顔を顰めて、難しい表情になってきた。
たぶん、俺の友達二人を思い浮かべているんだろう。
友達ができたか心配した縁に初めて会わせた時、縁が「なんか……あれだな? 三人とも小動物みたいだな? ヒヨコに、ハムスターに、リス」と俺たちに向かって言ったのを、未だ鮮明に覚えている。
「あぁ……まあ、あの先輩たちならそうか〜。ほわほわ三人衆だもんなぁ……」
縁は脱力したみたいにそう言うと、もう一度俺を抱きしめた。
「……あー、くそ。でも、当真が、んな扱いされてきたのほんとむかつく。……何が当て馬だ。当真は俺の彼氏だってのに……今まで気づいてなかった自分にも腹立つ」
そんな縁の苛立ちをはらんだ言葉が、静かな室内に落ちていく。
時間が止まったようにしんとして、俺は縁の腕の中で、固まった。
──当真は俺の彼氏だってのに。
その言葉が、頭の中でリフレインする。
瞬きを数回繰り返して、俺はやっと、縁の言葉の意味を理解した。
(え? 待って。俺って……縁の彼氏なの?)
これこそ、俺の中での一大事だ。
当て馬先輩と呼ばれていると知るよりも、ずっと衝撃的だった。
「え……えぇ〰〰〰〰〰〰⁉︎」
気づいた時には、これまで出したことのないくらいの大声で叫んでいた。
でも、無情にも、時間は、空気なんて読んではくれない。俺の叫びがうるさいとでもいうように、昼休みの終わりを告げるチャイムが鳴る。
縁からは「はぁ? なんだよ急にでかい声だして」って言われるだけで、何も聞けないまま、俺は教室に帰る羽目になったのだった。
俺は一度だけ来たことがあるけど、大多数の生徒は存在すら知らないような部屋だ。だから、普段は鍵がかかっているはずなのに、縁はすんなりドアを開けて、俺を押し込んだ。
淡い光が差し込む狭い室内には、古い棚が並ぶ。
埃っぽさと、ほんの少しのカビ臭さがあって、相変わらずほとんど人が来ないのも、頷ける。
(でも、なんで縁はここの鍵を持っているんだろう……?)
縁を見れば、すぐに内側から鍵をかけて、俺の方を向いた。
「……当真さぁ。ほんと勘弁してくれよ。最初、当真のことだし、ここに閉じ込められてっかもって、鍵まで借りてきたんだからな。……なのに、屋上って、マジで心臓止まるかと思った」
はぁ、とため息をこぼした縁は、背を丸めて、俺を力強く抱きしめた。どこか甘えるように俺の首筋に顔を擦り寄せてくる。
(鍵まで借りてきたって……そんなに俺のこと、心配してくれてたんだ)
「ごめんね……心配かけて」
「ほんと心配させんな。……GPS入れてんのにさ、階数まではわかんねぇし、めちゃくちゃ走り回ったし。……昼休み迎え行くって言ったの、ちゃんと守れよ」
縁は俺の存在を確かめるように、後ろ頭を優しく押さえてくる。
そういえば、去年の春、高校に一人でちゃんと通えるのかを心配して、縁は俺のスマホにGPSアプリを入れてくれてたんだっけ。
まさか、校内で使われることになるなんて、思いもしなかった。
「ごめん……」
「ごめんじゃすまねぇ。こちとら学年ちげーし、昼休みも放課後も、当真がちゃんと教室いるか気が気じゃねーってのに。ちゃんと言うこときけよ、ばか」
縁は俺を抱きしめたまま、拗ねたような声を上げる。縁の吐息が俺の首筋を撫でてきて、ちょっとくすぐったい。
「……ばかってひどい」
俺は縁の爽やかなシャンプーの香りを感じながら、ほんと過保護だなぁって思って、少しだけ笑った。
「あー……ばかって言って、ごめん。……てか、なんで屋上にいたんだよ」
縁はすぐに謝ると、急に俺の肩から顔を離して、真面目な表情でじっと見つめてきた。
「なんでって……たまごサンドくれるって言ったから」
「……は?」
「あ、えっと、佐々木さんに『たまごサンドあげるから、ついて来て』って言われて。……俺、ただ立ってただけなんだけど、ちょっと巻き込まれちゃった」
縁が眉間にしわを寄せて怖い顔をするので、俺は少しでもその心配を和らげようと、へらりと笑ってみせた。だけど、それは逆効果だったみたいだ。
俺を見る縁の表情は、みるみるうちに元気を無くす。
眉尻を下げて、まるで自分が何かを言われて傷ついてしまったかのように、悲しげだ。そんな顔をされたら、俺の胸までズキッと痛みを放ち始めてしまう。
「縁……もしかして、泣きそう?」
俺はそっと縁の頬に手を伸ばした。指先が肌に触れると、縁がぴくっと反応する。でも、縁は昔から、どんな時も俺の手だけは拒まない。
俺が触ることを許すように、そっと目を伏せてくれる。
「違う。怒ってんだよ。……心臓いくらあっても足んねぇ。当真……もっと自分を大事にしてくれ」
「ん? 大事にしてるよ? 俺、すごく健康だし」
「そういう意味じゃねぇわ」
縁はほんの少し、むすっとした表情を浮かべて、言葉を続けた。
「昨日……クラスの女子から、当真が『当て馬先輩』って呼ばれてるの聞いた。ほんと……もうさ、なんでそんな扱いされてんだよ。意味わかんねぇよ」
縁は苦しそうに言葉を吐き出した。
でも、俺は何をそんなに縁が怒るのか、よく分からなかった。むしろ、俺はなかなかのネーミングセンスに、感動を覚えていたくらいだ。
「でも、縁。そのあだ名つけた人、すごいよ?」
少しでも縁にこの感動を伝えたくてそう言ったのだけど、縁の眉がぴくりと動いた。
「……何がだよ」
「何がって、俺の真ん中の二つの漢字を逆にしたら、当て馬って言葉に──」
「それ、絶対違げぇから」
俺はちょっとした発見だと思ったのに、縁は表情をさらに曇らせて、力強く言葉を遮った。
「えっ、これがあだ名の由来じゃない感じ?」
「違う。そうじゃなくて──」
縁はためらうように口をつぐんで、くしゃりと自分の前髪を掴む。
そんな縁の指先は、震えている。苛立ちを我慢するようなその様子を見てようやく、俺は縁が本気で怒っていることに気がついた。
でも、すぐに縁は手を下ろして、深呼吸をひとつしてから、再び開口した。
「当真にもうこんなことさせたくないから言うわ。……女子たちが、当真の顔使って彼氏とか、好きな相手にヤキモチ妬かせてんだよ」
「え? 俺の顔使う? どういうこと?」
縁の言うことが意味わからなくて、俺の頭にははてながいくつも浮かぶ。
縁は「当真さぁ、自分の顔がやたらいいこと自覚してねぇのもどうかと思うわ」と言いながら、そんな俺の顎をガシッと掴んできた。
縁は俺を触る時、いつも加減をしてくれている。だから全く痛くはない。けど、身動きがとれなくなって、少し困った。
「当真が女子と話したり、笑ったりするだけで、その子を好きな男はモヤモヤすんだよ。盗られるんじゃねぇかって」
「……ほふなの?(そうなの?)」
縁の手で口が上手く開かなくて、俺の声がくぐもる。
すると、縁は俺の目をじっと見ながら「そうなんだよ」と言って、ようやく手を離してくれた。
俺は軽く顎をさすって、縁ってば過保護なのか雑なのか、よくわかんないなぁと思いながら、口を尖らせた。
でも、縁もよく言ってくれるけど、俺の顔って、そんなに良いのだろうか。
鏡を見るたびに、目が大きいなとか、肌が白いなとか、思うことはある。
けど、殴られたら一発KOしそうな頼りない見た目だ。
たまに「写真撮っていいですか?」ってカメラ向けられる時あるけど、怖くて逃げちゃうような俺が、女の子に騒がれる理由がわからない。
それより、縁みたいに骨格がしっかりしてて、厳ついピアスも似合う容姿の方が、絶対かっこいいのに。
そんなことを考えながら、俺は縁が何をそんなに怒ってるのか、まだよく分かっていなくて、「へぇ……」と、気の抜けた相槌をした。
だから、次の瞬間。
「と〜う〜ま〜! ほんとにちゃんとわかってんのかよ?」
また縁からグッと顎を掴まれて、俺の心臓が止まるかと思った。
「よく聞けよ?」
「ひゃい(はい)」
「当真がその気無くても、好きな奴が異性と話してるだけで気に食わねぇって奴はいっぱいいる」
「ひゃい(はい)」
「特に当真は顔が良いから、立ってるだけで『当て馬役』になるって……相手の気持ちを確かめたくて、当真使ってんの。たまごサンドを餌に女子に利用されてんだよ。クソ腹立つ」
縁は顔をしかめて、俺ではない誰かに対して、嫌悪感を露わにした。
俺も、まさかのそういう風に見られていたなんて、全然知らなかった。ようやく知った今、事の深刻さに手が震えてくる。
(俺と話して、彼氏や好きな人にヤキモチ妬かせたかった……って。俺、他の男子が嫌がることしてたんだ……。だから、宮田くんもあんなに怒って。縁にも、心配かけた)
考えただけで、申し訳なくて、鼻の奥がつんと痛くなってくる。
たぶん、まだ涙は出ていない。
でも、縁は俺の顎から手を離すと、またギュッと抱きしめてくれた。自分がいるから大丈夫とでも、言ってくれているように。
「ごめんな。当真。もうぜってぇ、当真がそんな扱いされねぇようにするから。あと、顎も掴んでごめん。痛かったよな」
縁の身体は温かくて、俺を全身で包み込んでくれる。まるで俺の心ごと抱きしめようとしているようだ。
俺は泣きそうになるのをぎゅっと堪えながら、縁の背中に手を回した。
縁は昔から、俺よりも俺のことで心を痛めてくれる。
小学生の頃の俺は、よく女の子と間違えられてたから、近所の子から「おとこおんな〜」なんて言われていた。だけど、その時も俺以上に縁が怒っていたっけ。
それに、中学に上がる前に、俺の母さんが亡くなった時だって……泣けない俺の代わりに泣いてくれて。俺も、釣られて泣けるようになったんだっけ。
たぶん、俺は縁が怒ったり、泣いたり、いろんな感情を出してくれるから、傷ついても、ちゃんと前を向けるようになるんだと思う。一緒になって悲しんでくれたり、苦しんでくれたり、気持ちを共有してくれるから、安心できる。
「……縁、ありがと」
「ありがとうなんか言うな。まだ、守れてねぇんだ」
「えぇ? 十分だよ?」
そう言うと、縁は少し離れるように腕をほどいて、俺をまっすぐ見た。
「どこがだよ。……つーか、当真の友達も、なんで誰も言ってやらねぇんだよ。俺しか気づいてねぇのか?」
「んー……皆、俺と似てるから?」
少し首を傾げながら言ったら、縁は黙り込んだ。
なんかだんだん、顔を顰めて、難しい表情になってきた。
たぶん、俺の友達二人を思い浮かべているんだろう。
友達ができたか心配した縁に初めて会わせた時、縁が「なんか……あれだな? 三人とも小動物みたいだな? ヒヨコに、ハムスターに、リス」と俺たちに向かって言ったのを、未だ鮮明に覚えている。
「あぁ……まあ、あの先輩たちならそうか〜。ほわほわ三人衆だもんなぁ……」
縁は脱力したみたいにそう言うと、もう一度俺を抱きしめた。
「……あー、くそ。でも、当真が、んな扱いされてきたのほんとむかつく。……何が当て馬だ。当真は俺の彼氏だってのに……今まで気づいてなかった自分にも腹立つ」
そんな縁の苛立ちをはらんだ言葉が、静かな室内に落ちていく。
時間が止まったようにしんとして、俺は縁の腕の中で、固まった。
──当真は俺の彼氏だってのに。
その言葉が、頭の中でリフレインする。
瞬きを数回繰り返して、俺はやっと、縁の言葉の意味を理解した。
(え? 待って。俺って……縁の彼氏なの?)
これこそ、俺の中での一大事だ。
当て馬先輩と呼ばれていると知るよりも、ずっと衝撃的だった。
「え……えぇ〰〰〰〰〰〰⁉︎」
気づいた時には、これまで出したことのないくらいの大声で叫んでいた。
でも、無情にも、時間は、空気なんて読んではくれない。俺の叫びがうるさいとでもいうように、昼休みの終わりを告げるチャイムが鳴る。
縁からは「はぁ? なんだよ急にでかい声だして」って言われるだけで、何も聞けないまま、俺は教室に帰る羽目になったのだった。