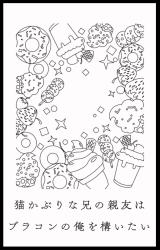昼休みの校庭では、同じクラスの男子たちが元気にサッカーをしている。でも、俺はその輪に加わらず、屋上の手すりに寄り掛かりながら、ぼんやりとその様子を見つめていた。
(縁が「教室で待ってろ」って言ったの、素直に聞いておけばよかったな)
今さら後悔しても遅いのだけど、俺のすぐ隣では、隣のクラスのカップルが痴話喧嘩とやらを繰り広げている。
やれ「浮気した」だの、やれ「ヤキモチ妬かせたかった」だの。キャンキャン吠える小型犬の争いみたいな喧嘩は、どうやら俺に原因があるらしい。
事の発端は、購買の一日三個限定のたまごサンド。
俺は恋愛には興味がないけれど、たまごサンドだけには目がない。
特に購買のたまごサンドは、からし入りのマヨネーズに、黒胡椒が効いたちょっと大人な味がする。一年前の春にその味に出会って以来、俺はすっかり虜になった。
それ以降、俺はたまごサンドをくれる人の頼み事をひとつ、お礼に聞いてあげることにしている。
だから、昼休みに佐々木さんから「購買のたまごサンドあげるからついてきて」と言われたら、断る理由なんてなかった。
言われるまま、屋上までついてきたのだけど、どういうわけか。お団子頭の彼女は自分の彼氏の前で「ほんと有馬くんって、綺麗な顔してるよね」なんて褒めるものだから、二人は喧嘩に発展してしまったのだ。
(……最近、こういうのが多いような? 女子からの頼まれ事の時は、他の男子の前で俺の容姿を褒めてきたり、俺に触ろうとしてきたりしてる気がする)
俺は、女子に興味もなければ、たまごサンドにしか関心がないのに、困ったものだ。
早く喧嘩が終わって欲しいなぁと思いながら、俺は頭上に広がる蒼穹を見上げた。
夏がやって来る前の、この時期の気温は心地良い。
柔らかな風は手持無沙汰な俺に、そっと眠気を運んでくる。あぁ、もうだめ。一応、二人が喧嘩してるからって、我慢していたのだけど、ふわぁっと、思いっきりあくびをこぼしてしまった。
でも、ちらりと横目で二人を見れば、すったもんだの痴話喧嘩はまだ終わりそうにない。
面倒臭いし、もうたまごサンドは諦めた方がいいのかな。仕方ないよね。
なんて考えた俺は、とりあえず、喧嘩をする二人に「ねぇ」と声をかけた。
「もう帰ってもいいかなぁ? たまごサンド貰えないなら、俺、ここにいる意味ないのかなぁって」
名残惜しい気持ちで佐々木さんの手にあるたまごサンドを見ながら、俺は屋内に戻る扉の方を指差した。
すると、佐々木さんの強面の彼氏──たしか、宮下くんが「はぁ?」と唸り声をあげた。
「おい! この状況、お前のせいだって分かってんのかよ!」
怒りの矛先を俺にぶつけるように、彼は鋭い眼光を向けてきた。
俺の通う高校は一応、県内上位の進学校だ。だけど、たまにこういうちょっと荒いタイプの生徒がいる。いわゆる、不良という人たち。佐々木さんの彼氏はまさに、その手の生徒だった。
佐々木さんが慌てて「あっくん! やめてよ!」と、制止しようとしたけれど、彼女の手は乱暴に振り払われた。
そうかと思えば、宮下くんは勢いよく俺の胸元に掴みかかってくる。
「お前、顔が良いからって、舐めてんじゃねぇぞ! ほんとなんでお前みたいな奴が女子にキャーキャー言われてんのか分かんねぇわ!」
宮下くんは、俺の顔に細かい唾を飛ばしながら、怒鳴りつけてきた。
困った。俺の顔が良いかはよく分からない。だけど、どう考えても、俺は巻き込まれただけだ。
それなのに、俺が「えぇ」と口を開いただけで、ガラ悪く「あぁ?」と凄まれてしまう。
この状況を説明したくとも出来そうになくて、泣きたくなってくる。
(うぅ……怖い)
しかも、こういう時に限って、運悪く、屋上には俺たち三人しかいない。今日は暑いわけでもないのに、俺の背中にじわりと汗が滲んできた。
誰にも助けを求められない焦りからか、口を開こうにも、喉が張り付くような感覚がある。
でも、なんとか振り絞ってみれば、「は、はなして」とわずかな声が出た。ただ、情けないことに、目尻に涙が浮かぶという、おまけ付きだ。
そんな俺の様子が、さらに癪に触ったのだろう。
「ほんとむかつく。このヘタレ! 一発殴らせろ! お前の顔、見るだけでむしゃくしゃする!」
俺の胸元を掴む宮下くんの手に、ぐっと力が入るのを感じた。彼が右手で握り拳を作って、腕を振り上げる。その刹那、俺はひいっと息を呑んで、ぎゅっと目を瞑った。
俺は身長こそ一七〇あれど、筋肉のほとんどない鶏ガラ体型だ。だから、殴られてこのままぶっ飛ばされるんだって思っていた。
だけど、いくら身構えても、一向に殴られる衝撃はやって来ない。あれ? それどころか、いつの間にか、俺の胸元にあったはずの手の感覚がなくなっている。
代わりに「あっくん!」と呼ぶ佐々木さんの声と、宮下の「痛ぇよ! 離せ!」という声が俺の鼓膜を震わせた。
「え……何?」
恐る恐る瞼を上げてみれば、横から誰かの逞しい腕が伸びていて、宮下くんの右手首をしっかりと掴んでいた。血管の浮いた手の甲には、見覚えのある黒子が二つ。
腕が伸びている方向を見ると、すぐそこには、縁がいた。
いつの間にか怖くて、唇が震えていた。
でも、もう誰も俺を傷つけられない。だって、縁がいれば安心だ。その安堵感でいっぱいになった俺の目から、ぽろりと涙がこぼれ落ちる。
「うわーん! えにしぃ〜!」
幼なじみの大きな身体に抱きつこうと、手を伸ばした。その刹那、縁は宮下くんの手を離して、すぐに右手で俺の腕を引っ張った。庇うように、俺をその大きな背中で隠してくれる。
一瞬だけ、緊張が走ったような気がした。
でも、縁は見た目に反して、実は人好きする性格だ。
「わーっ! すみません、宮田先輩っ! この食いしん坊がご迷惑かけたみたいで」
縁は人懐っこさを前面に押し出して、宮下くんと思っていた男に頭を下げた。
俺は縁の背中からそっと覗きながら、「え、この人、宮田くんだったの……?」とぽつりと呟く。すると、縁は「今それ言う? ほんと当真はほわほわしてんな」と、俺の方を見て、頭をぽんと撫でてくれる。
そんな俺たちに向けて、宮下くんもとい、宮田くんは「おい」と声を上げた。
再び宮田くんを見れば、彼は右手首を庇うようにさすりながら、今度は縁を睨みつけている。
「なんで久世が出てくるんだよ! ここは二年の校舎だろうが!」
宮田くんは血気盛んに叫ぶ。俺はビクッと身体を震わせたけど、縁は全く動じておらず、しれっとしている。
「いやー、俺たち幼なじみなんすよ。だから、責任持って連れて帰りますね」
「は? 何言って──」
「行くぞ、当真」
縁は宮田くんの話をぶった斬って、俺の肩をがっしりと抱き寄せた。そして、すぐさま、彼らから背を向ける。
俺は戸惑いながら、縁を見上げた。
「え? いいの?」
「こういうのは、逃げるが勝ちだから! 走れ!」
縁のその言葉と同時に、俺は半ば引きずられるように走り出す羽目になった。
背後から「おい待て!」という宮田くんの声が聞こえたけど、走るのに必死で、俺に振り返る余裕なんてない。
でも、縁は違うみたいだ。まるでスリルを楽しむかのように、屋上の扉を開けながら、振り向いた。
「修羅場はお二人で楽しんでーっ!」
そう叫んだ縁の横顔は、笑っている。けど、長いまつ毛に縁取られたその目は、全然笑っていない。
それこそ怖くて、俺の背筋はぞくぞくした。
(縁、物凄く……怒ってる)
だけど、そんな幼馴染のおかげで、俺はようやく息ができたような気がした。