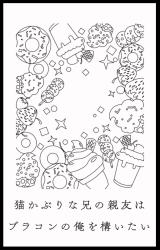俺の幼なじみは、過保護なんだと思う。──それも、ちょっと異常なくらい。
一つ下の幼なじみの久世縁が、俺と同じ高校に入学して、早一ヶ月。小さい頃からスキンシップは多かったけど、ここ最近は人目も気にせず、俺──有馬当真を容赦なく愛でてくる。
五月半ばのこの日も、縁は二年の昇降口前で、俺の薄茶色の髪をせっせと整えてくれていた。
ただ、もうかれこれ五分もこの調子だ。流石に、朝のホームルームの時間が気になってくる。
「縁……もういいよ? 十分、整ってるから」
俺は頭半分も背の高い縁を見上げて、目の前にあるカーディガンの袖をきゅっと引っ張った。
でも、縁は少し、意地悪だ。
「やーだね。納得いかねぇんだもん」
切れ長の目をふっと細めて、やたらと整った男前な顔を俺にぐいっと近づけてくる。口を少し尖らせながら、俺の頭をぐしゃぐしゃと撫でまわした。せっかく整えた髪は、一瞬で台無しになる。
だけど、「えぇ……?」と、戸惑う俺を見て、縁はとにかく楽しそうだった。口元を緩めると再び、骨ばった大きな手でああでもない、こうでもないと俺の髪の毛をいじっていく。
そんな幼なじみの手で、俺の朝はいつも始まる。
今日も、朝から布団を剥ぎ取られるようにして起こされ、寝惚けているうちにシャツを着せられていた。流石に自分でズボンは穿いたけど、紺色のネクタイを締めるのも、カーディガンのボタンを留めるのも、縁にしてもらう始末。そして、登校中に乱れた髪のお直し──という現在に至る。
あまりに縁が世話を焼いてくれるものだから、俺はこのままだと、ダメ人間まっしぐらな気がする。
(でも、あれこれ俺に構うのに、縁の方は校則守ろうとはしないんだよね……)
縁を見れば、ネクタイも締めず、カーディガンのボタンも留めていない。クセのある黒髪から覗く耳には、無骨なピアスがある。
どれも校則違反のはずなのに、先生も風紀委員の生徒も、誰も縁を咎めない。
縁はなんというか、大人っぽいというか、色気があるというか。顔が整いすぎてて、黙ってると冷たく見える。背も物凄く高くて、ちょっと周りが怖がってる気がしてならない。
今も、縁を畏怖するような俺の同級生たちの視線が、遠くからちくちくと刺さっていた。
「縁……皆も見てるし、もうやめよ?」
「はぁ? 何言ってんだよ。むしろ、見せつけてんのー。当真は俺のもんだぞーって」
「なんで」
「そりゃ、当真がほわほわしすぎて心配だからだろ。当真は俺のってわかるようにしときゃ、変なの寄ってこねぇじゃん」
縁はそう言って、俺の頬っぺたをふにっと軽くつまんできた。
そんな縁とはマンションのお隣同士で、赤ちゃんの頃からの付き合いだ。俺の方が一学上だけど、ほとんど一緒に育ったと言っても、過言じゃない。だから、縁は俺の扱いがこんな感じなんだと思う。
でも、今じゃ、考えられないけど、小さい頃は俺の方が縁の方を引っ張っていた。俺はもう少し年上らしくしたいんだけど、これじゃあ、どっちが年上なのか分からなくなる。
「そんなに、俺って頼りない……?」
否定してくれることを願いつつ、俺は縁の目をじっと見つめた。
すると、縁は目尻をふっと下げて「まぁ、当真は十六歳児だからな」と、言ってのける。
頭の中で一瞬、じゅうろくさいじってなんだ? と思ったけど、すぐに馬鹿にされているのが分かった。
十六歳児って、俺が幼児みたいってことだ。
「ひどい」
俺はむすっと頬を膨らませて、縁のたくましい腕を軽く一発、ぽこっと殴った。
「あははっ。悪い悪い。でも、まぁ、そこが当真の良いところだから」
「ほんとに思ってる?」
「思ってるよ。……当真のそういうほわんとしたとこ、俺はめちゃくちゃ好き。たまんねぇよ」
縁は時々、ストレートに「好き」という言葉を口にして、俺を愛おしそうに見てくる。
俺も縁のことが大好きだから別にいいんだけど、その言葉も、視線も、ちょっとだけむずむずする。
でも、毎度縁は「当真は? 俺のことどう思ってんの?」なんて聞いてくる。だから、仕方なく俺も「縁のこと大好きだよ」って言うようにしている。
少し照れるし、幼なじみにこんなこと毎日言うものかな? って思うけど、本当のことだし。
今日もいつもと同じように「俺も縁のこと、大好きだよ」って伝えたら、縁は弾けるような笑顔を浮かべてくれた。
「じゃ、そろそろ行くわ。昼休みは教室迎え行くから、ちゃんと良い子にして待ってろよ?」
縁は満足げに言うと、せっかく整えていたはずの俺の髪をまた、くしゃりと撫でてきた。毎度お馴染みの謎行動に俺は思わず、くすっと笑って「わかったよ」と返事をする。
そんな何でもないやりとり──だったはずなのに、縁は急にばっと顔を上げた。
靴箱の方を見つめる目は、さっきまでの柔らかさはどこにもない。何かを、睨みつけているように見えた。
そんな縁が心配になって、俺は「縁?」と、名前を呼んでいた。
縁は「……あぁ、悪い」と言って、何事もなかったかのように俺から手を離す。
「じゃあな。またあとで」
そう言って縁は、俺の額にちゅっと軽く口づけてきた。
この一ヶ月で、縁のスキンシップは増した。だけど、縁からおでこにキスをされるなんて、今日が初めてのことで、俺の頭は混乱し始めた。
(俺たちって……幼なじみ、だよね?)
縁はそんな俺を見てにやりと笑ってから、くるっと背中を向けた。そしてそのまま、俺を残して、隣の校舎へ歩いていく。
その背中が、ほんの少し慌てたように見えるのは、俺の気のせいだろうか。
立ち尽くす俺の髪を、北国の暑くもなく、寒くもない生温い五月の風がさらう。ただ風が吹いているだけなのに、俺の胸はざわついて仕方がない。
早く教室に行かなきゃって、思う。それなのに、いつになく縁のことが気になって。
視界から姿がいなくなるまで、俺は過保護な幼なじみの背中をじっと眺めていた。
一つ下の幼なじみの久世縁が、俺と同じ高校に入学して、早一ヶ月。小さい頃からスキンシップは多かったけど、ここ最近は人目も気にせず、俺──有馬当真を容赦なく愛でてくる。
五月半ばのこの日も、縁は二年の昇降口前で、俺の薄茶色の髪をせっせと整えてくれていた。
ただ、もうかれこれ五分もこの調子だ。流石に、朝のホームルームの時間が気になってくる。
「縁……もういいよ? 十分、整ってるから」
俺は頭半分も背の高い縁を見上げて、目の前にあるカーディガンの袖をきゅっと引っ張った。
でも、縁は少し、意地悪だ。
「やーだね。納得いかねぇんだもん」
切れ長の目をふっと細めて、やたらと整った男前な顔を俺にぐいっと近づけてくる。口を少し尖らせながら、俺の頭をぐしゃぐしゃと撫でまわした。せっかく整えた髪は、一瞬で台無しになる。
だけど、「えぇ……?」と、戸惑う俺を見て、縁はとにかく楽しそうだった。口元を緩めると再び、骨ばった大きな手でああでもない、こうでもないと俺の髪の毛をいじっていく。
そんな幼なじみの手で、俺の朝はいつも始まる。
今日も、朝から布団を剥ぎ取られるようにして起こされ、寝惚けているうちにシャツを着せられていた。流石に自分でズボンは穿いたけど、紺色のネクタイを締めるのも、カーディガンのボタンを留めるのも、縁にしてもらう始末。そして、登校中に乱れた髪のお直し──という現在に至る。
あまりに縁が世話を焼いてくれるものだから、俺はこのままだと、ダメ人間まっしぐらな気がする。
(でも、あれこれ俺に構うのに、縁の方は校則守ろうとはしないんだよね……)
縁を見れば、ネクタイも締めず、カーディガンのボタンも留めていない。クセのある黒髪から覗く耳には、無骨なピアスがある。
どれも校則違反のはずなのに、先生も風紀委員の生徒も、誰も縁を咎めない。
縁はなんというか、大人っぽいというか、色気があるというか。顔が整いすぎてて、黙ってると冷たく見える。背も物凄く高くて、ちょっと周りが怖がってる気がしてならない。
今も、縁を畏怖するような俺の同級生たちの視線が、遠くからちくちくと刺さっていた。
「縁……皆も見てるし、もうやめよ?」
「はぁ? 何言ってんだよ。むしろ、見せつけてんのー。当真は俺のもんだぞーって」
「なんで」
「そりゃ、当真がほわほわしすぎて心配だからだろ。当真は俺のってわかるようにしときゃ、変なの寄ってこねぇじゃん」
縁はそう言って、俺の頬っぺたをふにっと軽くつまんできた。
そんな縁とはマンションのお隣同士で、赤ちゃんの頃からの付き合いだ。俺の方が一学上だけど、ほとんど一緒に育ったと言っても、過言じゃない。だから、縁は俺の扱いがこんな感じなんだと思う。
でも、今じゃ、考えられないけど、小さい頃は俺の方が縁の方を引っ張っていた。俺はもう少し年上らしくしたいんだけど、これじゃあ、どっちが年上なのか分からなくなる。
「そんなに、俺って頼りない……?」
否定してくれることを願いつつ、俺は縁の目をじっと見つめた。
すると、縁は目尻をふっと下げて「まぁ、当真は十六歳児だからな」と、言ってのける。
頭の中で一瞬、じゅうろくさいじってなんだ? と思ったけど、すぐに馬鹿にされているのが分かった。
十六歳児って、俺が幼児みたいってことだ。
「ひどい」
俺はむすっと頬を膨らませて、縁のたくましい腕を軽く一発、ぽこっと殴った。
「あははっ。悪い悪い。でも、まぁ、そこが当真の良いところだから」
「ほんとに思ってる?」
「思ってるよ。……当真のそういうほわんとしたとこ、俺はめちゃくちゃ好き。たまんねぇよ」
縁は時々、ストレートに「好き」という言葉を口にして、俺を愛おしそうに見てくる。
俺も縁のことが大好きだから別にいいんだけど、その言葉も、視線も、ちょっとだけむずむずする。
でも、毎度縁は「当真は? 俺のことどう思ってんの?」なんて聞いてくる。だから、仕方なく俺も「縁のこと大好きだよ」って言うようにしている。
少し照れるし、幼なじみにこんなこと毎日言うものかな? って思うけど、本当のことだし。
今日もいつもと同じように「俺も縁のこと、大好きだよ」って伝えたら、縁は弾けるような笑顔を浮かべてくれた。
「じゃ、そろそろ行くわ。昼休みは教室迎え行くから、ちゃんと良い子にして待ってろよ?」
縁は満足げに言うと、せっかく整えていたはずの俺の髪をまた、くしゃりと撫でてきた。毎度お馴染みの謎行動に俺は思わず、くすっと笑って「わかったよ」と返事をする。
そんな何でもないやりとり──だったはずなのに、縁は急にばっと顔を上げた。
靴箱の方を見つめる目は、さっきまでの柔らかさはどこにもない。何かを、睨みつけているように見えた。
そんな縁が心配になって、俺は「縁?」と、名前を呼んでいた。
縁は「……あぁ、悪い」と言って、何事もなかったかのように俺から手を離す。
「じゃあな。またあとで」
そう言って縁は、俺の額にちゅっと軽く口づけてきた。
この一ヶ月で、縁のスキンシップは増した。だけど、縁からおでこにキスをされるなんて、今日が初めてのことで、俺の頭は混乱し始めた。
(俺たちって……幼なじみ、だよね?)
縁はそんな俺を見てにやりと笑ってから、くるっと背中を向けた。そしてそのまま、俺を残して、隣の校舎へ歩いていく。
その背中が、ほんの少し慌てたように見えるのは、俺の気のせいだろうか。
立ち尽くす俺の髪を、北国の暑くもなく、寒くもない生温い五月の風がさらう。ただ風が吹いているだけなのに、俺の胸はざわついて仕方がない。
早く教室に行かなきゃって、思う。それなのに、いつになく縁のことが気になって。
視界から姿がいなくなるまで、俺は過保護な幼なじみの背中をじっと眺めていた。