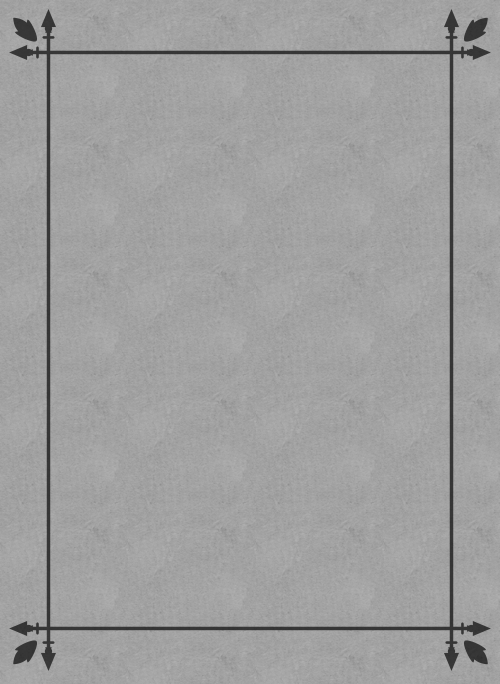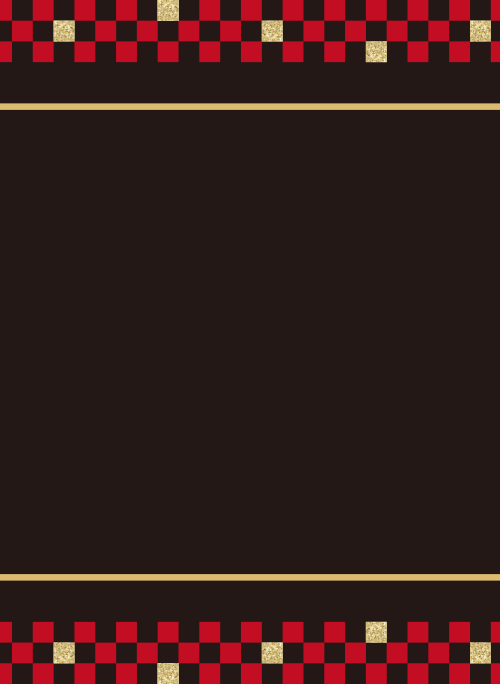夕暮れの通学路は、茜色の光がゆったりと電柱の影を伸ばし、どこか一日の終わりの匂いを漂わせていた。
悠は鞄を背中に軽く揺らしながら、はぁ、と深いため息をこぼした。
その吐息さえ、今日一日の重たさを象徴しているようだ。
(今日は……本当に色々ありすぎた……)
(弁当の送り主が神谷だったって分かって……)
(しかも、遼って名前呼びまでお願いされて……)
(あれ何?そういう……なんというか、距離感?)
(いや、でも遼だし……あの人、クールで何考えているか意味わからんとこあるし……)
(いやにしても……やっぱ俺、キャパオーバー……)
心臓のあたりだけが、ずっと騒がしい。
気温も風も穏やかで、景色も綺麗なのに、心の中だけはざわついて仕方ない。
(……帰ったら、晃にも何か言われんのかな……)
(勢いよく隣の家から出てきて、神谷と何あった?とか……)
(ああもう、考えたくない……)
そんなときだった。
「――裏切ったの!?」
鋭い声が、まるで空気を裂くように背後から飛んできた。
「えっ――」
振り返るよりも先に、風を切る音が耳を刺した。
視界に飛び込んできたのは、涙と怒りに濡れた瞳をした女子。
その手には、光を反射してきらりと光る――ハサミ。
「は……?」
理解よりも恐怖が勝った。
足が自然と後ろに下がる。
女子はそのまま悠に飛びかかってきた。
「ちょっ――危なっ!」
反射的に身を引いた瞬間、心臓がひゅっと冷たくなる感覚。
背中に汗が一気に吹き出す。
(なんで!?誰!?俺、なんかした!?いや絶対してねぇよ!?)
そんな混乱の中――
「危ない!」
聞き慣れた、低く鋭い声。
ドッと風が巻き起こり、悠の横を影が駆け抜ける。
気づけば女子の手はぐっと後ろへねじられ、後ろから押さえ込まれていた。
「離せッ……ッ痛い、やめ……!」
「暴れんな。危ないから」
女子を制圧していたのは――神谷遼だった。
「り、遼……!?」
遼の表情は、見たことがないほど冷ややかだった。
その鋭さに悠は一瞬、息を呑む。
「誰?」
押さえつけられながら、女子の視線が悠へ突き刺さる。
「……えっ?いやいや、お前こそ誰だわ!!」
もう叫んだ。叫ぶしかなかった。
恐怖と混乱が一気に口から漏れる。
そのとき――
「悠!?今の悲鳴、お前か!?」
ばたばたと駆け寄ってくる足音の塊。
幼馴染の佐伯晃、その後ろには先生。
さらに、通報によるパトカーの赤色灯が遠くで回っている。
「おい、何が……って、美咲……?」
晃の声色が、一気に変わる。
怒りでも驚きでもない、もっと複雑な響きを帯びていた。
女子――美咲は唇を震わせ、視線が揺れた。
「……え?晃くん……?」
その瞬間、表情がばらばらと崩れ落ちる。
晃が息をのんで、きつく言い放った。
「美咲、お前……まさか悠を俺だと思ったのか?」
「……だって……後ろ姿が……似てて……カーディガン……あなたがいつも……それに……香水も……一緒、で……」
(カーディガン……晃が貸してくれたやつ……香り……さっき晃にかけられたから……?うそだろ……それで刺されかけたの……?)
美咲は悠と晃を見比べ、顔を青くして固まっていく。
「悠!すまん!俺がモテるばっかりに!!」
「知らん!!知らんがな!?なんで俺が刺されかけてんの!?」
「美咲にさ、告白されて付き合ったら、思ってた以上に……その……メンヘラでさ……!」
「知るか!!元カノの処理くらい責任持て!!佐伯晃!!」
「悠!ほんと悪かったって!俺もさすがに心臓キュッてなったわ!」
「俺はリアルに死ぬかと思ったよ!!」
「いやだってさ、あいつ、付き合って二日目で家の前まで来るようになってさ……晃くんが忘れないようにマーキング♡って俺の服借りるし!」
「うわぁ……やっぱりお前の見る目が問題じゃん!もう、理由はわかった!怖い!でも俺を巻き込むな!!」
「後ろ姿似てんだよ、お前」
「お前が勝手に俺に自分のカーディガン着せて、香水吹きかけてきたんだろ!!」
その後の事情聴取と先生+警察の確認により、誤解による暴走という事で処理され、事件はひとまず収束した。
遼は最後まで冷静に対応し、美咲を警察に引き渡したあと、黙って悠のもとへ歩み寄る。
「家まで送る」
その声音は淡々としていたが、拒否を許さない強さがあった。
「え……あ、いや……」
悠が戸惑っても、遼は歩き出した。
歩幅が自然と悠に合わせられていて、断るタイミングさえ奪われる。
夕暮れが夜に溶け始め、街灯が一つずつ点く。
ふたりの影が並んで伸びていく。
しばらく沈黙が続き、悠が小さく口を開いた。
「……その……さ。さっきは……本当に、ありがとう。助けてくれて……」
遼は横目でちらりと悠を見て、静かに言った。
「悠がいつもこの道通るの、知ってるから」
「……え?」
「たまたま悠の後ろを歩いてたら、変な女がいたんだよ。お前の方、ずっと見てて……嫌な予感した」
「そんな……すごい偶然……」
「偶然じゃなかったら?」
遼の声は静かで、深い。
胸の奥にゆっくり沈んでいく。
(……なんでそんなに知ってるの?)
(俺の通学路とか……家の方向とか……)
(そんなの、普通、知ら……)
(いや……友達だから?)
(友達って、こんなに……守ってくれるもんなの?)
戸惑いで足元がぐらつく。
そんな悠の表情を見て、遼が急に思い出したように声を上げる。
「あ、そうだ。香水」
「え……?」
遼は突然悠の肩をつかみ、ぐっと引き寄せた。
距離が近い。近すぎて心臓が変な動きをする。
次の瞬間、遼の手からスプレーの音がカチッと響いた。
ふわりと、落ち着く香りが悠の首元に落ちる。
「っ……ちょ、なに……?」
「佐伯の匂い、まだ残ってたから。これで間違えられない」
遼は少しだけ視線をそらす。
「……勝手にかけて、ごめん」
悠は一度瞬きをしたあと、首元に触れた。
手にかすかについた香りをかいで、ふっと笑った。
「ううん。ありがとう。……好きだよ。こっちの香りの方が」
遼の動きがぴたりと止まる。
目がわずかに開かれ、それから、ゆっくりと柔らかな表情に変わる。
頬がほんの少し上がった。
「……そう」
その声は控えめなのに、悠の胸の奥まで温かく染みていくほど、嬉しそうだった。
ふたりはそのまま歩き続ける。
街灯が変わるたび、影が寄り添うように重なっていく。
(……なんでだろ。こんなに……安心するなんて)
香水の香りと夜風に包まれながら、悠の胸には、はじめての守られている実感が、静かに、確かに灯った。
悠は鞄を背中に軽く揺らしながら、はぁ、と深いため息をこぼした。
その吐息さえ、今日一日の重たさを象徴しているようだ。
(今日は……本当に色々ありすぎた……)
(弁当の送り主が神谷だったって分かって……)
(しかも、遼って名前呼びまでお願いされて……)
(あれ何?そういう……なんというか、距離感?)
(いや、でも遼だし……あの人、クールで何考えているか意味わからんとこあるし……)
(いやにしても……やっぱ俺、キャパオーバー……)
心臓のあたりだけが、ずっと騒がしい。
気温も風も穏やかで、景色も綺麗なのに、心の中だけはざわついて仕方ない。
(……帰ったら、晃にも何か言われんのかな……)
(勢いよく隣の家から出てきて、神谷と何あった?とか……)
(ああもう、考えたくない……)
そんなときだった。
「――裏切ったの!?」
鋭い声が、まるで空気を裂くように背後から飛んできた。
「えっ――」
振り返るよりも先に、風を切る音が耳を刺した。
視界に飛び込んできたのは、涙と怒りに濡れた瞳をした女子。
その手には、光を反射してきらりと光る――ハサミ。
「は……?」
理解よりも恐怖が勝った。
足が自然と後ろに下がる。
女子はそのまま悠に飛びかかってきた。
「ちょっ――危なっ!」
反射的に身を引いた瞬間、心臓がひゅっと冷たくなる感覚。
背中に汗が一気に吹き出す。
(なんで!?誰!?俺、なんかした!?いや絶対してねぇよ!?)
そんな混乱の中――
「危ない!」
聞き慣れた、低く鋭い声。
ドッと風が巻き起こり、悠の横を影が駆け抜ける。
気づけば女子の手はぐっと後ろへねじられ、後ろから押さえ込まれていた。
「離せッ……ッ痛い、やめ……!」
「暴れんな。危ないから」
女子を制圧していたのは――神谷遼だった。
「り、遼……!?」
遼の表情は、見たことがないほど冷ややかだった。
その鋭さに悠は一瞬、息を呑む。
「誰?」
押さえつけられながら、女子の視線が悠へ突き刺さる。
「……えっ?いやいや、お前こそ誰だわ!!」
もう叫んだ。叫ぶしかなかった。
恐怖と混乱が一気に口から漏れる。
そのとき――
「悠!?今の悲鳴、お前か!?」
ばたばたと駆け寄ってくる足音の塊。
幼馴染の佐伯晃、その後ろには先生。
さらに、通報によるパトカーの赤色灯が遠くで回っている。
「おい、何が……って、美咲……?」
晃の声色が、一気に変わる。
怒りでも驚きでもない、もっと複雑な響きを帯びていた。
女子――美咲は唇を震わせ、視線が揺れた。
「……え?晃くん……?」
その瞬間、表情がばらばらと崩れ落ちる。
晃が息をのんで、きつく言い放った。
「美咲、お前……まさか悠を俺だと思ったのか?」
「……だって……後ろ姿が……似てて……カーディガン……あなたがいつも……それに……香水も……一緒、で……」
(カーディガン……晃が貸してくれたやつ……香り……さっき晃にかけられたから……?うそだろ……それで刺されかけたの……?)
美咲は悠と晃を見比べ、顔を青くして固まっていく。
「悠!すまん!俺がモテるばっかりに!!」
「知らん!!知らんがな!?なんで俺が刺されかけてんの!?」
「美咲にさ、告白されて付き合ったら、思ってた以上に……その……メンヘラでさ……!」
「知るか!!元カノの処理くらい責任持て!!佐伯晃!!」
「悠!ほんと悪かったって!俺もさすがに心臓キュッてなったわ!」
「俺はリアルに死ぬかと思ったよ!!」
「いやだってさ、あいつ、付き合って二日目で家の前まで来るようになってさ……晃くんが忘れないようにマーキング♡って俺の服借りるし!」
「うわぁ……やっぱりお前の見る目が問題じゃん!もう、理由はわかった!怖い!でも俺を巻き込むな!!」
「後ろ姿似てんだよ、お前」
「お前が勝手に俺に自分のカーディガン着せて、香水吹きかけてきたんだろ!!」
その後の事情聴取と先生+警察の確認により、誤解による暴走という事で処理され、事件はひとまず収束した。
遼は最後まで冷静に対応し、美咲を警察に引き渡したあと、黙って悠のもとへ歩み寄る。
「家まで送る」
その声音は淡々としていたが、拒否を許さない強さがあった。
「え……あ、いや……」
悠が戸惑っても、遼は歩き出した。
歩幅が自然と悠に合わせられていて、断るタイミングさえ奪われる。
夕暮れが夜に溶け始め、街灯が一つずつ点く。
ふたりの影が並んで伸びていく。
しばらく沈黙が続き、悠が小さく口を開いた。
「……その……さ。さっきは……本当に、ありがとう。助けてくれて……」
遼は横目でちらりと悠を見て、静かに言った。
「悠がいつもこの道通るの、知ってるから」
「……え?」
「たまたま悠の後ろを歩いてたら、変な女がいたんだよ。お前の方、ずっと見てて……嫌な予感した」
「そんな……すごい偶然……」
「偶然じゃなかったら?」
遼の声は静かで、深い。
胸の奥にゆっくり沈んでいく。
(……なんでそんなに知ってるの?)
(俺の通学路とか……家の方向とか……)
(そんなの、普通、知ら……)
(いや……友達だから?)
(友達って、こんなに……守ってくれるもんなの?)
戸惑いで足元がぐらつく。
そんな悠の表情を見て、遼が急に思い出したように声を上げる。
「あ、そうだ。香水」
「え……?」
遼は突然悠の肩をつかみ、ぐっと引き寄せた。
距離が近い。近すぎて心臓が変な動きをする。
次の瞬間、遼の手からスプレーの音がカチッと響いた。
ふわりと、落ち着く香りが悠の首元に落ちる。
「っ……ちょ、なに……?」
「佐伯の匂い、まだ残ってたから。これで間違えられない」
遼は少しだけ視線をそらす。
「……勝手にかけて、ごめん」
悠は一度瞬きをしたあと、首元に触れた。
手にかすかについた香りをかいで、ふっと笑った。
「ううん。ありがとう。……好きだよ。こっちの香りの方が」
遼の動きがぴたりと止まる。
目がわずかに開かれ、それから、ゆっくりと柔らかな表情に変わる。
頬がほんの少し上がった。
「……そう」
その声は控えめなのに、悠の胸の奥まで温かく染みていくほど、嬉しそうだった。
ふたりはそのまま歩き続ける。
街灯が変わるたび、影が寄り添うように重なっていく。
(……なんでだろ。こんなに……安心するなんて)
香水の香りと夜風に包まれながら、悠の胸には、はじめての守られている実感が、静かに、確かに灯った。