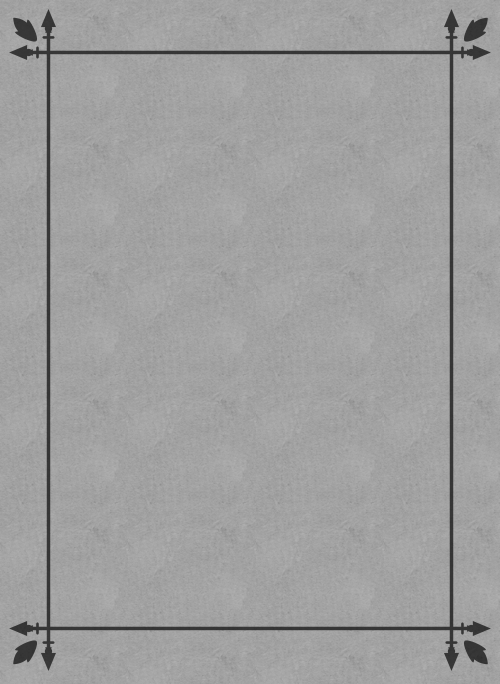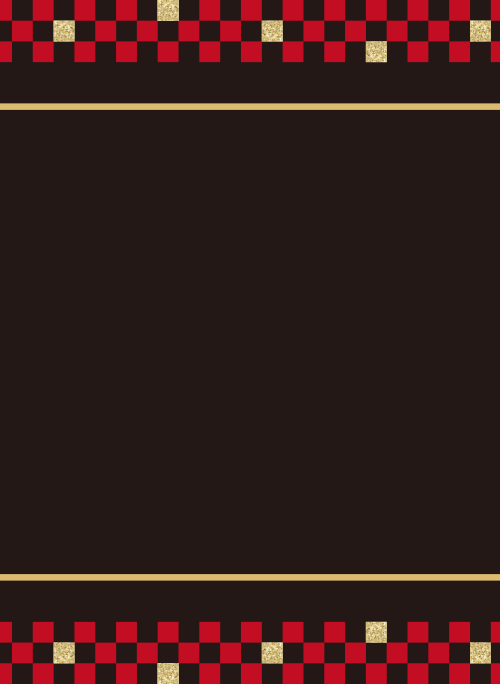「悠、お前……本当に作るつもりなのか?」
帰り道。
悠の背後に立つ遼が、少し呆れたように眉を下げて問いかけてきた。
振り返ると、遼は腕を組んで、まるで料理番組の審査員みたいな顔をしている。
「作るよ。だって……次は俺の番だろ」
悠は緊張をごまかすみたいに、視線を電柱の方へ向けた。
(言っちゃった……!言ったけど……うわ、なんか恥ずかしい……!)
「悠って、不器用なんだろ?無理しなくてもいいって」
「俺がやりたいの!」
はっきり言うと、遼が一瞬だけ目を丸くした。
その反応が妙に可愛くて――いや、可愛いって思った時点で、自分、どうかしている。
そして次の瞬間。
遼の口元に、ゆるい、柔らかい笑みが落ちた。
「……期待してる」
悠の心臓が、跳ねるだけじゃなくて爆ぜた。
(や……やば……その言い方、イケメン過ぎるだろ……期待してるって……)
(そんなの言われたら……がんばるしかないじゃんか……!)
そして――数日後。
机の中には、もう弁当はなかった。
あのそっと置かれた布の温もりも、付箋のメッセージも、そこにはない。
(……なくなったんだよな。分かってる。毎朝、届けてくれるようになったし)
(それに、今日は俺が作るって言ったんだし。でも……ちょっと、寂しい……かな)
そんなことを考えていると――
「悠」
名前を呼ばれるだけで、身体がびくっと跳ねた。
昼休みになると、まるで自然の流れみたいに遼が悠の机の脇に立っている。
「今日も一緒に食べよう」
落とされた声は静かで、不思議とあたたかい。
(……ずるいなぁ。こんな風に言われたら、断れないって)
「……うん」
風が通り抜ける屋上。
空は澄んで、土の匂いがひゅうっと頬を撫でる。
「……ここ、いいよな。人も来ないし」
「うん……落ち着く」
ふたりだけの昼休み。
悠は深呼吸して、弁当袋をそっと差し出した。
ほんの少し震える指を、遼が優しく見下ろす。
「宣言通り、今日は俺が作った」
言い終えた瞬間、心臓がぎゅっと痛くなるくらい跳ねた。
(あああ……言っちゃった……!もう後戻りできない……!)
遼は弁当箱を開き、しばらく無言のまま眺めていた。
その沈黙の長さに、悠の背中から冷や汗がにじむ。
不格好なおかず。
形のいびつなハンバーグ。
焼き色に微妙なムラのある卵焼き。
それでも――全部、遼のために作った。
「……」
「わ、笑うなよ?練習したんだから……!」
「笑ってない」
遼は静かに箸を取る。
ぎこちなく並んだ卵焼きをひとつ、口へ運んだ。
そして――
「……うまい」
短く、それでも確かに。
「ほんと?」
「ほんとだよ」
どこまでもまっすぐで、嘘の混じらない声。
悠は一瞬で頬が熱くなる。
(やばい……なんでそんな、普通に褒めてくるの……)
(もう……ほんと……好きになっちゃうだろ……)
遼は弁当箱を見下ろしながら、ほのかに嬉しそうに微笑んだ。
「こうやって食べるの、いいな」
「……そう?」
「うん。……なんか、落ち着く」
悠は風に髪を揺らしながら、照れくさく目を細める。
そして、ぽつり。
「でもさ。次は――一緒に作ろ」
遼の手が止まった。
そのままゆっくりと顔を上げる。
視線が絡んだ瞬間、胸がきゅっと縮まる。
「……うん。ふたり分、な」
その言葉の優しさに、悠は目を瞬いた。
(あ……やっぱり……この人の隣にいたいって、思っちゃうんだよな……)
屋上の風がふたりの間をゆっくりと通り抜ける。
まるで「これから」を祝福するみたいに。
ひとりで食べる弁当じゃない。
ひとりで作る弁当でもない。
これからの昼休みは――
ふたりで作って、ふたりで食べるものになる。
陽に照らされながら、悠はそっと目を細めた。
(……幸せって、こういうことなんだな)
ふたりの距離は、もう隠す必要なんてない。
屋上の空だけが、それを静かに見守っていた。
帰り道。
悠の背後に立つ遼が、少し呆れたように眉を下げて問いかけてきた。
振り返ると、遼は腕を組んで、まるで料理番組の審査員みたいな顔をしている。
「作るよ。だって……次は俺の番だろ」
悠は緊張をごまかすみたいに、視線を電柱の方へ向けた。
(言っちゃった……!言ったけど……うわ、なんか恥ずかしい……!)
「悠って、不器用なんだろ?無理しなくてもいいって」
「俺がやりたいの!」
はっきり言うと、遼が一瞬だけ目を丸くした。
その反応が妙に可愛くて――いや、可愛いって思った時点で、自分、どうかしている。
そして次の瞬間。
遼の口元に、ゆるい、柔らかい笑みが落ちた。
「……期待してる」
悠の心臓が、跳ねるだけじゃなくて爆ぜた。
(や……やば……その言い方、イケメン過ぎるだろ……期待してるって……)
(そんなの言われたら……がんばるしかないじゃんか……!)
そして――数日後。
机の中には、もう弁当はなかった。
あのそっと置かれた布の温もりも、付箋のメッセージも、そこにはない。
(……なくなったんだよな。分かってる。毎朝、届けてくれるようになったし)
(それに、今日は俺が作るって言ったんだし。でも……ちょっと、寂しい……かな)
そんなことを考えていると――
「悠」
名前を呼ばれるだけで、身体がびくっと跳ねた。
昼休みになると、まるで自然の流れみたいに遼が悠の机の脇に立っている。
「今日も一緒に食べよう」
落とされた声は静かで、不思議とあたたかい。
(……ずるいなぁ。こんな風に言われたら、断れないって)
「……うん」
風が通り抜ける屋上。
空は澄んで、土の匂いがひゅうっと頬を撫でる。
「……ここ、いいよな。人も来ないし」
「うん……落ち着く」
ふたりだけの昼休み。
悠は深呼吸して、弁当袋をそっと差し出した。
ほんの少し震える指を、遼が優しく見下ろす。
「宣言通り、今日は俺が作った」
言い終えた瞬間、心臓がぎゅっと痛くなるくらい跳ねた。
(あああ……言っちゃった……!もう後戻りできない……!)
遼は弁当箱を開き、しばらく無言のまま眺めていた。
その沈黙の長さに、悠の背中から冷や汗がにじむ。
不格好なおかず。
形のいびつなハンバーグ。
焼き色に微妙なムラのある卵焼き。
それでも――全部、遼のために作った。
「……」
「わ、笑うなよ?練習したんだから……!」
「笑ってない」
遼は静かに箸を取る。
ぎこちなく並んだ卵焼きをひとつ、口へ運んだ。
そして――
「……うまい」
短く、それでも確かに。
「ほんと?」
「ほんとだよ」
どこまでもまっすぐで、嘘の混じらない声。
悠は一瞬で頬が熱くなる。
(やばい……なんでそんな、普通に褒めてくるの……)
(もう……ほんと……好きになっちゃうだろ……)
遼は弁当箱を見下ろしながら、ほのかに嬉しそうに微笑んだ。
「こうやって食べるの、いいな」
「……そう?」
「うん。……なんか、落ち着く」
悠は風に髪を揺らしながら、照れくさく目を細める。
そして、ぽつり。
「でもさ。次は――一緒に作ろ」
遼の手が止まった。
そのままゆっくりと顔を上げる。
視線が絡んだ瞬間、胸がきゅっと縮まる。
「……うん。ふたり分、な」
その言葉の優しさに、悠は目を瞬いた。
(あ……やっぱり……この人の隣にいたいって、思っちゃうんだよな……)
屋上の風がふたりの間をゆっくりと通り抜ける。
まるで「これから」を祝福するみたいに。
ひとりで食べる弁当じゃない。
ひとりで作る弁当でもない。
これからの昼休みは――
ふたりで作って、ふたりで食べるものになる。
陽に照らされながら、悠はそっと目を細めた。
(……幸せって、こういうことなんだな)
ふたりの距離は、もう隠す必要なんてない。
屋上の空だけが、それを静かに見守っていた。