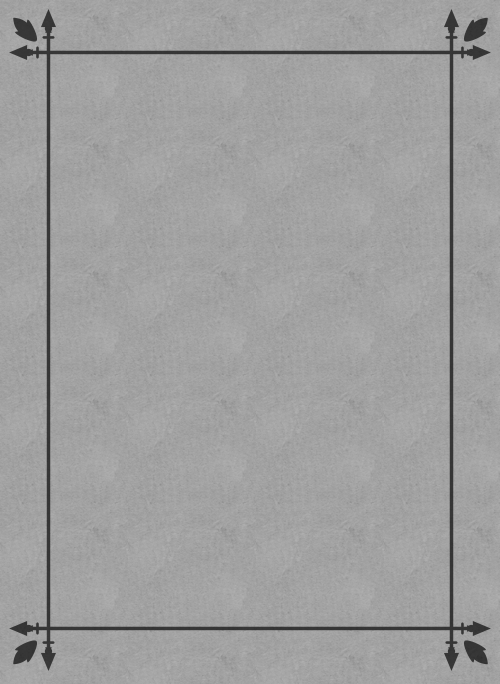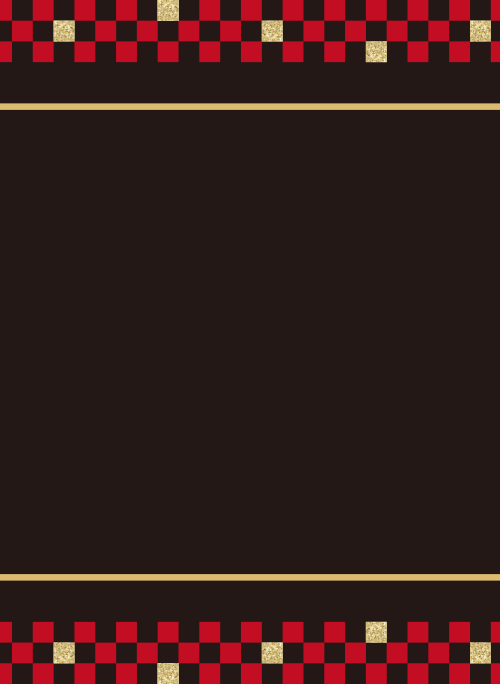朝の空気は、少しだけひんやりしていて、吸い込むたび胸の奥がきゅっと縮む。普段なら「眠い」で終わるはずの時間帯なのに、今日は心臓の鼓動のほうがずっと存在感を主張してくる。
(落ち着け、落ち着け……。昨日の告白は夢じゃない。ちゃんと覚えてる。遼が……俺のことを――)
そのとき。
家の呼び鈴が控えめに、でもはっきりと鳴った。
「……こんな時間に誰?」
胸が跳ねる。予感というより、確信に近いなにか。
恐る恐るドアを開けると、淡い朝光のなか、遼がまっすぐ立っていた。
「……遼?」
制服の襟元がいつもより整っていて、髪も少し湿っている。家を出るまえに急いで整えたのがわかる。そんな些細な部分すら、今日の特別を証明していた。
そして遼は手に弁当袋を持っていた。
「はい、これ」
その声は、昨日告白した人の声で。
俺の胸の奥にまで届く、低く穏やかな響き。
「わ、わざわざ……ありがとう」
受け取った瞬間、指先が触れる。微かな体温に、呼吸が揺れた。
(手渡し……やば。やばいやばい。これ、直接渡されるとか……心臓に悪い……)
昨日のあの夕陽の屋上から、まだ気持ちが現実世界に追いついていないのに。目の前の遼が当たり前みたいに俺の家に来て、当たり前みたいに弁当を渡してくる。
遼は口元だけで、ほんの少し笑った。
「今日からは、一緒に学校に行こう」
どくん、と胸が危険な音を立てた。
(いや……いやいやいや、普通のこと……?いや普通じゃないから!)
(告白翌日にこれって……!心の準備、まったく……!)
靴を履きながら、指先が震えているのが自分でも分かる。遼はそんな俺の様子を見ていたらしい。
通学路に出たところで、ふと思い出したように言った。
「……もう隠さなくていいんだな」
「え?」
「朝早く学校に行って、悠の引き出しに弁当を入れなくていい」
その言い方が、なんだか名残惜しそうで、でも幸せを含ませていて。
(ああ……本当に、遼が……作ってくれてたんだ……)
胸の奥がじわっと熱くなった。
「あ、うん……。直接渡されるってだけで緊張してるけど……その、一緒に登校するのも……」
そこで遼が、少し驚いたように眉を下げる。
「緊張、してるの?」
「してるって……!」
喉に何かつっかえた。
遼の目は細く優しくなっていて、俺の反応を楽しんでいるみたいで、なおさら顔が熱い。
二人で坂道を並んで歩く。
足音が重なるだけで、妙に共同生活感があって、胸がくすぐったい。
(待って……これなんか……)
(朝、一緒に登校って……カップルってこんな感じじゃない……?)
(無理……死ぬ……)
道端の影がふたり分並ぶだけで、胸の奥が溶けそうだった。
学校に着くまでの時間なんて、たった十数分のはずなのに、すべてが初めての感情で満たされていて、息がうまく吸えない。
そして――昼休み。
窓から差し込む光が柔らかくて、世界の輪郭がちょっとだけぼやける。
教室の喧騒が、いつもの何倍も遠く感じた。
二人並んで弁当を広げるだけで、胸の奥がぎゅっと熱い。
「……やっぱり、うまい」
言った瞬間、遼の眉がゆるむ。
「そりゃよかった」
その笑顔が眩しくて、視界がふわっと明るくなる。
(やめろよ……そんな嬉しそうな顔……。俺、どう反応したらいいかわかんねえよ……)
でも、次の瞬間、ふっと二人の間に笑いがこぼれた。
「なんか……変な感じだな」
「うん……。でも悪くない」
向かい合わせの距離感がくすぐったくて、逆に落ち着く。
弁当を食べ終わるころ、俺は思い切って聞いてみた。
「でもさ……朝も夕方も送ってくれるの、大変じゃない?無理してない?」
遼は、間髪入れずに答えた。
「そんなことないよ」
「いや、でも……ほら……いろいろ……」
「俺の家、悠の家の少し先だし」
「……え?」
箸を置く手が止まる。
「え、ちょっと待って。通り道……だったってこと?」
遼は当然のようにうなずく。
「知らなかった?ずっとそうだよ」
「し、知らないよ!初耳なんだけど!」
(なんでだよ!もっと早く言えよ!気を使って毎回遠回りしてるんじゃないかって、昨日までずっと思ってたんだけど!?)
そんな俺の混乱を楽しんでいるのか、遼はくすっと笑い、少しだけ真剣な表情に変わった。
「もっと俺のこと、知ってね?」
「っ……!?」
空気が、一気に甘くなる。
心臓が高鳴るという表現では足りない。
胸の奥が破裂するみたいに熱い。
遼は続ける。
「俺だって、悠のこと……まだ全然足りないって思ってる」
「な、なんでそんな……急に真面目になるの……」
「真面目じゃないと伝わらないだろ?」
距離が、また近い。
視線が絡む。
息が止まりそうになる。
「……昼休みからそんな距離感出すの反則……」
「じゃあ、放課後もっと近づく?」
「~~~っ!」
声にならない悲鳴を押し殺しながら、遼の肩を軽く叩く。
だが遼はただ嬉しそうに笑うだけだ。
(なんなんだよもう……!一生このくらいの距離感で甘やかしてくるの?)
(……勝てる気がしない……!)
こんなふうに照れ合って、冗談みたいな甘い言葉を交わして。
そんな関係が来るなんて、昨日の自分は想像もできなかった。
……いや、昨日じゃなくても、ずっと。
昼休みが終わるベルが鳴ったあとも――
ふたりの距離は、昨日までとは比べものにならないほど、あたりまえに近かった。
そして、このぎこちなくて、でも確かに甘い時間が。
これからの日常になっていく――そんな予感が、胸の奥で静かに灯り続けていた。
(落ち着け、落ち着け……。昨日の告白は夢じゃない。ちゃんと覚えてる。遼が……俺のことを――)
そのとき。
家の呼び鈴が控えめに、でもはっきりと鳴った。
「……こんな時間に誰?」
胸が跳ねる。予感というより、確信に近いなにか。
恐る恐るドアを開けると、淡い朝光のなか、遼がまっすぐ立っていた。
「……遼?」
制服の襟元がいつもより整っていて、髪も少し湿っている。家を出るまえに急いで整えたのがわかる。そんな些細な部分すら、今日の特別を証明していた。
そして遼は手に弁当袋を持っていた。
「はい、これ」
その声は、昨日告白した人の声で。
俺の胸の奥にまで届く、低く穏やかな響き。
「わ、わざわざ……ありがとう」
受け取った瞬間、指先が触れる。微かな体温に、呼吸が揺れた。
(手渡し……やば。やばいやばい。これ、直接渡されるとか……心臓に悪い……)
昨日のあの夕陽の屋上から、まだ気持ちが現実世界に追いついていないのに。目の前の遼が当たり前みたいに俺の家に来て、当たり前みたいに弁当を渡してくる。
遼は口元だけで、ほんの少し笑った。
「今日からは、一緒に学校に行こう」
どくん、と胸が危険な音を立てた。
(いや……いやいやいや、普通のこと……?いや普通じゃないから!)
(告白翌日にこれって……!心の準備、まったく……!)
靴を履きながら、指先が震えているのが自分でも分かる。遼はそんな俺の様子を見ていたらしい。
通学路に出たところで、ふと思い出したように言った。
「……もう隠さなくていいんだな」
「え?」
「朝早く学校に行って、悠の引き出しに弁当を入れなくていい」
その言い方が、なんだか名残惜しそうで、でも幸せを含ませていて。
(ああ……本当に、遼が……作ってくれてたんだ……)
胸の奥がじわっと熱くなった。
「あ、うん……。直接渡されるってだけで緊張してるけど……その、一緒に登校するのも……」
そこで遼が、少し驚いたように眉を下げる。
「緊張、してるの?」
「してるって……!」
喉に何かつっかえた。
遼の目は細く優しくなっていて、俺の反応を楽しんでいるみたいで、なおさら顔が熱い。
二人で坂道を並んで歩く。
足音が重なるだけで、妙に共同生活感があって、胸がくすぐったい。
(待って……これなんか……)
(朝、一緒に登校って……カップルってこんな感じじゃない……?)
(無理……死ぬ……)
道端の影がふたり分並ぶだけで、胸の奥が溶けそうだった。
学校に着くまでの時間なんて、たった十数分のはずなのに、すべてが初めての感情で満たされていて、息がうまく吸えない。
そして――昼休み。
窓から差し込む光が柔らかくて、世界の輪郭がちょっとだけぼやける。
教室の喧騒が、いつもの何倍も遠く感じた。
二人並んで弁当を広げるだけで、胸の奥がぎゅっと熱い。
「……やっぱり、うまい」
言った瞬間、遼の眉がゆるむ。
「そりゃよかった」
その笑顔が眩しくて、視界がふわっと明るくなる。
(やめろよ……そんな嬉しそうな顔……。俺、どう反応したらいいかわかんねえよ……)
でも、次の瞬間、ふっと二人の間に笑いがこぼれた。
「なんか……変な感じだな」
「うん……。でも悪くない」
向かい合わせの距離感がくすぐったくて、逆に落ち着く。
弁当を食べ終わるころ、俺は思い切って聞いてみた。
「でもさ……朝も夕方も送ってくれるの、大変じゃない?無理してない?」
遼は、間髪入れずに答えた。
「そんなことないよ」
「いや、でも……ほら……いろいろ……」
「俺の家、悠の家の少し先だし」
「……え?」
箸を置く手が止まる。
「え、ちょっと待って。通り道……だったってこと?」
遼は当然のようにうなずく。
「知らなかった?ずっとそうだよ」
「し、知らないよ!初耳なんだけど!」
(なんでだよ!もっと早く言えよ!気を使って毎回遠回りしてるんじゃないかって、昨日までずっと思ってたんだけど!?)
そんな俺の混乱を楽しんでいるのか、遼はくすっと笑い、少しだけ真剣な表情に変わった。
「もっと俺のこと、知ってね?」
「っ……!?」
空気が、一気に甘くなる。
心臓が高鳴るという表現では足りない。
胸の奥が破裂するみたいに熱い。
遼は続ける。
「俺だって、悠のこと……まだ全然足りないって思ってる」
「な、なんでそんな……急に真面目になるの……」
「真面目じゃないと伝わらないだろ?」
距離が、また近い。
視線が絡む。
息が止まりそうになる。
「……昼休みからそんな距離感出すの反則……」
「じゃあ、放課後もっと近づく?」
「~~~っ!」
声にならない悲鳴を押し殺しながら、遼の肩を軽く叩く。
だが遼はただ嬉しそうに笑うだけだ。
(なんなんだよもう……!一生このくらいの距離感で甘やかしてくるの?)
(……勝てる気がしない……!)
こんなふうに照れ合って、冗談みたいな甘い言葉を交わして。
そんな関係が来るなんて、昨日の自分は想像もできなかった。
……いや、昨日じゃなくても、ずっと。
昼休みが終わるベルが鳴ったあとも――
ふたりの距離は、昨日までとは比べものにならないほど、あたりまえに近かった。
そして、このぎこちなくて、でも確かに甘い時間が。
これからの日常になっていく――そんな予感が、胸の奥で静かに灯り続けていた。