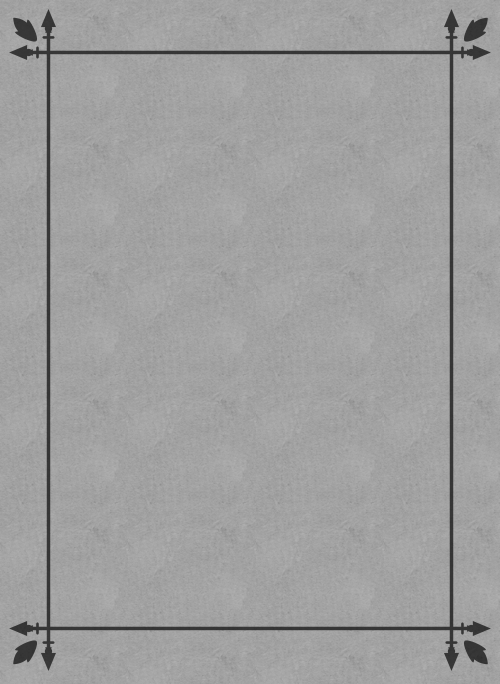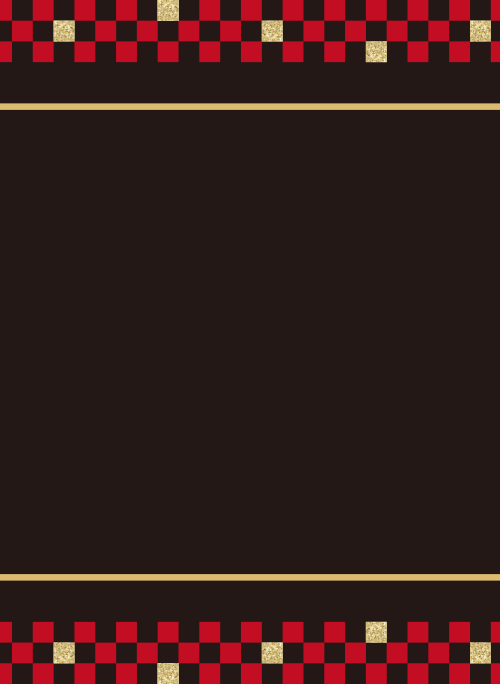夕陽が、校舎の壁をゆっくりと朱に染めていく。
放課後の屋上は、昼間の喧騒が嘘のように静かで、金網を揺らす春の風だけが規則正しく鳴っていた。
悠は、半分だけ開いた鉄製のドアの前で足を止めた。
心臓が、変なリズムで跳ねている。
呼吸を整えようとしても、肺がうまく動いてくれない。
(……やばい。なんで、こんな緊張してんだ俺)
ほんの少し覗き込むと、そこに遼がいた。
手すりに片手を置き、斜めに差す夕陽を浴びている横顔は、いつも以上に大人っぽく見える。
どこか遠くを見るような表情なのに、妙に決意が滲んでいた。
「悠」
不意に呼ばれて、悠の身体がびくっと震える。
名前一つ呼ばれるだけで、どうしてこんなに胸が跳ねるんだ。
「……遼」
絞り出すように返した声は、情けないくらい掠れていた。
遼はゆっくりと歩き出した。
夕陽を背負ったシルエットが、影を長く伸ばしながら悠へ向かってくる。
その歩幅は急がないのに、迫力がある。
(逃げられない……てか、逃げちゃだめなんだよな、ここで)
距離が近づき、逆光の向こうで瞳が揺れているのが分かった。
そして――その瞬間は、あまりにも唐突に落ちてきた。
「あの弁当、俺が作ってた」
風が止んだ。
世界まで止まった気がした。
「……え?」
悠の声は、驚きというより覚悟していた真実が実際に来た瞬間の痛みに近かった。
胸の奥がじくじくと熱い。
遼は立ち止まり、深く息を吐いた。
その横顔はいつもの冷静さを保っているのに、言葉だけが僅かに震えていた。
「気づかれないようにしてた。でも……もう隠すのやめたい」
(……やっぱり、遼なんだ。ずっと……俺のこと、見てたんだ)
喉がぎゅっと詰まる。
呼吸が浅い。
遼は一歩近づいた。
手すりから離れたその手が、わずかに握られていることに気づく。
夕陽が彼の横顔を照らし、睫毛の影が頬に落ちていた。
その唇が、夕暮れの空気を震わせる。
「好きだよ、悠」
止めてくれ、と心が叫ぶのに。
同時に、もっと聞きたい、と胸が渇いていた。
一気に身体が熱くなる。
逃げたいのに逃げたくない。
この瞬間だけは、絶対に目を逸らしたくなかった。
悠は、震える唇を噛みしめ、小さく息を飲む。
「……知ってた。ずっと前から。遼がお弁当を作ってくれているって」
自分で言いながら、声が震えているのが分かる。
夕陽の赤が揺れて、視界が少し滲んだ。
「でも……言ったら、せっかく仲良くなったのに、今の関係が壊れるんじゃないかって……思って……」
一度言葉にしてしまえば、この関係が終わってしまう気がして。
薄いガラスで守っていた距離を、割る勇気がなかった。
「壊したくなかった。だから言えなかった。弁当作っているの、お前だよね?って」
遼はゆっくりと目を見開き、それからふっと微笑んだ。
その笑みは穏やかで、どこか安心に似ていた。
「壊れないよ」
近づいてきて、そっと悠の肩に触れる。
まるで、壊れものに触れるような優しさで。
「……むしろ、やっと繋がった」
胸の奥がじんわり熱くなる。
触れられた肩から、優しい熱が広がっていく。
風が屋上を抜け、二人の距離だけが静かに縮まっていく。
夕陽の赤は濃くなり、影が長く伸びた。
その距離はもう、以前のふたりには戻れないほど近くて。
そしてその近さが、何よりも心地よかった。
昼と夜のあいだにだけ生まれる独特の静けさが、金網やコンクリートに薄い膜のように張りついて、世界を少しだけ幻のように見せている。
その中で――遼の腕が、ふっと動いた。
悠の肩に触れていた手が、ためらいを捨てたように、確かな力を帯びて引き寄せる。
その動きは一瞬で、でも驚くほど優しかった。
「……えっ」
声が漏れたときにはもう、遼の胸の中に閉じ込められていた。
腕の強さは包み込むようで、苦しくなるほどじゃないのに、逃げようとしても逃げられない意思だけが明確だった。
制服越しに伝わる体温が甘くて、胸の奥がじわじわ熱くなる。
(なんで……なんでこんな……)
混乱よりも先に、遼の香りが鼻先に触れた。
夕暮れの風に混じった、落ち着くような、少しだけ甘い匂い。
「悠」
耳元に落ちる低い声。
その声は、心臓の奥を撫でるみたいに優しいのに、芯だけが揺らがずに貫いてくる。
「今、お前以外見えてない。……俺の気持ちはもう引き返せないから」
囁くと同時に、遼は悠の頭にそっと額を押し当てた。
額と額が触れた瞬間、悠の身体がびくりと震える。
(……嘘だろ。なんで……そんな顔で言うんだよ)
胸の中の鼓動が急に跳ね上がる。
逃げ場がないどころか、逃げる気さえ奪われてしまう。
そして、また遼の腕の中にすっぽり収まると、遼の胸板に触れてた耳に、同じ速さの鼓動が響いてくる。
(あれ……同じ……?遼の心臓……俺と同じ速さで……)
自分の心臓だけじゃない。
相手の鼓動も自分と重なるなんて、そんな都合のいいことがあるはずないのに。
「な、なんで……そんなにドキドキして……」
気づけば、こぼれ落ちるような声が漏れていた。
言った本人のほうが真っ赤になっている。
遼は、胸に悠を抱えたまま、くくっと笑う。
「それ、今言うか?」
「ち、違っ……!言うつもりじゃ……!」
「知ってる。悠は思ったこと、すぐ顔に出る」
言いながら、遼の腕がゆっくりと強まった。
力じゃなくて、意志を伝えるための抱きしめ方。
悠の背中を撫でる手つきは慎重で、まるで壊れ物に触れるように優しい。
でもその指先は、どこか手放したくないと語っている。
心臓の音が重なるたび、悠の中で固まっていた不安が溶けていく。
呼吸も自然と同じリズムに揺れ始めて、まるで最初からこうするために生まれてきたみたいだった。
(……繋がってる。ほんとに繋がってる……)
夕暮れの風がふたりの身体の間をすり抜けるたびに、屋上の影がひとつにまとまっていく。
世界が静かに閉じていき、ふたりだけを包み込むように見えた。
悠は、遼の制服の胸元をぎゅっと握った。
無意識の癖みたいな動きだったけど、それは確かにここにいたいという証だった。
「……遼」
名前を呼ぶだけで、涙がこぼれそうになる。
胸の奥の熱が、もう抑えきれなかった。
遼は小さく息を吸い込み、耳元に落とす。
「絶対に離さないから」
どこか静かで、それでいて迷いのひとかけらもない声。
自信と優しさが混ざったその言葉が、悠の胸にまっすぐ刺さる。
(……ああ、だめだ。こんなの、もっと好きになるに決まってる)
その瞬間だった。
――ふたりの恋が、本物になったのは。
抱きしめる力も、触れ合う呼吸も、重なる鼓動も。
全部が同じ温度を示していて、全部が同じ答えを告げていた。
悠は遼の腕の中でそっと目を閉じた。
もう逃げない、と静かに決めるように。
そして、この場所から始まる未来を、ほんの少し震える息で受け入れた。
放課後の屋上は、昼間の喧騒が嘘のように静かで、金網を揺らす春の風だけが規則正しく鳴っていた。
悠は、半分だけ開いた鉄製のドアの前で足を止めた。
心臓が、変なリズムで跳ねている。
呼吸を整えようとしても、肺がうまく動いてくれない。
(……やばい。なんで、こんな緊張してんだ俺)
ほんの少し覗き込むと、そこに遼がいた。
手すりに片手を置き、斜めに差す夕陽を浴びている横顔は、いつも以上に大人っぽく見える。
どこか遠くを見るような表情なのに、妙に決意が滲んでいた。
「悠」
不意に呼ばれて、悠の身体がびくっと震える。
名前一つ呼ばれるだけで、どうしてこんなに胸が跳ねるんだ。
「……遼」
絞り出すように返した声は、情けないくらい掠れていた。
遼はゆっくりと歩き出した。
夕陽を背負ったシルエットが、影を長く伸ばしながら悠へ向かってくる。
その歩幅は急がないのに、迫力がある。
(逃げられない……てか、逃げちゃだめなんだよな、ここで)
距離が近づき、逆光の向こうで瞳が揺れているのが分かった。
そして――その瞬間は、あまりにも唐突に落ちてきた。
「あの弁当、俺が作ってた」
風が止んだ。
世界まで止まった気がした。
「……え?」
悠の声は、驚きというより覚悟していた真実が実際に来た瞬間の痛みに近かった。
胸の奥がじくじくと熱い。
遼は立ち止まり、深く息を吐いた。
その横顔はいつもの冷静さを保っているのに、言葉だけが僅かに震えていた。
「気づかれないようにしてた。でも……もう隠すのやめたい」
(……やっぱり、遼なんだ。ずっと……俺のこと、見てたんだ)
喉がぎゅっと詰まる。
呼吸が浅い。
遼は一歩近づいた。
手すりから離れたその手が、わずかに握られていることに気づく。
夕陽が彼の横顔を照らし、睫毛の影が頬に落ちていた。
その唇が、夕暮れの空気を震わせる。
「好きだよ、悠」
止めてくれ、と心が叫ぶのに。
同時に、もっと聞きたい、と胸が渇いていた。
一気に身体が熱くなる。
逃げたいのに逃げたくない。
この瞬間だけは、絶対に目を逸らしたくなかった。
悠は、震える唇を噛みしめ、小さく息を飲む。
「……知ってた。ずっと前から。遼がお弁当を作ってくれているって」
自分で言いながら、声が震えているのが分かる。
夕陽の赤が揺れて、視界が少し滲んだ。
「でも……言ったら、せっかく仲良くなったのに、今の関係が壊れるんじゃないかって……思って……」
一度言葉にしてしまえば、この関係が終わってしまう気がして。
薄いガラスで守っていた距離を、割る勇気がなかった。
「壊したくなかった。だから言えなかった。弁当作っているの、お前だよね?って」
遼はゆっくりと目を見開き、それからふっと微笑んだ。
その笑みは穏やかで、どこか安心に似ていた。
「壊れないよ」
近づいてきて、そっと悠の肩に触れる。
まるで、壊れものに触れるような優しさで。
「……むしろ、やっと繋がった」
胸の奥がじんわり熱くなる。
触れられた肩から、優しい熱が広がっていく。
風が屋上を抜け、二人の距離だけが静かに縮まっていく。
夕陽の赤は濃くなり、影が長く伸びた。
その距離はもう、以前のふたりには戻れないほど近くて。
そしてその近さが、何よりも心地よかった。
昼と夜のあいだにだけ生まれる独特の静けさが、金網やコンクリートに薄い膜のように張りついて、世界を少しだけ幻のように見せている。
その中で――遼の腕が、ふっと動いた。
悠の肩に触れていた手が、ためらいを捨てたように、確かな力を帯びて引き寄せる。
その動きは一瞬で、でも驚くほど優しかった。
「……えっ」
声が漏れたときにはもう、遼の胸の中に閉じ込められていた。
腕の強さは包み込むようで、苦しくなるほどじゃないのに、逃げようとしても逃げられない意思だけが明確だった。
制服越しに伝わる体温が甘くて、胸の奥がじわじわ熱くなる。
(なんで……なんでこんな……)
混乱よりも先に、遼の香りが鼻先に触れた。
夕暮れの風に混じった、落ち着くような、少しだけ甘い匂い。
「悠」
耳元に落ちる低い声。
その声は、心臓の奥を撫でるみたいに優しいのに、芯だけが揺らがずに貫いてくる。
「今、お前以外見えてない。……俺の気持ちはもう引き返せないから」
囁くと同時に、遼は悠の頭にそっと額を押し当てた。
額と額が触れた瞬間、悠の身体がびくりと震える。
(……嘘だろ。なんで……そんな顔で言うんだよ)
胸の中の鼓動が急に跳ね上がる。
逃げ場がないどころか、逃げる気さえ奪われてしまう。
そして、また遼の腕の中にすっぽり収まると、遼の胸板に触れてた耳に、同じ速さの鼓動が響いてくる。
(あれ……同じ……?遼の心臓……俺と同じ速さで……)
自分の心臓だけじゃない。
相手の鼓動も自分と重なるなんて、そんな都合のいいことがあるはずないのに。
「な、なんで……そんなにドキドキして……」
気づけば、こぼれ落ちるような声が漏れていた。
言った本人のほうが真っ赤になっている。
遼は、胸に悠を抱えたまま、くくっと笑う。
「それ、今言うか?」
「ち、違っ……!言うつもりじゃ……!」
「知ってる。悠は思ったこと、すぐ顔に出る」
言いながら、遼の腕がゆっくりと強まった。
力じゃなくて、意志を伝えるための抱きしめ方。
悠の背中を撫でる手つきは慎重で、まるで壊れ物に触れるように優しい。
でもその指先は、どこか手放したくないと語っている。
心臓の音が重なるたび、悠の中で固まっていた不安が溶けていく。
呼吸も自然と同じリズムに揺れ始めて、まるで最初からこうするために生まれてきたみたいだった。
(……繋がってる。ほんとに繋がってる……)
夕暮れの風がふたりの身体の間をすり抜けるたびに、屋上の影がひとつにまとまっていく。
世界が静かに閉じていき、ふたりだけを包み込むように見えた。
悠は、遼の制服の胸元をぎゅっと握った。
無意識の癖みたいな動きだったけど、それは確かにここにいたいという証だった。
「……遼」
名前を呼ぶだけで、涙がこぼれそうになる。
胸の奥の熱が、もう抑えきれなかった。
遼は小さく息を吸い込み、耳元に落とす。
「絶対に離さないから」
どこか静かで、それでいて迷いのひとかけらもない声。
自信と優しさが混ざったその言葉が、悠の胸にまっすぐ刺さる。
(……ああ、だめだ。こんなの、もっと好きになるに決まってる)
その瞬間だった。
――ふたりの恋が、本物になったのは。
抱きしめる力も、触れ合う呼吸も、重なる鼓動も。
全部が同じ温度を示していて、全部が同じ答えを告げていた。
悠は遼の腕の中でそっと目を閉じた。
もう逃げない、と静かに決めるように。
そして、この場所から始まる未来を、ほんの少し震える息で受け入れた。