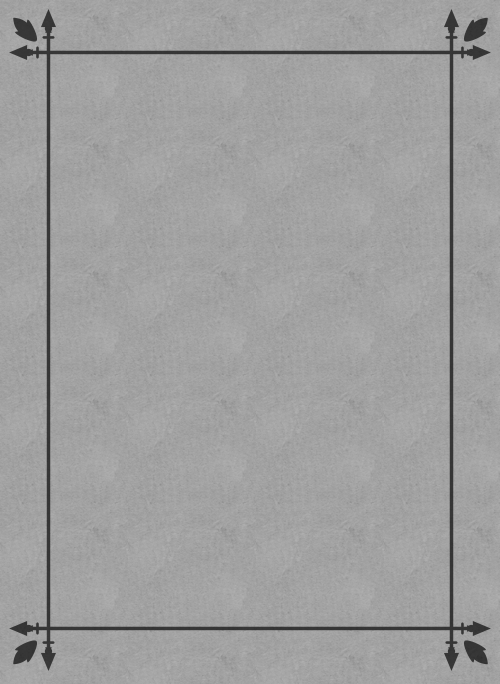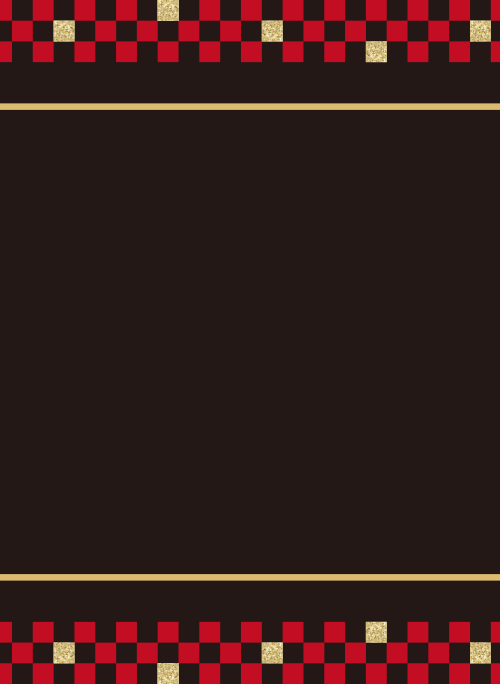夕方のチャイムが遠くに消えたあとも、あの噂だけはずっと耳の奥に残って離れなかった。
――神谷が誰かに片想いしてるらしいぞ。
軽いノリで放たれたクラスメイトの声。
本来なら笑って流せるはずなのに、悠の心臓はその瞬間、妙なリズムで跳ね上がった。
(……は?か、片想い?誰に?いやいや、なんで今そんな話……)
ざわついた、なんて言葉じゃ足りなかった。
むしろ胸の奥で小型の嵐でも暴れているようで、
息を吸うたびに胸の内側がどくんと音を立てる。
(女子……だよな?普通に考えて……でも、もし相手が……俺)
(いや、ないって。そんなの、あるわけ……)
思考が無限ループし続ける中、悠は鞄を持って席を立つタイミングですらわずかに遅れた。
教室を出て廊下を歩いても、階段を降りても、玄関で靴を履き替えても――噂はずっと頭に貼りついていた。
(頼むから、もう黙れ……俺の脳みそ……)
校門を出た瞬間、いつも通りの顔で神谷遼が待っていた。
「行くぞ」
短く。ぶっきらぼうで。
でもなぜか、胸のざわつきに追い打ちをかける声だった。
悠が何も言わないうちに、当然のように歩幅を合わせて並んで歩き出す。
その自然さが、この日はやけにこたえた。
(……ほんとに、当たり前みたいに来るなよ……)
夕暮れの風がゆるく吹き、制服の裾を揺らす。
オレンジ色の空が住宅街の屋根を照らし、坂道の影が長く伸びていく。
二人の靴音だけが、交互に規則正しく響く。
いつもなら安心できるリズムなのに、今日は逆に胸を締めつけてきた。
(……無理だ。今日だけは、このまま家まで行くとか……無理)
耐えきれなくなった悠は、スニーカーのつま先を止めるようにして、ふいに立ち止まった。
遼が一歩先で振り返る。
「……どうした?」
「あ、あのさ。もう送らなくても……大丈夫だよ」
言いながら、心臓は嫌になるほど暴れている。
遼はゆっくり悠に近づき、その瞳でこちらをまっすぐ射抜いてきた。
夕陽を反射したその目は、いつもより深い色をしていて、逃げ場がなかった。
「……なんで?」
低く、静かで、でも眼差しには確かな圧があった。
「だって……いいのかなって。毎日……ほら、迷惑っていうか」
言葉を選びながらも、声は勝手に震えてしまう。
遼の表情はほとんど変わらない。
けれど一度だけ小さく息を吸い、ゆっくりと視線を落とした。
「迷惑なわけないだろ」
その一言が、空気を変えた。
悠の胸は、物理的に跳ねた。
遼は目線を再び上げ、今度は逃がさないと言わんばかりに悠を見据える。
「……守りたいって思うんだ」
夕陽が斜めから遼の横顔を照らし、その陰影がやけに綺麗で、やけに強くて――
冗談でも気まぐれでもないことは一瞬で分かった。
(ちょ、待て……そういう言い方……反則だろ……)
(誰を守りたいかなんて決まってるみたいな……)
(え、でも……なんで……?)
脳が追いつかないまま、口が先に動いていた。
「……それ、誰に対して?」
言いながら、心臓は爆音。
鼓動が遼にも聞こえてしまいそうなほどだった。
遼はほんの一瞬だけ瞳を細める。
その仕草は微笑とも違う。
けれど確かに何かを伝える覚悟のような光が宿っていた。
そして、低く、短く。
「決まってるだろ」
風が止まった気がした。
二人の視線が――ぶつかった。
時間が伸び、世界の音が全部薄れていく。
目の奥が熱くなる。
喉が詰まる。
言葉が――出ない。
(……そんな顔で、そんな声で言うなよ……俺、本当に……)
どちらも先の言葉を続けられず、沈黙だけがゆっくり落ちた。
坂道には、ふたりの影が寄り添うように伸びている。
沈みかけた夕陽がその影を赤く染め、まるでふたりの距離をそっと後押しするように淡い光を落としていた。
――神谷が誰かに片想いしてるらしいぞ。
軽いノリで放たれたクラスメイトの声。
本来なら笑って流せるはずなのに、悠の心臓はその瞬間、妙なリズムで跳ね上がった。
(……は?か、片想い?誰に?いやいや、なんで今そんな話……)
ざわついた、なんて言葉じゃ足りなかった。
むしろ胸の奥で小型の嵐でも暴れているようで、
息を吸うたびに胸の内側がどくんと音を立てる。
(女子……だよな?普通に考えて……でも、もし相手が……俺)
(いや、ないって。そんなの、あるわけ……)
思考が無限ループし続ける中、悠は鞄を持って席を立つタイミングですらわずかに遅れた。
教室を出て廊下を歩いても、階段を降りても、玄関で靴を履き替えても――噂はずっと頭に貼りついていた。
(頼むから、もう黙れ……俺の脳みそ……)
校門を出た瞬間、いつも通りの顔で神谷遼が待っていた。
「行くぞ」
短く。ぶっきらぼうで。
でもなぜか、胸のざわつきに追い打ちをかける声だった。
悠が何も言わないうちに、当然のように歩幅を合わせて並んで歩き出す。
その自然さが、この日はやけにこたえた。
(……ほんとに、当たり前みたいに来るなよ……)
夕暮れの風がゆるく吹き、制服の裾を揺らす。
オレンジ色の空が住宅街の屋根を照らし、坂道の影が長く伸びていく。
二人の靴音だけが、交互に規則正しく響く。
いつもなら安心できるリズムなのに、今日は逆に胸を締めつけてきた。
(……無理だ。今日だけは、このまま家まで行くとか……無理)
耐えきれなくなった悠は、スニーカーのつま先を止めるようにして、ふいに立ち止まった。
遼が一歩先で振り返る。
「……どうした?」
「あ、あのさ。もう送らなくても……大丈夫だよ」
言いながら、心臓は嫌になるほど暴れている。
遼はゆっくり悠に近づき、その瞳でこちらをまっすぐ射抜いてきた。
夕陽を反射したその目は、いつもより深い色をしていて、逃げ場がなかった。
「……なんで?」
低く、静かで、でも眼差しには確かな圧があった。
「だって……いいのかなって。毎日……ほら、迷惑っていうか」
言葉を選びながらも、声は勝手に震えてしまう。
遼の表情はほとんど変わらない。
けれど一度だけ小さく息を吸い、ゆっくりと視線を落とした。
「迷惑なわけないだろ」
その一言が、空気を変えた。
悠の胸は、物理的に跳ねた。
遼は目線を再び上げ、今度は逃がさないと言わんばかりに悠を見据える。
「……守りたいって思うんだ」
夕陽が斜めから遼の横顔を照らし、その陰影がやけに綺麗で、やけに強くて――
冗談でも気まぐれでもないことは一瞬で分かった。
(ちょ、待て……そういう言い方……反則だろ……)
(誰を守りたいかなんて決まってるみたいな……)
(え、でも……なんで……?)
脳が追いつかないまま、口が先に動いていた。
「……それ、誰に対して?」
言いながら、心臓は爆音。
鼓動が遼にも聞こえてしまいそうなほどだった。
遼はほんの一瞬だけ瞳を細める。
その仕草は微笑とも違う。
けれど確かに何かを伝える覚悟のような光が宿っていた。
そして、低く、短く。
「決まってるだろ」
風が止まった気がした。
二人の視線が――ぶつかった。
時間が伸び、世界の音が全部薄れていく。
目の奥が熱くなる。
喉が詰まる。
言葉が――出ない。
(……そんな顔で、そんな声で言うなよ……俺、本当に……)
どちらも先の言葉を続けられず、沈黙だけがゆっくり落ちた。
坂道には、ふたりの影が寄り添うように伸びている。
沈みかけた夕陽がその影を赤く染め、まるでふたりの距離をそっと後押しするように淡い光を落としていた。