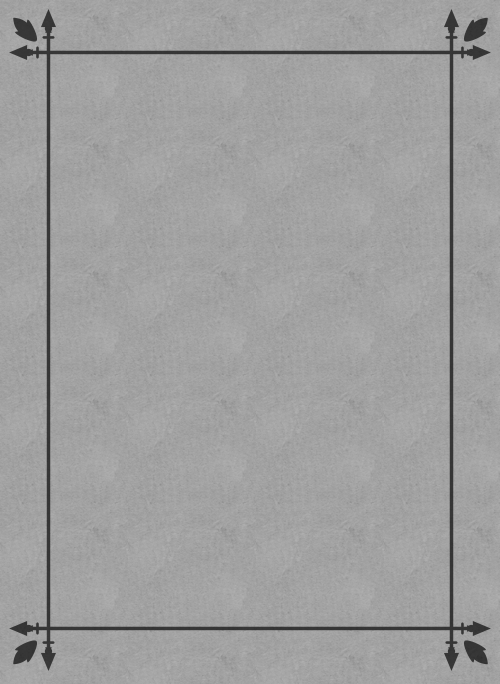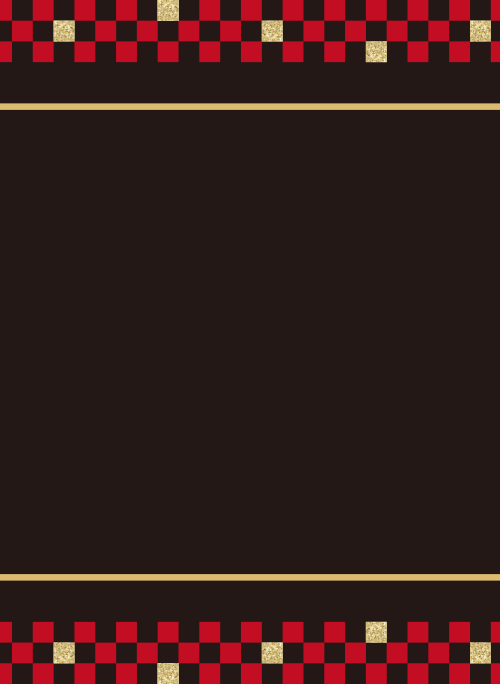昼休みのざわめきは、ふたりのあいだだけ妙に遠かった。
まるで教室の喧騒が、彼らの席を避けて流れていくみたいに。
悠は箸を持ったまま、ほとんど手をつけられずに弁当を見つめていた。
ふわりと立ちのぼる甘い香り。
目の前には、丁寧に折りたたまれた卵焼きが整列していて、いつもより少し焼き色が濃い。
(……これも、遼が作ったんだよな)
胸の奥がじわりと熱を帯びる。
喉が苦しくて、息をひとつ吸うのさえ気をつかわなきゃいけない感じだ。
(なんで……こんな、気まずいんだよ……)
遼は斜め後ろの席で教科書を閉じ、腕を組んだまま悠の様子を静かに伺っていた。
いつもなら無表情に近いはずの瞳が、今日はかすかに揺れている。
「……どうした。食わないのか?」
落ち着いた、低い声。
けれど、そこには確かに不安が混ざっていた。
悠はびくっと肩を震わせ、慌てて笑った。
「い、いや、食べるよ。……うまいし」
「ならいいけど」
遼はそれ以上追及しない。
でも、本当は言いたかった。
弁当のこと、もう知ってるって。
朝、机にそっと忍ばせてた姿を目撃したって。
あのとき……ほんとは嬉しくて仕方なかったって。
こんなに近くで、自分のこと考えてくれてたんだって。
でも。
(言ったら……距離、戻っちゃうかもしれない)
あの穏やかで優しい日々が、綺麗に割れて、取り返しのつかない形になるような気がして。
怖くて、言葉が喉につっかえたまま出てこない。
気づけば、箸の先から卵焼きがぽとりと落ちた。
「あ……」
「……悠?」
遼の声色が、いつもよりわずかに柔らかい。
それだけで、胸に刺さっていた棘が揺れた。
「最近、お前……元気ない」
「えっ……そんなことないよ。ほんとに」
「嘘つくの下手だろ、お前」
その一言は、優しくも鋭い。
遼はふっと目を伏せた。
怒るでもなく、詰めるでもなく、ただ寄り添うような感じで。
(言われなくても、全部……気づいてるのかな……弁当の送り主のこと、俺はもう知っているって……)
悠の胸が大きく揺れる。
だが、それでも喉は固まったままだ。
言いたいのに。言えない。
遼はしばらく黙り込んでいたが、やがて息をひとつ吐く。
「……無理に話さなくていい。話したくなったらでいいから」
「遼……」
「ただ、ちゃんと食え。昼食べないと、俺――」
言いかけた言葉が急に止まった。
遼は唇をきゅっと結んで視線をそらす。
その仕草が妙に不器用で、妙に優しくて。
悠の喉がきゅっと鳴る。
(言いたい。言いたいよ)
(知ってるよ、ありがとうって)
(毎日嬉しいよって)
(遼が俺にしてくれた全部……ちゃんと、大切に思ってるって)
でも怖い。
どう言えばいいのか、どこから言えばいいのか。
もし遼が「やりすぎだった」と後悔したら。
それを知った自分に距離を置こうとしたら。
(これが壊れるの、ほんとに……怖い……)
どうしてこんなに、遼のことで苦しくなるんだろう。
どうしてこんなに、遼の表情ひとつで揺れてしまうんだろう。
悠が目を伏せると、遼は何か言いたげに口を開きかけ――また閉じた。
「……食えよ。冷める」
「……うん」
そのやりとりがあまりにささやかで、かえって胸に刺さる。
ふたりの沈黙だけが、机の上にゆっくり積もっていく。
しかしその沈黙は、離れようとしての沈黙ではない。
近づきすぎたふたりが、踏み込めずに震えている――そんな温度の沈黙だった。
遼の指先が、ほんの少しだけ悠の弁当箱の縁に触れる。
何かを確かめるように。
でも、決して押しつけようとはしない。
悠もまた気づいている。
遼が気づいていることを、気づいている。
互いに言葉にできず、でも確かに気持ちだけは交差していた。
重なりそうで、触れられないまま。
昼休みのざわめきは、やっぱりふたりの席だけを避けて流れていた。
まるで教室の喧騒が、彼らの席を避けて流れていくみたいに。
悠は箸を持ったまま、ほとんど手をつけられずに弁当を見つめていた。
ふわりと立ちのぼる甘い香り。
目の前には、丁寧に折りたたまれた卵焼きが整列していて、いつもより少し焼き色が濃い。
(……これも、遼が作ったんだよな)
胸の奥がじわりと熱を帯びる。
喉が苦しくて、息をひとつ吸うのさえ気をつかわなきゃいけない感じだ。
(なんで……こんな、気まずいんだよ……)
遼は斜め後ろの席で教科書を閉じ、腕を組んだまま悠の様子を静かに伺っていた。
いつもなら無表情に近いはずの瞳が、今日はかすかに揺れている。
「……どうした。食わないのか?」
落ち着いた、低い声。
けれど、そこには確かに不安が混ざっていた。
悠はびくっと肩を震わせ、慌てて笑った。
「い、いや、食べるよ。……うまいし」
「ならいいけど」
遼はそれ以上追及しない。
でも、本当は言いたかった。
弁当のこと、もう知ってるって。
朝、机にそっと忍ばせてた姿を目撃したって。
あのとき……ほんとは嬉しくて仕方なかったって。
こんなに近くで、自分のこと考えてくれてたんだって。
でも。
(言ったら……距離、戻っちゃうかもしれない)
あの穏やかで優しい日々が、綺麗に割れて、取り返しのつかない形になるような気がして。
怖くて、言葉が喉につっかえたまま出てこない。
気づけば、箸の先から卵焼きがぽとりと落ちた。
「あ……」
「……悠?」
遼の声色が、いつもよりわずかに柔らかい。
それだけで、胸に刺さっていた棘が揺れた。
「最近、お前……元気ない」
「えっ……そんなことないよ。ほんとに」
「嘘つくの下手だろ、お前」
その一言は、優しくも鋭い。
遼はふっと目を伏せた。
怒るでもなく、詰めるでもなく、ただ寄り添うような感じで。
(言われなくても、全部……気づいてるのかな……弁当の送り主のこと、俺はもう知っているって……)
悠の胸が大きく揺れる。
だが、それでも喉は固まったままだ。
言いたいのに。言えない。
遼はしばらく黙り込んでいたが、やがて息をひとつ吐く。
「……無理に話さなくていい。話したくなったらでいいから」
「遼……」
「ただ、ちゃんと食え。昼食べないと、俺――」
言いかけた言葉が急に止まった。
遼は唇をきゅっと結んで視線をそらす。
その仕草が妙に不器用で、妙に優しくて。
悠の喉がきゅっと鳴る。
(言いたい。言いたいよ)
(知ってるよ、ありがとうって)
(毎日嬉しいよって)
(遼が俺にしてくれた全部……ちゃんと、大切に思ってるって)
でも怖い。
どう言えばいいのか、どこから言えばいいのか。
もし遼が「やりすぎだった」と後悔したら。
それを知った自分に距離を置こうとしたら。
(これが壊れるの、ほんとに……怖い……)
どうしてこんなに、遼のことで苦しくなるんだろう。
どうしてこんなに、遼の表情ひとつで揺れてしまうんだろう。
悠が目を伏せると、遼は何か言いたげに口を開きかけ――また閉じた。
「……食えよ。冷める」
「……うん」
そのやりとりがあまりにささやかで、かえって胸に刺さる。
ふたりの沈黙だけが、机の上にゆっくり積もっていく。
しかしその沈黙は、離れようとしての沈黙ではない。
近づきすぎたふたりが、踏み込めずに震えている――そんな温度の沈黙だった。
遼の指先が、ほんの少しだけ悠の弁当箱の縁に触れる。
何かを確かめるように。
でも、決して押しつけようとはしない。
悠もまた気づいている。
遼が気づいていることを、気づいている。
互いに言葉にできず、でも確かに気持ちだけは交差していた。
重なりそうで、触れられないまま。
昼休みのざわめきは、やっぱりふたりの席だけを避けて流れていた。