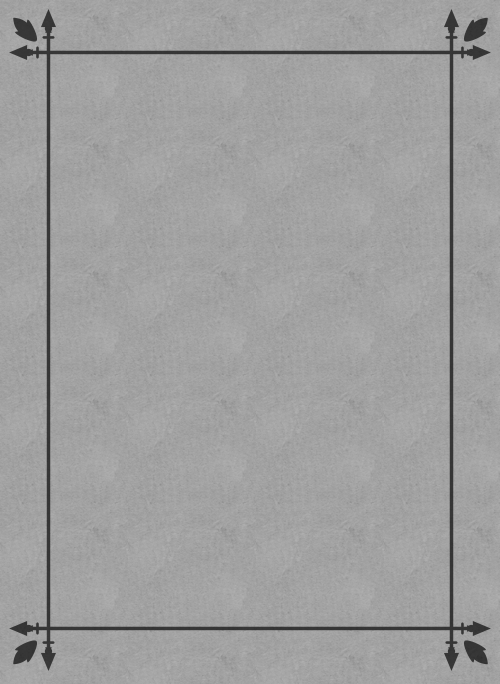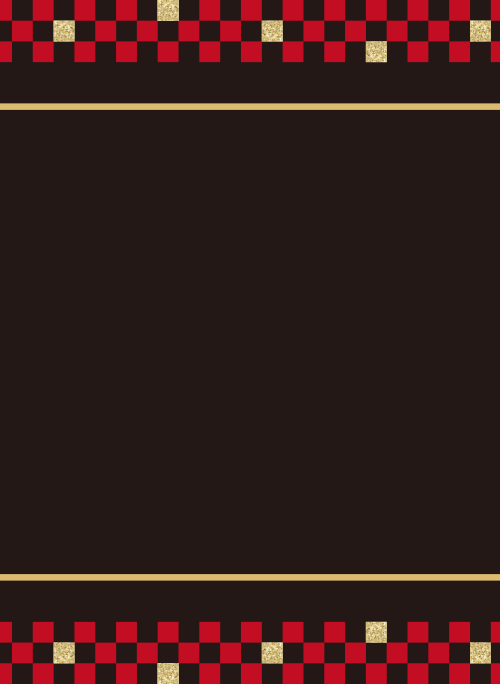昼休みのチャイムが鳴った瞬間、教室内のざわざわした空気の向こうから、ひとつだけ音の粒立ちが違うような足音が近づいてきた。
……神谷遼だ。
相変わらず、無駄に絵になる。
ただ歩いてるだけなのに、まるでドラマのスローモーションみたいで、女子の視線もちらほら吸い寄せられてるし、男子からも「おい、あいつ」みたいな視線が飛んでいる。
けど本人は、当然のように気づいていない。
いや、それとも気づいてるけど気にしてないのか……どっちでもいいけど。
そんな遼が、真っ直ぐ俺の机の前で止まった。
「悠……今日、一緒に食べられる?」
え?
え?
え?
その一言が、あまりにも自然で、当たり前みたいで。
心臓の奥を直接つつかれたみたいに、胸がドクッと跳ねた。
「え、あ……うん。いいよ」
ヤバい。
今、確実に声のトーンがおかしかった気がする。
(ちょっと待って……平常心どこ行った……?)
(いや、初めて誘われたからびっくりしただけだし……)
(なんで俺、昼飯の誘いひとつでこんなに動揺してるんだよ……)
遼が机を少し引いて、自分の椅子を机を挟んで俺の目の前に置く。
自然すぎて、息を止めるタイミングを完全に逃した。
(いや……待てよ)
(これって……遼が俺に食べさせたくて作った弁当なんだよな?)
(それを遼本人の前で食べるの?俺……?)
(これ……なんのプレイ……?)
距離——近い。
(え、目の前って……近……近っ……!)
(今まで気にしてなかったけど、これが普通?まあ、友達と食べる時としては普通か……)
(あ、弁当を作った本人が目の前にいるからこんなに緊張するのか……)
(頼む、俺の心臓返して……)
遼が何気なく弁当箱を開けると、ふわっといい匂いが広がる。
俺は自分の弁当を開けながら、視線が勝手に遼の顔へ吸い寄せられる。
目元、陽の色で少しだけ柔らかく見えるんだよな。
いや、今は陽じゃなくて蛍光灯なんだけど。
「……いただきます」
「ん」
たったそれだけの会話なのに、妙に空気が静かで、二人だけの世界みたいな気がしてくる。
箸を動かす音が、やけに耳に残る。
俺の咀嚼音、大きくないかな?とか余計なことばかり気になる。
(落ち着けって俺……ただの昼飯……ただの……いや、ただのじゃないけどさ……)
そんな内心のてんやわんやが最高潮に達してきたころ。
「おっす悠!……って、あれ?」
わざわざ不穏なタイミングで現れる男、佐伯晃がやってきた。
こいつの嗅覚、なんでこんなに良いんだ。
ぱっと俺と遼の弁当に目を落とし——
そこで眉がピクッと跳ねた。
「え、待って。なんか、お前ら……弁当の中身似てない?」
ピシッ。
空気が本当にそう鳴った気がした。
俺は固まり、遼は箸を止める。
晃だけが状況に気づかず、さらに波を立てるみたいに続ける。
「ほら見ろって、この卵焼き!色も形もそっくり——」
「……黙れ」
その瞬間だった。
バッ。
遼が晃の口を片手で塞ぎ、もう片腕で肩を押さえ込み、
完全に動きを封じ込めた。
速い。
はや……なにこれ、忍者……?
晃の目が完全に見開かれる。
「……っ……!おま、強……っ、死ぬかと思ったぞ!?」
「変なこと言うからだ、お前が」
いつもの落ち着いた声なのに、晃がビクッとするくらいの威圧感があった。
(うわ……絶対弁当のことがバレないようにしている)
(……やっぱ遼、俺に弁当のこと気づかれたくないってことだよな……?)
(ていうか俺はどうすれば……)
(知らないふり……!そう、知らないフリが最適解!!)
晃は小動物みたいに肩を震わせながら、
「……っ、じゃ、じゃあ俺は……彼女のところ行くし……!」
と逃げるように去っていった。
「……は?お前、あの事件のあとで……彼女……?早すぎだろ、それ……」
俺が吐き出した言葉は温度を失って、ただ静かに消えていった。
一瞬で、教室のざわつきが遠のいたように感じた。
まるでスイッチひとつで世界の音量を下げたみたいだ。
遼は何事もなかったように弁当に戻る。
箸を動かすたびに、その顔がほんの少しだけ揺れて、光が柔らかく髪に落ちる。
(なんで……そんな自然に優しい顔できるんだよ……)
(くそ……近いってば……)
俺はそっと遼を見た。
その瞬間、遼がゆるく笑う。
「悠って、ほんと無防備だな」
「……心配してくれてるの?」
思わずこぼれた声は、ほんの少し震えていた。
自分で聞いて驚くくらい弱かった。
遼は一瞬だけ目を丸くし、次の瞬間、かすかな笑みとともに視線を合わせてきた。
「それ以外に見える?」
近い。
息が触れそうな距離。
昼休みの喧騒が、全部遠ざかっていく。
目の前の遼の呼吸音だけが、はっきり聞こえる。
(……やだ……もう……こんなの、意識しない方がおかしい……)
心臓が暴れまくっているのが、遼に見透かされている気がして。
それでも俺は、目をそらせなかった。
遼の笑顔を見るたびに、胸がじんじん熱くなる。
触れたら壊れそうで、でも触れたくてたまらない。
——そんな、甘くて息が詰まりそうな昼休みだった。
……神谷遼だ。
相変わらず、無駄に絵になる。
ただ歩いてるだけなのに、まるでドラマのスローモーションみたいで、女子の視線もちらほら吸い寄せられてるし、男子からも「おい、あいつ」みたいな視線が飛んでいる。
けど本人は、当然のように気づいていない。
いや、それとも気づいてるけど気にしてないのか……どっちでもいいけど。
そんな遼が、真っ直ぐ俺の机の前で止まった。
「悠……今日、一緒に食べられる?」
え?
え?
え?
その一言が、あまりにも自然で、当たり前みたいで。
心臓の奥を直接つつかれたみたいに、胸がドクッと跳ねた。
「え、あ……うん。いいよ」
ヤバい。
今、確実に声のトーンがおかしかった気がする。
(ちょっと待って……平常心どこ行った……?)
(いや、初めて誘われたからびっくりしただけだし……)
(なんで俺、昼飯の誘いひとつでこんなに動揺してるんだよ……)
遼が机を少し引いて、自分の椅子を机を挟んで俺の目の前に置く。
自然すぎて、息を止めるタイミングを完全に逃した。
(いや……待てよ)
(これって……遼が俺に食べさせたくて作った弁当なんだよな?)
(それを遼本人の前で食べるの?俺……?)
(これ……なんのプレイ……?)
距離——近い。
(え、目の前って……近……近っ……!)
(今まで気にしてなかったけど、これが普通?まあ、友達と食べる時としては普通か……)
(あ、弁当を作った本人が目の前にいるからこんなに緊張するのか……)
(頼む、俺の心臓返して……)
遼が何気なく弁当箱を開けると、ふわっといい匂いが広がる。
俺は自分の弁当を開けながら、視線が勝手に遼の顔へ吸い寄せられる。
目元、陽の色で少しだけ柔らかく見えるんだよな。
いや、今は陽じゃなくて蛍光灯なんだけど。
「……いただきます」
「ん」
たったそれだけの会話なのに、妙に空気が静かで、二人だけの世界みたいな気がしてくる。
箸を動かす音が、やけに耳に残る。
俺の咀嚼音、大きくないかな?とか余計なことばかり気になる。
(落ち着けって俺……ただの昼飯……ただの……いや、ただのじゃないけどさ……)
そんな内心のてんやわんやが最高潮に達してきたころ。
「おっす悠!……って、あれ?」
わざわざ不穏なタイミングで現れる男、佐伯晃がやってきた。
こいつの嗅覚、なんでこんなに良いんだ。
ぱっと俺と遼の弁当に目を落とし——
そこで眉がピクッと跳ねた。
「え、待って。なんか、お前ら……弁当の中身似てない?」
ピシッ。
空気が本当にそう鳴った気がした。
俺は固まり、遼は箸を止める。
晃だけが状況に気づかず、さらに波を立てるみたいに続ける。
「ほら見ろって、この卵焼き!色も形もそっくり——」
「……黙れ」
その瞬間だった。
バッ。
遼が晃の口を片手で塞ぎ、もう片腕で肩を押さえ込み、
完全に動きを封じ込めた。
速い。
はや……なにこれ、忍者……?
晃の目が完全に見開かれる。
「……っ……!おま、強……っ、死ぬかと思ったぞ!?」
「変なこと言うからだ、お前が」
いつもの落ち着いた声なのに、晃がビクッとするくらいの威圧感があった。
(うわ……絶対弁当のことがバレないようにしている)
(……やっぱ遼、俺に弁当のこと気づかれたくないってことだよな……?)
(ていうか俺はどうすれば……)
(知らないふり……!そう、知らないフリが最適解!!)
晃は小動物みたいに肩を震わせながら、
「……っ、じゃ、じゃあ俺は……彼女のところ行くし……!」
と逃げるように去っていった。
「……は?お前、あの事件のあとで……彼女……?早すぎだろ、それ……」
俺が吐き出した言葉は温度を失って、ただ静かに消えていった。
一瞬で、教室のざわつきが遠のいたように感じた。
まるでスイッチひとつで世界の音量を下げたみたいだ。
遼は何事もなかったように弁当に戻る。
箸を動かすたびに、その顔がほんの少しだけ揺れて、光が柔らかく髪に落ちる。
(なんで……そんな自然に優しい顔できるんだよ……)
(くそ……近いってば……)
俺はそっと遼を見た。
その瞬間、遼がゆるく笑う。
「悠って、ほんと無防備だな」
「……心配してくれてるの?」
思わずこぼれた声は、ほんの少し震えていた。
自分で聞いて驚くくらい弱かった。
遼は一瞬だけ目を丸くし、次の瞬間、かすかな笑みとともに視線を合わせてきた。
「それ以外に見える?」
近い。
息が触れそうな距離。
昼休みの喧騒が、全部遠ざかっていく。
目の前の遼の呼吸音だけが、はっきり聞こえる。
(……やだ……もう……こんなの、意識しない方がおかしい……)
心臓が暴れまくっているのが、遼に見透かされている気がして。
それでも俺は、目をそらせなかった。
遼の笑顔を見るたびに、胸がじんじん熱くなる。
触れたら壊れそうで、でも触れたくてたまらない。
——そんな、甘くて息が詰まりそうな昼休みだった。