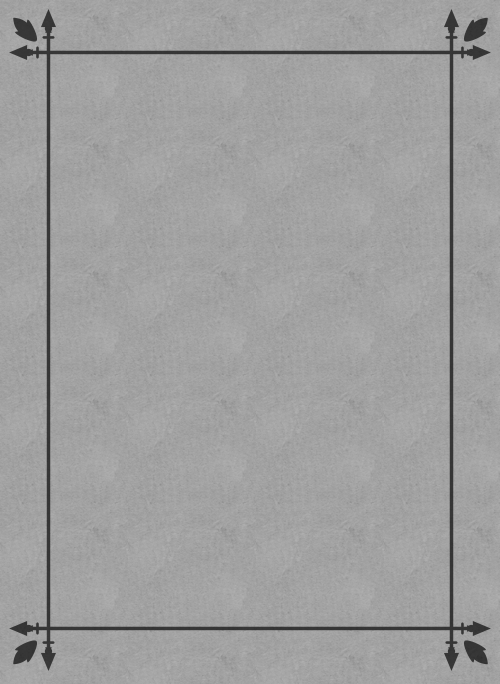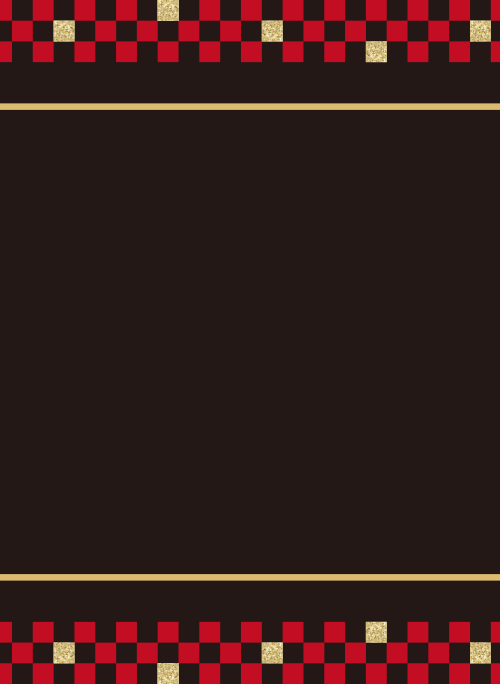「――!?何このお弁当」
朝イチの俺の机の中に、明らかに俺のじゃないお弁当が入っていた。
しかも青いチェック柄の布で丁寧に包まれ、まるで「おはよう、待ってたよ」とでも言いたげに、そこだけやたら存在感を放っている。
(ちょ、待って待って……誰だよ、俺に弁当仕込むヤツなんていたっけ!?)
心の声が教室中に響き渡りそうなくらい動揺し、思わず辺りをキョロキョロと見渡す。
ゴールデンウィーク明けの朝。
今からほんの数分前、連休の眠気をまだ引きずった一ノ瀬悠は、欠伸を噛み殺しながら桜南高校の校舎へ足を踏み入れていた。
湿った春の空気が、まだどこか漂っている。
開け放たれた窓から吹き込む風に、廊下の掲示物がぱらりと揺れた。
「ふぁ……眠……」
伸びをしながら二年三組の教室に入り、自分の席へと向かう。
誰もが休み明けのテンションで、教室の空気は妙にスローだった。
「……おはよー」
半分惰性で、ぼそりと声を出す。特に誰かが返事するわけでもないが、毎朝の儀式みたいなものだ。
悠はいつものように鞄を机に置き、教科書を中へしまおうと手を伸ばした――その瞬間、動きがぴたりと止まった。
「……え?」
机の奥に、妙な影。
覗き込むと、それは青いチェック柄の布に包まれた、小さな包みだった。
丁寧に結ばれたリボン。
布の柄は、男女どちらが持っていても違和感がない落ち着いたデザイン。
そして――物語は再び、あの奇妙な始まりへ戻る。
(……え、ちょっと待て。誰の?)
一瞬、時間が止まったように感じた。
じわりと背中が粟立つ。
(俺の……?俺のなのか?いやいや、そんなバカな……)
(これ絶対違う人宛だろ……?)
(俺、誰かに弁当もらえるキャラじゃないし)
(じゃあ誰かの好意の結晶を――よりにもよって俺の机にイン?)
(いや、そんなピンポイントで間違えるか?)
(ちょっと待って、急に事態が複雑すぎない!?)
(それはそれでややこしいし、俺にそんなイベント来るわけないし!)
思考が高速で回り始める。
同時に、胸の内側がじわじわと騒ぎ出す。
幻かもしれない。
いや、本当にそうならどれほど安心するか。
悠はそっと頬をつねった。
「……痛っ」
普通に痛い。現実だ。
(マジか……いや、でも、誰が?なんのために?)
恐る恐る包みを取り出し、周囲を見回す。
早く来た数人のクラスメイトがいるが、誰も怪しい視線を向けてこない。
むしろ全員、自分のことで精一杯という様子だ。
(幻じゃ……ないよな?)
動悸を抑えつつ、悠は布をゆっくりとほどく。
指先がわずかに震えた。
現れたのは黒の二段弁当箱。
シンプルだが、どこか上品な雰囲気が漂っている。
「……ほんとに弁当だ……」
蓋を開けると、ふわりと柔らかな香りが立ちのぼった。
出汁の香りと、甘みの気配。
それに鶏肉の香ばしい香りが続く。
(……っ、やば……うまそう……)
上段には黄金色の卵焼き、彩り豊かなブロッコリーや人参のグラッセ。
照りのついた鶏の照り焼きと、切り口がつやりと光るミニトマト。
下段にはご飯。
「……レベル高っ」
自分がいつもパンを二つと適当な飲み物で済ませている現実が、急に恥ずかしく思えるほどの完成度だ。
迷った末、そっと卵焼きをつまんでみる。
ぱく。
「……っ……うま……」
口に広がるじんわりした甘さ。
やさしい味が舌を包み込んでいく。
(なにこれ……手作りだよな?市販じゃないよな?)
もう一口――と伸ばしかけた手が止まった。
弁当箱の隅に、小さな付箋が貼られていたからだ。
『今日もがんばって』
淡い色の付箋。
細く、整った、美しい文字。
(女子……?いや、これ女子の字……だよな?美しすぎる……)
胸がどくん、と大きく跳ねた。
(でも……俺?俺に?俺なんかに?)
混乱の波が押し寄せる。
頭がぐるぐるして、息が少し浅くなった。
と、その時――。
「お?珍しいな、弁当。お前、いつも購買じゃん?」
背後からふっと声がして、悠はびくっと肩を跳ねさせた。
振り返ると、陽の光が似合いすぎる男――佐伯晃が立っていた。
軽くセットされた茶色がかった髪。
気の抜けた笑顔。
なのに女子から「王子」だの「天使」だの呼ばれるほどの人気。
幼馴染だから慣れてはいるものの、改めて見るとイケメン過ぎて腹立つ。
「……いや、あの、これは……」
「いや、食ってんだから、お前のだろ?」
「さあ……?」
悠の返答に、晃の眉がぴくりと跳ねる。
「はあ?なんで自分でわかんねえんだよ。朝から謎すぎるわ」
晃は興味津々で覗き込んでくる。
悠は慌てて弁当箱を引き寄せた。
(見せたらダメだ……絶対変なこと言われる……!)
晃はモテすぎて、彼を好きな女子からの「情報提供係」として悠が絡まれるのが日常。
「佐伯くん、好きな食べ物なに?」
「今、彼女いる?」
「放課後どこにいるか知らない?」
そんな質問攻めを何度受けてきたことか。
イケメンの幼馴染を持つと苦労が絶えない。
晃は当然のように悠の隣の席へ腰をかけ、肘を机に乗せて覗きこんできた。
距離が近い。幼馴染ゆえ、パーソナルスペースは皆無だ。
「でさ」
指先で弁当箱をちょん、とつつく。
「これ、どう見てもお前の手作りじゃねぇよな?」
「……いや、その……」
「ほら、誤魔化すなって。誰にもらったんだよ?」
悠が口ごもると、晃はすかさず身を乗り出す。
「お前、包丁持ったら指切るタイプだろ?で、親も朝弱いって前に言ってただろ。だから、悠。お前が作ったわけない。これは断言できる。家庭の事情も俺が一番知ってるしな。で――誰だよ、お前にこんなの作ってくれるヤツ?」
「知らない……マジで知らない」
「作り慣れてる人の弁当って、こういうのだよな~。なあ悠、これ本気のヤツだよ。渡す相手にお前選ぶとか……ガチ恋だろ」
晃の顔は完全に面白がってる。
けれど、幼馴染だからわかる。
興味と心配が半々で、軽口の裏にちゃんと悠を見てる気配がある。
「でもさ――お前、気づいてねぇだけで案外モテてんのかもな」
「やめろ……」
「赤くなってる。かわいいな」
「やめろって!」
晃はますます楽しそうに悠をつついてくる。
そして、何かを察したように目を細めた。
「いいじゃん。春だし。お前にもついに春が来たんじゃね?」
「やめろ……そういうのじゃないから……!」
「ほー?じゃあなんだよ?」
「……わかんねえよ……」
悠は弁当箱の蓋を閉じ、深く息をついた。
最初はイタズラだと思った。
でも、このクオリティは絶対にただの悪ふざけではない。
(誰だよ……こんなの……俺のために……?)
けれど、考えれば考えるほど誰も思い当たらない。
女子に好かれるタイプでもない。
むしろ、晃のせいでイケメンの幼馴染がいるという不遇ポジションが定位置だ。
(もしかして、晃のための弁当とか?いや、考えすぎ……だよな?うーん……)
結局その日の昼休み、悠は誰にもこの弁当のことを言わず、一口一口味わいながら食べきった。
美味しかった。
びっくりするほど。
でも、食べ終わった後の胸に残ったのは、満足よりもむしろ――妙なざわつきだった。
(誰が……なんで……俺に……?)
そして、翌朝。
机の中を覗いた瞬間、悠は固まった。
また、青い包みが入っていた。
昨日と同じ布、同じ大きさ、同じ結び目。
(……また、だ)
心臓が、跳ねた。
朝イチの俺の机の中に、明らかに俺のじゃないお弁当が入っていた。
しかも青いチェック柄の布で丁寧に包まれ、まるで「おはよう、待ってたよ」とでも言いたげに、そこだけやたら存在感を放っている。
(ちょ、待って待って……誰だよ、俺に弁当仕込むヤツなんていたっけ!?)
心の声が教室中に響き渡りそうなくらい動揺し、思わず辺りをキョロキョロと見渡す。
ゴールデンウィーク明けの朝。
今からほんの数分前、連休の眠気をまだ引きずった一ノ瀬悠は、欠伸を噛み殺しながら桜南高校の校舎へ足を踏み入れていた。
湿った春の空気が、まだどこか漂っている。
開け放たれた窓から吹き込む風に、廊下の掲示物がぱらりと揺れた。
「ふぁ……眠……」
伸びをしながら二年三組の教室に入り、自分の席へと向かう。
誰もが休み明けのテンションで、教室の空気は妙にスローだった。
「……おはよー」
半分惰性で、ぼそりと声を出す。特に誰かが返事するわけでもないが、毎朝の儀式みたいなものだ。
悠はいつものように鞄を机に置き、教科書を中へしまおうと手を伸ばした――その瞬間、動きがぴたりと止まった。
「……え?」
机の奥に、妙な影。
覗き込むと、それは青いチェック柄の布に包まれた、小さな包みだった。
丁寧に結ばれたリボン。
布の柄は、男女どちらが持っていても違和感がない落ち着いたデザイン。
そして――物語は再び、あの奇妙な始まりへ戻る。
(……え、ちょっと待て。誰の?)
一瞬、時間が止まったように感じた。
じわりと背中が粟立つ。
(俺の……?俺のなのか?いやいや、そんなバカな……)
(これ絶対違う人宛だろ……?)
(俺、誰かに弁当もらえるキャラじゃないし)
(じゃあ誰かの好意の結晶を――よりにもよって俺の机にイン?)
(いや、そんなピンポイントで間違えるか?)
(ちょっと待って、急に事態が複雑すぎない!?)
(それはそれでややこしいし、俺にそんなイベント来るわけないし!)
思考が高速で回り始める。
同時に、胸の内側がじわじわと騒ぎ出す。
幻かもしれない。
いや、本当にそうならどれほど安心するか。
悠はそっと頬をつねった。
「……痛っ」
普通に痛い。現実だ。
(マジか……いや、でも、誰が?なんのために?)
恐る恐る包みを取り出し、周囲を見回す。
早く来た数人のクラスメイトがいるが、誰も怪しい視線を向けてこない。
むしろ全員、自分のことで精一杯という様子だ。
(幻じゃ……ないよな?)
動悸を抑えつつ、悠は布をゆっくりとほどく。
指先がわずかに震えた。
現れたのは黒の二段弁当箱。
シンプルだが、どこか上品な雰囲気が漂っている。
「……ほんとに弁当だ……」
蓋を開けると、ふわりと柔らかな香りが立ちのぼった。
出汁の香りと、甘みの気配。
それに鶏肉の香ばしい香りが続く。
(……っ、やば……うまそう……)
上段には黄金色の卵焼き、彩り豊かなブロッコリーや人参のグラッセ。
照りのついた鶏の照り焼きと、切り口がつやりと光るミニトマト。
下段にはご飯。
「……レベル高っ」
自分がいつもパンを二つと適当な飲み物で済ませている現実が、急に恥ずかしく思えるほどの完成度だ。
迷った末、そっと卵焼きをつまんでみる。
ぱく。
「……っ……うま……」
口に広がるじんわりした甘さ。
やさしい味が舌を包み込んでいく。
(なにこれ……手作りだよな?市販じゃないよな?)
もう一口――と伸ばしかけた手が止まった。
弁当箱の隅に、小さな付箋が貼られていたからだ。
『今日もがんばって』
淡い色の付箋。
細く、整った、美しい文字。
(女子……?いや、これ女子の字……だよな?美しすぎる……)
胸がどくん、と大きく跳ねた。
(でも……俺?俺に?俺なんかに?)
混乱の波が押し寄せる。
頭がぐるぐるして、息が少し浅くなった。
と、その時――。
「お?珍しいな、弁当。お前、いつも購買じゃん?」
背後からふっと声がして、悠はびくっと肩を跳ねさせた。
振り返ると、陽の光が似合いすぎる男――佐伯晃が立っていた。
軽くセットされた茶色がかった髪。
気の抜けた笑顔。
なのに女子から「王子」だの「天使」だの呼ばれるほどの人気。
幼馴染だから慣れてはいるものの、改めて見るとイケメン過ぎて腹立つ。
「……いや、あの、これは……」
「いや、食ってんだから、お前のだろ?」
「さあ……?」
悠の返答に、晃の眉がぴくりと跳ねる。
「はあ?なんで自分でわかんねえんだよ。朝から謎すぎるわ」
晃は興味津々で覗き込んでくる。
悠は慌てて弁当箱を引き寄せた。
(見せたらダメだ……絶対変なこと言われる……!)
晃はモテすぎて、彼を好きな女子からの「情報提供係」として悠が絡まれるのが日常。
「佐伯くん、好きな食べ物なに?」
「今、彼女いる?」
「放課後どこにいるか知らない?」
そんな質問攻めを何度受けてきたことか。
イケメンの幼馴染を持つと苦労が絶えない。
晃は当然のように悠の隣の席へ腰をかけ、肘を机に乗せて覗きこんできた。
距離が近い。幼馴染ゆえ、パーソナルスペースは皆無だ。
「でさ」
指先で弁当箱をちょん、とつつく。
「これ、どう見てもお前の手作りじゃねぇよな?」
「……いや、その……」
「ほら、誤魔化すなって。誰にもらったんだよ?」
悠が口ごもると、晃はすかさず身を乗り出す。
「お前、包丁持ったら指切るタイプだろ?で、親も朝弱いって前に言ってただろ。だから、悠。お前が作ったわけない。これは断言できる。家庭の事情も俺が一番知ってるしな。で――誰だよ、お前にこんなの作ってくれるヤツ?」
「知らない……マジで知らない」
「作り慣れてる人の弁当って、こういうのだよな~。なあ悠、これ本気のヤツだよ。渡す相手にお前選ぶとか……ガチ恋だろ」
晃の顔は完全に面白がってる。
けれど、幼馴染だからわかる。
興味と心配が半々で、軽口の裏にちゃんと悠を見てる気配がある。
「でもさ――お前、気づいてねぇだけで案外モテてんのかもな」
「やめろ……」
「赤くなってる。かわいいな」
「やめろって!」
晃はますます楽しそうに悠をつついてくる。
そして、何かを察したように目を細めた。
「いいじゃん。春だし。お前にもついに春が来たんじゃね?」
「やめろ……そういうのじゃないから……!」
「ほー?じゃあなんだよ?」
「……わかんねえよ……」
悠は弁当箱の蓋を閉じ、深く息をついた。
最初はイタズラだと思った。
でも、このクオリティは絶対にただの悪ふざけではない。
(誰だよ……こんなの……俺のために……?)
けれど、考えれば考えるほど誰も思い当たらない。
女子に好かれるタイプでもない。
むしろ、晃のせいでイケメンの幼馴染がいるという不遇ポジションが定位置だ。
(もしかして、晃のための弁当とか?いや、考えすぎ……だよな?うーん……)
結局その日の昼休み、悠は誰にもこの弁当のことを言わず、一口一口味わいながら食べきった。
美味しかった。
びっくりするほど。
でも、食べ終わった後の胸に残ったのは、満足よりもむしろ――妙なざわつきだった。
(誰が……なんで……俺に……?)
そして、翌朝。
机の中を覗いた瞬間、悠は固まった。
また、青い包みが入っていた。
昨日と同じ布、同じ大きさ、同じ結び目。
(……また、だ)
心臓が、跳ねた。