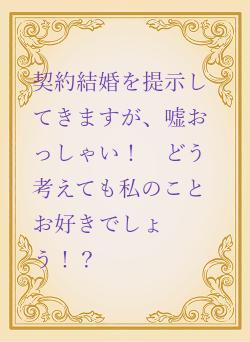『きっと皆どこかに孤独を抱えていて、それに負けそうになる日もあると思います。でももし、そんな時に寄り添うことが出来たのなら、それは素敵なことなのだと思います。それでは歌います。――ひかりを探して』
アルバイトが終わってスマートフォンを見ると、同じくスマートフォンを見ていた同期が「大丈夫?」と尋ねてきた。何が、と聞き返すより先にSNSのトレンドが目に入り、思わずスマートフォンを握りしめた。手帳型のカバーがぎゅっと音を立てる。
トレンドの上位に来ているのは「ユイナさん」という文字だった。好きな歌手の、名前。
「ま、待って、何」
つい最近、とあるアニメの主題歌で一躍有名となったアーティストが活動休止を発表した時も、こうやってアーティストの名前がトレンド入りしていた。嫌な予感に身を強張らせ、恐る恐るトレンドを開くと、真っ先に出てきたのは、ユイナの訃報を知らせるものだった。ユイナの夫が書いたらしい彼女の死を知らせる文面が、彼女のアカウントに載せられていて、わたしはその文字の羅列を理解するのにしばらくの時間を要した。同期がわたしの隣で立ち止まっていて、わたしの指先をじっと見ている。その視線に気が散りながらもやっと文書の意味を理解して、それからやっとのことで呟いた。
「推しが死んだ」
「藤倉さん、ずっと好きだったよね。ユイナさん」
「うん」
「つらいね」
「死んじゃった」
ぷらりと、スマートフォンを持った手から力が抜ける。かろうじて指先に引っかかっているストラップからそれの重みが伝わってきて、ストラップがCDを買った時の特典だったと思い出して、スマートフォンを握りなおした。
「ごめん。先帰る」
「気を付けてね」
同期の声を置き去りにして、わたしは走り始めた。そうしないと人前で泣いてしまいそうだった。本当はスーパーに寄って買い物をしなくちゃいけなかったけれど、スーパーは時折ユイナの歌が流れる。今彼女の曲を聴いたらそれこそ堪えられなくなるから、脇目も振らずにまっすぐアパートに向かった。塾講師のスーツにパンプスという恰好は走りにくくて、靴が踵にこすれて、途中から痛くなってくる。だけどわたしはたったひとりで泣くわたしを許してくれるところに、少しでも早く行きたかった。
アパートについても、ただいまと言う人もいない。どうしたの、と尋ねてくれる人もいない。わたしを当たり前に包んでいる孤独が今はありがたくて、わたしはその中に丸く座り込んだ。
『ユイナさん、自殺しちゃったのかな』
SNSを開くと、彼女があの世で幸せになることを祈る声と共に、夫が出した文書で明確にされなかった死因をあれこれと推測する声が混ざっていた。不謹慎だな、と思う自分を見つけると共に、自殺という推測に納得する自分を見つけて、スマートフォンをベッドの上に投げつける。
ユイナの歌は繊細で、ふつうに生きられれば見落としてしまうけれど、生きづらさを抱えている人ならば気にしてしまうような些細なことを、そっと優しく包んでくれるような温かさがあった。だけどそれは同時にユイナ自身の脆さと危うさを含んだもので、だから、彼女が自ら死を選んだのだとしても、納得してしまう。だけどわたしは、生きづらさの中で見つけた光を歌う彼女の歌に救われて、これまでどうにか生きてきたのだ。ユイナという人がいなくなってしまったことはもちろん悲しいのだけれど、それと同じくらい、もうわたしを救ってくれる人はいないのだという事実が、苦しかった。
わたしは姉がシャーペンを置く音に怯える子どもだった。八つ年上の姉は勉強の出来が良くなかったらしく、でも母に気に入ってもらうために一生懸命に勉強をしていた。しかし小学校低学年の時から姉を諦めていた母は、姉が望むような愛情を決して傾けることはなかった。
「お前は医者になるのよ。お姉ちゃんには無理だけれど、あゆみはお母さんの代わりに医者になってね」
母は医者になりかった人だった。高校生まで非常に優秀な成績を収めていたようだったけれど、女が医者になるなんてと父親に馬鹿にされ、有名でもなければ偏差値も高くない短大に押し込められたらしい。それに不満を抱えたまま結婚した母は、子どもに自分の人生のやり直しを歩むように求めた。旧帝国大学に入りなさい、医学部に入りなさい、医者になりなさい。小さいころから呪いのように言われてきた言葉だ。幼稚園の頃、歌手になりたいと書いて教室の壁に貼ったら、それを知った母親に「あゆみは医者になるのが夢でしょ? 違うの?」と責められた。それ以降、わたしの夢は「医者になること」に決められてしまって、わたしは自分の手で教室の掲示物を剥がした。
「お姉ちゃんもおいしゃさまになりたいの?」
「違うよあゆみ。あたしたちは医者になるように決まってるんだよ。なりたいなりたくない、じゃなくて、ならなくちゃいけないの」
姉も同じ目に遭ってきただろうに、姉はわたしを助けてくれることはなかった。他の子よりも早く文字を教えられているわたしを見ながら、いつもどこか睨みつけるような目をしていた。そうして黙々と勉強に励み、時折えんぴつを荒々しく置いた。姉は中学生になっても、母に勉強を教えられているわたしを見ると乱暴な動作でシャーペンを置き、消しゴムで書いたものを消していた。それは母に対する苛立ちよりも、わたしに対する苛立ちなのだろうと幼いながらに理解して、姉をほんの少し、怖く思った。
母はしばしば姉を罵った。出来が悪い、せっかく生んだのに、私の子供なのにちっともできない。そう言って、模試の結果を見るたびに文句を言った。姉はその頃すでに、子どもの作り方を知っていたらしい。子どもは親を選べないくせに、親は子どもの作る作らないを、生む生まないを選べることを知っていた。そして、自分の出来が悪いから妹が作られたのだと、気が付いてしまった。
「お母さんが欲しいのはあんただけだったみたいだね。あたしなんか産まれなければ良かったのにね」
中学生の姉の言うことは、五歳になるかならないかの年頃のわたしにはよく分からなかった。だけど、大学生になった今なら分かる。母が欲しかったのは、母の分身で、母の夢を叶える子どもだ。たったひとりの人間を慈しむために子どもを作ったわけではない。わたしたちは、勉強が出来なければ母にごく潰しのように扱われる存在だった。しかしわたしは文字を覚えるのも早く、計算を覚えるのも早かった。文章の塊を理解するのも早かった。みるみるうちに優秀と言われる子どもに変わっていったわたしは、姉がなりたかった姿そのもので、母からの疑似的な愛を与えられると共に、姉の心は離れていった。
高校生になった姉は、わたしが話しかけても返事をしてくれなくなった。母は勉強の話以外にはとても冷たいから、軽い雑談が出来るのは姉しかいなかったのに、姉はわたしが話しかけるたびに睨みつけてくるようになった。お姉ちゃん、そう呼んでも、その唇から小さく息を零して、シャーペンを乱暴に置くだけだった。安物のシャーペンは文字を書いていても机に置いてもキィキィと嫌な音を立てる。それは出て行ってくれと言われているみたいで、姉の視線とその音に、怯えた。
母に諦められている姉は、進路に口を出されることは無かった。どこで野たれ死んでも知らないとばかりに、少しの興味も持ってもらえなかったようだった。母はそれよりもわたしの中学受験を成功させるために一生懸命で、わたしは姉に対して、こうなってはいけないという気持ちばかり募らせていった。あれはわたしの失敗した姿なのだと、幼いながらに理解した。多分、そう思っているのが態度や顔に出ていたらしい。姉はますますわたしを睨むようになり、母には時折縋るような目をして、諦めたように県外の大学に進んでいった。ホストにはまっているとか、薬の飲みすぎで病院に運ばれたとか、父が大慌てで姉の住む地域に向かう出来事は度々あったけれど、母とわたしがそこに向かうことはなかった。
「あゆみは何になりたいの?」
父は無力だった。母の本質を見抜けないまま結婚し、ただ優秀な遺伝子を提供するための存在として扱われていてもなお、母に反抗しなかった。道具のように扱われる子たちをおろおろと眺め、逃げるように仕事に励んでいた。そのくせ、子どもの将来の夢にだけは過敏だった。
「わたしは医者になるのが決まっているの」
「歌手になりたいんじゃなかったのかい」
中学校の入学式に出席したのは、母ではなく父だった。初めて着る中学校の制服はぶかぶかしていて、身に着けるとかっこ悪かったのに、父は成長したねと褒めてくれた。
帰りの車の中では、雨が車体を打ち付ける音とワイパーの音が、静かに響いていた。
「お母さんの言う通り、私立の学校に入学したよ。わたしはお母さんの言う通りにするしかないの」
そうしないと、お姉ちゃんみたいになっちゃうから。その言葉を飲み込む。すると父はわたしが隠した言葉を理解したように、困ったように笑った。
「これはお姉ちゃんにも言ったんだけどな、いつか家族以外にお前を必要としてくれる人が現れるよ」
「そうかな」
「人間、みんな欠けているんだ。欠けたところを繋げて、ちょうど重なるくらいがうまくいくんだよ」
「お父さんとお母さんも、欠けたものを繋げたら重なるの?」
どうかなあ。父はまた困ったように笑った。ほら、お父さんとお母さんはうまくいっていない結婚だったんじゃない。わたしたちは失敗作だったってことじゃない。そう思ったら胸のうちをつきりと痛みが走って、うつむいた。
「お前もお姉ちゃんも、きっとそういう人に出会えるよ」
そうだといいな。父の手前そう呟いたけれど、きっとわたしたちにそんな未来は来ないのだと、薄っすら想像がついてしまった。わたしも姉も、誰かに埋め合わせてもらうには欠けすぎている。姉は特に愛情に飢え、わたしは捨てられることに怯えすぎている。誰かに埋め合わせてもらおうと思っても、ひとり分の愛では足りないのだ。きっと誰か大切な人が出来ても、愛というものを吸い取りすぎて、相手を空っぽにしてしまうのだと思う。
「お姉ちゃん、だからホストにはまっちゃったんだね」
わたしの一言は、雨音にかき消された。
「なんか言ったか?」
「なんでもない」
わたしたちが母に道具のように扱われていても、助けることのなかった父には、分からなくて良いと思った。
わたしは人目を気にしすぎる中学生になった。成績でクラス分けがされる中高一貫校では、最初の一年が今後の学校生活を決めてしまうように思えたから、わたしは誰にも嫌われないように、誰にも睨まれないように、期待されすぎないように振る舞った。そして皆も自分の六年間を左右する一年をどう過ごすかに悩み、皆人という集団の中に溶けていった。人に怯えているわたしはその集団に溶けることはできず、浮いてしまった。
教室は水みたいだった。誰かの意見ひとつで色を変える水。誰かが溺れても、水は自らの力で退くことはなく、誰かが出口を開けてくれるのを待っている。それどころか一度溺れた人を飲み込むように、一度同化したクラスメイトは、もうその枠から外れられない。わたしはずっとその水の中で、背泳ぎを続けているようだった。溺れることもできず、岸に上がることもできず、ずっとまぶしい太陽に焼かれ続けて、水の中に半分だけ漬かっている。下から水でつつかれて、追い返す力も強くて、わたしは居場所を見つけられなかった。
「フジクラはどうしてそんなに生きづらいんだろうな」
何か月経ってもクラスというものに馴染めないわたしを見かねて、担任はしばしばわたしを呼び出した。多感な年ごろだから苦しいこともあるだろう、しかしいつかきっと抜け出せる時が来る。そういうことを彼は語った。しかしわたしは「生きづらい」という言葉が引っかかって、彼の言葉を素直に受け入れることが出来なかった。
「先生。生きづらいって、どういうことですか」
問うと、彼は最初茶化されたのだと思ったらしい。子どもを揶揄うような笑みを見せたかと思ったら、こちらの困惑に気が付いたようで、眉を寄せる。
「生きづらい――繊細で感じやすい、と言えばいいかな。他の人がけろっと忘れてしまうようなことを、気にしているような状態だ」
「心が弱い、ってことですか」
担任は慌てて首を振った。
「いや、良いこともある。他の人が忘れてしまう、でも大切なことに気が付けるのは、生きづらい人だ」
褒められているのか、貶されているのかよく分からなかった。ただ彼の口調から、いつまでも教室の中で浮いているわたしを憐れんでいるような、面倒に思っているような感情がどこか伺えて、彼を担任として信じて良いのかが分からなくなった。
きっと、生きづらいとはこういうことなのだと思った。
友達が出来ないまま高校生になり、別の中学から入学してきた子となんとなくつるんだ。人と馴染めないなりに人と親しいふりをすることだけは出来るようになってしまって、本当に友達と呼べる人はいないのに、生きづらいと思ってしまうことは変わらないのに、教室の中に沈んでいることだけは覚えてしまった。でも正しく溺れてはいなくて、薄い膜で自分を包んで、水から乖離されているのを感じてはいた。
高校生になった途端、母の激しかった勉強への関与がさらにひどくなり、難関校であるのに関わらず、試験で満点を取らないと怒鳴られるようになった。姉の時は試験で赤点を取ろうが知らんぷりだったから、姉のほうがわたしよりマシだったのではないかと思ったけれど、きっと姉がわざと赤点を取ったのだろうということは分かるから、姉のことは思い出さないように、記憶の奥に押し込めた。
学校が終われば補習。それから塾。それから宿題。わたしは医学部に入らなくちゃいけないんだから、わたしは医学部に入らなくちゃいけないんだから。そう思って自分を追い込んでいたら、ある日突然、涙が止まらなくなってしまった。塾の帰りだった。多すぎる宿題に途方に暮れていたのはあったけれど、もっと根本的な、心の大事な部分が悲鳴を上げていたようだった。
家に帰ることもできず、まだ開いていた駅前のCDショップに立ち寄った。涙を隠すようにハンカチを持ち、店員の目から逃げるようにそこにあったヘッドフォンを掴むと、それは最近デビューしたばかりの歌手のシングルの試し聞きだった。
知らないアニメの主題歌だったから、そこに据えられたテーマは知らない。だけどそれは壊れて歪んでしまった心をそっと撫でて、繋ぎ合わせるような優しさがあって、わたしの胸にすっと染み込んでいった。これは生きづらい人のために作られた、救いの歌なのだ。父の言う、欠けたものを埋め合わせる歌なのだ。そう思った。
「あの、これ、ください」
余計に涙を流していたわたしに店員はぎょっとして、おろおろしながらCDを袋に入れてくれた。これが、わたしとユイナの出会いだった。
泥の中をはい回るような息苦しい高校生活だったけれど、ユイナの曲がわたしを救ってくれると思うと、なんとか耐えられた。母が押しつぶし、ただ父が見ているだけのわたしの大事な部分を、確かに包んでくれるのはユイナが紡ぐ言葉と、優しい声色だった。母はなんでこんな明るくない曲を好むのかと、私のスマートフォンから漏れる音を不思議に思っていたようだったけれど、明るい歌はわたしにはまぶしくて、焼かれてしまうのだと言っても、きっと理解してくれないと思ったから、黙っていた。
一浪したけれど、なんとか母が第二志望に挙げた大学の医学部に合格できた。東京で暮らすことになったわたしはやっと一人暮らしが叶い、母の支配からほんの少し逃れられる生活を送ることになった。しかし家族からの愛情を十分に受けることのなかったわたしを襲ったのは、抱えきれないほどの孤独だった。友達もいない、家族との仲も良好とは言えない。誰にも頼れない。そんなわたしに一人暮らしの部屋は暗すぎた。ひとりになったからと言って、医者になれという母の重圧から逃れることもできなくて、学校が開いているぎりぎりの時間まで学校で勉強をし、片手間に塾講師のアルバイトをし、CDやグッズを買うお金を稼いでいた。
「藤倉さんはなんで医者になりたいの?」
がむしゃらに勉強をしているわたしに、ある日学生番号がひとつ違う子が尋ねてきた。
「親に言われたから」
「あたしも。親が開業医で、跡継がないといけなくて」
「そう」
この頃から、わたしは人それぞれが生き地獄を抱えていることに気が付き始めていた。ただ他人の抱えている苦しいものに自分の身を浸すほど、皆お人よしではない。皆、自分のことで精いっぱいなのだ。わたしがこの人のことに踏み込まないのと同じように、この人がわたしの救いになることはないのだと思った。
「ねえ、ユイナって歌手知ってる?」
「ごめん、知らない」
「そう」
会話はそれきりで終わった。もう講義の話しかしないだろうと思った。
その点、アルバイトの同期は不思議な色を持つ人だった。人のことに踏み込まない、踏み込ませないくせに、会話のリズムだけは心地よかった。人と通じ合わなくても仲良くすることは出来るのだと、その人に教えられたような気がする。しかし彼女は救いを求める人でもなければ、救いを与える人でもなく、誰かに寄り添うことができるわけでもない、たったひとりで力強く生きていられる人だった。わたしには彼女がまぶしくて、太陽のように思った。だからこそ、少しだけ、嫌いだった。
「藤倉さんは学校どう? うちは調理実習がしにそう」
「栄養士の学校でも調理実習するんだ。こっちはまあ、なんとか」
「そっか」
このままだと多分留年させられそうだ、というのは黙っておいた。わたしは難関校になんとか入学できただけで、医者になれと言われているだけで、医者になりたいわけではない。医学部の勉強を楽しいと思っているわけでもなく、ただ母の圧力に逆らえないという理由だけでは難しい学問についていくのは厳しかった。
わたしは親に用意された道を歩くだけの存在で、でも親の用意した道を歩くことすらままならない。きっと、何者にもなれない。ただ生きづらさを抱えたまま、成長してしまっただけだ。せめてユイナのように自分の生きづらさを歌に出来たら良かったのだけれど、わたしはそういった才能は持っていなかった。
『きっと大丈夫。いつかあなたにも花が咲く』
ユイナの歌のように、いつか何者かになれるだろうか。医者になって、母に認めてもらえるのだろうか。そう思っていた時に、ユイナの訃報を見てしまった。
「なんで、なんで」
どうしてわたしをのこして死んでしまったの。わたしはこれからどうやって生きていったらいいの。ユイナの死よりも自分のことを心配する自分が醜くて、口の中が変な味がした。しばらくの間部屋で蹲って泣き続けていると、部屋の中のいたるところをユイナのCDやグッズで埋めていたことを思い出して、呆然としてしまう。
電話がかかってきたのは、その時だった。
「お姉ちゃん、なんで」
『わかんない。勘』
「なにそれ」
『泣いてるの?』
「好きな歌手が死んじゃったの」
電話越しに赤ちゃんの笑い声がした。旦那と思わしき人の声も。そういえば、結婚していたんだっけ、と遠いことのように思う。
『ユイナさん?』
「なんで分かったの」
『ネットみてたら、なんか急に。あんたのことずっと嫌いだったけど、でもやっぱりお姉ちゃんだからね。分かっちゃうんだよ』
「お姉ちゃん、まだわたしのこと嫌いだと思ってた」
『なんだろうね、自分の家庭が出来たらさ、分かったんだよ。あんたのこと嫌いなのはあんたのせいじゃないって』
「お母さんのせい?」
問うと、姉は電話越しに唸った。
『そうかも。でもお母さんも自分の親のせいで歪んだわけでしょ。お母さんもまあ被害者なわけで。許さないけど』
「よく分からない」
『ごめんごめん』
姉が笑う。赤ちゃんのきゃっきゃっと笑う声は、姉の今が少しでも幸せに傾いていることのように思えて、今まで首元でつかえていた疑問が、ゆっくりと零れた。
「わたしが生きづらいのって、わたしのせいなのかな」
『あんたのせいだけじゃないよ。あたしもあんたを追い詰めた』
「そんなこと言ったら、わたしだって」
『あたしもね、生きづらいって思ってた。けど今旦那いるし、子どもいるし。あたしを好きって言ってくれる人がいるから、なんとかやれてる』
「わたしを好きになる人なんて、いないよ。だからわたしはユイナの歌に救われていたんだよ」
『それってさ、あんたのためだけではないけれど、あんたみたいな人が他にいるから、歌って歌になるんだよ。だから響くの。ひとりじゃないってことだよ』
姉も母に投げ捨てられた人生を、随分苦労して過ごしたらしかった。その間にずっと考えていたことがあったのだろう。わたしの疑問に答えられるのは、きっとそういうことなのだ。
『いつかさ、生きていたんだなって思えるようになるよ。その時にはあんたは少し強くなって、前に進んでる』
姉は電話の向こうで、少しだけ笑った。それから、鍋が焦げちゃうと言って、少しだけ名残惜しそうに、電話を切った。
わたしがひとりじゃない? いつか生きていたのだと思える? 疑問はいくつもあって、まだ胸の中で蠢いている。だけど、そうであったらいいな、と思う気持ちは自然と思い浮かんできて、すっと染み込んでいった。
『春の訪れ。僕は目覚めを待っている』
ユイナの歌を、口ずさむ。そうだ、彼女の歌はわたしの心に残っている。死んだからといって、生きていたという事実が、作った歌がなくなるわけではない。わたしを救ってくれたということだって、消えない。
「あなたに出会えて良かった」
明日講義が終わったら、カラオケに行こう。ユイナの歌をたくさん歌って、彼女が生きていた事実を身に刻もう。それから、姉に今度遊びに行っていいか聞いてみよう。前に進み始めた姉の姿を見てみたい。
「生きてくれて、ありがとう」
アルバイトが終わってスマートフォンを見ると、同じくスマートフォンを見ていた同期が「大丈夫?」と尋ねてきた。何が、と聞き返すより先にSNSのトレンドが目に入り、思わずスマートフォンを握りしめた。手帳型のカバーがぎゅっと音を立てる。
トレンドの上位に来ているのは「ユイナさん」という文字だった。好きな歌手の、名前。
「ま、待って、何」
つい最近、とあるアニメの主題歌で一躍有名となったアーティストが活動休止を発表した時も、こうやってアーティストの名前がトレンド入りしていた。嫌な予感に身を強張らせ、恐る恐るトレンドを開くと、真っ先に出てきたのは、ユイナの訃報を知らせるものだった。ユイナの夫が書いたらしい彼女の死を知らせる文面が、彼女のアカウントに載せられていて、わたしはその文字の羅列を理解するのにしばらくの時間を要した。同期がわたしの隣で立ち止まっていて、わたしの指先をじっと見ている。その視線に気が散りながらもやっと文書の意味を理解して、それからやっとのことで呟いた。
「推しが死んだ」
「藤倉さん、ずっと好きだったよね。ユイナさん」
「うん」
「つらいね」
「死んじゃった」
ぷらりと、スマートフォンを持った手から力が抜ける。かろうじて指先に引っかかっているストラップからそれの重みが伝わってきて、ストラップがCDを買った時の特典だったと思い出して、スマートフォンを握りなおした。
「ごめん。先帰る」
「気を付けてね」
同期の声を置き去りにして、わたしは走り始めた。そうしないと人前で泣いてしまいそうだった。本当はスーパーに寄って買い物をしなくちゃいけなかったけれど、スーパーは時折ユイナの歌が流れる。今彼女の曲を聴いたらそれこそ堪えられなくなるから、脇目も振らずにまっすぐアパートに向かった。塾講師のスーツにパンプスという恰好は走りにくくて、靴が踵にこすれて、途中から痛くなってくる。だけどわたしはたったひとりで泣くわたしを許してくれるところに、少しでも早く行きたかった。
アパートについても、ただいまと言う人もいない。どうしたの、と尋ねてくれる人もいない。わたしを当たり前に包んでいる孤独が今はありがたくて、わたしはその中に丸く座り込んだ。
『ユイナさん、自殺しちゃったのかな』
SNSを開くと、彼女があの世で幸せになることを祈る声と共に、夫が出した文書で明確にされなかった死因をあれこれと推測する声が混ざっていた。不謹慎だな、と思う自分を見つけると共に、自殺という推測に納得する自分を見つけて、スマートフォンをベッドの上に投げつける。
ユイナの歌は繊細で、ふつうに生きられれば見落としてしまうけれど、生きづらさを抱えている人ならば気にしてしまうような些細なことを、そっと優しく包んでくれるような温かさがあった。だけどそれは同時にユイナ自身の脆さと危うさを含んだもので、だから、彼女が自ら死を選んだのだとしても、納得してしまう。だけどわたしは、生きづらさの中で見つけた光を歌う彼女の歌に救われて、これまでどうにか生きてきたのだ。ユイナという人がいなくなってしまったことはもちろん悲しいのだけれど、それと同じくらい、もうわたしを救ってくれる人はいないのだという事実が、苦しかった。
わたしは姉がシャーペンを置く音に怯える子どもだった。八つ年上の姉は勉強の出来が良くなかったらしく、でも母に気に入ってもらうために一生懸命に勉強をしていた。しかし小学校低学年の時から姉を諦めていた母は、姉が望むような愛情を決して傾けることはなかった。
「お前は医者になるのよ。お姉ちゃんには無理だけれど、あゆみはお母さんの代わりに医者になってね」
母は医者になりかった人だった。高校生まで非常に優秀な成績を収めていたようだったけれど、女が医者になるなんてと父親に馬鹿にされ、有名でもなければ偏差値も高くない短大に押し込められたらしい。それに不満を抱えたまま結婚した母は、子どもに自分の人生のやり直しを歩むように求めた。旧帝国大学に入りなさい、医学部に入りなさい、医者になりなさい。小さいころから呪いのように言われてきた言葉だ。幼稚園の頃、歌手になりたいと書いて教室の壁に貼ったら、それを知った母親に「あゆみは医者になるのが夢でしょ? 違うの?」と責められた。それ以降、わたしの夢は「医者になること」に決められてしまって、わたしは自分の手で教室の掲示物を剥がした。
「お姉ちゃんもおいしゃさまになりたいの?」
「違うよあゆみ。あたしたちは医者になるように決まってるんだよ。なりたいなりたくない、じゃなくて、ならなくちゃいけないの」
姉も同じ目に遭ってきただろうに、姉はわたしを助けてくれることはなかった。他の子よりも早く文字を教えられているわたしを見ながら、いつもどこか睨みつけるような目をしていた。そうして黙々と勉強に励み、時折えんぴつを荒々しく置いた。姉は中学生になっても、母に勉強を教えられているわたしを見ると乱暴な動作でシャーペンを置き、消しゴムで書いたものを消していた。それは母に対する苛立ちよりも、わたしに対する苛立ちなのだろうと幼いながらに理解して、姉をほんの少し、怖く思った。
母はしばしば姉を罵った。出来が悪い、せっかく生んだのに、私の子供なのにちっともできない。そう言って、模試の結果を見るたびに文句を言った。姉はその頃すでに、子どもの作り方を知っていたらしい。子どもは親を選べないくせに、親は子どもの作る作らないを、生む生まないを選べることを知っていた。そして、自分の出来が悪いから妹が作られたのだと、気が付いてしまった。
「お母さんが欲しいのはあんただけだったみたいだね。あたしなんか産まれなければ良かったのにね」
中学生の姉の言うことは、五歳になるかならないかの年頃のわたしにはよく分からなかった。だけど、大学生になった今なら分かる。母が欲しかったのは、母の分身で、母の夢を叶える子どもだ。たったひとりの人間を慈しむために子どもを作ったわけではない。わたしたちは、勉強が出来なければ母にごく潰しのように扱われる存在だった。しかしわたしは文字を覚えるのも早く、計算を覚えるのも早かった。文章の塊を理解するのも早かった。みるみるうちに優秀と言われる子どもに変わっていったわたしは、姉がなりたかった姿そのもので、母からの疑似的な愛を与えられると共に、姉の心は離れていった。
高校生になった姉は、わたしが話しかけても返事をしてくれなくなった。母は勉強の話以外にはとても冷たいから、軽い雑談が出来るのは姉しかいなかったのに、姉はわたしが話しかけるたびに睨みつけてくるようになった。お姉ちゃん、そう呼んでも、その唇から小さく息を零して、シャーペンを乱暴に置くだけだった。安物のシャーペンは文字を書いていても机に置いてもキィキィと嫌な音を立てる。それは出て行ってくれと言われているみたいで、姉の視線とその音に、怯えた。
母に諦められている姉は、進路に口を出されることは無かった。どこで野たれ死んでも知らないとばかりに、少しの興味も持ってもらえなかったようだった。母はそれよりもわたしの中学受験を成功させるために一生懸命で、わたしは姉に対して、こうなってはいけないという気持ちばかり募らせていった。あれはわたしの失敗した姿なのだと、幼いながらに理解した。多分、そう思っているのが態度や顔に出ていたらしい。姉はますますわたしを睨むようになり、母には時折縋るような目をして、諦めたように県外の大学に進んでいった。ホストにはまっているとか、薬の飲みすぎで病院に運ばれたとか、父が大慌てで姉の住む地域に向かう出来事は度々あったけれど、母とわたしがそこに向かうことはなかった。
「あゆみは何になりたいの?」
父は無力だった。母の本質を見抜けないまま結婚し、ただ優秀な遺伝子を提供するための存在として扱われていてもなお、母に反抗しなかった。道具のように扱われる子たちをおろおろと眺め、逃げるように仕事に励んでいた。そのくせ、子どもの将来の夢にだけは過敏だった。
「わたしは医者になるのが決まっているの」
「歌手になりたいんじゃなかったのかい」
中学校の入学式に出席したのは、母ではなく父だった。初めて着る中学校の制服はぶかぶかしていて、身に着けるとかっこ悪かったのに、父は成長したねと褒めてくれた。
帰りの車の中では、雨が車体を打ち付ける音とワイパーの音が、静かに響いていた。
「お母さんの言う通り、私立の学校に入学したよ。わたしはお母さんの言う通りにするしかないの」
そうしないと、お姉ちゃんみたいになっちゃうから。その言葉を飲み込む。すると父はわたしが隠した言葉を理解したように、困ったように笑った。
「これはお姉ちゃんにも言ったんだけどな、いつか家族以外にお前を必要としてくれる人が現れるよ」
「そうかな」
「人間、みんな欠けているんだ。欠けたところを繋げて、ちょうど重なるくらいがうまくいくんだよ」
「お父さんとお母さんも、欠けたものを繋げたら重なるの?」
どうかなあ。父はまた困ったように笑った。ほら、お父さんとお母さんはうまくいっていない結婚だったんじゃない。わたしたちは失敗作だったってことじゃない。そう思ったら胸のうちをつきりと痛みが走って、うつむいた。
「お前もお姉ちゃんも、きっとそういう人に出会えるよ」
そうだといいな。父の手前そう呟いたけれど、きっとわたしたちにそんな未来は来ないのだと、薄っすら想像がついてしまった。わたしも姉も、誰かに埋め合わせてもらうには欠けすぎている。姉は特に愛情に飢え、わたしは捨てられることに怯えすぎている。誰かに埋め合わせてもらおうと思っても、ひとり分の愛では足りないのだ。きっと誰か大切な人が出来ても、愛というものを吸い取りすぎて、相手を空っぽにしてしまうのだと思う。
「お姉ちゃん、だからホストにはまっちゃったんだね」
わたしの一言は、雨音にかき消された。
「なんか言ったか?」
「なんでもない」
わたしたちが母に道具のように扱われていても、助けることのなかった父には、分からなくて良いと思った。
わたしは人目を気にしすぎる中学生になった。成績でクラス分けがされる中高一貫校では、最初の一年が今後の学校生活を決めてしまうように思えたから、わたしは誰にも嫌われないように、誰にも睨まれないように、期待されすぎないように振る舞った。そして皆も自分の六年間を左右する一年をどう過ごすかに悩み、皆人という集団の中に溶けていった。人に怯えているわたしはその集団に溶けることはできず、浮いてしまった。
教室は水みたいだった。誰かの意見ひとつで色を変える水。誰かが溺れても、水は自らの力で退くことはなく、誰かが出口を開けてくれるのを待っている。それどころか一度溺れた人を飲み込むように、一度同化したクラスメイトは、もうその枠から外れられない。わたしはずっとその水の中で、背泳ぎを続けているようだった。溺れることもできず、岸に上がることもできず、ずっとまぶしい太陽に焼かれ続けて、水の中に半分だけ漬かっている。下から水でつつかれて、追い返す力も強くて、わたしは居場所を見つけられなかった。
「フジクラはどうしてそんなに生きづらいんだろうな」
何か月経ってもクラスというものに馴染めないわたしを見かねて、担任はしばしばわたしを呼び出した。多感な年ごろだから苦しいこともあるだろう、しかしいつかきっと抜け出せる時が来る。そういうことを彼は語った。しかしわたしは「生きづらい」という言葉が引っかかって、彼の言葉を素直に受け入れることが出来なかった。
「先生。生きづらいって、どういうことですか」
問うと、彼は最初茶化されたのだと思ったらしい。子どもを揶揄うような笑みを見せたかと思ったら、こちらの困惑に気が付いたようで、眉を寄せる。
「生きづらい――繊細で感じやすい、と言えばいいかな。他の人がけろっと忘れてしまうようなことを、気にしているような状態だ」
「心が弱い、ってことですか」
担任は慌てて首を振った。
「いや、良いこともある。他の人が忘れてしまう、でも大切なことに気が付けるのは、生きづらい人だ」
褒められているのか、貶されているのかよく分からなかった。ただ彼の口調から、いつまでも教室の中で浮いているわたしを憐れんでいるような、面倒に思っているような感情がどこか伺えて、彼を担任として信じて良いのかが分からなくなった。
きっと、生きづらいとはこういうことなのだと思った。
友達が出来ないまま高校生になり、別の中学から入学してきた子となんとなくつるんだ。人と馴染めないなりに人と親しいふりをすることだけは出来るようになってしまって、本当に友達と呼べる人はいないのに、生きづらいと思ってしまうことは変わらないのに、教室の中に沈んでいることだけは覚えてしまった。でも正しく溺れてはいなくて、薄い膜で自分を包んで、水から乖離されているのを感じてはいた。
高校生になった途端、母の激しかった勉強への関与がさらにひどくなり、難関校であるのに関わらず、試験で満点を取らないと怒鳴られるようになった。姉の時は試験で赤点を取ろうが知らんぷりだったから、姉のほうがわたしよりマシだったのではないかと思ったけれど、きっと姉がわざと赤点を取ったのだろうということは分かるから、姉のことは思い出さないように、記憶の奥に押し込めた。
学校が終われば補習。それから塾。それから宿題。わたしは医学部に入らなくちゃいけないんだから、わたしは医学部に入らなくちゃいけないんだから。そう思って自分を追い込んでいたら、ある日突然、涙が止まらなくなってしまった。塾の帰りだった。多すぎる宿題に途方に暮れていたのはあったけれど、もっと根本的な、心の大事な部分が悲鳴を上げていたようだった。
家に帰ることもできず、まだ開いていた駅前のCDショップに立ち寄った。涙を隠すようにハンカチを持ち、店員の目から逃げるようにそこにあったヘッドフォンを掴むと、それは最近デビューしたばかりの歌手のシングルの試し聞きだった。
知らないアニメの主題歌だったから、そこに据えられたテーマは知らない。だけどそれは壊れて歪んでしまった心をそっと撫でて、繋ぎ合わせるような優しさがあって、わたしの胸にすっと染み込んでいった。これは生きづらい人のために作られた、救いの歌なのだ。父の言う、欠けたものを埋め合わせる歌なのだ。そう思った。
「あの、これ、ください」
余計に涙を流していたわたしに店員はぎょっとして、おろおろしながらCDを袋に入れてくれた。これが、わたしとユイナの出会いだった。
泥の中をはい回るような息苦しい高校生活だったけれど、ユイナの曲がわたしを救ってくれると思うと、なんとか耐えられた。母が押しつぶし、ただ父が見ているだけのわたしの大事な部分を、確かに包んでくれるのはユイナが紡ぐ言葉と、優しい声色だった。母はなんでこんな明るくない曲を好むのかと、私のスマートフォンから漏れる音を不思議に思っていたようだったけれど、明るい歌はわたしにはまぶしくて、焼かれてしまうのだと言っても、きっと理解してくれないと思ったから、黙っていた。
一浪したけれど、なんとか母が第二志望に挙げた大学の医学部に合格できた。東京で暮らすことになったわたしはやっと一人暮らしが叶い、母の支配からほんの少し逃れられる生活を送ることになった。しかし家族からの愛情を十分に受けることのなかったわたしを襲ったのは、抱えきれないほどの孤独だった。友達もいない、家族との仲も良好とは言えない。誰にも頼れない。そんなわたしに一人暮らしの部屋は暗すぎた。ひとりになったからと言って、医者になれという母の重圧から逃れることもできなくて、学校が開いているぎりぎりの時間まで学校で勉強をし、片手間に塾講師のアルバイトをし、CDやグッズを買うお金を稼いでいた。
「藤倉さんはなんで医者になりたいの?」
がむしゃらに勉強をしているわたしに、ある日学生番号がひとつ違う子が尋ねてきた。
「親に言われたから」
「あたしも。親が開業医で、跡継がないといけなくて」
「そう」
この頃から、わたしは人それぞれが生き地獄を抱えていることに気が付き始めていた。ただ他人の抱えている苦しいものに自分の身を浸すほど、皆お人よしではない。皆、自分のことで精いっぱいなのだ。わたしがこの人のことに踏み込まないのと同じように、この人がわたしの救いになることはないのだと思った。
「ねえ、ユイナって歌手知ってる?」
「ごめん、知らない」
「そう」
会話はそれきりで終わった。もう講義の話しかしないだろうと思った。
その点、アルバイトの同期は不思議な色を持つ人だった。人のことに踏み込まない、踏み込ませないくせに、会話のリズムだけは心地よかった。人と通じ合わなくても仲良くすることは出来るのだと、その人に教えられたような気がする。しかし彼女は救いを求める人でもなければ、救いを与える人でもなく、誰かに寄り添うことができるわけでもない、たったひとりで力強く生きていられる人だった。わたしには彼女がまぶしくて、太陽のように思った。だからこそ、少しだけ、嫌いだった。
「藤倉さんは学校どう? うちは調理実習がしにそう」
「栄養士の学校でも調理実習するんだ。こっちはまあ、なんとか」
「そっか」
このままだと多分留年させられそうだ、というのは黙っておいた。わたしは難関校になんとか入学できただけで、医者になれと言われているだけで、医者になりたいわけではない。医学部の勉強を楽しいと思っているわけでもなく、ただ母の圧力に逆らえないという理由だけでは難しい学問についていくのは厳しかった。
わたしは親に用意された道を歩くだけの存在で、でも親の用意した道を歩くことすらままならない。きっと、何者にもなれない。ただ生きづらさを抱えたまま、成長してしまっただけだ。せめてユイナのように自分の生きづらさを歌に出来たら良かったのだけれど、わたしはそういった才能は持っていなかった。
『きっと大丈夫。いつかあなたにも花が咲く』
ユイナの歌のように、いつか何者かになれるだろうか。医者になって、母に認めてもらえるのだろうか。そう思っていた時に、ユイナの訃報を見てしまった。
「なんで、なんで」
どうしてわたしをのこして死んでしまったの。わたしはこれからどうやって生きていったらいいの。ユイナの死よりも自分のことを心配する自分が醜くて、口の中が変な味がした。しばらくの間部屋で蹲って泣き続けていると、部屋の中のいたるところをユイナのCDやグッズで埋めていたことを思い出して、呆然としてしまう。
電話がかかってきたのは、その時だった。
「お姉ちゃん、なんで」
『わかんない。勘』
「なにそれ」
『泣いてるの?』
「好きな歌手が死んじゃったの」
電話越しに赤ちゃんの笑い声がした。旦那と思わしき人の声も。そういえば、結婚していたんだっけ、と遠いことのように思う。
『ユイナさん?』
「なんで分かったの」
『ネットみてたら、なんか急に。あんたのことずっと嫌いだったけど、でもやっぱりお姉ちゃんだからね。分かっちゃうんだよ』
「お姉ちゃん、まだわたしのこと嫌いだと思ってた」
『なんだろうね、自分の家庭が出来たらさ、分かったんだよ。あんたのこと嫌いなのはあんたのせいじゃないって』
「お母さんのせい?」
問うと、姉は電話越しに唸った。
『そうかも。でもお母さんも自分の親のせいで歪んだわけでしょ。お母さんもまあ被害者なわけで。許さないけど』
「よく分からない」
『ごめんごめん』
姉が笑う。赤ちゃんのきゃっきゃっと笑う声は、姉の今が少しでも幸せに傾いていることのように思えて、今まで首元でつかえていた疑問が、ゆっくりと零れた。
「わたしが生きづらいのって、わたしのせいなのかな」
『あんたのせいだけじゃないよ。あたしもあんたを追い詰めた』
「そんなこと言ったら、わたしだって」
『あたしもね、生きづらいって思ってた。けど今旦那いるし、子どもいるし。あたしを好きって言ってくれる人がいるから、なんとかやれてる』
「わたしを好きになる人なんて、いないよ。だからわたしはユイナの歌に救われていたんだよ」
『それってさ、あんたのためだけではないけれど、あんたみたいな人が他にいるから、歌って歌になるんだよ。だから響くの。ひとりじゃないってことだよ』
姉も母に投げ捨てられた人生を、随分苦労して過ごしたらしかった。その間にずっと考えていたことがあったのだろう。わたしの疑問に答えられるのは、きっとそういうことなのだ。
『いつかさ、生きていたんだなって思えるようになるよ。その時にはあんたは少し強くなって、前に進んでる』
姉は電話の向こうで、少しだけ笑った。それから、鍋が焦げちゃうと言って、少しだけ名残惜しそうに、電話を切った。
わたしがひとりじゃない? いつか生きていたのだと思える? 疑問はいくつもあって、まだ胸の中で蠢いている。だけど、そうであったらいいな、と思う気持ちは自然と思い浮かんできて、すっと染み込んでいった。
『春の訪れ。僕は目覚めを待っている』
ユイナの歌を、口ずさむ。そうだ、彼女の歌はわたしの心に残っている。死んだからといって、生きていたという事実が、作った歌がなくなるわけではない。わたしを救ってくれたということだって、消えない。
「あなたに出会えて良かった」
明日講義が終わったら、カラオケに行こう。ユイナの歌をたくさん歌って、彼女が生きていた事実を身に刻もう。それから、姉に今度遊びに行っていいか聞いてみよう。前に進み始めた姉の姿を見てみたい。
「生きてくれて、ありがとう」