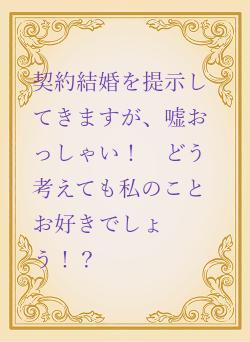「やっぱりさ、今時恋愛もタイパでしょ」
大学の調理実習の後の、飲み会だった。わたしたちは栄養学部生だけれど、管理栄養士になる上で、調理が出来ないと困る、という理由で、調理実習は必修の講義として設けられている。実際、わたしたちが就職して調理にメインで関わるかというと、必ずしもそんなことはなく、調理に携わるのは、現場を知るという目的か、人件費との関りでそうなっているという事例が多いらしい、と先輩に聞く。その会社に依るらしいから、一括りにして考えることは出来ない、とも聞いたけれど。
調理の練習もしないといけないけれど、それよりも大事なのは座学だ。家に帰ったら調理の練習もしつつ、座学の復習もしないといけない。それをする人としない人で大きく成績に差が出るのは、前期の期末試験で皆分かったろうに、遊び惚ける人は遊び惚けるし、バイトを優先する人はバイトを優先するし、飲み会が好きな人は飲み会が好きなままだ。「今日も調理実習疲れたねー、飲みにいこ」と班のメンバーが話していて、優希ちゃんも来る? ぜひ行こ! と話を振られて、断れなかった。わたしは飲み会なんて、好きではないのに。そもそも、なお二十を越しているのは、わたしだけだ。飲み会というより、ご飯会だ。
「恋愛にタイパってどゆこと」
「ほらぁ、あたしら忙しいじゃん。遊びたきゃバイトしなきゃいけないし。でも単位落とせないじゃん。だからほら、彼氏にばっかり時間使ってられない」
「それは分かる」
「夜中にだらだら電話するの好きだけどさ。でもそれ毎日は疲れるし」
「あんたが鬼電しといて何言ってんの」
メンバー六人のうち、盛り上がっているのは三人だけだった。イツメン、というやつらしい。なんであたしたち巻き込まれたんだろうね、と残る二人がアイコンタクトをとっている。みんなと仲良しなんて、理想でしかないのにね、気持ち悪いね、と。
「ほらさ、彼氏と付き合っても、彼氏のご機嫌取りしないと浮気されちゃうじゃない」
「男って結局やれるかやれないか、だもんね」
「でもそんな毎週会ってられなくない?」
成績、底辺のくせに、何言ってるんだろう。いや、これは失礼か。地下ドルのライブに頻繁に行って、友達と飲んで、大して勉強してもいないのに、学校が忙しい忙しい言い張って、彼氏との時間は持ちたくなくて、それをタイパと表現する。タイパというのは、使った時間に対して得るものの効率のことであって、人付き合いに使う言葉ではない気がする。そもそも、効率で測るものなのだろうか、人付き合いって。
「ねーねー、みんなの彼氏ってどんな感じ?」
「優希ちゃんはどうなの?」
わたしに話を振ってどうするのだろう、と思いながら、曖昧に笑う。「彼氏、いたことないから」と言えば、その三人はわっと顔を見合わせた。
「えーッ、マチアプやりなよぉ、すぐできるよ彼氏」
「うちの大学さー、高校の時から彼氏いた割合高いじゃん? 純正の女の子だ」
純正の女の子って、なんだ。気持ち悪い。反射的にそう思ったけれど、小学校の時、こういうきゃぴきゃぴした女の子を敵に回して、無邪気に、ただし陰湿にいじめられたことがある。彼女たちは中学校に入ってから、自分たちがいじめをしたという自覚を一切持たずに、なぜか自分たちが嫌われていると知って、どういうことかと詰め寄ってきたのだから、一層質が悪かった。こういう人種は敵に回してはいけない、という教訓として、十分すぎる。
「うーん、今はいいかな。男の人、苦手だし」
「まーね、女子大だとねぇ、どうしてもね。でもバイト先に男の人いるっしょ」
「でも優希ちゃん男遊びするタイプじゃないよね、純正の女の子だもんね」
あ、帰りたい。そう思った。だけど、話を切り上げて逃げることもできなくて、解散になった時は、いつの間にか十一時近くなっていた。終電まで、あと一時間くらい。
「あたし彼氏んち寄ってくわ、酔いすぎた」
「楽しんでね」
「ういっす」
東京方面の電車に乗るのは、わたし一人だけだった。みんな反対側か、別の路線を使って帰っていく。わたしは、冬空の、星が瞬く下でやっと息の仕方を思い出して、その場に座り込んだ。さっきまで座っていたのに、怠い。都会の人は、通行人はみんな冷たい。しゃがみこんでいる人も、地面で寝ている人も、景色のひとつとして通り過ぎていく。稀に優しい人がいたけれど、大丈夫です、平気です、と言って帰ってもらった。
『先輩、もう校舎出ました?』
メールを入れたのは、バイト先の塾の柚木先輩。頭が良くて、話すと論理的で、視野を広く持とうと努めている。頭が良い人は、論破が好きなイメージがあるけれど、彼は論破よりも聞く方がよほど好きらしく、何かあるとよく話を聞いてくれた。男の人だけれど、男性というよりは、お兄さんや先生みたいなポジションだ。わたしの中では。
『もちろん。麻雀なう』
『ほんと麻雀好きですね』
『徹夜麻雀、なんで好きな男多いのか、検証が終わっていない』
『なんですかそれ』
『で、どしたん』
『先輩は、人付き合いにタイパって言葉がふさわしいと思いますか?』
『ほうほう、この議題は興味深い。まずは高橋さんがなぜこの議題を選んだか教えてくれるかい?』
わたしは先ほど飲み会に呼ばれたこと、そこでクラスメイトが彼氏との付き合いをタイパ良くしたいと言っていたことを、文字にして打ち込んだ。
『ほうほう。ひとまず議論の前に、つまり高橋クン、まだ外にいるね』
『その通りです、柚木センセイ』
『こんな時間に一人でいたら危ないよ、俺そっちいくわ。駅にいて。何駅なのそこ?』
柚木先輩は、わたしがなかなか家に帰ろうとしないのを、知っている。土曜日も出来るだけ学校に籠って勉強をしているのも知っているし、居候先の祖父母と折り合いが悪いのも、知っている。悩みを抱えて家に帰った日には、ほしくない正反対の気遣いにいら立って、当たり散らして、その後に落ち込むような、そんな自傷行為を繰り返しているのも知っているから、わたしがまだ外にいると、すぐに分かったのだろう。
わたしは本当は、国立大学で栄養学を学びたかった。学歴は大事だし、真面目な大学の方が、気の合う人が多いような気がしたからだ。だけど栄養学を学べる国立大学が極端に少ないために、偏差値はわたしには高すぎた。現役の時は見事に落ちて、一年自宅で浪人しても、また落ちた。結局、頭が良い人もそうでない人もごちゃまぜに通う私立の栄養学部に通うことになって、人付き合いに苦労している。加えて、私立の理系大学の学費は、下に兄弟を抱えた我が家には厳しく、東京付近に家を持つ、親戚の家に間借りして棲むことになったのが、わたしの抱えるストレスを加速させていた。帰りたくない日ばかりだ。
のろのろ駅に向かうと、しばらくして、先輩が改札をくぐってきた。塾講師のバイトの帰りらしい、オフィスカジュアルな恰好だ。わたしは調理実習で動きやすい、シンプルな服。なんだかちょうどいい、と思った。終電まであと三十分。間に合わないから、諦めた。もういい。
「麻雀やってたのに、すみません」
「議題が面白そうだったから」
変な人だ、先輩は。そこに下心は一切ないように見えるのに、面倒見が良くて、研究が好き。考えるのが好き。わたしが提案した議題が面白ければ、バイト先のメンツでの麻雀をそっちのけにする。世間的には浮いているのだろうけれど、どうせわたしも浮いている。女のコミュニケーションには入れない。先輩みたいな人が、多分ちょうど良い。
「二十四時間営業のコーヒーショップと、二十四時間営業のハンバーガー、どっちが良い?」
「コーヒーですかね。先輩は?」
「ハンバーガー」
「それならじゃんけんですね」
行きたい場所が異なって、それが重要な案件でなければじゃんけん。そういうルールが、わたしたちにある。じゃんけんに気合が入る先輩は、突然小学生っぽくなるのだが、なぜかじゃんけんはわたしが強い。
「はい、じゃあコーヒーに決定で」
「異議なし」
「では行きましょう」
わたしたちはよく行くコーヒーショップで温かいコーヒーを頼み、先輩はそれに追加でホットサンドやら何やらを注文していた。窓際の席に座ると、電灯の下を歩く人の姿がちらちらうつる。
「――というわけで、彼女らの主張は、恋愛もタイムパフォーマンスが重要なのだそうで」
「なるほどね、そういう考え方ね」
「しかしそれは、恋愛をしたいがその人には時間を使いたくない、都合の良い人がほしい、という言葉を、都合よく表現しているのではなかろうか、と思いまして」
「ふむふむ、そう考えるのも分かるね」
「で、まずは恋愛とは何か、を定義しなければならないと思うのです」
「高橋さんの定義は」
「人それぞれ定義はあると思います。なので、彼女たちの定義からまず考えます」
先輩はコーヒーをやっと飲んだ。猫舌で、少し温くなってからが一番美味しいらしい。
「彼女たちの定義は、おそらく、『男って結局やれるかやれないか』という発言から、性交を伴う、ドキドキであったり、会って話したいと思う感情を肯定してくれる人かと」
「地下ドルとホストと何が違うのか聞いても良い?」
「地下ドルとホストは、お金を払うことで、肯定を得られます。自己肯定感です。ホストも地下ドルも行ったことがないので、推測ですが。肯定を、それらは買うのです」
「恋愛、というのは、買うのではないと?」
「そうです、恋愛、というのは、無償でそれらが与えられると、錯覚するものではないでしょうか」
「錯覚、がキーだね」
「そうです。しかし無償の愛を錯覚するためには、相手に無償の愛がほしいとアピールする行動が伴います」
「それが電話であったりデートであったりと」
「そうです。無償の愛を求めるのに、最低限必要な行動で済ませたい。それが彼女たちのいうタイパの良い恋愛であるように思います」
「理屈は通っているように、思うけれど。でも納得してないようだね」
「そう、理屈が通っているから、困るのです」
わたしもコーヒーを飲む。なるほどなるほど、と彼もコーヒーを飲む。
「さて、ここで問題にしたいのが、人付き合いは、タイムパフォーマンスで測れるか、ということです」
「ほう。続けて」
「人付き合いとは、双方への尊重がないと成り立たないものです。これは理屈というよりも経験や感情ですが。タイムパフォーマンスに依存して、最低限のやりとりで相手からの肯定を引き出す、というのは、依存ないしは、相手を軽んじる行為ではないかと」
「しかし人付き合いが面倒な人もいる」
「それはそう」
「人付き合いはしたくない、だけど肯定を得たい人ってどうしていると思う?」
「性交をするのではないでしょうか」
「性交で得をするのって男の方、って理屈かな」
双方が納得していれば、人間関係を築いていくことが出来るとは思う。それは、知っている。だけどわたしは、人間関係を均等に積み上げていくことができない。人の気持ちが分からないと、高校の時に先生に言われるくらいには、何かが欠けている。大学に入って、やっと友達が出来たと思ったけれど、その人はたった半年で大学を辞めてしまった。うつ病だった。結局わたしはクラスでひとりで、どうしたら欠けているものを埋められるのかを探して、そして人と交わるのを恐れて、ずっと人を観察している。その観察の目、面白いね。彼がそう言ったから、こうして、人と繋がれている。不思議なことに。
それからずっと議論が続いて、コーヒーがなくなった。時刻、深夜一時。
「うーん、それだとタイムパフォーマンスで人とのつながりが測れてしまうな」
「そうですね、今話してて気が付きました」
「相手の尊重の有無があるかどうか、それが双方に感じられるかどうかってことでいいのかな」
「ただそれを、タイムパフォーマンスを上げるため、と認識してしまうと、相手が人間から物になってしまうので、それに気を付けて接する必要がある、と認識すべきではないかと思いました」
「いいね」
高橋さんの終電すぎちゃった、と先輩が立ち上がる。議論が落ち着いたことの合図だ。話せてすっきりしたし、ある程度納得もしたので、わたしもこの店を出ることに異存はない。
「高橋さんは、歩いて帰る、タクシーで帰る、朝まで時間潰す、の三択が存在するけれど」
「歩きます。明日は土曜日ですし」
「送ります」
店の外は、冷たい空気が漂う。さぶい、と先輩が言って、少しおかしかった。
「俺さ、高橋さんと付き合っているんかって言われてさ」
「笑える」
「その距離感の男女っておかしいよって桜井に言われたんだよ」
「そうですね、桜井さんにはそう見えるのでしょうね」
「男女の友情はあり得ない派らしい」
「そういう人もいるでしょう。性交がその間に存在することが多いので」
先輩が、俺たちってそういう関係になると思う? と聞くから、わたしは「それはあり得ないでしょ」と返した。
「なんでわたしたちが、世間の目に合わせて、姿を変えないといけないかを先に話さないといけなくなります。カメレオンですか、わたしたち。なんだか今日、純正の女の子って揶揄されたのを思い出しました。話して良いですか?」
「お、それ面白い。歩きながら話そう」
思ったことをつらつら話しながら、きっと、自分たちは、これからもこんな関係を続けていくのだと思った。
大学の調理実習の後の、飲み会だった。わたしたちは栄養学部生だけれど、管理栄養士になる上で、調理が出来ないと困る、という理由で、調理実習は必修の講義として設けられている。実際、わたしたちが就職して調理にメインで関わるかというと、必ずしもそんなことはなく、調理に携わるのは、現場を知るという目的か、人件費との関りでそうなっているという事例が多いらしい、と先輩に聞く。その会社に依るらしいから、一括りにして考えることは出来ない、とも聞いたけれど。
調理の練習もしないといけないけれど、それよりも大事なのは座学だ。家に帰ったら調理の練習もしつつ、座学の復習もしないといけない。それをする人としない人で大きく成績に差が出るのは、前期の期末試験で皆分かったろうに、遊び惚ける人は遊び惚けるし、バイトを優先する人はバイトを優先するし、飲み会が好きな人は飲み会が好きなままだ。「今日も調理実習疲れたねー、飲みにいこ」と班のメンバーが話していて、優希ちゃんも来る? ぜひ行こ! と話を振られて、断れなかった。わたしは飲み会なんて、好きではないのに。そもそも、なお二十を越しているのは、わたしだけだ。飲み会というより、ご飯会だ。
「恋愛にタイパってどゆこと」
「ほらぁ、あたしら忙しいじゃん。遊びたきゃバイトしなきゃいけないし。でも単位落とせないじゃん。だからほら、彼氏にばっかり時間使ってられない」
「それは分かる」
「夜中にだらだら電話するの好きだけどさ。でもそれ毎日は疲れるし」
「あんたが鬼電しといて何言ってんの」
メンバー六人のうち、盛り上がっているのは三人だけだった。イツメン、というやつらしい。なんであたしたち巻き込まれたんだろうね、と残る二人がアイコンタクトをとっている。みんなと仲良しなんて、理想でしかないのにね、気持ち悪いね、と。
「ほらさ、彼氏と付き合っても、彼氏のご機嫌取りしないと浮気されちゃうじゃない」
「男って結局やれるかやれないか、だもんね」
「でもそんな毎週会ってられなくない?」
成績、底辺のくせに、何言ってるんだろう。いや、これは失礼か。地下ドルのライブに頻繁に行って、友達と飲んで、大して勉強してもいないのに、学校が忙しい忙しい言い張って、彼氏との時間は持ちたくなくて、それをタイパと表現する。タイパというのは、使った時間に対して得るものの効率のことであって、人付き合いに使う言葉ではない気がする。そもそも、効率で測るものなのだろうか、人付き合いって。
「ねーねー、みんなの彼氏ってどんな感じ?」
「優希ちゃんはどうなの?」
わたしに話を振ってどうするのだろう、と思いながら、曖昧に笑う。「彼氏、いたことないから」と言えば、その三人はわっと顔を見合わせた。
「えーッ、マチアプやりなよぉ、すぐできるよ彼氏」
「うちの大学さー、高校の時から彼氏いた割合高いじゃん? 純正の女の子だ」
純正の女の子って、なんだ。気持ち悪い。反射的にそう思ったけれど、小学校の時、こういうきゃぴきゃぴした女の子を敵に回して、無邪気に、ただし陰湿にいじめられたことがある。彼女たちは中学校に入ってから、自分たちがいじめをしたという自覚を一切持たずに、なぜか自分たちが嫌われていると知って、どういうことかと詰め寄ってきたのだから、一層質が悪かった。こういう人種は敵に回してはいけない、という教訓として、十分すぎる。
「うーん、今はいいかな。男の人、苦手だし」
「まーね、女子大だとねぇ、どうしてもね。でもバイト先に男の人いるっしょ」
「でも優希ちゃん男遊びするタイプじゃないよね、純正の女の子だもんね」
あ、帰りたい。そう思った。だけど、話を切り上げて逃げることもできなくて、解散になった時は、いつの間にか十一時近くなっていた。終電まで、あと一時間くらい。
「あたし彼氏んち寄ってくわ、酔いすぎた」
「楽しんでね」
「ういっす」
東京方面の電車に乗るのは、わたし一人だけだった。みんな反対側か、別の路線を使って帰っていく。わたしは、冬空の、星が瞬く下でやっと息の仕方を思い出して、その場に座り込んだ。さっきまで座っていたのに、怠い。都会の人は、通行人はみんな冷たい。しゃがみこんでいる人も、地面で寝ている人も、景色のひとつとして通り過ぎていく。稀に優しい人がいたけれど、大丈夫です、平気です、と言って帰ってもらった。
『先輩、もう校舎出ました?』
メールを入れたのは、バイト先の塾の柚木先輩。頭が良くて、話すと論理的で、視野を広く持とうと努めている。頭が良い人は、論破が好きなイメージがあるけれど、彼は論破よりも聞く方がよほど好きらしく、何かあるとよく話を聞いてくれた。男の人だけれど、男性というよりは、お兄さんや先生みたいなポジションだ。わたしの中では。
『もちろん。麻雀なう』
『ほんと麻雀好きですね』
『徹夜麻雀、なんで好きな男多いのか、検証が終わっていない』
『なんですかそれ』
『で、どしたん』
『先輩は、人付き合いにタイパって言葉がふさわしいと思いますか?』
『ほうほう、この議題は興味深い。まずは高橋さんがなぜこの議題を選んだか教えてくれるかい?』
わたしは先ほど飲み会に呼ばれたこと、そこでクラスメイトが彼氏との付き合いをタイパ良くしたいと言っていたことを、文字にして打ち込んだ。
『ほうほう。ひとまず議論の前に、つまり高橋クン、まだ外にいるね』
『その通りです、柚木センセイ』
『こんな時間に一人でいたら危ないよ、俺そっちいくわ。駅にいて。何駅なのそこ?』
柚木先輩は、わたしがなかなか家に帰ろうとしないのを、知っている。土曜日も出来るだけ学校に籠って勉強をしているのも知っているし、居候先の祖父母と折り合いが悪いのも、知っている。悩みを抱えて家に帰った日には、ほしくない正反対の気遣いにいら立って、当たり散らして、その後に落ち込むような、そんな自傷行為を繰り返しているのも知っているから、わたしがまだ外にいると、すぐに分かったのだろう。
わたしは本当は、国立大学で栄養学を学びたかった。学歴は大事だし、真面目な大学の方が、気の合う人が多いような気がしたからだ。だけど栄養学を学べる国立大学が極端に少ないために、偏差値はわたしには高すぎた。現役の時は見事に落ちて、一年自宅で浪人しても、また落ちた。結局、頭が良い人もそうでない人もごちゃまぜに通う私立の栄養学部に通うことになって、人付き合いに苦労している。加えて、私立の理系大学の学費は、下に兄弟を抱えた我が家には厳しく、東京付近に家を持つ、親戚の家に間借りして棲むことになったのが、わたしの抱えるストレスを加速させていた。帰りたくない日ばかりだ。
のろのろ駅に向かうと、しばらくして、先輩が改札をくぐってきた。塾講師のバイトの帰りらしい、オフィスカジュアルな恰好だ。わたしは調理実習で動きやすい、シンプルな服。なんだかちょうどいい、と思った。終電まであと三十分。間に合わないから、諦めた。もういい。
「麻雀やってたのに、すみません」
「議題が面白そうだったから」
変な人だ、先輩は。そこに下心は一切ないように見えるのに、面倒見が良くて、研究が好き。考えるのが好き。わたしが提案した議題が面白ければ、バイト先のメンツでの麻雀をそっちのけにする。世間的には浮いているのだろうけれど、どうせわたしも浮いている。女のコミュニケーションには入れない。先輩みたいな人が、多分ちょうど良い。
「二十四時間営業のコーヒーショップと、二十四時間営業のハンバーガー、どっちが良い?」
「コーヒーですかね。先輩は?」
「ハンバーガー」
「それならじゃんけんですね」
行きたい場所が異なって、それが重要な案件でなければじゃんけん。そういうルールが、わたしたちにある。じゃんけんに気合が入る先輩は、突然小学生っぽくなるのだが、なぜかじゃんけんはわたしが強い。
「はい、じゃあコーヒーに決定で」
「異議なし」
「では行きましょう」
わたしたちはよく行くコーヒーショップで温かいコーヒーを頼み、先輩はそれに追加でホットサンドやら何やらを注文していた。窓際の席に座ると、電灯の下を歩く人の姿がちらちらうつる。
「――というわけで、彼女らの主張は、恋愛もタイムパフォーマンスが重要なのだそうで」
「なるほどね、そういう考え方ね」
「しかしそれは、恋愛をしたいがその人には時間を使いたくない、都合の良い人がほしい、という言葉を、都合よく表現しているのではなかろうか、と思いまして」
「ふむふむ、そう考えるのも分かるね」
「で、まずは恋愛とは何か、を定義しなければならないと思うのです」
「高橋さんの定義は」
「人それぞれ定義はあると思います。なので、彼女たちの定義からまず考えます」
先輩はコーヒーをやっと飲んだ。猫舌で、少し温くなってからが一番美味しいらしい。
「彼女たちの定義は、おそらく、『男って結局やれるかやれないか』という発言から、性交を伴う、ドキドキであったり、会って話したいと思う感情を肯定してくれる人かと」
「地下ドルとホストと何が違うのか聞いても良い?」
「地下ドルとホストは、お金を払うことで、肯定を得られます。自己肯定感です。ホストも地下ドルも行ったことがないので、推測ですが。肯定を、それらは買うのです」
「恋愛、というのは、買うのではないと?」
「そうです、恋愛、というのは、無償でそれらが与えられると、錯覚するものではないでしょうか」
「錯覚、がキーだね」
「そうです。しかし無償の愛を錯覚するためには、相手に無償の愛がほしいとアピールする行動が伴います」
「それが電話であったりデートであったりと」
「そうです。無償の愛を求めるのに、最低限必要な行動で済ませたい。それが彼女たちのいうタイパの良い恋愛であるように思います」
「理屈は通っているように、思うけれど。でも納得してないようだね」
「そう、理屈が通っているから、困るのです」
わたしもコーヒーを飲む。なるほどなるほど、と彼もコーヒーを飲む。
「さて、ここで問題にしたいのが、人付き合いは、タイムパフォーマンスで測れるか、ということです」
「ほう。続けて」
「人付き合いとは、双方への尊重がないと成り立たないものです。これは理屈というよりも経験や感情ですが。タイムパフォーマンスに依存して、最低限のやりとりで相手からの肯定を引き出す、というのは、依存ないしは、相手を軽んじる行為ではないかと」
「しかし人付き合いが面倒な人もいる」
「それはそう」
「人付き合いはしたくない、だけど肯定を得たい人ってどうしていると思う?」
「性交をするのではないでしょうか」
「性交で得をするのって男の方、って理屈かな」
双方が納得していれば、人間関係を築いていくことが出来るとは思う。それは、知っている。だけどわたしは、人間関係を均等に積み上げていくことができない。人の気持ちが分からないと、高校の時に先生に言われるくらいには、何かが欠けている。大学に入って、やっと友達が出来たと思ったけれど、その人はたった半年で大学を辞めてしまった。うつ病だった。結局わたしはクラスでひとりで、どうしたら欠けているものを埋められるのかを探して、そして人と交わるのを恐れて、ずっと人を観察している。その観察の目、面白いね。彼がそう言ったから、こうして、人と繋がれている。不思議なことに。
それからずっと議論が続いて、コーヒーがなくなった。時刻、深夜一時。
「うーん、それだとタイムパフォーマンスで人とのつながりが測れてしまうな」
「そうですね、今話してて気が付きました」
「相手の尊重の有無があるかどうか、それが双方に感じられるかどうかってことでいいのかな」
「ただそれを、タイムパフォーマンスを上げるため、と認識してしまうと、相手が人間から物になってしまうので、それに気を付けて接する必要がある、と認識すべきではないかと思いました」
「いいね」
高橋さんの終電すぎちゃった、と先輩が立ち上がる。議論が落ち着いたことの合図だ。話せてすっきりしたし、ある程度納得もしたので、わたしもこの店を出ることに異存はない。
「高橋さんは、歩いて帰る、タクシーで帰る、朝まで時間潰す、の三択が存在するけれど」
「歩きます。明日は土曜日ですし」
「送ります」
店の外は、冷たい空気が漂う。さぶい、と先輩が言って、少しおかしかった。
「俺さ、高橋さんと付き合っているんかって言われてさ」
「笑える」
「その距離感の男女っておかしいよって桜井に言われたんだよ」
「そうですね、桜井さんにはそう見えるのでしょうね」
「男女の友情はあり得ない派らしい」
「そういう人もいるでしょう。性交がその間に存在することが多いので」
先輩が、俺たちってそういう関係になると思う? と聞くから、わたしは「それはあり得ないでしょ」と返した。
「なんでわたしたちが、世間の目に合わせて、姿を変えないといけないかを先に話さないといけなくなります。カメレオンですか、わたしたち。なんだか今日、純正の女の子って揶揄されたのを思い出しました。話して良いですか?」
「お、それ面白い。歩きながら話そう」
思ったことをつらつら話しながら、きっと、自分たちは、これからもこんな関係を続けていくのだと思った。