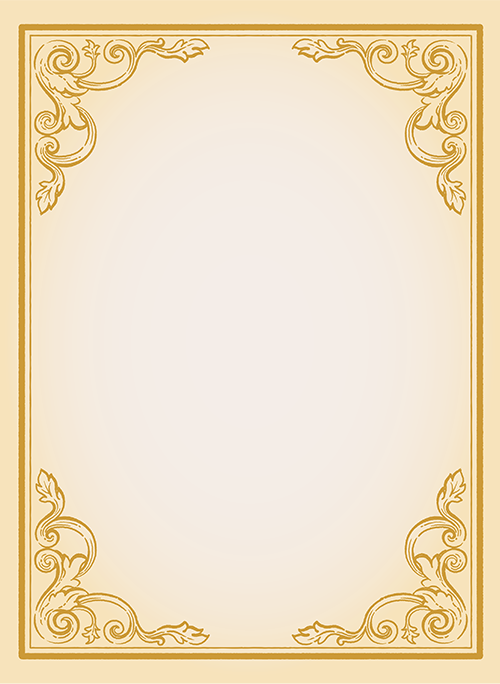追い越してやる。
それが、いつしか私の呪文になっていた。
幼いころから、自分は「できる子」だと信じていた。
褒められるのが当たり前。何をやっても、だいたい平均より上。
「すごいね」と言われるたび、私は自分の輪郭をなぞるように存在を確かめていた。
そんな私の前に、彼女は現れた。
成績、運動、言葉遣い、立ち居振る舞い。
すべてにおいて、彼女は私の「少し上」にいた。
しかも、飾らず、誇らず、どこまでも自然に。
誰にも嫌われず、誰よりも輝いていた。
「私なんか、全然だよ」
褒められるたび、肩をすくめて笑う彼女が、私はどうしようもなく憎かった。
その無自覚な輝きが、私の努力を踏みにじっている気がした。
追い越してやる。
寝ても覚めても、心の奥にこだまするその声に突き動かされて、私は走り続けた。
早朝からランニングをし、休み時間には単語帳を開き、誰からも好かれるように振る舞った。
すべては、彼女に勝つために。
だけど、結果はいつも同じだった。
彼女は「首席」。私はその下。
憎い。
どうして私じゃないの。
あれだけ努力しても届かない。何が足りないの。
才能? 環境? 運?
それとも、私はただ──普通なだけ?
*
そんなある日の放課後だった。
廊下でばったり彼女に会った私が、思わず声をかけた。
「一位、すごいね」
それは、どうしても抑えられなかった言葉だった。尊敬でも、羨望でもなく、ただ──
確認したかった。彼女の「本音」を。
彼女は、一瞬だけ目を見開いて、すぐに柔らかく微笑んだ。
「そうかな。ときどき、簡単なゲームみたいだよ。でも……ありがとう」
そのとき、彼女は廊下の壁にもたれていた。
足元は少し内向きで、肩はかすかに傾いていた。
まるで、そこに立っているだけでも精一杯のように。
「……簡単なゲーム?」
私は思わず聞き返した。
「うん。簡単で、やりがいがないゲーム。夢も目標もないのに、死ぬまでやらなきゃいけないの」
「でも、その成績なら、なんにだってなれるよ」
「……うん。先生は『医者』や『弁護士』になれるって言うけど、本当はなんにもやりたくない。……それなのに、親も同じこと言うんだ」
簡単な、ゲーム。
その言葉が、脳に焼きついた。
一位はすごいに決まってる。
私がどれだけ必死になっても手に入らないその場所を、彼女は「簡単」って言った。
一位にこだわっている自分が、ちっぽけに感じた。
私の努力が突然、無意味だって言われたみたいで。
私をばかにしてるの?
──そう思った。いや、思いたかったのかもしれない。
「憎い、憎い、憎い」
その言葉だけが、私の感情を支えていた。
嫉妬がなければ、自分が何者なのかもわからなくなるほどに。
ペンだこが真っ赤に腫れるくらいペンを握って、
朝から晩まで机に向かった。
虚しくて、ときどき涙がこぼれる。
でも、涙を拭く時間さえも無駄だと思った。
遊ぶ時間も、睡眠時間も全部削って、
すべてを勉強に捧げた。
たった一つの目標のため。
彼女に勝つために。
──そして、ある日、彼女が突然死んだ。
原因は自殺だった。
遺書には、こう記されていたという。
「いつも一位で、つまらなかった」
言葉の意味が、理解できなかった。
「彼女が死んだ」という現実が、頭に入ってこなかった。
そんなわけがない、と心のどこかで思い続けていた。
もう、順位表の一番上に、彼女の名前が載ることもない。
代わりに、私の名前が一位になった。
私は、勝ったのだ。
彼女に。
死んだ人間に。
でも、勝利の味は何もなかった。
誇りも喜びも湧かない。
あるのは、底の抜けたような虚しさだけだった。
──死んでしまったんだ。
彼女は、もう、どこにもいない。
その事実を、どうしても受け入れられなかった。
朝起きても、彼女のSNSを無意識に開いてしまう。
学食で「今日は彼女、何食べるのかな」なんて考えている自分がいる。
なのに、現実は静かで、取り返しがつかない。
「いつも一位で、つまらなかった」
あの言葉が、頭の奥で何度も反響した。
一位がつまらない?
じゃあ私は、なんのために、命を削ってまで二位を走っていたの?
──私は、何と戦っていたのだろう。
*
テストの順位発表があった、あの日。
教室の窓の外では、白い雲がゆっくりと流れていた。
風が吹くたびに、カーテンがゆらりと揺れる。
その向こうで笑い声が弾ける。
「また二位だったんだって」
「かわいそう。頑張ってるのにね」
教科書に視線を落としたまま、鉛筆の芯を折った。
机の上に砕けた黒い線がこぼれ落ちる。
誰もこちらを見ていない。
見られていないのに、見透かされているようだった。
手のひらに爪を立てる。
痛みは、なかった。
廊下を歩く彼女の姿が、窓の向こうに映る。
姿勢はまっすぐで、顔はいつもと変わらず。
何も背負っていないように見えた。
それが、悔しかった。
放課後の教室にひとり残り、黒板を見つめた。
小さく書かれた「おつかれさま」。
彼女の字かもしれないと思った。
指先でなぞると、チョークの粉がふわりと舞った。
一位じゃなければ、意味がない。
そう信じていた。
勝ちたかった。
せめて、認められたかった。
でも──
春の光に照らされた黒板消しの跡が、ぼやけて見えた。
何かを消しても、完全には消えない。
うっすらと残る白の痕が、消せなかった気持ちのようだった。
*
葬儀の日、空は晴れていた。
黒い服を着た人々の背中が、列を作って進んでいく。
私はただ、その背に続いて歩いた。
遺影のなかで、彼女は笑っていた。
何も知らなかったころと同じ顔で。
祭壇の花は、白くて静かだった。
指先で香典袋をなぞると、紙の感触がひどく冷たかった。
どこかに、まだ彼女の声がある気がして、振り返る。
けれど、そこには誰もいなかった。
夜、部屋の明かりもつけずに、床に座り込んだ。
足元に積まれたノートの山が、頼りなげに傾いていた。
ひとつ手に取り、ページをめくる。
詰め込んだ文字が滲んでにじんで、見えなくなった。
目の奥が熱くなる。
涙がこぼれる音だけが、部屋のなかに落ちていく。
私はずっと、何と戦っていたんだろう。
窓の外で、風が植木を揺らしている。
カーテンがふわりと膨らみ、すぐにしぼむ。
その繰り返しが、呼吸のようだった。
あのときの教室。
こぼれた鉛筆の芯。
ひとりきりで見上げた黒板。
笑われたあの声たち。
全部、私のなかにある。
彼女じゃない。
彼女の輝きでもない。
私が戦っていたのは、私だった。
静かに目を閉じる。
息を吸い込むと、空気が肺の奥にしみわたった。
もう誰かを追わなくていい。
誰かと比べなくていい。
誰かを憎む必要なんて、どこにもなかった。
机の上のノートに手を伸ばし、そっと開く。
白いページが、まっすぐ私を待っていた。
追い越してやる。
その相手は、これからは私だ。
私はゆっくりと立ち上がる。
誰もいない部屋に朝の光が差し込み始めていた。
それが、いつしか私の呪文になっていた。
幼いころから、自分は「できる子」だと信じていた。
褒められるのが当たり前。何をやっても、だいたい平均より上。
「すごいね」と言われるたび、私は自分の輪郭をなぞるように存在を確かめていた。
そんな私の前に、彼女は現れた。
成績、運動、言葉遣い、立ち居振る舞い。
すべてにおいて、彼女は私の「少し上」にいた。
しかも、飾らず、誇らず、どこまでも自然に。
誰にも嫌われず、誰よりも輝いていた。
「私なんか、全然だよ」
褒められるたび、肩をすくめて笑う彼女が、私はどうしようもなく憎かった。
その無自覚な輝きが、私の努力を踏みにじっている気がした。
追い越してやる。
寝ても覚めても、心の奥にこだまするその声に突き動かされて、私は走り続けた。
早朝からランニングをし、休み時間には単語帳を開き、誰からも好かれるように振る舞った。
すべては、彼女に勝つために。
だけど、結果はいつも同じだった。
彼女は「首席」。私はその下。
憎い。
どうして私じゃないの。
あれだけ努力しても届かない。何が足りないの。
才能? 環境? 運?
それとも、私はただ──普通なだけ?
*
そんなある日の放課後だった。
廊下でばったり彼女に会った私が、思わず声をかけた。
「一位、すごいね」
それは、どうしても抑えられなかった言葉だった。尊敬でも、羨望でもなく、ただ──
確認したかった。彼女の「本音」を。
彼女は、一瞬だけ目を見開いて、すぐに柔らかく微笑んだ。
「そうかな。ときどき、簡単なゲームみたいだよ。でも……ありがとう」
そのとき、彼女は廊下の壁にもたれていた。
足元は少し内向きで、肩はかすかに傾いていた。
まるで、そこに立っているだけでも精一杯のように。
「……簡単なゲーム?」
私は思わず聞き返した。
「うん。簡単で、やりがいがないゲーム。夢も目標もないのに、死ぬまでやらなきゃいけないの」
「でも、その成績なら、なんにだってなれるよ」
「……うん。先生は『医者』や『弁護士』になれるって言うけど、本当はなんにもやりたくない。……それなのに、親も同じこと言うんだ」
簡単な、ゲーム。
その言葉が、脳に焼きついた。
一位はすごいに決まってる。
私がどれだけ必死になっても手に入らないその場所を、彼女は「簡単」って言った。
一位にこだわっている自分が、ちっぽけに感じた。
私の努力が突然、無意味だって言われたみたいで。
私をばかにしてるの?
──そう思った。いや、思いたかったのかもしれない。
「憎い、憎い、憎い」
その言葉だけが、私の感情を支えていた。
嫉妬がなければ、自分が何者なのかもわからなくなるほどに。
ペンだこが真っ赤に腫れるくらいペンを握って、
朝から晩まで机に向かった。
虚しくて、ときどき涙がこぼれる。
でも、涙を拭く時間さえも無駄だと思った。
遊ぶ時間も、睡眠時間も全部削って、
すべてを勉強に捧げた。
たった一つの目標のため。
彼女に勝つために。
──そして、ある日、彼女が突然死んだ。
原因は自殺だった。
遺書には、こう記されていたという。
「いつも一位で、つまらなかった」
言葉の意味が、理解できなかった。
「彼女が死んだ」という現実が、頭に入ってこなかった。
そんなわけがない、と心のどこかで思い続けていた。
もう、順位表の一番上に、彼女の名前が載ることもない。
代わりに、私の名前が一位になった。
私は、勝ったのだ。
彼女に。
死んだ人間に。
でも、勝利の味は何もなかった。
誇りも喜びも湧かない。
あるのは、底の抜けたような虚しさだけだった。
──死んでしまったんだ。
彼女は、もう、どこにもいない。
その事実を、どうしても受け入れられなかった。
朝起きても、彼女のSNSを無意識に開いてしまう。
学食で「今日は彼女、何食べるのかな」なんて考えている自分がいる。
なのに、現実は静かで、取り返しがつかない。
「いつも一位で、つまらなかった」
あの言葉が、頭の奥で何度も反響した。
一位がつまらない?
じゃあ私は、なんのために、命を削ってまで二位を走っていたの?
──私は、何と戦っていたのだろう。
*
テストの順位発表があった、あの日。
教室の窓の外では、白い雲がゆっくりと流れていた。
風が吹くたびに、カーテンがゆらりと揺れる。
その向こうで笑い声が弾ける。
「また二位だったんだって」
「かわいそう。頑張ってるのにね」
教科書に視線を落としたまま、鉛筆の芯を折った。
机の上に砕けた黒い線がこぼれ落ちる。
誰もこちらを見ていない。
見られていないのに、見透かされているようだった。
手のひらに爪を立てる。
痛みは、なかった。
廊下を歩く彼女の姿が、窓の向こうに映る。
姿勢はまっすぐで、顔はいつもと変わらず。
何も背負っていないように見えた。
それが、悔しかった。
放課後の教室にひとり残り、黒板を見つめた。
小さく書かれた「おつかれさま」。
彼女の字かもしれないと思った。
指先でなぞると、チョークの粉がふわりと舞った。
一位じゃなければ、意味がない。
そう信じていた。
勝ちたかった。
せめて、認められたかった。
でも──
春の光に照らされた黒板消しの跡が、ぼやけて見えた。
何かを消しても、完全には消えない。
うっすらと残る白の痕が、消せなかった気持ちのようだった。
*
葬儀の日、空は晴れていた。
黒い服を着た人々の背中が、列を作って進んでいく。
私はただ、その背に続いて歩いた。
遺影のなかで、彼女は笑っていた。
何も知らなかったころと同じ顔で。
祭壇の花は、白くて静かだった。
指先で香典袋をなぞると、紙の感触がひどく冷たかった。
どこかに、まだ彼女の声がある気がして、振り返る。
けれど、そこには誰もいなかった。
夜、部屋の明かりもつけずに、床に座り込んだ。
足元に積まれたノートの山が、頼りなげに傾いていた。
ひとつ手に取り、ページをめくる。
詰め込んだ文字が滲んでにじんで、見えなくなった。
目の奥が熱くなる。
涙がこぼれる音だけが、部屋のなかに落ちていく。
私はずっと、何と戦っていたんだろう。
窓の外で、風が植木を揺らしている。
カーテンがふわりと膨らみ、すぐにしぼむ。
その繰り返しが、呼吸のようだった。
あのときの教室。
こぼれた鉛筆の芯。
ひとりきりで見上げた黒板。
笑われたあの声たち。
全部、私のなかにある。
彼女じゃない。
彼女の輝きでもない。
私が戦っていたのは、私だった。
静かに目を閉じる。
息を吸い込むと、空気が肺の奥にしみわたった。
もう誰かを追わなくていい。
誰かと比べなくていい。
誰かを憎む必要なんて、どこにもなかった。
机の上のノートに手を伸ばし、そっと開く。
白いページが、まっすぐ私を待っていた。
追い越してやる。
その相手は、これからは私だ。
私はゆっくりと立ち上がる。
誰もいない部屋に朝の光が差し込み始めていた。