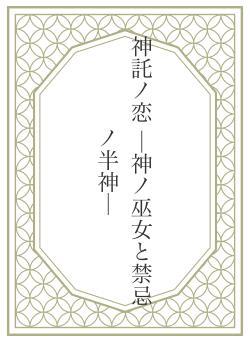空に呑み込まれそうだった。
朝焼けがゆっくりと動いていく。
茜色、薄紅色、韓紅。
雲がまるで魚のように空を泳いでいる。雲は、呼吸して、その度に分裂している。
雲は生きているんだと、思う。
あの雲から、うっすらと湧き出ているのは、菫色。そして、所々漏れ出づる朝陽に空が焦がされていく。
あぁ、これは、何という名前の色だろう。
赤褐色、栗色、紅檜皮。そのどれにも当てはまらない胸を焦がすかのような色。そして、それらを全て包み込むかのような群青色。
そうだ、世界は青に守られているんだ。
この空にしよう、原田瑞葉は直感でそう思った。この空に最後の勝負を託そう、と。
全国高校生絵画コンクール。
原田瑞葉にとって三度目の挑戦だった。そして、高校生活最後の大きなコンクールでもある。これが終わったら、受験勉強に精を出さねばならない。
瑞葉の通う県立青陵高校は、普通科と特進科に分かれていた。簡単に言えば、部活に明け暮れる三年間か、勉強に明け暮れる三年間か。特に特進科は、全国でもトップクラスの偏差値を誇っている。瑞葉は普通科で、美術部に所属し、文字通り部活に明け暮れる毎日を過ごしていた。だが、今年はもう受験生だ。特進科程ではないが、周りも受験を意識し始めている。
授業って、なんのためにあるんだろう。
二時間目の数Ⅱの時間。瑞葉は担当教師の明朗快活な数学の授業をぼんやりと眺めていた。それはまるで、視界の端で捉える景色のように瑞葉にとってはどうでもいいものだった。ノートの隅に、幾つもの小さな空を生み出す。シャーペンだけで描くモノクロの空はつまらない。
早く、部活の時間にならないかな。
ビブン、セキブン。
この先、どこで使うのか分からないそれらの単語と数字の羅列をただひたすらにノートに書き写していく。近くの席の運動部の子たちは、あくびを嚙み殺しながら授業を受けている。特進科の先生は違うと思うけれど、普通科の先生は、誰も注意したりしない。
自己責任。もう、そういう年代に入っているのだ。それは、楽、だけれどもどこか心許ない鎖に緩やかに繋がれているようでもある。
春の空はこんなにも優しくて、私とここではないどこかを繋いでくれるのに、高校生の私は、この狭い世界に繋ぎ留められている。空は毎日違っていて、一瞬だって同じ表情は見せてくれないのに、学校で過ごす時間は代わり映えしない。
瑞葉にとって、絵を描いている時だけが、自分らしくいられる時間だった。
あの頃の私は、すべてから解放されたかった。女子特有の面倒くさい人間関係から。義務のようにすら思える恋愛から。学校や社会の規則から。ーーそして、先の見えない将来からも。幸運にも、私は自分をこの世界から切り離す術を持っていた。絵を描いている時、私はこの世界にはいなくて、友達とか家族とか、進路とか、そういった身体を重くする重力から解放されて浮遊する。ここではないどこかで、私は心を休めることができる。
絵を描くことは、私にとってこの世界で息をすることを辞めることだった。
あまりにも理解できない数学の解法に辟易して、机の引き出しの中から、空白の進路希望調査票を取り出した。
絵なんて、描いて、どうするの?
昨夜の母の疲れ切った声が蘇る。昨年、離婚してからパートを始めた母は忙しそうで、いつもイライラしている。瑞葉の進路に対しても、難色を示すようになった。昨日は、部室に残って遅くまで水彩画の練習をしていた。
どうして、そんなこと、言うの。
喉元まで出かかった言葉を消して、ただの趣味だし、と逃げた。
母の言いたいことは分かっている。絵を描き続けた先に、何があるのか。
なにもなかったら――そう思うと、私はとても、怖い。
いつだったか、親友、と言っていいのか分からない――けれど少なくとも私はそう思っている國重璃光は「瑞葉は夢があって、しかもそれに向ってちゃんと努力してるからすごいよ」と零した。
夢って、なんて甘美な響きなんだろう。すごく、子供じみている。それは言外に、自分が子供じみているのではないかということだ。
私からしたら、成績優秀で、スポーツもできて、人望の厚い璃光の将来の方が明るく見える。どれも、私にはないものばかりだ。
高二の学年末試験で、最下位から数えた方が早い順位を取ってしまったとき、私の試験勉強の努力は何だったんだと愕然とした。授業も、それなりには聞いていた。試験勉強も、部活と自主練習の合間を縫って時間を確保した。サボっていたわけではない。それなのに、どうして。
勉強をする、その先に、私は将来を見出せなかった。
私は、絵を描くことしかできない。
それを、すごいねって、言われても、それしかないからって否定する。
何もかもできないことが多くて、その中にたった1つだけ、ひとよりもほんの少しだけ誇れることがあるとしたら。それはきっと、絶対に手放してはいけないものなのだと、思う。暗闇でたったひとつ、輝く星。それは、泣いてしまいそうなくらい綺麗だ。
絵を描く、その先に、何もなかったとしても。
救いを求めることを、赦してほしい。
*
ずっと、息苦しかった。
初めて、瑞葉が描いた絵を見たとき――それは、抜けるような青空だった。國重璃光は、ひとりで、泣いていた。
高校一年の文化祭、お祭り騒ぎの喧騒から逃げるようにたどり着いた美術室で、私は、原田瑞葉の絵と出合った。
夏の始まりを知らせるように、蝉の鳴き声が誰もいない南校舎の美術室に響いていた。特進課三年の教室は、東校舎の二階に位置する。南校舎の端にある美術室からはずいぶん離れているから、こんな朝早くに特進課の生徒と会うことはない。
部室が並んでいる南校舎の三階が、部活動の時間になると活気づいているのを私は青春とはかけ離れた場所でいつも感じている。
美術室には、部員たちの描きかけの絵がイーゼルに立てかけられている。その中でも、やっぱり目を引くのは、胸を衝くような朝焼けの水彩画と全てを攫っていってしまいそうな海を描いた油絵だった。空の絵は瑞葉で、海の絵は美術部創立以来の天才で、油絵の貴公子と呼ばれている北谷紫悠の絵だ。
「あれ、今日も来てくれたの?夏休みまで、わざわざいいのに」
瑞葉の声で、我に返った。
「今日も今から夏期講習があるから。これ、コンクールに出すの?」
「まだ、下絵なんだけどね。今回は、美術部以外も全員提出だよね。璃光はどうするの?」
「うーん、私は誰かにモデルをお願いして人物画にしようかなって思ってる。瑞葉はやっぱり、空にするの?」
「もちろん、私は空一択だから。まぁ多分、北谷は今回も海だろうね。今回こそは負けないから」
瑞葉は昨年のコンクールで準優勝だった北谷にあと一歩で及ばず、佳作となったことを今も根に持っている。それだけ、真剣に絵と向き合っているということだ。
私は、瑞葉の絵が大好きだった。あと、絵に対して一生懸命なところも。それに比べて同じクラスの北谷は、いけ好かない。瑞葉とは正反対の努力のかけらもない奴だと思う。第一、やる気が見受けられない。口には出さないけれど、最後のコンクールぐらい瑞葉に花を持たせてあげればいいのに、と思う。
「そっか、応援してる。瑞葉の方が絶対上手いって」
瑞葉が口をパクパクさせながら何かを訴えている。
「聞き捨てならねぇな」
まずい……聞かれていたようだ。
「原田の絵ってさ、なんかこう、審査員ウケは良さそうだよな。まあ、その下絵じゃ俺の足元にも及ばないけどな」
「なにそれ、嫌みのつもり?北谷の絵は抽象的すぎるんだよ」
珍しく、瑞葉も言い返す。
二人の絵は、良くも悪くも対照的だ。瑞葉は水彩絵の具を使って、細部まで綺麗に仕上げるのが持ち味なのに対して、北谷の絵は大胆な構図で、素人には分からないような抽象的な表現がなされている。繊細な水彩画と大胆な油絵。果たして、今年のコンクールの軍配はどちらに上がるのだろうか。
受験生である以上、夏休みだからと言ってうかうかとはしてられない。今日も朝から課外授業がある。昼前には終わるけれど、帰りの時間帯は冗談みたいに暑い。
國重璃光は、勉強が得意で優秀だった。全国模試も上位が常で、おまけに運動もそこそこできたから、周りからは一目置かれていた。自分でも自覚があるぐらいには。だから、部活熱心な瑞葉とは、全く違う世界線を生きていた。璃光にとって、特進課の生徒はいつ自分の立場を脅かすか分からない優秀な原石の集まりだった。だからこそ、瑞葉は数少ない気の置けない親友である。口を開けば模試や堅苦しい話ばかりする周りの人間と違って、瑞葉の話はすごく面白かった。瑞葉の絵を見ていると、綺麗な音楽を聴いているようないい気分になった。瑞葉と話すと、気持ちが、楽になる。璃光には、趣味らしき趣味というものがなかった。器楽部に入ってはいるものの、もはや幽霊部員だ。幼くして亡くなった母の分まで背負っているつもりなのか、厳格な祖母が部活をすることを良く思わない。ピアノを、弾きたかった。
全国模試でいつも上位をキープしているからか、國重さん、と同級生からもさん付けで呼ばれることがある。正直言って、やめてほしい。私はそんなに、すごくない。それは、私を知らないから、言えることだ。
瑞葉といることも、表面上は瑞葉が私を慕っているように思う人が多い。表面上は。
だけど、本当は違う。
全くの逆だ。私が瑞葉に憧れて慕っているんだ。瑞葉の絵に対する熱意とか努力を心底格好いいと思っている。話しかけたのも自分からだった。多分、私が瑞葉に憧がれてるなんてことは、誰も知らない。瑞葉でさえも。私は、憧れる側じゃなくて、憧れられる側の人間だから。だけど、高校という狭い世界の中でみんなから憧れられる人間なんて、大したことない。その他大勢の憧れる側の人間との差なんてほとんどない。
最初に瑞葉を知ったのも、ちょうどこのコンクールで瑞葉が入賞して、学校で表彰されている姿を見たのがきっかけだった。もちろん、北谷も表彰されていたけれど。最初はただ単に絵が上手な子という認識だった。そして多分、私と関わる事はない子。瑞葉は、特進科ではないから接点などできるはずもない。もともと、絵に興味があったわけではなかった。けれど、高一の文化祭で、初めて瑞葉の絵を見た時から、私はずっと瑞葉に近づきたかった。この絵を描く子は、どんな世界を見ているんだろう。初めての感情だった。私にとって他人は気を使わなければいけない存在で、自分を見せてはいけない存在で、誰と笑っていても特段、楽しくはなかった。頭が良くて、品行方正で、家柄もよくて。周囲から持たれるそんなイメージに私は押しつぶされそうだった。だが、そのパブリックイメージに加担したのは、紛れもなく私自身だった。実際のところは、仕事ばかりしている無口な父親と、厳しい祖母がいるだけだ。厳しい祖母に叱られないため、そして姉の分まで、私が頑張らなくてはいけない。そんな思いから、必死に勉強をした。誰に対しても、分け隔てなく親切にした。学校では、どんな時も笑顔を崩したりはしなかった。全てがいっぱいいっぱいで、それを誰かにぶちまけてしまいたかった。その衝動は、どんどん大きくなってきているように感じる。
この子なら、私の気持ちを分かってくれるんじゃないか。瑞葉の絵を見ながら、美術室で泣きながらそう思っていた。
そんな矢先、高一の三学期に行われた研修旅行で、瑞葉と同じ班になった。例年、青陵高校の特進科と普通科で行われる研修旅行は、私たちの代だけ行き先が違ったのだ。難関大合格を目指す特進科は大学のキャンパス、部活熱心な普通科は体力づくりということで登山キャンプ……のはずだったがその年はなんでも特進科の受け入れ先の大学が見つからなかったとかで、急遽特進科と普通科の合同キャンプに変更されたのだ。どうせならこの機会に特進科と普通科の交流を図ろうということで、班編成も両学科混合になったのだった。このキャンプで交友関係が広がったと言う子は多い。私達の代以降は、通常の研修旅行に戻ったらしく、この話をすると後輩達からは羨ましがられる。一部では、青陵のキセキとも言われているらしい。キセキって言う程ではない気もするけれど、確かに楽しかったし、瑞葉とも仲良くなれたから、やっぱりキセキだったのかもしれない。
瑞葉は、正直言って損な子だと思う。殊、対人関係に関しては。愛想とか笑顔とかそういうのがちょっと下手だ。原田さんって冷たいという声をよく聞くが、そう言うあなた達の方がよっぽど冷たいんじゃないのと言いたくなるくらい本当は優しい子だった。
研修旅行で、瑞葉と同じ班になった時、瑞葉は誰に対しても興味がなさそうだった。それに加えて、大人しい子だからか、同じ班だった他の女子からは、空気のように触れられない存在にされていた。だから、思い切って自分から話しかけた。その頃好きだったマイナーバンドを瑞葉も知っていたことから、急速に距離が縮まった。
高校に入って、初めて心から笑った瞬間だった。
普通科の瑞葉とは、放課後の美術室で部活が始まる前にほんの少し話すのが日課になっていた。初めて瑞葉の絵を見た時から、私は瑞葉の絵が一番好きだった。私が瑞葉の絵を見て泣いていたことは、恥ずかしくて本人には言えないけれど。
学校の自習室の前を通ると殺気立った熱を感じる。暑いのが余計に暑くなる。席の大半を占めているのは、やはり三年生だ。受験について、夏休みの過ごし方をさんざん聞かされてきた。学校の自習室を利用しなさい、分からなかったらすぐに質問に来なさい、とか。だけど、璃光は学校の自習室はどうしても入る気になれない。特に三年になってからは。三年になってから、みんなピリピリし過ぎている。自習室の空気が良い例だ。先生は、その緊張感が良いんだとか言うけれど、先生は何を言っているのだろう。みんな顔の色がおかしいじゃないか。殺気立った赤か血の気が引いた青。過ぎたるは及ばざるが如しってやつだ。足速に自習室の前を通りすぎる。まだ塾の自習室や図書館の方がましだ。
学校を出て、自転車に乗る。しばらくしてから、うだるような夏の暑さに耐えきれず、瑠璃は、コンビニの駐輪場に自転車を止めた。
アイスを買ってコンビニを出ると、駐輪場には篠田玲路がいた。高校に入ってからは、話した記憶がない。二人きりになるのは、中学の時以来だろうか。
中学から一緒で、それなりに親しかった時期もあった。だが、あることをきっかけにお互いに距離を置くようになっていた。
玲路は、中学時代の璃光が唯一、気を許していたひとだった。
「お疲れ」
意外にも、玲路からの挨拶だった。
咄嗟のことに、声を詰まらせる。自分が玲路とどんな声で話していたかが分からない。
「大丈夫?」
「……あ、うんお疲れ様」
「それさ、半分ちょうだい」
玲路が指さしたのは璃光の買ったアイスだった。半分にぱきっとできるやつ。
「いいけど……」
久しぶりに話したのに、あの頃と変わらない態度の玲路に肩の力が抜けていく。
「夏期講習?」
「うん、玲路は?」
「俺は部活。相変わらず真面目にやってるんだな」
「はーほんと、嫌になるよ」
「出たな、本音」
「こんな模試ばっかだと嫌にもなるでしょ」
「……いいと思うけどな」
「え?」
「友達の前でくらい、気ぃ張らなくていいんじゃないの。俺に話すみたいに」
中学の頃の玲路の言葉を思い出す。
「そんな気に病む必要、ないんじゃねぇの。秋月はさ、自分のことを裏表の激しいヤツだって否定的に言うけどさ、周りの人や社会に迷惑なんてかけてないだろ。むしろ、そうやって成績トップを維持して、周りに気ぃつかいまくって、素直にすげぇなって思うよ。そんなん、誰だってしんどくなるだろ。どっかで、発散しないとやってけねぇよ。」
あの頃は、玲路だけが居場所だった。
だけど、誰かに寄りかかることの危うさを知ってしまった。
「そうだね」
それでも、誰にでも見せられるわけじゃない。
本当の気持ちも、壊れそうな自分も。
*
海に、呑み込まれそうだった。
北谷紫悠は毎朝、海に行くのが日課だ。
朝日が昇ると水温は、秒速0. 02℃ずつ上昇する。弾き出される泡は、一秒で消え、押し寄せる波は、二. 五秒で押し戻される。波の音は、淡々と一定のリズムを刻むメトロノームのようで、貝殻から聴こえるのは、無機質な機械音だ。まさに、海は周期の世界だ。その周期が俺の心に安定をもたらす。
そして、俺は周期の世界を画用紙に描く。退屈で暇だから。ただそれだけの理由で。
海の季節になると毎年やってくる全国高校生絵画コンクール。顧問のゆきねえに勧められて毎年出してきたコンクールも今年が最後。そもそも美術部もゆきねえに誘われて入った。美術の時間に俺が描いた絵を見たゆきねえから、そんなに退屈で持て余してるなら入ってみない?せっかくいいもの持ってるんだから、と言われて。中学の時は帰宅部で、高校に入ってからも部活になど入る気もなかった。しかし、それはこの高校が許さなかった。特進科の連中は、勉強で忙しいからという理由で帰宅部が認められていたが、普通科は半ば強制だった。この学校の普通科は、かなり部活熱心で、インターハイ出場や全国大会出場を経験している部活も多い。なんの目的もなく、家から一番近いからという単純な理由でこの高校を選んだ俺はそんな事知る由もなかった。絵を描くようになった俺は、様々なコンクールで賞を獲るようになった。どうやら俺は絵に向いていたらしい。上達が速く、中学の頃から絵を描いていた奴らをすぐに追い越してしまっていた。
だが、何一つ面白くはなかった。
*
國重に人物画のモデルを頼まれたとき、放課後をいつも一緒に過ごす相手が俺でいいのか、というのが率直な感想だった。國重が人物画を選んだことに、驚いたりはしなかった。俺は、國重の寂しさを知っていた。
國重とは、もともと同じ中学だった。その頃から、國重は成績優秀で生徒のみならず、教師からも一目置かれるような存在だった。友達に誘われて入った生徒会活動をしていた実績から、俺は青陵に推薦入試で合格している。純粋な学力だけで入った周りの大勢とは違っていたため、最初は授業についていくのに必死だったが三年目にも入れば、ずいぶん慣れていた。紫悠のような才能と器用さはないが、俺は多分、そこそこ要領がいい方なのだと思う。
勉強も、人間関係も、部活も、不満がないくらいには全て順調だった。ただ一つ、篠田玲路という存在の希薄さを除いては。
國重は、思っていたよりずっと繊細な子だった。それを知ったのは、中三の時。
成り行きで生徒会の書記になった俺は副会長になった國重と自然と仲良くなった。
だんだん、気を許してくれたのか愛想のいい女の子といった印象から、本音を話すときついのに、そのもっと奥に繊細さがある子という印象に変わっていった。
「好きだからだよ」
あの時、どう返したらいいのか分からなかった。
恋と友情の境目が、分からなかった。
朝焼けがゆっくりと動いていく。
茜色、薄紅色、韓紅。
雲がまるで魚のように空を泳いでいる。雲は、呼吸して、その度に分裂している。
雲は生きているんだと、思う。
あの雲から、うっすらと湧き出ているのは、菫色。そして、所々漏れ出づる朝陽に空が焦がされていく。
あぁ、これは、何という名前の色だろう。
赤褐色、栗色、紅檜皮。そのどれにも当てはまらない胸を焦がすかのような色。そして、それらを全て包み込むかのような群青色。
そうだ、世界は青に守られているんだ。
この空にしよう、原田瑞葉は直感でそう思った。この空に最後の勝負を託そう、と。
全国高校生絵画コンクール。
原田瑞葉にとって三度目の挑戦だった。そして、高校生活最後の大きなコンクールでもある。これが終わったら、受験勉強に精を出さねばならない。
瑞葉の通う県立青陵高校は、普通科と特進科に分かれていた。簡単に言えば、部活に明け暮れる三年間か、勉強に明け暮れる三年間か。特に特進科は、全国でもトップクラスの偏差値を誇っている。瑞葉は普通科で、美術部に所属し、文字通り部活に明け暮れる毎日を過ごしていた。だが、今年はもう受験生だ。特進科程ではないが、周りも受験を意識し始めている。
授業って、なんのためにあるんだろう。
二時間目の数Ⅱの時間。瑞葉は担当教師の明朗快活な数学の授業をぼんやりと眺めていた。それはまるで、視界の端で捉える景色のように瑞葉にとってはどうでもいいものだった。ノートの隅に、幾つもの小さな空を生み出す。シャーペンだけで描くモノクロの空はつまらない。
早く、部活の時間にならないかな。
ビブン、セキブン。
この先、どこで使うのか分からないそれらの単語と数字の羅列をただひたすらにノートに書き写していく。近くの席の運動部の子たちは、あくびを嚙み殺しながら授業を受けている。特進科の先生は違うと思うけれど、普通科の先生は、誰も注意したりしない。
自己責任。もう、そういう年代に入っているのだ。それは、楽、だけれどもどこか心許ない鎖に緩やかに繋がれているようでもある。
春の空はこんなにも優しくて、私とここではないどこかを繋いでくれるのに、高校生の私は、この狭い世界に繋ぎ留められている。空は毎日違っていて、一瞬だって同じ表情は見せてくれないのに、学校で過ごす時間は代わり映えしない。
瑞葉にとって、絵を描いている時だけが、自分らしくいられる時間だった。
あの頃の私は、すべてから解放されたかった。女子特有の面倒くさい人間関係から。義務のようにすら思える恋愛から。学校や社会の規則から。ーーそして、先の見えない将来からも。幸運にも、私は自分をこの世界から切り離す術を持っていた。絵を描いている時、私はこの世界にはいなくて、友達とか家族とか、進路とか、そういった身体を重くする重力から解放されて浮遊する。ここではないどこかで、私は心を休めることができる。
絵を描くことは、私にとってこの世界で息をすることを辞めることだった。
あまりにも理解できない数学の解法に辟易して、机の引き出しの中から、空白の進路希望調査票を取り出した。
絵なんて、描いて、どうするの?
昨夜の母の疲れ切った声が蘇る。昨年、離婚してからパートを始めた母は忙しそうで、いつもイライラしている。瑞葉の進路に対しても、難色を示すようになった。昨日は、部室に残って遅くまで水彩画の練習をしていた。
どうして、そんなこと、言うの。
喉元まで出かかった言葉を消して、ただの趣味だし、と逃げた。
母の言いたいことは分かっている。絵を描き続けた先に、何があるのか。
なにもなかったら――そう思うと、私はとても、怖い。
いつだったか、親友、と言っていいのか分からない――けれど少なくとも私はそう思っている國重璃光は「瑞葉は夢があって、しかもそれに向ってちゃんと努力してるからすごいよ」と零した。
夢って、なんて甘美な響きなんだろう。すごく、子供じみている。それは言外に、自分が子供じみているのではないかということだ。
私からしたら、成績優秀で、スポーツもできて、人望の厚い璃光の将来の方が明るく見える。どれも、私にはないものばかりだ。
高二の学年末試験で、最下位から数えた方が早い順位を取ってしまったとき、私の試験勉強の努力は何だったんだと愕然とした。授業も、それなりには聞いていた。試験勉強も、部活と自主練習の合間を縫って時間を確保した。サボっていたわけではない。それなのに、どうして。
勉強をする、その先に、私は将来を見出せなかった。
私は、絵を描くことしかできない。
それを、すごいねって、言われても、それしかないからって否定する。
何もかもできないことが多くて、その中にたった1つだけ、ひとよりもほんの少しだけ誇れることがあるとしたら。それはきっと、絶対に手放してはいけないものなのだと、思う。暗闇でたったひとつ、輝く星。それは、泣いてしまいそうなくらい綺麗だ。
絵を描く、その先に、何もなかったとしても。
救いを求めることを、赦してほしい。
*
ずっと、息苦しかった。
初めて、瑞葉が描いた絵を見たとき――それは、抜けるような青空だった。國重璃光は、ひとりで、泣いていた。
高校一年の文化祭、お祭り騒ぎの喧騒から逃げるようにたどり着いた美術室で、私は、原田瑞葉の絵と出合った。
夏の始まりを知らせるように、蝉の鳴き声が誰もいない南校舎の美術室に響いていた。特進課三年の教室は、東校舎の二階に位置する。南校舎の端にある美術室からはずいぶん離れているから、こんな朝早くに特進課の生徒と会うことはない。
部室が並んでいる南校舎の三階が、部活動の時間になると活気づいているのを私は青春とはかけ離れた場所でいつも感じている。
美術室には、部員たちの描きかけの絵がイーゼルに立てかけられている。その中でも、やっぱり目を引くのは、胸を衝くような朝焼けの水彩画と全てを攫っていってしまいそうな海を描いた油絵だった。空の絵は瑞葉で、海の絵は美術部創立以来の天才で、油絵の貴公子と呼ばれている北谷紫悠の絵だ。
「あれ、今日も来てくれたの?夏休みまで、わざわざいいのに」
瑞葉の声で、我に返った。
「今日も今から夏期講習があるから。これ、コンクールに出すの?」
「まだ、下絵なんだけどね。今回は、美術部以外も全員提出だよね。璃光はどうするの?」
「うーん、私は誰かにモデルをお願いして人物画にしようかなって思ってる。瑞葉はやっぱり、空にするの?」
「もちろん、私は空一択だから。まぁ多分、北谷は今回も海だろうね。今回こそは負けないから」
瑞葉は昨年のコンクールで準優勝だった北谷にあと一歩で及ばず、佳作となったことを今も根に持っている。それだけ、真剣に絵と向き合っているということだ。
私は、瑞葉の絵が大好きだった。あと、絵に対して一生懸命なところも。それに比べて同じクラスの北谷は、いけ好かない。瑞葉とは正反対の努力のかけらもない奴だと思う。第一、やる気が見受けられない。口には出さないけれど、最後のコンクールぐらい瑞葉に花を持たせてあげればいいのに、と思う。
「そっか、応援してる。瑞葉の方が絶対上手いって」
瑞葉が口をパクパクさせながら何かを訴えている。
「聞き捨てならねぇな」
まずい……聞かれていたようだ。
「原田の絵ってさ、なんかこう、審査員ウケは良さそうだよな。まあ、その下絵じゃ俺の足元にも及ばないけどな」
「なにそれ、嫌みのつもり?北谷の絵は抽象的すぎるんだよ」
珍しく、瑞葉も言い返す。
二人の絵は、良くも悪くも対照的だ。瑞葉は水彩絵の具を使って、細部まで綺麗に仕上げるのが持ち味なのに対して、北谷の絵は大胆な構図で、素人には分からないような抽象的な表現がなされている。繊細な水彩画と大胆な油絵。果たして、今年のコンクールの軍配はどちらに上がるのだろうか。
受験生である以上、夏休みだからと言ってうかうかとはしてられない。今日も朝から課外授業がある。昼前には終わるけれど、帰りの時間帯は冗談みたいに暑い。
國重璃光は、勉強が得意で優秀だった。全国模試も上位が常で、おまけに運動もそこそこできたから、周りからは一目置かれていた。自分でも自覚があるぐらいには。だから、部活熱心な瑞葉とは、全く違う世界線を生きていた。璃光にとって、特進課の生徒はいつ自分の立場を脅かすか分からない優秀な原石の集まりだった。だからこそ、瑞葉は数少ない気の置けない親友である。口を開けば模試や堅苦しい話ばかりする周りの人間と違って、瑞葉の話はすごく面白かった。瑞葉の絵を見ていると、綺麗な音楽を聴いているようないい気分になった。瑞葉と話すと、気持ちが、楽になる。璃光には、趣味らしき趣味というものがなかった。器楽部に入ってはいるものの、もはや幽霊部員だ。幼くして亡くなった母の分まで背負っているつもりなのか、厳格な祖母が部活をすることを良く思わない。ピアノを、弾きたかった。
全国模試でいつも上位をキープしているからか、國重さん、と同級生からもさん付けで呼ばれることがある。正直言って、やめてほしい。私はそんなに、すごくない。それは、私を知らないから、言えることだ。
瑞葉といることも、表面上は瑞葉が私を慕っているように思う人が多い。表面上は。
だけど、本当は違う。
全くの逆だ。私が瑞葉に憧れて慕っているんだ。瑞葉の絵に対する熱意とか努力を心底格好いいと思っている。話しかけたのも自分からだった。多分、私が瑞葉に憧がれてるなんてことは、誰も知らない。瑞葉でさえも。私は、憧れる側じゃなくて、憧れられる側の人間だから。だけど、高校という狭い世界の中でみんなから憧れられる人間なんて、大したことない。その他大勢の憧れる側の人間との差なんてほとんどない。
最初に瑞葉を知ったのも、ちょうどこのコンクールで瑞葉が入賞して、学校で表彰されている姿を見たのがきっかけだった。もちろん、北谷も表彰されていたけれど。最初はただ単に絵が上手な子という認識だった。そして多分、私と関わる事はない子。瑞葉は、特進科ではないから接点などできるはずもない。もともと、絵に興味があったわけではなかった。けれど、高一の文化祭で、初めて瑞葉の絵を見た時から、私はずっと瑞葉に近づきたかった。この絵を描く子は、どんな世界を見ているんだろう。初めての感情だった。私にとって他人は気を使わなければいけない存在で、自分を見せてはいけない存在で、誰と笑っていても特段、楽しくはなかった。頭が良くて、品行方正で、家柄もよくて。周囲から持たれるそんなイメージに私は押しつぶされそうだった。だが、そのパブリックイメージに加担したのは、紛れもなく私自身だった。実際のところは、仕事ばかりしている無口な父親と、厳しい祖母がいるだけだ。厳しい祖母に叱られないため、そして姉の分まで、私が頑張らなくてはいけない。そんな思いから、必死に勉強をした。誰に対しても、分け隔てなく親切にした。学校では、どんな時も笑顔を崩したりはしなかった。全てがいっぱいいっぱいで、それを誰かにぶちまけてしまいたかった。その衝動は、どんどん大きくなってきているように感じる。
この子なら、私の気持ちを分かってくれるんじゃないか。瑞葉の絵を見ながら、美術室で泣きながらそう思っていた。
そんな矢先、高一の三学期に行われた研修旅行で、瑞葉と同じ班になった。例年、青陵高校の特進科と普通科で行われる研修旅行は、私たちの代だけ行き先が違ったのだ。難関大合格を目指す特進科は大学のキャンパス、部活熱心な普通科は体力づくりということで登山キャンプ……のはずだったがその年はなんでも特進科の受け入れ先の大学が見つからなかったとかで、急遽特進科と普通科の合同キャンプに変更されたのだ。どうせならこの機会に特進科と普通科の交流を図ろうということで、班編成も両学科混合になったのだった。このキャンプで交友関係が広がったと言う子は多い。私達の代以降は、通常の研修旅行に戻ったらしく、この話をすると後輩達からは羨ましがられる。一部では、青陵のキセキとも言われているらしい。キセキって言う程ではない気もするけれど、確かに楽しかったし、瑞葉とも仲良くなれたから、やっぱりキセキだったのかもしれない。
瑞葉は、正直言って損な子だと思う。殊、対人関係に関しては。愛想とか笑顔とかそういうのがちょっと下手だ。原田さんって冷たいという声をよく聞くが、そう言うあなた達の方がよっぽど冷たいんじゃないのと言いたくなるくらい本当は優しい子だった。
研修旅行で、瑞葉と同じ班になった時、瑞葉は誰に対しても興味がなさそうだった。それに加えて、大人しい子だからか、同じ班だった他の女子からは、空気のように触れられない存在にされていた。だから、思い切って自分から話しかけた。その頃好きだったマイナーバンドを瑞葉も知っていたことから、急速に距離が縮まった。
高校に入って、初めて心から笑った瞬間だった。
普通科の瑞葉とは、放課後の美術室で部活が始まる前にほんの少し話すのが日課になっていた。初めて瑞葉の絵を見た時から、私は瑞葉の絵が一番好きだった。私が瑞葉の絵を見て泣いていたことは、恥ずかしくて本人には言えないけれど。
学校の自習室の前を通ると殺気立った熱を感じる。暑いのが余計に暑くなる。席の大半を占めているのは、やはり三年生だ。受験について、夏休みの過ごし方をさんざん聞かされてきた。学校の自習室を利用しなさい、分からなかったらすぐに質問に来なさい、とか。だけど、璃光は学校の自習室はどうしても入る気になれない。特に三年になってからは。三年になってから、みんなピリピリし過ぎている。自習室の空気が良い例だ。先生は、その緊張感が良いんだとか言うけれど、先生は何を言っているのだろう。みんな顔の色がおかしいじゃないか。殺気立った赤か血の気が引いた青。過ぎたるは及ばざるが如しってやつだ。足速に自習室の前を通りすぎる。まだ塾の自習室や図書館の方がましだ。
学校を出て、自転車に乗る。しばらくしてから、うだるような夏の暑さに耐えきれず、瑠璃は、コンビニの駐輪場に自転車を止めた。
アイスを買ってコンビニを出ると、駐輪場には篠田玲路がいた。高校に入ってからは、話した記憶がない。二人きりになるのは、中学の時以来だろうか。
中学から一緒で、それなりに親しかった時期もあった。だが、あることをきっかけにお互いに距離を置くようになっていた。
玲路は、中学時代の璃光が唯一、気を許していたひとだった。
「お疲れ」
意外にも、玲路からの挨拶だった。
咄嗟のことに、声を詰まらせる。自分が玲路とどんな声で話していたかが分からない。
「大丈夫?」
「……あ、うんお疲れ様」
「それさ、半分ちょうだい」
玲路が指さしたのは璃光の買ったアイスだった。半分にぱきっとできるやつ。
「いいけど……」
久しぶりに話したのに、あの頃と変わらない態度の玲路に肩の力が抜けていく。
「夏期講習?」
「うん、玲路は?」
「俺は部活。相変わらず真面目にやってるんだな」
「はーほんと、嫌になるよ」
「出たな、本音」
「こんな模試ばっかだと嫌にもなるでしょ」
「……いいと思うけどな」
「え?」
「友達の前でくらい、気ぃ張らなくていいんじゃないの。俺に話すみたいに」
中学の頃の玲路の言葉を思い出す。
「そんな気に病む必要、ないんじゃねぇの。秋月はさ、自分のことを裏表の激しいヤツだって否定的に言うけどさ、周りの人や社会に迷惑なんてかけてないだろ。むしろ、そうやって成績トップを維持して、周りに気ぃつかいまくって、素直にすげぇなって思うよ。そんなん、誰だってしんどくなるだろ。どっかで、発散しないとやってけねぇよ。」
あの頃は、玲路だけが居場所だった。
だけど、誰かに寄りかかることの危うさを知ってしまった。
「そうだね」
それでも、誰にでも見せられるわけじゃない。
本当の気持ちも、壊れそうな自分も。
*
海に、呑み込まれそうだった。
北谷紫悠は毎朝、海に行くのが日課だ。
朝日が昇ると水温は、秒速0. 02℃ずつ上昇する。弾き出される泡は、一秒で消え、押し寄せる波は、二. 五秒で押し戻される。波の音は、淡々と一定のリズムを刻むメトロノームのようで、貝殻から聴こえるのは、無機質な機械音だ。まさに、海は周期の世界だ。その周期が俺の心に安定をもたらす。
そして、俺は周期の世界を画用紙に描く。退屈で暇だから。ただそれだけの理由で。
海の季節になると毎年やってくる全国高校生絵画コンクール。顧問のゆきねえに勧められて毎年出してきたコンクールも今年が最後。そもそも美術部もゆきねえに誘われて入った。美術の時間に俺が描いた絵を見たゆきねえから、そんなに退屈で持て余してるなら入ってみない?せっかくいいもの持ってるんだから、と言われて。中学の時は帰宅部で、高校に入ってからも部活になど入る気もなかった。しかし、それはこの高校が許さなかった。特進科の連中は、勉強で忙しいからという理由で帰宅部が認められていたが、普通科は半ば強制だった。この学校の普通科は、かなり部活熱心で、インターハイ出場や全国大会出場を経験している部活も多い。なんの目的もなく、家から一番近いからという単純な理由でこの高校を選んだ俺はそんな事知る由もなかった。絵を描くようになった俺は、様々なコンクールで賞を獲るようになった。どうやら俺は絵に向いていたらしい。上達が速く、中学の頃から絵を描いていた奴らをすぐに追い越してしまっていた。
だが、何一つ面白くはなかった。
*
國重に人物画のモデルを頼まれたとき、放課後をいつも一緒に過ごす相手が俺でいいのか、というのが率直な感想だった。國重が人物画を選んだことに、驚いたりはしなかった。俺は、國重の寂しさを知っていた。
國重とは、もともと同じ中学だった。その頃から、國重は成績優秀で生徒のみならず、教師からも一目置かれるような存在だった。友達に誘われて入った生徒会活動をしていた実績から、俺は青陵に推薦入試で合格している。純粋な学力だけで入った周りの大勢とは違っていたため、最初は授業についていくのに必死だったが三年目にも入れば、ずいぶん慣れていた。紫悠のような才能と器用さはないが、俺は多分、そこそこ要領がいい方なのだと思う。
勉強も、人間関係も、部活も、不満がないくらいには全て順調だった。ただ一つ、篠田玲路という存在の希薄さを除いては。
國重は、思っていたよりずっと繊細な子だった。それを知ったのは、中三の時。
成り行きで生徒会の書記になった俺は副会長になった國重と自然と仲良くなった。
だんだん、気を許してくれたのか愛想のいい女の子といった印象から、本音を話すときついのに、そのもっと奥に繊細さがある子という印象に変わっていった。
「好きだからだよ」
あの時、どう返したらいいのか分からなかった。
恋と友情の境目が、分からなかった。