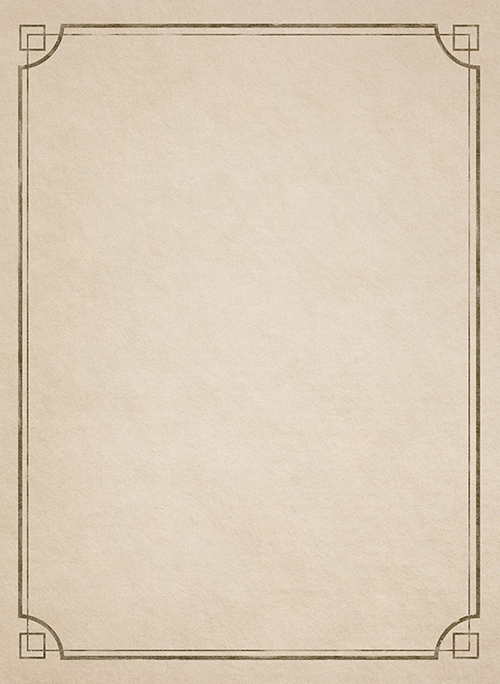五
三日後、平廬河東范陽節度使安禄山は、兵数二十万と号して軍を発した。日は天宝十五載(西暦七五四年)、十一月九日。
「我らは安節度使の軍。天子より密詔を受け、逆賊楊国忠を討つ。速やかに城門を開けい!」
軍は途上の州県でこう叫び、勢いよく南下する。
しかし常山というところへ来たとき、先鋒だった雷梧は、太守(長官)に訊ねられた。
「こんな大軍が通るとは何故だ。おかしいぞ」
雷梧は返答に困って、指示を仰いだ。
やがて、安禄山の巨体が現れる。ひどく不機嫌な顔をしていた。
「敵は天子の懐にいるのだ。隠密に行動せねば、こちらが逆賊に仕立てられてしまうではないか」
安禄山は太守を突き飛ばし、進軍を命じる。
こうして連日、軍は南へと向かい続けた。
ある日の行軍途中、雷梧は、草原で馬に草を食ませていた。
「世に平和を、か。僕にそんな手伝いができるなんて、思ってもみなかったな」
そんなつぶやきが出たとき、なぜか宇文平が嘲るように笑った。
「雷将軍は、本気で信じてるんですか。この軍が密詔を受けた義軍だって」
おかしな事を言う、と雷梧は呆れた。
「そうさ。途中から付き従って来た兵もたくさんいるじゃないか」
「そうですか。まあ、いいんです」
何かを伏せるように宇文平は言い、その場を去っていく。
雷梧は意味が分からず、ただ首をひねった。
十二月一日。挙兵からほぼ一ヶ月が過ぎた。
安禄山軍は黄河に差し掛かった。古くから国土を潤してきた、泥混じりの広大な流れである。
ここを渡れば霊昌という都市に着く。
安禄山は何を思ったか、全軍を見渡しの悪い、橋も無い岸辺に集めた。十二月の風が、兵士たちを足下から凍えさせる。
「雷梧」
安禄山が呼んだ。
「木でも草でもいい、水に浮く物をできるだけ集めて来い。ここを渡る」
「え? 泳ぐのは……それより、船を」
雷梧は、かじかんだ手を擦りながら答えた。安禄山は笑っている。
「だめだ。霊昌の連中は、抗戦する気配だからな。船で渡れば、その途中を襲われる」
雷梧にはまだ意味が分からなかったが、手勢を総動員して草の束やら船の残骸やらを大量に集めた。
安禄山の指示で、それを全て河面に浮かべる。あまりにも大量だったので、黄河の流れを遮ってしまった。
それを見渡して、安禄山は頷く。
「よし。一晩このままにする」
翌朝、雷梧が河を見に行くと、昨日浮かべた草木は見事に凍り付き、頑丈な浮橋となって対岸に繋がっている。
それを報告すると、安禄山はうっすらと笑った。
「進め」
大軍は、一気に黄河を越えた。
水面を歩いてくるとは相手も思わない。この奇襲で、霊昌はあっけなく降伏した。